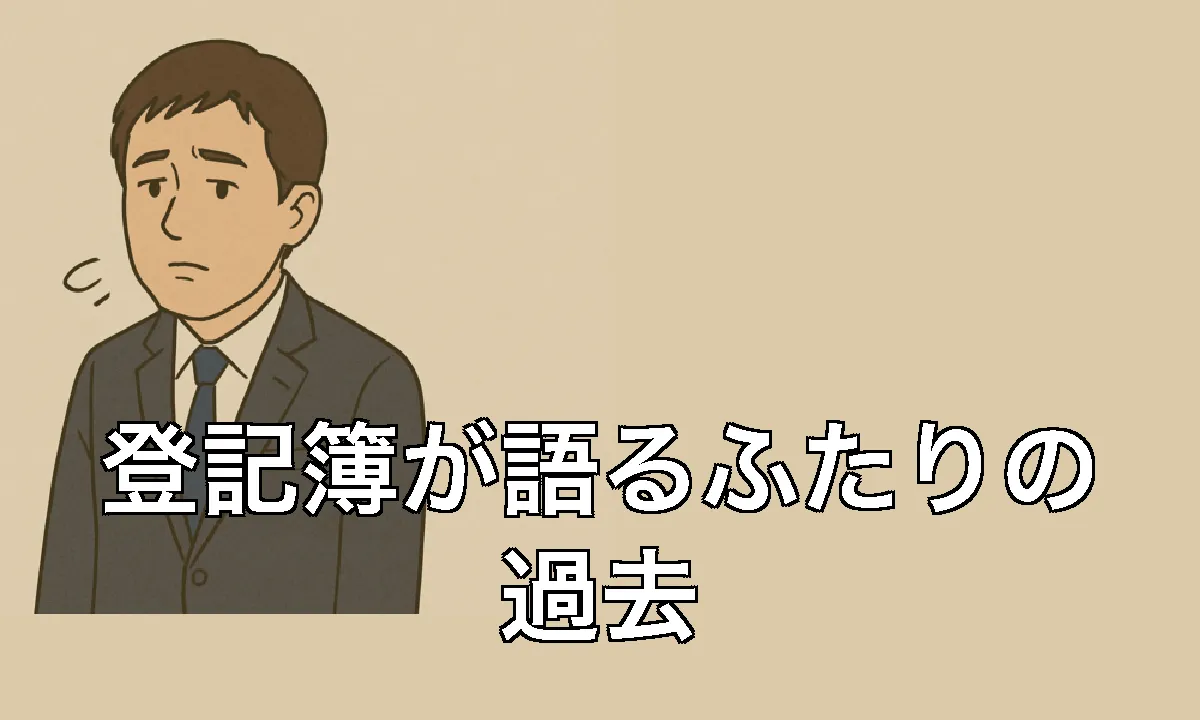午前九時の依頼人
赤いファイルを抱えた女
その女は、事務所のドアが開く音と同時に現れた。小雨の中を歩いてきたのか、コートの裾は濡れていた。手には赤い分厚いファイル。表紙には「登記関連資料」と走り書きされていた。
「合筆登記をお願いしたいんです」と、女は言った。声に揺らぎはなかったが、その目は何かを押し殺しているようだった。やけに静かだった朝の空気に、妙な違和感が立ちこめた。
「詳しく話を聞かせてください」そう応じた私は、コーヒーを入れるようサトウさんに目で合図した。
合筆という名の相談
女が持ち込んだのは、隣接する二筆の土地の合筆だった。地目も用途も一致しており、表面的には何の問題もないように思えた。だが、登記簿を見ると、所有者の欄に奇妙な並びがあった。
一筆目は女の名前。二筆目には「吉川政人」とある。「この人はご主人ですか?」と尋ねると、女は一瞬だけ視線を泳がせた。「いえ、もう関係のない人です」
その言葉は、事務的な口調の中にも微かな震えを含んでいた。合筆には共同申請が必要になる。元夫に連絡を取ることができるのか。私はその点を確認した。
ふたつの土地ひとつの記憶
地番が語る分かれ道
申請書の下書きを作りながら、私はふと、土地の地番の末尾に目が止まった。奇妙な連番ではあるが、両筆の分筆元が同じだったのだ。元々は一つの土地。そこに込められた経緯があるはずだった。
「この土地、昔は一筆でしたよね?」と聞くと、女はうなずいた。「結婚したとき、ふたりで一緒に買った土地です。でも離婚して、分筆して…」
「分けた土地を、今また戻すんですね」そう呟くと、女は微かに微笑んだが、それはどこか寂しい笑みだった。
未了の境界と終わらぬ感情
土地の境界線には杭が打たれていたが、法務局の資料ではそれが正式に確定したとは言いがたい。合筆の前提条件に、境界の確認は欠かせない。
サザエさんの家のように、隣の家とは簡単に行き来できる関係が理想だが、現実はそうはいかない。愛が終わっても、土地はそこにある。名義も、境界も、感情も。
この依頼、ただの登記では済まされない。私はそう直感していた。
調査の始まりは雨の音とともに
固定資産台帳の片隅に
翌日、私は市役所で固定資産課の台帳を閲覧した。ふたつの筆は、数年前まで減免措置の対象になっていた。理由は「共有財産としての評価」。つまり夫婦共有の形が続いていたのだ。
登記上はすでに所有者が分かれていたが、行政上の処理が遅れていたのか、それとも意図的か。そこには、登記簿には載らない「生活」の痕跡があった。
過去は、帳簿の隙間からこちらを見ている。私はその視線に気付かないふりをして、必要な写しを受け取った。
登記原因証明情報の違和感
依頼人から提出された登記原因証明情報には、「贈与」と書かれていた。しかしその文書には、明らかに形式的な記述の矛盾があった。年月日、住所、立会人の記載。
「これ、書式どこから持ってきました?」と私が聞くと、サトウさんが横からぼそりと「ネットで拾ったPDFですね。フォントが違います」と指摘した。
やれやれ、、、またか。時代は便利になっても、人間の浅知恵は変わらない。私はため息をつきつつ、真正な証明書の再取得を勧めた。
サトウさんの冷静な視線
所有者の名に潜む謎
事務所に戻ると、サトウさんが黙ってある資料を差し出した。そこには吉川政人の戸籍謄本の写しがあった。「勝手に調べたんですか?」と聞くと、「ええ、まあ」と塩対応。
そこには、驚くべき事実があった。吉川政人は二年前に死亡していた。つまり、依頼人の元夫はもうこの世にいなかったのだ。
合筆登記は、相続人の協力がなければ進められない。私はそっとファイルを閉じた。
共有者欄の余白にあるもの
不動産登記簿の共有者欄。その余白が、妙に広く感じられた。「吉川政人 相続人代表」と記されたその欄に、名前はなかった。法定相続人の誰かが、遺産分割協議書を出していないのだ。
「代表って、誰ですか?」と私は尋ねた。「息子です。二十歳になります」そう言った彼女の声は、さっきまでとは違い、どこか誇らしげだった。
サトウさんが、「連絡先は?」と聞くと、「来週、帰ってくるんです」と彼女は答えた。
過去帳と今をつなぐもの
昭和五十年の売買契約書
古い資料を調べる中で、私は一枚の契約書を見つけた。昭和五十年、依頼人の父が土地を購入した際のものだ。それが娘とその夫に引き継がれた。
土地はただのモノではない。記憶と関係と感情の塊だ。昭和から令和にまたがるその契約書の文字は、時代を超えて、今に続いていた。
合筆は、単に筆をまとめるだけではない。物語を一つにする作業でもある。
名字が変わるときに起きたこと
依頼人は、離婚後も名字を変えていなかった。それは、息子と同じ姓を保つためだという。しかし、登記簿の記録には旧姓での登録が残っていた。
登記名義人の変更には、ただの「変更申請」で済む。しかしその裏にある感情は、書類一枚で済むものではない。
それでも彼女は進もうとしていた。土地を、そして人生を、再びひとつにするために。
登記官とのやり取り
不一致を指摘するメール
申請を出すと、登記官からメールが届いた。「登記原因証明情報に不備があります」「相続関係の証明書類が不足しています」
当たり前のようでいて、心が削られる通知だった。何度も修正を繰り返すうちに、私は少しだけ情に流されていたかもしれない。
けれど、登記は感情では動かない。事実と証拠、それだけがすべてだ。
補正か取下げかの岐路
「このままでは補正しても通らない可能性が高いです」私は正直に告げた。依頼人はしばらく黙ったあと、「でも、やりたいんです」と答えた。
「息子が帰ってきたら、ちゃんと話します。そのあとで、正しい書類を揃えます」
その言葉に、私は静かにうなずいた。依頼はまだ終わらないが、道筋は見え始めていた。
サザエさん方式の推理法
波平が相続したと仮定してみよう
「波平さんがフネさんに先立たれたとして、名義がどう動くか考えてみてください」と私は冗談めかして言った。
「あー、そういうことですか」とサトウさんが反応した。「波平の名義をカツオが相続したら、ワカメの同意がいりますね」
その喩えに依頼人もふっと笑った。重たかった空気が、少しだけ柔らかくなった。
夜の法務局と決定的証拠
鍵を握る登記識別情報
法務局の端末で閲覧した閉鎖登記簿には、旧名義人の登記識別情報発行履歴があった。死亡直前に発行されたそのデータこそが、最終的な合筆の鍵だった。
息子がこの情報を元に、相続人として申請すれば、登記は完了する。あとは、彼がその意思を示すだけだった。
やれやれ、、、ようやくここまでたどり着いた。私は軽く首を鳴らし、コーヒーを一口飲んだ。
愛か裏切りか嘘の始まり
サトウさんがぽつりとつぶやいた。「でも、ほんとにこれって“愛”ですかね」
「さあな」と私は答えた。「ただ、嘘ではないんだろう。少なくとも、あの人にとっては」
そしてそれが、司法書士として関われる限界なのかもしれない、と私は思った。
事件の結末とそれぞれの道
司法書士としてのけじめ
数週間後、合筆登記が完了した。正確な書類、相続人の承諾、すべてが整った。
それを見届けた私は、静かにデータを保存し、ファイルを閉じた。依頼人は深く頭を下げ、「ありがとうございました」と言った。
私はそれにただ一礼を返した。司法書士として、やるべきことをやった。ただ、それだけだった。
サトウさんの少しだけ柔らかい言葉
「コーヒー、今日はおいしいですね」とサトウさんが言った。いつも通りの塩対応のあとに、ほんの少しだけ柔らかい声色が混じっていた。
「ありがとう」と私は言った。まるで、長い試合が終わったあとの挨拶のように。
コーヒーの香りが、静かに事務所を包んでいた。