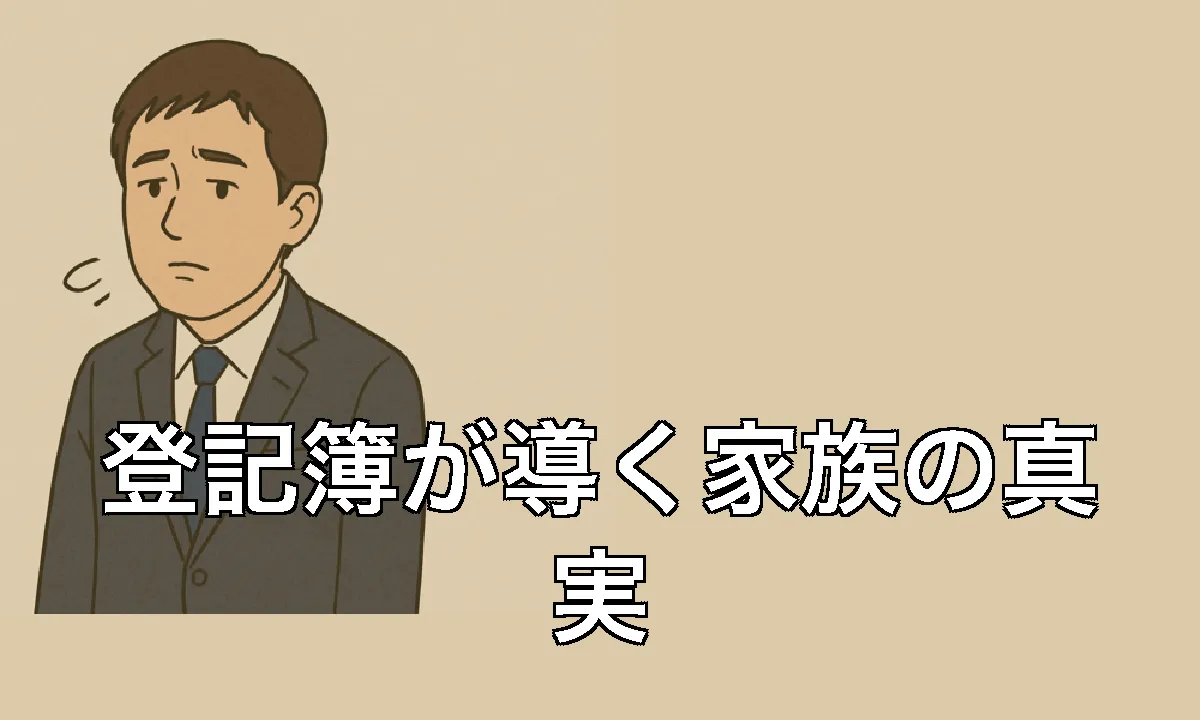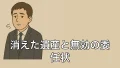朝の訪問者が持ち込んだ謎
朝のコーヒーに手を伸ばす間もなく、事務所のチャイムが鳴った。扉の向こうには、スーツ姿の女性が立っていた。目元に疲れの色を浮かべたその人は、私に封筒を差し出しながら口を開いた。
「父が亡くなり、遺産のことで兄と揉めていまして……」と彼女は言う。封筒の中には一枚の登記事項証明書が入っていた。築四十年の古い家、名義は父と誰かの共有になっている。
サトウさんの無表情な迎え
後ろから「いつも朝からトラブルですね」とサトウさんの冷たい声。私は肩をすくめながら「まあ、そういう仕事だからさ」と返したが、内心ではコーヒーが冷めていくことにしょんぼりしていた。
彼女はすでにパソコンを開き、依頼人の名前を検索している。「登記の変更履歴、ちょっとおかしいかもしれません」と彼女がぼそりと言った時、背筋にかすかな違和感が走った。
一枚の登記事項証明書が語る違和感
登記簿には父ともう一人の名義が並んでいたが、そのもう一人の人物は、依頼人が知らない名前だった。しかも登記日は今から十年以上前のものだ。遺産相続の話なのに、その名義人の情報が何も出てこない。
「兄が何か隠してる気がするんです」と依頼人は言った。私はその言葉の裏にある“違和感”を確かめるため、登記簿と戸籍を照らし合わせてみることにした。
依頼人の話に潜む食い違い
依頼人は兄が遺産を勝手に使っているのではと疑っていたが、話を聞けば聞くほど、兄の行動には一貫性があるように思えた。どこかで情報が食い違っている。だが、それがどこなのか、まだ見えてこない。
「兄はずっと父の面倒を見ていたんです。だから遺産も当然だと主張していて……」その言葉に私はひとつの可能性を思い描いた。もしかすると、これは“兄弟間の感情”の問題ではないのか?
亡き父の家を巡る兄妹の対立
「父は私には何も言わなかった」と依頼人はつぶやいた。私にはそれが少し引っかかった。親というものは、何かしらの痕跡を残すものだ。書き置きでも、印鑑証明でも、形として見えるはずなのに。
登記簿にあったもう一人の名義人、それが鍵かもしれない。私はサトウさんにその人物の戸籍を追ってもらうよう指示した。
サザエさん一家に例えるとややこしい構図
「なんというか……波平が二人いたような感じですね」と私はぼそりとつぶやいた。「つまり、父が二つの家族を持っていた可能性があるってことですか?」とサトウさん。
「その可能性もある。フネさんが二人だったら、それはそれで地獄絵図だな……」と冗談を言ってみたが、サトウさんは真顔で「例えが昭和ですね」と冷たく返した。
登記簿と戸籍の奇妙なズレ
登記上の名義人の一人「木下亮太」という名は、戸籍上では依頼人の異母兄に該当する人物だった。しかも、亡き父が若い頃に認知した子供で、母親とは婚姻していない。完全に別戸籍だった。
「やれやれ、、、またこういうパターンか」と思わずつぶやいた。相続人がもう一人。しかも依頼人も知らない、隠された存在が現れた。まるで少年探偵団が見つける第八の被害者のように。
共有名義の謎の一筆
登記簿には、父と木下亮太の名義で共有と記されていたが、その共有割合が50対50ではなく、70対30になっていた。これが不自然だった。もし認知していたのなら、半々にするのが通常だ。
この数字に何か意味があるのか。あるいは、相続とは別の事情があったのか。私は司法書士としての視点で、当時の契約書を調べることにした。
司法書士の地味な調査開始
市役所と法務局、時には図書館。まるで昔の名探偵コナンが地味に推理を進めるように、私は地味にコツコツ調べを進めた。誰に感謝されるわけでもなく、ただ真実を突き止めるために。
その過程で、10年前に書かれた「贈与契約書」が出てきた。そこには、父が木下亮太に土地の30%を譲る旨が書かれていた。理由は「生活に困っていたから」とある。
市役所と法務局をまたぐ情報の断層
登記はある、贈与契約もある。しかし戸籍や住民票では、木下亮太はここ十年間、別の町に住んでいた痕跡があった。なのに、その家には兄が住んでいる。この間に何があったのか。
兄が木下の持分を買い取った形跡もない。何もかもが中途半端で、不完全だ。私はこの“隙間”が、真相へとつながるドアだと感じていた。
古い謄本に隠された手がかり
古い登記簿の閉鎖謄本には、一度だけ父の単独名義になった履歴が残っていた。それが約20年前。その後、再び共有に戻されている。贈与というより、差し戻しのような処理だった。
これはもしかすると、税務署を意識した仮登記の可能性がある。つまり“持分を渡したように見せかけて、実際は兄が相続するように仕組まれた”のではないか。
塩対応サトウの推理が冴える
「つまり、木下さんは最初から関わってない可能性もあるんですよね」とサトウさんが言った。私は驚いた。確かに、彼の署名や押印は一切出てきていない。すべて父の記載のみ。
「となると……」と私が言いかけると、サトウさんは冷たく一言。「兄がすべて演出したんでしょう。父の死後、自分に都合よく財産を独占するために。」
やれやれ、、、また私がやるんですか
「じゃあ、その持分移転登記は無効の可能性があるってことか……」と私がつぶやくと、サトウさんはプリンターから資料を出しながら、「やれやれ、、、また私がやるんですか」とぼやいた。
私は小さく頷きながら、やっぱり彼女がいないと事務所は回らないな、と心の中で思った。
真相は家族の再編と裏切り
兄は、父が昔認知した子供の名前を使い、書類を整え、自分が相続するための“物語”を作り上げていた。しかし、戸籍と登記の整合性が取れていないことで、その嘘は明るみに出た。
「家族って、名前だけじゃないですよね」と依頼人がつぶやいた時、私も思った。司法書士の仕事は、名前や数字だけでなく、その背景にある人間関係まで見抜かないといけないのだと。
隠し子が生んだもうひとつの相続
その後、本物の木下亮太が現れた。彼はすでに別の家庭を持ち、今回の件には関わりたくないと言った。だが、法的には彼にも相続権がある。私たちは彼と依頼人との間で協議を進めることにした。
最終的に亮太氏は相続を放棄し、兄の独断による行為も撤回された。登記は無事に修正され、依頼人の家族にも平和が戻った。
最後に司法書士ができること
正直、法的な調整や書類の整備に終始する地味な仕事だが、こうして一つの家族の問題が解決するのを見ると、少しだけ報われた気持ちになる。たとえ誰にも感謝されなくても。
サトウさんは淡々と書類のチェックを終え、席を立った。「次の相談者、もう待ってますよ」とだけ言って。私は冷めたコーヒーを一口すすると、いつもの一言がこぼれた。
サトウさんの小さなため息と一言
「お疲れ様でした」と言いながらも、サトウさんはため息をついた。「まったく、家族って厄介ですね。サザエさん家のようにはいかないか……」
私は椅子に体を沈めて天井を見上げた。「やれやれ、、、次はどんな事件が来ることやら」