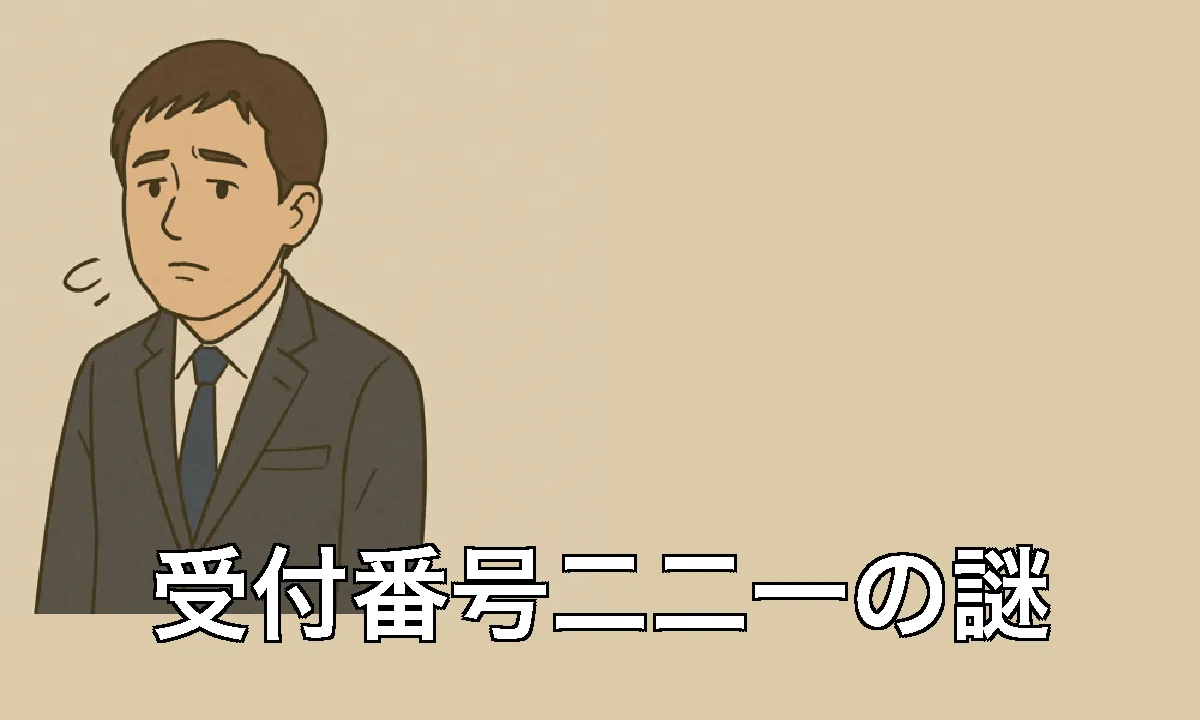受付札が呼ばれた朝
朝の事務所は、いつもと変わらず書類の山に囲まれていた。コーヒーの香りとサトウさんの無言の圧が、月曜の始まりを告げる。そんな中、インターホンが鳴り、俺は椅子を軋ませながら立ち上がった。
「ご予約の方ですか?」と尋ねると、ドアの外には控えめな女性が立っていた。彼女の手には、古びた受付番号札が握られていた。「二二一番です」と、少し緊張した面持ちで彼女は告げた。
受付番号二二一――聞き覚えのない番号だった。なにか胸騒ぎがした。
月曜日の司法書士事務所
週明けはいつもバタバタだ。登記関係の相談が多く、相続や離婚、時には遺言の相談が続く。だがこの女性の依頼は、まるでそれらとは別次元だった。
「これは法律相談というより…心の整理、なのかもしれません」と彼女は言った。事務所の空気が一瞬凍った。
まるで昭和の恋愛ドラマでも始まりそうな雰囲気に、思わず笑いそうになったが、サトウさんの鋭い視線に撃たれた。
見知らぬ女性と番号札
彼女が差し出した番号札は、どう見てもこの事務所のものだった。だがうちでは100番台までしか札を発行していない。おまけにその札、裏面に赤いインクで「戻る場所」と書かれていた。
「これ、どこで手に入れたんですか?」と俺が尋ねると、彼女は曖昧に微笑むばかりだった。やれやれ、、、面倒な依頼の匂いがしてきた。
それでも断れないのが俺の悪い癖だ。
依頼内容は恋愛相談
女性の名は伏せられた。語ったのは、五年前に別れた恋人との未練と、彼が亡くなったこと。そして、彼の最後の手紙がどこかに預けられているという謎だった。
「その手紙には、私が知らなかった彼の過去が記されている気がするんです」と彼女は言った。まるで名探偵コナンの最終話のような、死者からの謎解きだ。
俺は少し背筋を伸ばして、「で、その手紙はどこに?」と尋ねた。
登記簿ではなく恋心の整理
この仕事をしていると、登記簿よりも人間の感情の方がよっぽど複雑だと痛感することがある。今回もそのパターンだ。
彼女は、手紙がこの事務所に預けられているかもしれないと言う。そんな記録はないが、心当たりが一つだけあった。俺の古い師匠が使っていた金庫だ。
あれには過去の依頼者がこっそり物を預けていったという噂がある。
サトウさんの冷静な視線
「師匠の金庫ですか…。また厄介ごと、引き受けましたね」
サトウさんが無感情に呟いた。その目は完全に諦めていた。俺がうっかり金庫の鍵を落とした過去を忘れていないらしい。
「探しますよ。どうせ放っておけないんでしょう?」と、彼女は無言で金庫の鍵の所在リストを開いた。
受付番号二二一の違和感
金庫を開けると、出てきたのは封筒がひとつ。そして一緒に入っていたのが、あの番号札と同じもの。札の裏には違う文字が書かれていた。
「本当の気持ちはここにある」
まるでキャッツアイの次回予告のような洒落た演出に、正直ゾッとした。
発行されていないはずの番号
あの札はやはり、うちでは作っていない。師匠が個人的に発行したものか、あるいは依頼者が自作したのか…。封筒の中には便箋が一枚。
「彼女にこの手紙を渡してほしい」そう書かれていた。日付は五年前、彼の死亡日の前日だった。
それは彼の最後の恋文だった。
記録には存在しない来訪者
女性の名はどこにも記録されていなかった。だが、その筆跡は彼のものに間違いなかった。俺はそっと封筒を閉じ、女性にそれを差し出した。
彼女は何も言わず、深々と頭を下げ、そして去って行った。
残されたのは、机の上に置かれた番号札だけだった。
消えた女性と忘れられた札
次の日、彼女の姿はどこにもなかった。連絡先も、控えも残っていない。俺は札を引き出しに戻そうとして、ふと気づいた。
札の裏の文字が変わっていたのだ。「ありがとう、さようなら」
サザエさんのエンディングみたいな、なんとも後味のいい幕切れだ。
封筒の中の遺言書
その後、俺は彼の遺言書を探してみた。どこにもなかったが、たぶんあの手紙が彼にとっての本当の遺言だったのだろう。
法律じゃ割り切れない想いが、この事務所にはいつも転がっている。
「やれやれ、、、恋愛相談が一番やっかいだ」俺はため息をついた。
やれやれ、、、俺の出番か
その夜、サトウさんが呟いた。「番号札、燃やしておきましょうか」
「いや、記念に残しておこう。俺の探偵ごっこ第一号だからな」
彼女は呆れた顔をして、それ以上何も言わなかった。
調査開始と不審なカフェ
数日後、街の小さなカフェで彼女に似た人を見かけた気がした。だが、声はかけなかった。記憶の中の彼女のままでいてほしかった。
カフェの奥には、受付番号札をモチーフにしたインテリアが飾られていた。
あの札と同じものが、まるで記念品のように。
常連が語る奇妙な噂
「五年前からあの札、飾ってるんですよ。誰が置いたのか、誰も知らないけど」
常連の女性が語った。まるで都市伝説のようだ。
俺は微笑みながら、アイスコーヒーをすすった。
番号二二一の真実に迫る
誰も知らない、だけど確かに存在した番号二二一。
それはただの受付札じゃなかった。誰かの想いを託す鍵だった。
俺の仕事は、紙の上だけの正義じゃ測れない。
過去の事件との奇妙な一致
帰り道、五年前の未解決失踪事件の記録を見直してみた。
記録には、名前の消された女性の届け出が残っていた。
それ以上の情報はなかった。ただ、受付番号の記載だけが。
五年前の失踪届
届け出を出したのは、彼――手紙の差出人本人だった。
彼は、自分が死ぬ前に、彼女の存在をこの世界から消そうとしたのか。
その意図は分からない。ただ、彼なりの愛だったのだろう。
番号札は何を意味するのか
番号札二二一。それは再会の合言葉であり、記憶の鍵でもあった。
「探偵ってのも、悪くないかもな」と独り言ちた。
きっと、また誰かがこの番号を持って現れる気がした。
司法書士が辿り着いた結論
事件の真相は誰にも分からない。けれど、少なくとも俺は知っている。
番号札一枚で繋がった想いが、ここに確かにあったことを。
それだけで、今日の仕事は意味がある。
恋文に託された最後の願い
「法律は人を裁くけど、気持ちは裁けませんね」とサトウさんが言った。
たまには良いこと言うじゃないかと茶化すと、塩対応で返された。
「別に褒めてませんけど」と。
戸籍と記憶の境界線
人は紙の上では分類されるが、心までは記録できない。
この仕事をしていても、そう思うことばかりだ。
だからこそ、番号二二一は忘れないでおこうと思った。
結末は静かに
事務所の引き出しには今も、あの番号札が眠っている。
来客の記録にはないが、心の中では確かにいた依頼人。
時折、無意識に引き出しを開ける自分がいる。
番号二二一が意味するもの
それは恋の記憶であり、忘れられた願いの象徴だった。
サザエさんのように、何も変わらない日常に見えても。
実は小さな奇跡が、ひっそりと紛れているのかもしれない。
サトウさんのひと言
「ところでその番号、次の依頼人が持ってきたらどうするんですか?」
サトウさんがコーヒーを飲みながら言った。
「やれやれ、、、また探偵ごっこか」俺は肩をすくめた。