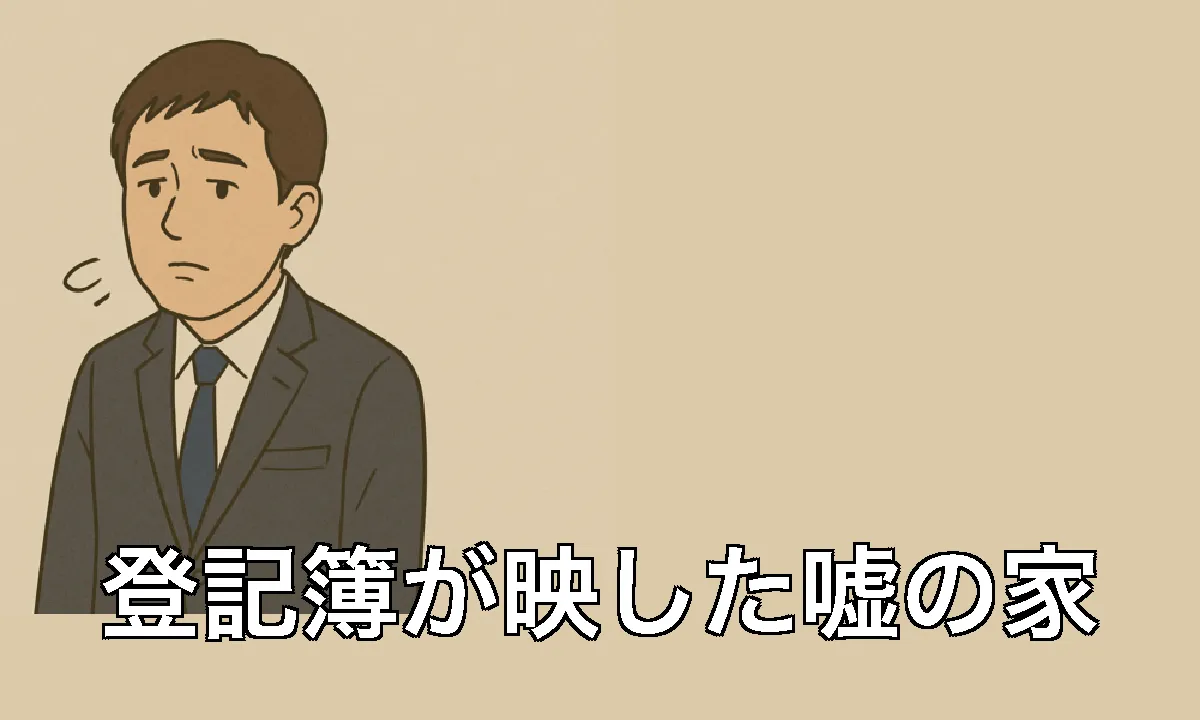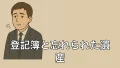登記簿が映した嘘の家
「先生、これ、なんか変です」とサトウさんが机に書類をトンと置いた。
それは郊外にある古い一軒家の相続手続きに関する登記簿だった。
建物自体は立派だが、そこに書かれている所有者の履歴がどうにも妙だった。
忙しさの合間に届いた一通の封書
郵便受けに放り込まれていた分厚い封筒。送り主は、最近亡くなった資産家の次男と名乗る人物。
封の中には、相続関係説明図と遺産分割協議書、そしてシンプルな依頼文が添えられていた。
「相続登記をお願いしたい」とだけあるその文面に、どこか拭えない違和感を覚えた。
遺産分割協議書に潜む違和感
協議書には三人の兄弟の署名捺印があった。しかし印影が不自然に揃いすぎている。
サトウさんが「これ、コピーじゃないですか?」と呟いた瞬間、胸騒ぎが加速した。
形式上は完璧でも、人間の息遣いがまるで感じられない書類だった。
サトウさんの冷たい一言が火をつけた
「全部そのまま処理すれば楽ですけど、先生はそういうの嫌いでしょ」
塩対応のその一言に、火がついた。
「……ああ、わかったよ。やるしかないんだろ、結局」そう呟いて、私は調査に踏み出すことにした。
家族全員が語るそれぞれの真実
三兄弟はそれぞれ違うことを語った。
長男は「家なんて興味ない」と言い、次男は「自分が世話したから当然だ」と主張し、三男は「そんな家知らない」と言い放った。
この家に住んでいたのは誰なのか、誰が本当に所有していたのか、霧は濃くなるばかりだった。
司法書士の立場で踏み込む危うさ
第三者的立場を保つべき司法書士が、ここまで首を突っ込んでいいのか。
けれど、登記に携わる者として、このまま目を瞑るわけにはいかなかった。
この家には、どうしても解き明かさなければならない「誰かの嘘」が潜んでいる気がしてならなかった。
古い登記簿の文字が語る過去の矛盾
法務局で閲覧した昭和時代の登記簿。
そこには「所有者 ハヤミカズオ」の名前があったが、依頼者の父親は「タカオ」だと言っていた。
同姓同名の可能性もあるが、記載されている住所に戦慄した。依頼書と一致している。
被相続人の本当の家はどこだったのか
被相続人が住んでいたとされる「本家」は、別の市街地にあるマンションの一室だった。
近隣住民の話では「奥さんと二人きりで、こぢんまりと暮らしていた」とのこと。
この郊外の家には、一度も住んだ形跡がないという。
名義変更の裏に隠されたもう一つの名前
謄本の隅に、消えかけたような筆跡で書かれた付記があった。
そこには「名義変更申請中」のメモとともに、ある司法書士事務所の名前が残されていた。
それは十年以上前に廃業した、近隣でも評判の悪かった事務所だった。
破れた相続関係説明図にあった落書き
協議書に同封されていた関係説明図の裏面には、赤ペンで走り書きがあった。
「この家はアイツのモノじゃない、絶対に」そう書かれていたその文字は、怒りと執念を感じさせた。
誰かが無理やり自分のものにしようとしていたのは間違いなかった。
サトウさんが見つけた登記の決定的ミス
「先生、この筆界確認書、見てください」
サトウさんが差し出したのは、昔の隣地所有者と交わされた境界確認書。
そこには、現況の建物が越境しているという決定的な証拠が書かれていた。
調査協力を渋る法務局職員とのやりとり
「そういうのは、こちらでは対応できません」
何度も言い訳を繰り返す法務局の窓口職員に、私は食い下がった。
「このまま登記を進めたら、虚偽登記になりますよ」と言った瞬間、職員の顔色が変わった。
亡き父が残したメモの意味
依頼人の長男から、ぽつりと渡された一枚のメモ。
そこには「家は、カズオに借りただけ。登記するな」と震える文字で記されていた。
嘘を隠し通そうとした末、父親は最後に真実をメモに残したのだった。
真実を語るにはあまりに重すぎた結末
結局、家の所有権は他人名義のまま、相続は不成立となった。
依頼人たちは納得せず怒りをあらわにしたが、これが法のもとで導かれた答えだった。
「サザエさんの波平さんみたいに、黙ってひっくり返すしかないな」そんな心の声を飲み込んだ。
やれやれと呟いて事務所に戻る背中
帰り道、空がどんより曇っていた。
「やれやれ、、、また嫌われただけか」とつぶやいて、肩をすくめた。
でも隣を歩くサトウさんが、珍しく「先生、お疲れ様でした」と言った。それだけで少し救われた気がした。