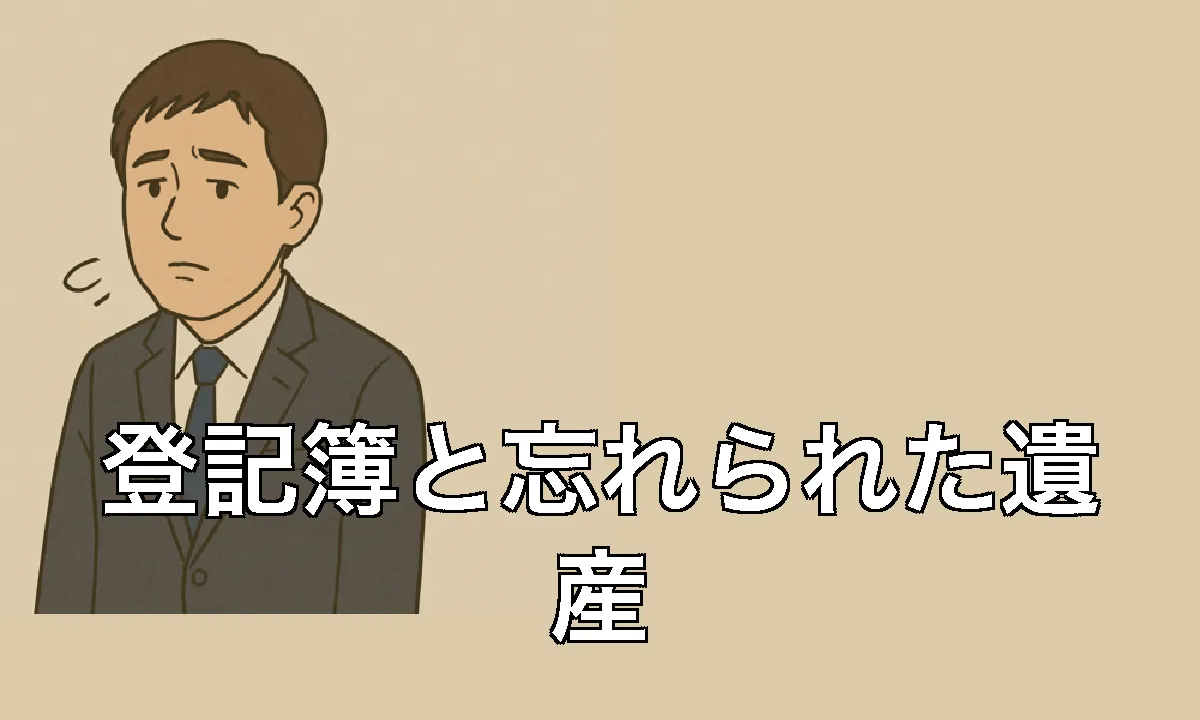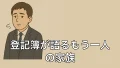序章 忙しすぎる火曜日の朝
朝から雨。しかもコピー機が紙詰まりを起こし、サトウさんの表情はいつも以上に冷たい。電話のベルが鳴るたびに、こっちは肝を冷やす。「また相続ですか? この時期、呪いでもあるんでしょうか」と、半ば独り言のようにつぶやいた。
そして、その一本の電話が、地味で疲れた一日を一変させた。「亡くなった父の相続登記をお願いしたいのですが」――そう切り出した女性の声は、妙に落ち着いていて、逆にこちらの不安をあおってくるのだった。
疲れた頭に響く一本の電話
電話の主は黒川という女性。喪服のまま、すぐにでも事務所へ向かうと言う。断る理由もなく、いや断る気力もなく、スケジュールに「13時 黒川様」と無言で書き込んだ。
「シンドウ先生、カレーうどんの汁、ネクタイについてますよ」とサトウさんの無機質な指摘が飛ぶ。やれやれ、、、この日はもうダメな予感しかしなかった。
依頼人は喪服の女性だった
正午過ぎ、黒川さんがやってきた。喪服に黒髪をひっつめた姿はまるで昭和のサスペンスドラマのヒロインのようだった。彼女は父の遺産について語り出したが、話の節々に何か釈然としない点があった。
「登記名義が父ではなく、まったく知らない名前なんです」——彼女のその言葉に、私は一気に眠気が吹き飛んだ。これはただの登記では終わらない案件だ。
謎の相続登記依頼
黒川家が所有していたはずの土地。その登記簿を確認すると、そこに記されていたのは「岸本文蔵」という聞いたこともない名前だった。どういう経緯でこの人物が登記名義人となったのか、何の手続きもされていない。
しかも、その登記は平成8年。黒川氏の生存中の時期であり、かつて売却や譲渡の履歴も見つからない。「お父様は何か特殊な契約をされた記憶はありませんか?」と尋ねると、黒川さんは「わかりません。父は無口でしたから」と首を振るだけだった。
所有者欄に浮かぶ知らない名前
登記簿謄本の記載は確かに「岸本文蔵」。だが、この人物の住所は現住所とはかけ離れた地域。移転登記の痕跡もない。登記の目的欄は「仮登記抹消後の所有権登記」とある。
仮登記? 抹消? それならば前段の仮登記情報を調べねばなるまい。古い閉鎖登記簿を取り寄せることにした。
隠された遺言書の存在
調査の過程で、被相続人である黒川氏が、自筆の遺言書を役場に届けていたことがわかった。だが不思議なことに、その内容は相続人である黒川さんを一切記載せず、第三者の名が並んでいた。
しかも、その一人が岸本文蔵だった。だが、岸本はすでに10年前に亡くなっており、相続登記もされていなかった。これは偶然か、それとも誰かが意図的に“残した”のか。
相続人の誰かが嘘をついている
不自然な点は他にもある。黒川家の戸籍を追っていくと、見知らぬ養子の存在が浮かび上がった。「岸本誠」。岸本文蔵の子として届出されていたが、黒川家と同じ住所で住民票が登録されていた時期がある。
つまり、この“養子”が遺産のカギを握っている可能性がある。黒川さんにそれを伝えると、驚いたように目を見開いた。「まさか……あの人……」と彼女は何かを思い出したようだった。
戸籍を追うサトウさんの執念
「この人、平成14年の3月だけ、この家に住んでました」——そう言ってサトウさんが差し出したのは、住民票の履歴と除票、そして名寄帳。すでに法務局、市役所、役場と三ヶ所を回っていたらしい。
「もしかして、探偵になったほうがいいんじゃないですか?」と冗談を言ったが、塩対応の彼女からは「いや、司法書士が探偵やるほうが滑稽ですよ」と即答された。うむ、痛いところを突かれる。
養子縁組の裏に潜む動機
岸本誠は、黒川家の長年の家政婦の息子だった。黒川氏は彼を密かに養子にし、全財産を譲ろうとした形跡がある。だが、誠は20代で事故死していた。そして、それに気づいていたのは黒川氏だけだったのだ。
つまり、現登記名義の「岸本文蔵」は架空の存在。いや、存在していたが、既に死亡。登記は一度、意図的に止められていた可能性がある。なぜなら、遺言を実行させたくなかった人間がいたからだ。
旧登記簿の中に残された痕跡
閉鎖された登記簿の中に、わずかに残っていた「却下」の記載。その申請人の名前は「黒川静子」——依頼人の名前だった。つまり、彼女は一度、自分に有利な内容で登記申請をし、それが却下されていたのだ。
「父は私に全てを遺すと言っていた」と彼女は言った。しかし、法的にはそうではなかった。無効な遺言、無効な登記、偽りの申請——すべてが絡み合っていた。
昭和の登記に仕込まれた罠
昭和末期の登記にはしばしば“裏技”が仕込まれていた。仮登記→抹消→本登記という流れもその一つ。今回も、黒川氏が生前に仮登記だけを済ませ、その後、誰にも言わずに死んだ可能性がある。
「これは一種の遺産隠しです」と私はサトウさんに言った。「ただし、法律の網の目を縫った遺産隠しですね」と彼女は淡々と返した。
見落とされた仮登記の意味
仮登記の意味は、いわば“将来の予約”。しかし、その予約が期限切れとなれば、法的な意味は失われる。今回の事件では、それが逆に“闇に葬る装置”として機能していた。
結局、岸本文蔵名義の登記は抹消手続きを経て、法定相続分に基づいて登記されることとなった。黒川さんは不満げだったが、それが法律だ。納得してもらうしかない。
真相へと繋がる鍵
一連の経緯をまとめると、被相続人は養子に全財産を遺そうとしたが、相続人の一人がそれを妨害した。しかし、その妨害行為は手続上、完全ではなかったため、事実が明るみに出た。
私は一枚の名寄帳を手にした時に確信した。「この住所、この筆跡、そしてこの登録時期……全部つながった」。パズルの最後のピースが、ようやくはまった瞬間だった。
権利証の筆跡に潜む違和感
黒川氏の最後の権利証に記されたサイン。それは、岸本文蔵の筆跡と酷似していた。つまり、黒川氏は岸本の名を借りて自ら登記したのだ。養子への愛情、そして相続人への不信——動機は複雑だった。
「結局、登記って人間関係が全部出るんですね」とサトウさんが言った。まったくその通りだ。やれやれ、、、これだからこの仕事はやめられない。
決め手はたった一枚の名寄帳
全てが解決したのは、名寄帳のおかげだった。地味で目立たないその書類が、最大の証拠になったことに感謝する。派手な探偵漫画には出てこないが、司法書士には司法書士のやり方がある。
「この結末、コナンくんじゃなくて、まる子ちゃんにでも語らせたほうが平和だったかもですね」と私が言うと、サトウさんは鼻で笑った。「先生、今回はうっかりじゃなくて、本当に役に立ちましたね」と。うむ、それが一番うれしい評価だった。
結末 サインされた遺産分割協議書
最後に、すべての相続人が集まり、正式な遺産分割協議書が作成された。感情的な対立はあったが、法的な整合性のもと、全員が署名した。やれやれ、、、書類がそろえば、事件は終わる。
「先生、次の案件は未登記建物です」——サトウさんの一言に、私は机に突っ伏した。平和な日常は、いつだって書類の向こう側にある。