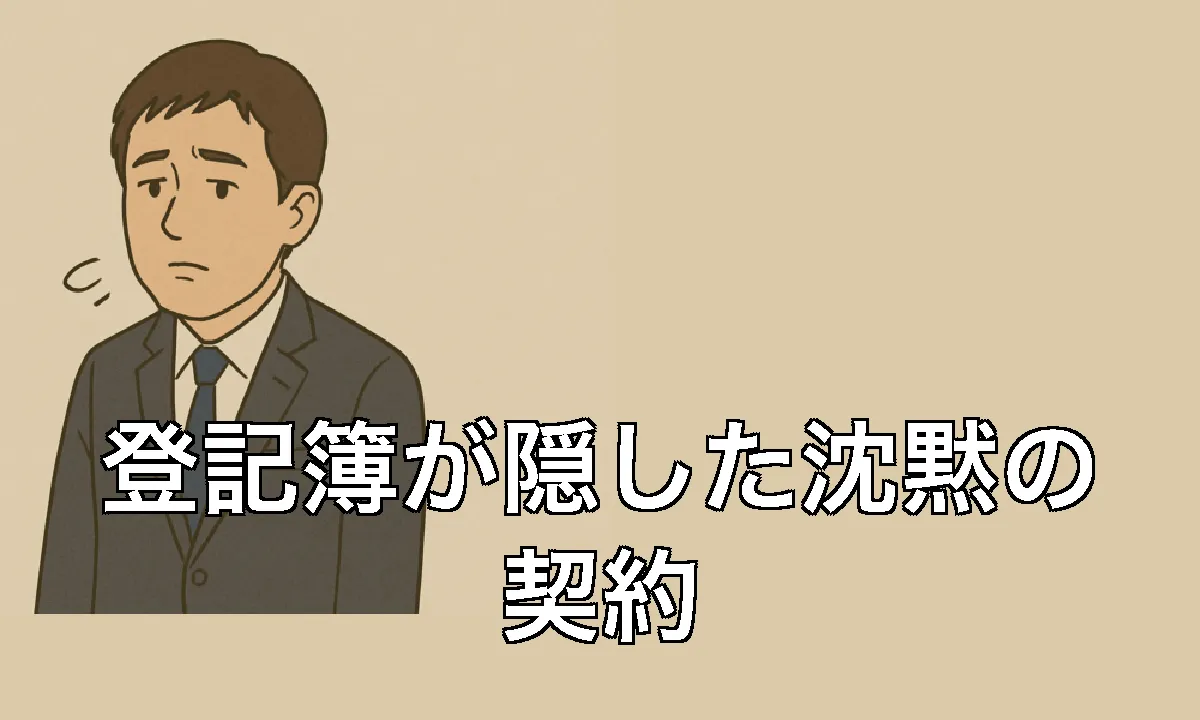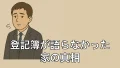朝の訪問者が運んできた違和感
雨上がりの朝、古びた革カバンを抱えた初老の男性が、事務所のドアを静かに開けた。控えめな身なりに似合わず、その目は異様に澄んでいる。挨拶もそこそこに、彼は一枚の登記事項証明書をテーブルに置いた。
「この不動産、売りたいんです」それだけを口にした。だが、記載された情報にはどこか引っかかるものがあった。所有者の名義が十年前のままで、しかもその人物は既に亡くなっているはずなのだ。
サトウさんがパタパタと書類棚から関連資料を引っ張り出す横で、僕は嫌な予感に眉をひそめた。
不動産登記の依頼と曖昧な説明
「名義変更は親族間で済ませたと思っていました」と依頼人は言う。だが、その表情はどう見ても『忘れていた』のではなく『伏せておきたい』という意思に満ちていた。口の端がわずかに震え、語尾が濁る。
まるでサザエさんの波平が“いいから黙ってろカツオ!”と言う前の、あの一瞬の間のようだった。どう考えても何かを隠している。
「どうしますか?」とサトウさんが低い声で訊いてくる。選択肢は少ない。確認するしかないのだ、この沈黙の背後にあるものを。
サトウさんの冷静な観察眼
「この申請書、筆跡が妙に整ってますね。年配の方にしては綺麗すぎます」そう呟きながら、彼女は筆跡の違いに気づいた。さすが元コナン好きだけあって、観察力が尋常ではない。
さらに、添付された印鑑証明書も微妙に違和感があった。発行日が妙に古いのだ。なぜわざわざ5年前の証明書を提出してきたのか。それは、まだ存在していたころの証拠として使いたかったということではないか。
「これは、偽装の可能性があります」とサトウさん。冷ややかな声が事務所に響いた。
契約書に記された奇妙な但し書き
預かった契約書を読み込むと、一般的な売買契約の文面に紛れて、ひときわ異質な一文があった。「本契約は、第三者の承諾を要しない」と。え?承諾が要らない?それはつまり、相続人を無視してもよいという意図か?
契約書の体裁は整っていたが、この一文は“誰かに見られたくない”という意図の表れのように感じられた。こうした文言が混ざるとき、それは常に“後ろめたさ”のサインだ。
僕はその文を指差し、「これ、司法書士ナメてますよね」と小声で呟いた。
定型文に紛れた一文の意味
法律家でなくとも、おかしな文面には気づくはずだ。しかし、依頼人は気づいていないふりをしていた。それが彼の“防御”なのだ。聞かれなければ言わない。バレなければ通ると思っている。
だがそれは、僕たちのような仕事をしている者には、逆に目立って見える。サザエさんのエンディングに磯野家の誰かがいなかったら、すぐ気づくのと同じだ。
つまり、この但し書きは“第三者の登場を恐れている”証拠だった。
元所有者の不在と空白期間
法務局の資料を取り寄せると、登記簿上の空白期間が明らかになった。亡くなったとされる所有者の名義のまま、何年も放置されていた。その間、固定資産税も支払われていなかった。
にもかかわらず、今になって突然売却しようとするのは、何らかの事情が解消されたか、あるいは焦りが出てきたかのどちらかだ。
「登記の沈黙は、真実の叫びと紙一重ですね」とサトウさん。詩人か。
相続登記が放置された理由
依頼人に問いただすと、ようやく口を開いた。「実は…兄が失踪していたんです」。なるほど、相続人の一人が所在不明。だから登記もできなかったというわけか。
しかし、失踪宣告もされていないし、行方調査の履歴もない。つまり、それを“口実”にして、書類の処理だけを進めたかったということだ。
その瞬間、僕の中で何かが確信に変わった。これは“合法に見せかけた詐欺”だ。
再登記の裏に潜む動機
こうしたケースでよくあるのは、借金絡みの土地売却だ。案の定、過去の抵当権設定履歴が出てきた。しかも抹消登記がなされていない。つまり、まだその土地には“見えない縄”がかかっている状態だったのだ。
登記簿には語らないが、確実に残っている“負の証拠”。それを覆い隠そうとする者の手口は、パターン化している。
ここまできたら、司法書士として引けない。正直、面倒ごとはご免だが、やるしかない。
司法書士なら見逃さない文言の罠
僕は再度、提出された書類一式をチェックした。すると、“委任状”に違和感を覚えた。筆跡が契約書と一致していないのだ。つまり、偽造の可能性がある。
「…これ、提出できません」と僕は告げた。依頼人の顔がサッと青くなる。「お力にはなれません」とサトウさんが淡々と続ける。もはやこれまで、と悟ったようだった。
「やれやれ、、、やっぱり一筋縄ではいかないよな」と僕は頭を掻いた。
事件の核心に迫る鍵となった古い謄本
結局、すべての謎を解いた鍵は、法務局の地下室から引っ張り出した昭和時代の古い謄本だった。そこにあったのは、失踪したとされた兄が正式に土地を放棄していた記録だった。
だが、それが無効となるような後日談がなかったため、依頼人は“無効扱いになるかも”という不安から勝手な手続きを進めようとしたらしい。
嘘と沈黙の上に成り立った“契約”は、結局破綻した。
登記簿の余白に残された数字
その謄本の余白に、ボールペンで書かれた数字があった。「2-7-6」。これが法務局の通し番号と一致し、時系列が判明したことで、兄の放棄が“真正”であることが裏付けられた。
サトウさんは静かに頷き、コーヒーをすすった。「情報は、声よりも余白に宿るんですね」どこで覚えたのか、そんな名台詞を残す。
まるで探偵漫画の締めのような気分だった。
解決のあとに残った小さな後悔
依頼人は深々と頭を下げて帰っていった。感謝というよりは、諦めのような静けさが漂っていた。僕は机に突っ伏して、小さなため息を吐いた。
「今日、野球中継ありましたっけ?」とつぶやくと、サトウさんがピクリとも動かずに言った。「甲子園はとっくに終わってます」
やれやれ、、、これが現実か。
司法書士としての正義と苦い記憶
今回の件で登記簿の怖さを改めて思い知らされた。紙の上に沈黙がある。それを読み解くのが司法書士の仕事。だけど、それは心を削る作業でもある。
僕がかつて野球で流した汗よりも、今のほうがずっと泥臭い。
でも、誰かの未来を守るために、今日もまた書類に目を通す。それが僕の仕事だから。
やれやれ、、、次はどんな依頼が来るのやら
椅子にもたれ、天井を見上げる。次は相続放棄か、あるいは後見か。いや、不動産売買の依頼だったらまだ楽かもしれない。
その時、ドアがまた開いた。次の依頼人の影が、ゆっくりと差し込む。僕はペンを握り直し、小さく呟いた。
「やれやれ、、、終わりが見えないな」