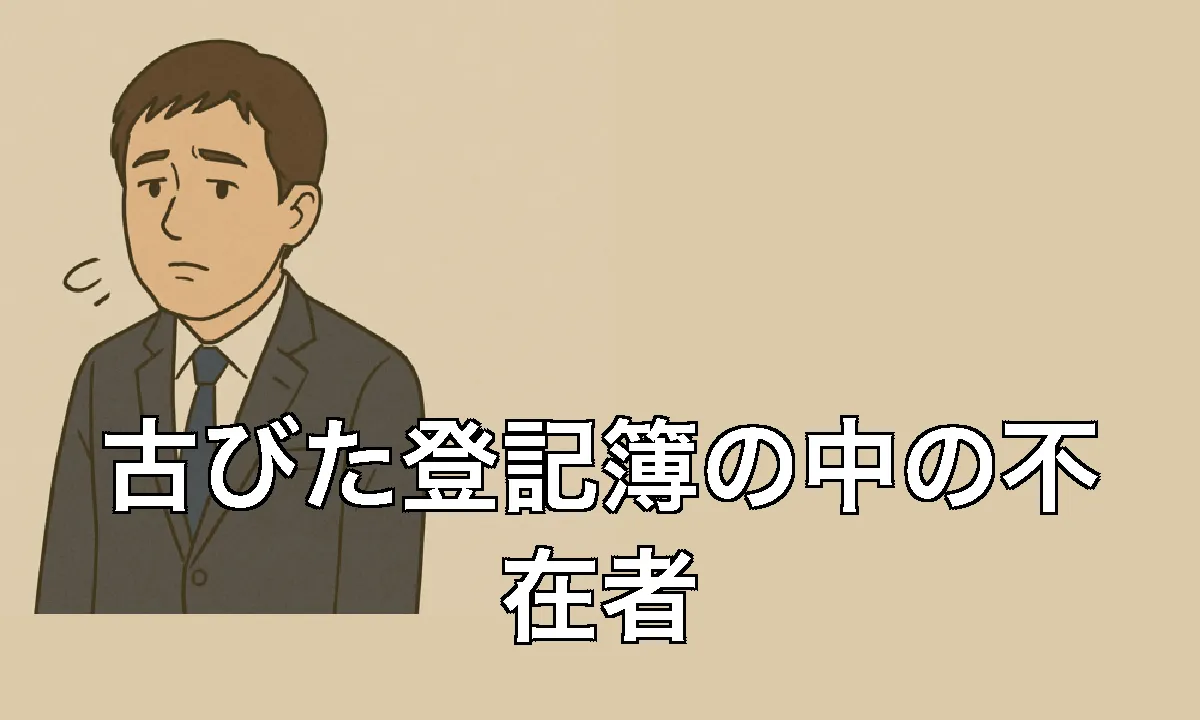古びた登記簿の中の不在者
午前10時、事務所のドアがギイと音を立てて開いた。 入ってきたのは、近所の商店を営む老婦人だった。 「空き家の相続手続きをお願いしたいんですけど…」と、不安げに言う彼女の手には、黄ばんだ登記簿の写しが握られていた。
依頼人の語る相続の不安
話を聞けば、依頼人の兄が数年前に亡くなったまま、相続登記が手つかずになっていたらしい。 しかし、登記簿を見るとその兄の名前が載っていない。いや、それ以前に誰の名前もなかった。 「登記が無いんですよ」とサトウさんが冷静に指摘したとき、老婦人は「そんなはずは…」と驚きの声をあげた。
登記簿の空白が示す謎
法務局の閲覧記録を調べると、その土地の登記簿は昭和の終わり頃に閉鎖されたものしかなかった。 通常ならば新しい登記が作られるが、それも無い。 まるで、その土地が法的に「存在しない」ことになっているようだった。
空き家の中に残された影
午後、僕とサトウさんはその空き家を訪れた。 雨ざらしの木造家屋は今にも崩れそうで、玄関の鍵も外されていた。 埃の積もった室内には、かつて誰かが住んでいた痕跡がそのまま残っていた。
地元住民の証言と不審な噂
近所の住民に聞き込みをすると、「あそこはね、昔の地主が失踪してからずっと空き家だよ」と口々に語った。 中には、「夜になると灯りがつくんだ」と言う人までいた。 都市伝説的な噂話に、僕はつい顔をしかめたが、サトウさんは眉一つ動かさなかった。
登記簿と現実の矛盾
僕は再度、閉鎖登記簿を精査した。そこに載っていたのは、戦後すぐの古い所有者の名前だけ。 「おかしいですね。この土地、売買の記録が一切ない」と僕が呟くと、 サトウさんは「それ、贈与された可能性がありますね。でも贈与登記がなければ法的には無効です」と即答した。
書類の筆跡が語る真実
ふと、閉鎖登記簿の所有者欄に書かれた署名に目を凝らした。 達筆ながら妙に不自然な箇所がある。どうやら複写か、あるいは筆跡偽造の疑いがあった。 ここから事件は、単なる登記の問題ではないと気づいた。
サトウさんの冷静な視点
事務所に戻ると、サトウさんは机の上に一枚の地図を広げていた。 「この隣接地、2年前に不動産会社が取得してます」と言いながら、目を細めて僕に視線を投げた。 なるほど、無登記地を占有し、境界線をごまかして取得しようとした可能性が高い。
登記簿閲覧の中に潜む手がかり
さらに登記情報提供サービスでその不動産会社の取得経緯を調べると、 申請書に添付された隣地所有者の同意書に違和感のある印影があった。 僕の司法書士としての嗅覚が、「これはニセモノだ」と叫んでいた。
僕が気づいた一点の違和感
押印の日付が、所有者の死亡日より後になっていた。 「死人が押印するのは、幽霊でもなきゃ無理だ」と、思わず独りごちる。 やれやれ、、、こういう時だけ、元野球部の集中力が役に立つ。
サザエさん方式の推理開始
これはもはや完全に「波平の筆跡でなぜかカツオが書いた手紙」状態だった。 つまり、他人になりすました誰かが、勝手に書類を作成したということだ。 この状況、波平さんならきっと「バッカモーン!」と怒鳴っていたことだろう。
司法書士が暴いた隠された取引
結果として、不動産会社の社員が、旧所有者の孫を騙し、 勝手に隣地と一体で申請書を作成していたことが判明した。 虚偽の申請書により、法務局も登記を受理してしまっていたのだ。
犯人の動機は書類の一行
すべては、たった一行の「境界確認済」という記述から始まっていた。 その一行を入れることで、土地をまるごと買収したかのように見せかける。 目的は、区画整理に伴う大規模再開発による転売利益だった。
やれやれ僕の出番か
僕はすべての資料をまとめ、虚偽登記抹消の手続を急いだ。 不動産会社は法的責任を問われ、役員が謝罪に訪れた。 「やれやれ、、、これで少しは静かになるか」と僕はため息をついた。
結末とその後の沈黙
無事に正しい相続登記が完了し、依頼人の老婦人は深々と頭を下げた。 「兄が喜んでると思います」と目を潤ませるその姿に、僕もつい口元が緩んだ。 古びた登記簿は、再び静かに法務局の棚に収められた――何も語らずに。