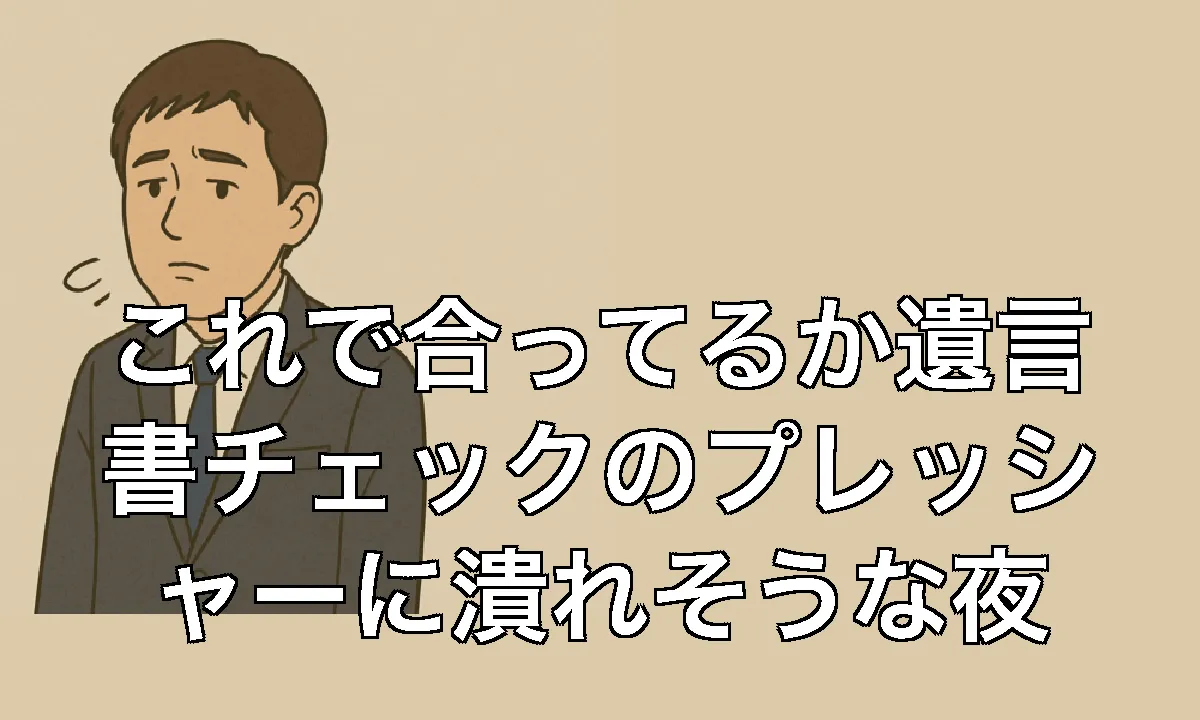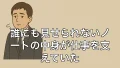遺言書のチェックを任された瞬間に走る冷や汗
依頼人から「これ、先生に最終チェックお願いできますか」と差し出された遺言書。表情には信頼の色が浮かんでいる。だが、その瞬間、背中を冷たい汗がつたう。誰かの人生の最後の意志を、自分が見届ける。この紙一枚に、家族の未来が乗っている。少しでも誤字や解釈違いがあれば、遺族間の争いの火種になる。そう思うと、手が震えてしまう。登記のように書類を揃えれば済む話ではない。文面の裏にある人間関係、想い、背景すべてに目を通す必要がある。プレッシャーの重さは、想像を超えていた。
見落としが命取りになるという恐怖
この仕事にミスは許されないと常々思ってきたが、遺言書のチェックだけは次元が違う。たとえば「長男に財産を相続させる」と書かれていても、「長男」とは誰か、戸籍上の表現と一致しているか、前後の文脈と矛盾がないか、すべて確認しないといけない。「~させる」の語尾ひとつで、法的効力が変わることもある。しかも、その責任はすべてこちらにかかってくる。ふと目を離した一文に、とんでもないトラブルの火種が潜んでいることも。あの日、自分の読み飛ばした句読点が、依頼人の家族にどう響いたのか、今でも忘れられない。
たった一文字の違いが全てを狂わせる
以前、「土地を譲渡する」という文言が「土地を遺贈する」に変わっていたのに気づかず、そのまま通したことがあった。結果、相続人ではない孫に所有権が移ることになり、兄弟間で激しい争いが起きた。結局、内容の修正と再調整に追われ、依頼人の信頼も大きく揺らいだ。たった一文字。それが、家族関係を壊す引き金になる。自分の目が曇った瞬間に、人の人生が変わる。その重みを、自分は軽く見ていたのかもしれない。
他人の人生を左右するという責任
「先生がそう言うなら大丈夫です」——その言葉を何度聞いただろう。そのたびに、心がざわつく。信頼されるのは嬉しい。だが同時に、その信頼の重さが肩に食い込む。「大丈夫」と言ったことが、後々「先生のせいで」と変わる可能性もある。慎重に、冷静に、すべてに目を配る。それでも完璧とは言いきれない世界で、自分はなぜこの役目を引き受けてしまったのかと夜中に自問する。
疲れと焦りで頭が回らない夜
日中に詰まった案件を片付け、ようやく一息ついたのは夜の10時過ぎ。そこからようやく遺言書に向き合う時間が始まる。机の上にはお菓子の袋とコーヒー。目は疲れていても、集中は必要。誤字脱字を見落とさないよう、指でなぞりながら読み進める。でも、気づけば同じ行を何度も読んでいる。まるで砂漠で同じサボテンを何度も見ている気分だ。
遺言の読み込みが終わらない深夜の机
一行ごとに意味を確認し、条文と照らし合わせていく作業は、静かだが重い。事務員はすでに帰宅し、事務所は物音一つしない。キーボードのカチャカチャという音と、自分のため息だけが響く。時計を見れば、もう午前1時。「あと少し」と思いながらも、集中力は限界に近い。間違えられないという意識が、逆に判断力を鈍らせている気さえする。
あの事務所の明かりはまだ点いていた
深夜、事務所の前を通る人がいるかはわからないが、もし誰かが見たら「まだ働いてるのか」と思うだろう。近くのパン屋の職人もすでに寝てるはずなのに、司法書士の自分がまだ働いてる。不思議なもんだ。あの時、隣の事務所の同業者に「そんなに遺言って気張らなくていいんだよ」と言われた。でも、自分にはそれができない。万が一の一行を恐れて、明かりを消せない夜がある。
眠気より怖い判断ミスへの不安
夜が更けると、体が重くなる。まぶたも落ちそうになる。けれど、いちばん怖いのは眠気ではない。うっかりの判断ミスが、次の日の地雷になることだ。依頼人に渡した瞬間、「これは違いますよ」と言われたらどうする? その恐怖が頭を離れず、余計に慎重になる。そして朝方、ようやく終えたチェックリストをプリントして、そっと机に置く。自分なりに全力を尽くしたつもりだが、不安は完全には消えない。
元野球部の自分がここまで緊張するとは
学生時代、甲子園を目指していた頃は、ノーアウト満塁のピンチに立つこともあった。それでも、あの時より今の方が怖い。野球は失敗しても次がある。でも、この仕事はそうはいかない。一発勝負。しかも、相手は法律だ。どれだけ打ち込んでも、正確でなければ意味がない。
ミスできない局面に打席に立つ気持ち
依頼人の遺志を守るというバットを握って、間違いなくボールを打たなければいけない。しかも、審判は誰でもなく、のちに問題が起きたときの家族や裁判所だ。打席に立つ前から、何十もの視線がこちらを見ている気がする。正直、逃げ出したいと思ったこともある。でも、もうここまで来たら、振るしかない。ミスを恐れてバットを構え続けるより、一球一球を正確に見極める力が問われる。
サインに従うだけでは許されない立場
野球では監督のサインに従えばいい。でも、今の自分にはそのサインがない。どこまでがOKで、どこからがNGか、自分で判断しないといけない。依頼人も、上司もいない。最終チェックを下すのは、いつだって自分だけ。責任の矢印がまっすぐ自分に向かっている。それが、こんなにも重く感じる日が来るとは、若い頃の自分は思いもしなかった。
またひとつ髪が抜けていた朝
朝、鏡を見ながら無意識に頭を撫でたら、指に抜けた髪の毛が数本。思わずため息が出た。「またか」。たぶん寝不足とストレスのせいだろう。遺言書のチェックという仕事が、ここまで精神的に削ってくるとは。今日も笑顔で依頼人に書類を返す。自分の内側の不安や疲れは、表に出さない。でも、ふとした瞬間に感じる「限界かも」という心の声が、今日も静かに鳴っている。