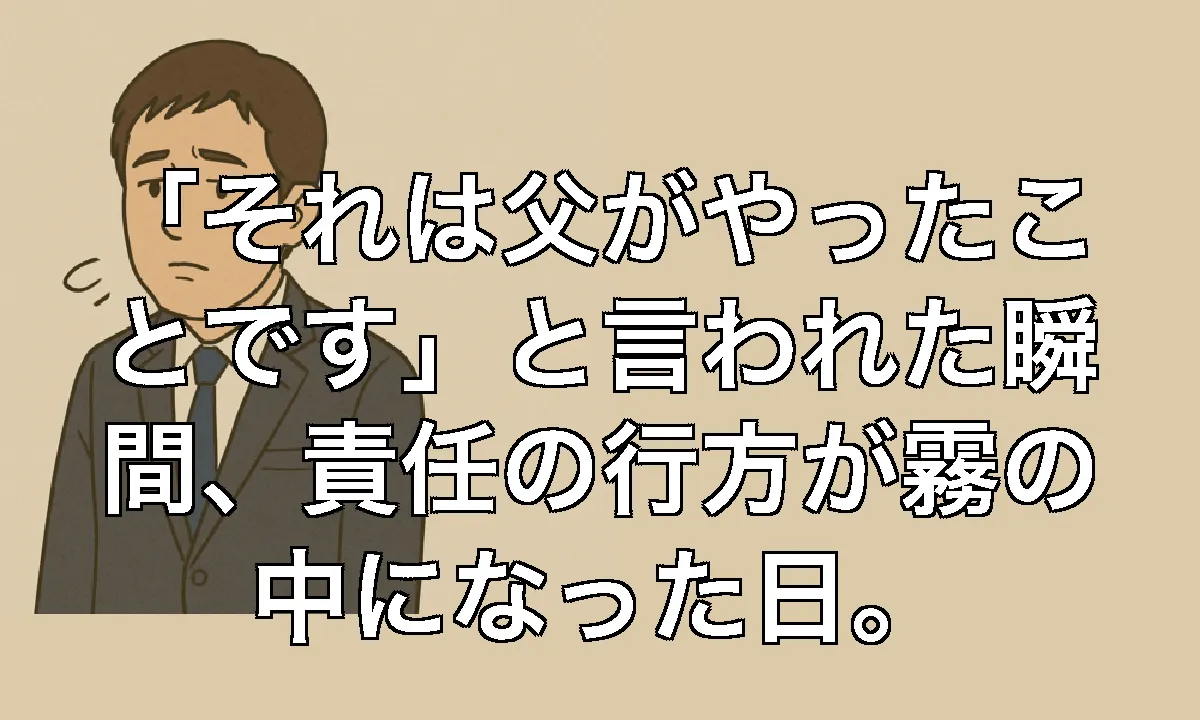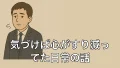誰の責任なのか、わからない案件が一番疲れる
登記の仕事において、最も精神的にくたびれるのは、責任の所在がはっきりしない案件に出くわしたときだ。今回もそうだった。「それは父がやったことです」と依頼人が言い張ったその瞬間、全ての歯車が噛み合わなくなった。書類上は本人名義、しかし行為者は「父」。あまりに曖昧で、手続きの正確性を求められる立場としては地獄の始まりだった。何度確認しても明確にならず、時間と気力だけが削られていった。
「父がやった」と言われた時の、あの独特の沈黙
司法書士として、何度もクライアントと面談していると、ある種の“沈黙の種類”がわかるようになる。「父がやったんです」と口にしたあと、その方の視線が少し泳ぐ。こちらの問いかけに対する返答がどこかよそよそしくなる。その空気に触れた瞬間、ああこれは面倒な流れだな、と内心ため息をつくのが常だ。心の中では「それ、父ってことにしようとしてない?」と何度も突っ込んでいるが、もちろん口には出せない。
質問を重ねるたびに濁る事実
「では、その書類をご自身で用意されたんですね?」と訊くと、「いえ、父が持ってきたものです」と返ってくる。念のため「押印はどなたが?」と尋ねれば、「父が勝手に…かも」と続く。すべてが曖昧。真実をつかもうとすればするほど、霧が濃くなる。真剣に誠実に対応しているこちら側が、まるで“しつこく詮索する人”のような立場になってしまう不条理さがたまらなくつらい。
言い分を尊重するしかない無力感
法律上の処理を行う以上、「事実」を書類と本人の確認で積み重ねる必要がある。しかし、曖昧な主張の前では、それを丁寧に突き崩す術がほとんどない。言い分を否定すればクライアントとの信頼関係が崩れるし、かといってそのまま通せば後々のリスクが残る。そういう板挟みの中で、「まあ、信じるしかないか…」と判断せざるを得ないとき、自分の無力さが嫌になる。
登記の本質は「正しさ」ではなく「納得の形」かもしれない
本来、登記は“事実”を記録する手続きのはずだ。しかし現実の現場では、完全な真実を追求するより、関係者全員が納得し、争いにならない形に着地させることが求められる。まるで職人が見えない傷をパテで埋めていくように。法的には正しくても、納得してもらえなければ意味がない。この感覚が、日々私の中で少しずつ「法律家」という立場を侵食してくる。
誰がやったかより、誰が納得するか
「お父さんが勝手にやった」という主張が、たとえ事実と異なっていても、家族全員がそれで納得しているなら、それが“正解”になってしまう。そんなバランス感覚が求められる仕事だ。登記の正確性と、人間関係のなめらかさの間で、何を優先するか。机上の論理と現実の折り合いをつけながら、私たちは日々、書類と人の間で綱渡りをしている。
正義感では食っていけない世界
昔の私は、もっと「法的に正しくあるべきだ」と強く思っていた。けれど、この仕事を続けるうちに気づいた。正しさを追求しすぎると、誰も得をしない。報酬ももらえないし、クライアントにも感謝されない。そして、事務員さんにも面倒がられる。正義感では食っていけない。そう自覚することで、ようやく自分のスタンスが定まってきた気がする。
地方の現場でよくある「家族ぐるみの言い分」
都市部では「個人」が明確に立っているが、地方では「家族」が一つの単位で動くことが多い。依頼主が息子でも、実際に動いているのは父親だったり祖父だったりする。名義の裏に見え隠れする家族の力関係や歴史が、手続きをややこしくしてしまう。司法書士としては「書類上の人」が主役なのに、実際にはその背後の家族劇場を読み解かねばならない。
父と息子の言い分が食い違う時
「お父さんはこう言ってましたけど」「え?僕はそんなこと聞いてませんよ」。こんなやりとりが繰り返されると、こっちの頭が混乱してくる。誰が正しいのか、という問題ではなく、「誰が一貫して発言できるのか」という信頼性の問題。感情が混じった話を記録の上に載せるわけにはいかず、結局、話の整合性をつけるのに何度も足を運ぶ羽目になる。
家の中のことを、外の人が記録に残すという難しさ
家族間のやりとりは、外から見ればわからないものが多い。だからこそ、司法書士という“外の人間”がそれを記録に残すという行為には、大きなプレッシャーがある。「こういう感じで進めてください」と言われても、「感じ」では登記できない。あくまで証明可能な事実だけを記録しなければならないのに、感情と記憶に振り回される。これが精神的に非常にきつい。
高齢の親が絡むと、余計にややこしい
田舎の案件では、70代80代の親が登場することが多い。耳が遠かったり、記憶が曖昧だったり、でも登記上の権利者である以上、話を聞かざるを得ない。一方で、子ども世代は「もう父はそんなこと理解できないから」と言う。じゃあ誰に確認すればいいんだ…。このやりとりが長期化する原因であり、また自分の中の無力感を強く刺激してくる。
耳が遠い・認知がある・でも権利者
面談の場で「〇〇さん、こちらの内容ご理解いただけますか?」と尋ねると、「はぁ?なんてぇ?」と聞き返されることもしばしば。何度も繰り返すと、こっちが責めてるみたいになってしまい、いたたまれなくなる。けれど、それでも「理解してる」とは言ってもらわねば、手続きは進まない。冷たいようだが、記録を残す人間としては、このあたりの線引きを毎回苦しみながら判断している。