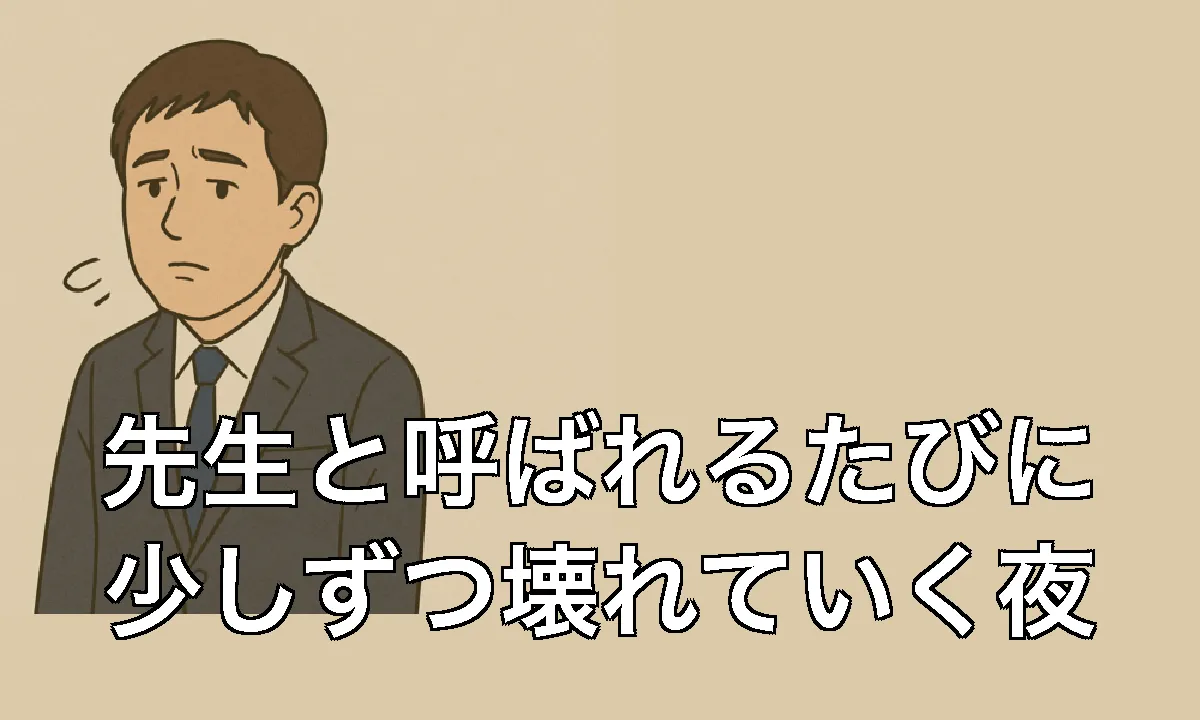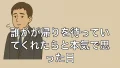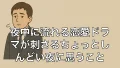自分で選んだはずの道に立ち尽くす夜
司法書士という仕事を選んだのは、確かに自分だった。学生時代、野球部の練習で泥だらけになった帰り道、「人の役に立つ仕事がしたい」と思ったあの感情は嘘じゃない。それでも、今、夜の事務所に一人取り残されて、机の上に積まれた書類を前にすると、ふと「この道で本当に良かったのか」と考えてしまう。誰にも頼れず、孤独の中で“先生”という看板を背負うのは、なかなか堪える。
思い描いていた“司法書士”とのギャップ
開業前の自分は、もっと凛々しくて、頼りがいのある“先生像”を思い描いていた。でも現実は、納税や書類の締切に追われる毎日。朝から晩まで書類に埋もれているだけで、世の中を変えるようなことなんて一度もしたことがない。電話一本、印紙一枚で、クライアントとの信頼がぐらつくこともある。理想と現実のはざまで、どうにも自分が小さく感じる瞬間がある。
「正義の味方」では食っていけなかった
新人の頃は、登記の正義を語っていた。「それは違法ですよ」と強く言えた時代もあった。でも経験を重ねるほどに、現実のグレーゾーンに足を踏み入れざるを得なくなる。正論だけでは食っていけない、そう痛感したのは、初めて“妥協”したときだった。どこかで割り切ってしまった自分に気づいて、帰りの車でひとり反省する。あれからずっと、「正しいこと」と「食えること」の間で揺れている。
なぜかしっくりこない“先生”という呼ばれ方
「先生、いつもありがとうございます」と言われるたび、ありがたい反面、どこかこそばゆい。自分が“先生”にふさわしいのか、未だにわからない。駅前のラーメン屋で、学生時代のジャージ姿のままの同級生とすれ違うと、「俺は何になったんだろうな」と思ってしまう。先生って、こんなに虚しく響くものだったか?と、自問する夜は少なくない。
先生って呼ばれるたびに背筋がこわばる
人は尊敬を込めて「先生」と呼んでくれる。でもその呼び名の裏にある期待や責任が、時に重く感じる。何かを背負って生きるというのは、言葉にするとかっこいいが、実際は息苦しい。肩書きにふさわしい振る舞いをしなければというプレッシャーが、どんどん自分を硬くしていく。
世間の期待と自分の中のちいさな違和感
「先生ならなんとかしてくれるだろう」と思われるのは、ありがたい。だが、どこかで“それ、俺がやるべきことなのか?”という違和感が残る。依頼人は人生の一部を預けるような気持ちで頼ってくるけれど、こちらは毎日、同じような登記を処理しているだけ。いつの間にか、期待と現実の間に、大きなズレが生まれていた。
名刺に刻まれた肩書きに負けそうになる
名刺には立派に「司法書士」と書かれている。でもその文字を見るたび、「俺、本当にそんなに立派かな」と思ってしまう。お客様から見れば「プロ」でも、自分の中ではまだまだ未熟で、わからないことも多い。肩書きが自分より一歩先に歩いていってしまうようで、追いつけない自分に焦りばかりが募る。
先生と呼ばれる自分と、ラーメン屋でぼんやりしている自分
夜中に一人、ラーメンをすすりながら、ネクタイを緩めてふと思う。「先生って誰のことだ?」と。昼間は“先生”として振る舞い、夜はただの独身男性。ギャップがありすぎて、同じ人間とは思えない。自分の中にいる“先生”と“ただの俺”が、仲良くなれないまま共存している。いつかどちらかが壊れるんじゃないかと、ふと怖くなる夜がある。
なにかを背負うには、ちょっと疲れすぎていた
誰かの人生を預かる仕事。責任があることは重々承知しているけれど、正直、疲れている。事務員に気を使い、依頼人に頭を下げ、税理士や弁護士と連携しながら、どこかで自分を後回しにしている。そんな日々が積み重なると、ちょっとしたことで崩れそうになる。
相談は受けるけど、こっちも誰かに相談したい
相談される立場というのは、時に孤独だ。誰も「あなたは大丈夫ですか?」とは聞いてくれない。弱音を吐けば、信用を失うんじゃないかと怖くて言えない。だから、笑顔を貼りつけて、今日もまた誰かの相談にのる。ほんの少しでいい、自分の話も誰かに聞いてほしいと思う夜がある。
仕事は山ほどあっても、心を預ける人はいない
仕事の電話は鳴る。メールも山ほど届く。だが、プライベートのLINEはほぼ鳴らない。気づけば、誕生日もクリスマスも、誰とも過ごさずに終わる。誰かの人生を支えることはできても、自分の人生を支えてくれる人は見当たらない。そんな日々が続くと、「先生」って何だろうと、ますますわからなくなる。
“頼られる”ことが、なぜか寂しい
誰かに頼られるというのは、本来嬉しいことのはずだ。でも、その頼られ方に「役割」しか感じられないと、どこか寂しさが残る。「先生」ではなく、「あなた」として必要とされたい。それなのに現実は、都合の良い“専門家”としてしか見られていない気がして、心の奥に冷たい風が吹く夜がある。
それでも誰かの役に立っていたいと思ってしまう
それでもやっぱり、依頼人の「助かりました」という一言があると、もう少しだけ頑張ろうと思ってしまう。不器用だけれど、自分なりに誠実にやっている。それだけで十分じゃないかと、時々自分に言い聞かせる。壊れそうになっても、“先生”であることをやめられない自分がいる。
報酬より、ありがとうの一言で救われた夜
印紙代を立て替えたのに謝りもせず、連絡もくれない依頼人に疲れ果てていた日。別の依頼人から届いた手書きの「ありがとうございました」の文字に、涙が出そうになった。報酬じゃない、感謝だ。そう思える瞬間がある限り、この仕事を投げ出すことはできない。
他人の人生を支えることで、自分が保たれている
誰かの役に立っている実感が、自分の存在価値を証明してくれる。それがなければ、自分はとっくに壊れていただろう。司法書士という肩書きは、ただの名札じゃない。きっと、誰かのために立ち続ける理由そのものだ。だから、今日もまた事務所の明かりをつけて、一日を始める。
今日もまた、誰かの「先生」でいようと思う
いろいろあるけど、やっぱり今日も“先生”と呼ばれる仕事を選ぶ。壊れそうになっても、迷っても、それでもやめない自分を少しだけ誇りに思う。誰かの支えになれるなら、それだけで十分かもしれない。今日もまた、先生と呼ばれて背筋を伸ばす。ほんの少し、心が壊れかけていても。