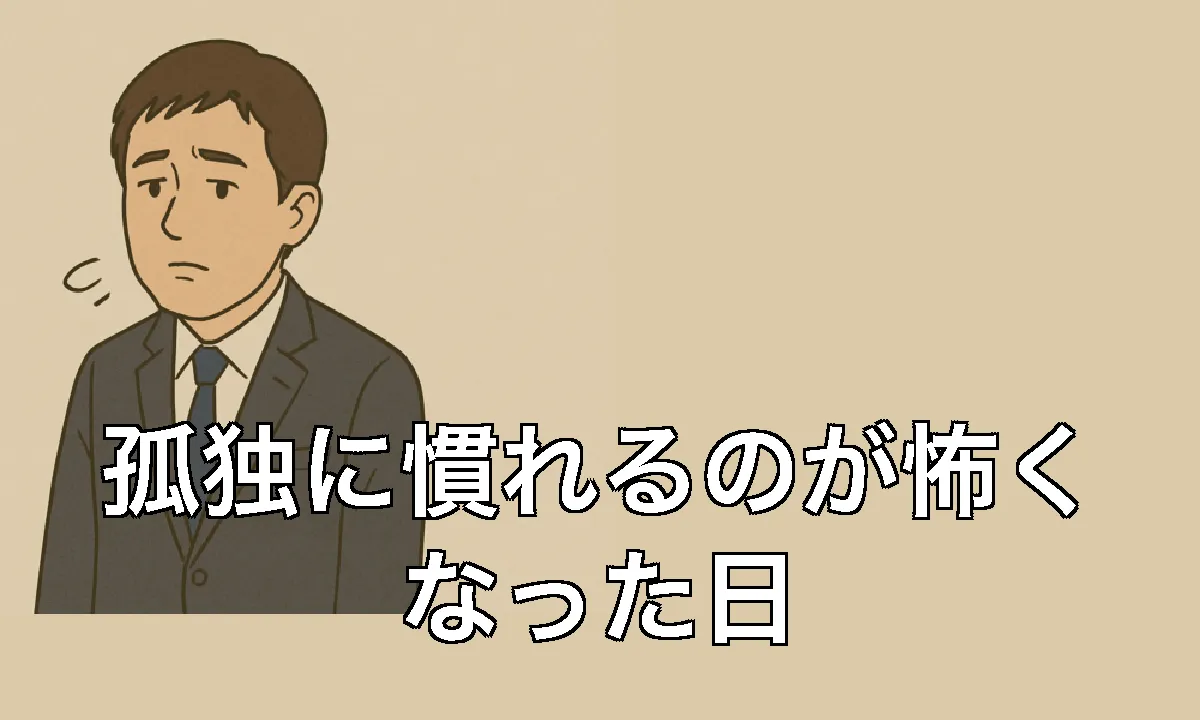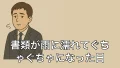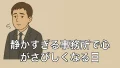孤独に慣れるのが怖くなった日
気づけばひとりでいることが当たり前になっていた
司法書士として地方で事務所を構えてもう十数年。最初のうちは、誰かとつながっていたいと思っていた。仲間との飲み会もあったし、休日に野球の草チームに顔を出すこともあった。だけど、年齢を重ね、仕事が忙しくなり、誘いを断ることが増えていくうちに、いつの間にか「誰かと過ごす時間」より「ひとりでいる時間」が当たり前になっていた。誰かに会わなくても不自由を感じない。むしろ、気を遣わなくて済む分、楽だとさえ思うようになっていた。でも、ある日ふと、そんな“楽さ”が薄ら寒く感じた。これは孤独に“強くなった”んじゃなくて、“慣れてしまった”だけなのかもしれない。
依頼人との会話はあるけれど
仕事柄、人とまったく話さないということはない。依頼人と面談することもあるし、電話対応もある。でも、それはあくまで「業務」であって、「会話」じゃない。例えば、相続の相談を受けながら、こちらは法的な整合性ばかりを考え、相手の感情に寄り添う余裕がなくなっていることに気づいた瞬間、自分が人としての何かを置き去りにしているような気がして、ゾッとすることがある。事務員さんとは最低限の会話しか交わさないし、雑談なんてもう何ヶ月もしていない。孤独って、誰もいないことじゃなくて、誰かがいても繋がれていないことなんじゃないかと思う。
家に帰っても無音の部屋
夜、事務所を出て自宅に戻る。玄関の扉を開けると、当然誰もいない。冷蔵庫の音と換気扇の風だけが聞こえる部屋に、ため息をつきながら靴を脱ぐ。テレビをつけることもなく、スマホをいじりながらインスタントの夕飯をすする。そんな毎日を何年も繰り返してきたのに、なぜか最近になって、その「静かさ」が怖く感じるようになってきた。若い頃は「自由」だと思っていたこの時間が、今はただ「空っぽ」なだけに思える。
独り言が増えたことにふと気づく瞬間
気づけば最近、無意識に独り言をつぶやいていることが増えた。書類を整理しながら「これは後でいいか…」とか、「あーあ、やっぱ間違ってたか」なんて誰に聞かせるでもなくつぶやく自分に、ハッとすることがある。誰かに向けて発しているわけでもない、でも黙っていられない何かが、心の中に溜まっているんだと思う。孤独に慣れるって、こうやって少しずつ、自分自身との対話しかできなくなっていく過程なのかもしれない。
テレビの音量を上げるのは寂しさの裏返し
テレビをつけても観たい番組があるわけじゃない。ただ、音がないと不安になるだけだ。最近は音量を少し大きめに設定している。静寂が怖い。誰かの笑い声、騒がしいニュース、無意味なバラエティの音。全部が「自分はひとりじゃない」と思い込ませてくれる材料になる。そんな自分を客観的に見て、情けなくなる反面、「こうでもしないと、精神的に壊れてしまうのかもしれない」と思うこともある。
仕事に追われていれば寂しさは感じないと思っていた
司法書士の仕事は、やろうと思えばいくらでもある。登記、遺言、相続、成年後見、そして補正、補正、補正…。それに対応するだけで、1日が過ぎる。でも、仕事をしているときは確かに寂しさを感じない。だからこそ、意識的に自分を忙しくしていたのかもしれない。だけどそれは、単なる逃避でしかなかった。タスクを終えた夜、ふと天井を見つめて、「今日、自分は何をしたんだろう」と思う瞬間がある。
目の前の案件をさばくだけで精一杯
毎日が〆切との勝負。補正通知が来れば即座に対応しないといけないし、登記完了までの時間との戦いに追われる日々。ミスは許されないし、気を張っていないと簡単に信頼を失う仕事だ。でもそれゆえに、感情を殺して生きている部分がある。嬉しいことも、悔しいことも、誰かと分かち合う時間すら惜しんでしまう。笑うことが減ったし、泣くことも減った。そのうち「感情が薄くなった」とさえ感じるようになった。
終わった瞬間に押し寄せる虚しさ
仕事が終わると、ふと気が抜ける。静かな部屋で椅子にもたれ、目を閉じて「さて、何をしよう」と思った瞬間、何も浮かばない。若い頃はゲームをしたり、スポーツニュースを見たり、それなりに楽しみもあった。でも今は何も楽しめない。酒を飲んでも酔わないし、食事もただ胃を満たすだけ。達成感もない。成果が出ても、誰かに褒めてもらうわけでもない。自己満足で生きていくには、人間ってあまりにも脆い。
「今日は誰とも目を合わせなかったな」と思う夜
ある日ふと、「今日、誰とも目を合わせなかったな」と気づいたことがある。事務員さんはマスク越しに事務処理の報告をするだけで、こちらも目線を合わせないまま返事をした。依頼人とは電話だけ。コンビニの店員とはセルフレジ。誰かの目に自分が映っていた時間がゼロの日。それは単なる「ひとり」じゃない、存在が希薄になるような怖さだった。こんな日々に慣れていく自分が、何よりも怖かった。
誰かと深く関わるのが怖くなっていた
思えば、人と深く関わるのが苦手になっていた。若い頃は恋もしたし、友達と語り明かしたこともあった。でも、うまくいかなかったことが続くと、少しずつ自分から距離を取るようになっていく。「どうせうまくいかない」「面倒なことになるくらいなら最初から深入りしないほうがいい」そんな考え方が、今の孤独を招いたのかもしれない。自分で自分を孤立させていたという現実に、ようやく向き合い始めている。
忙しさを理由にして距離を置く癖
「仕事が忙しいから」という言い訳はとても便利だ。誘いを断る理由になるし、自分の本心を隠す盾にもなる。だけど、実際は心のどこかで「人と関わるのが怖い」と思っているのだ。特に司法書士という職業は、冷静さや中立性が求められる分、プライベートでも感情を出すのが下手になる気がする。人に弱みを見せるのが下手で、だからこそ孤独を招く。忙しさは「防波堤」であって、「救い」ではなかった。
人間関係に踏み込まないほうが楽という選択
人付き合いにはエネルギーがいる。言葉を選び、相手の気分を読み、場の空気を壊さないように気を張る。そんなことに疲れて、「一人のほうが楽」と思ってしまう瞬間がある。実際、何も気を遣わなくていい生活はストレスが少ない。けれど、それは一時的な安らぎであって、長く続くと「味気なさ」に変わる。やっぱり人は、人と関わってこそ、心が温まるんだと最近思うようになった。
でもそれは本当に「楽」だったのか
結局、「楽」を選んできたつもりが、今は「苦しさ」に変わってきている。関係を築く努力を放棄した結果、心を通わせられる相手がいなくなってしまった。楽をした報いなのかもしれない。寂しさに鈍感になりすぎて、ふとした拍子にその重さに押しつぶされそうになる。「慣れ」とは、必ずしも「良いこと」じゃない。孤独に慣れるということは、心の大事な感覚を失っていく過程でもあるのだと、ようやく理解した。