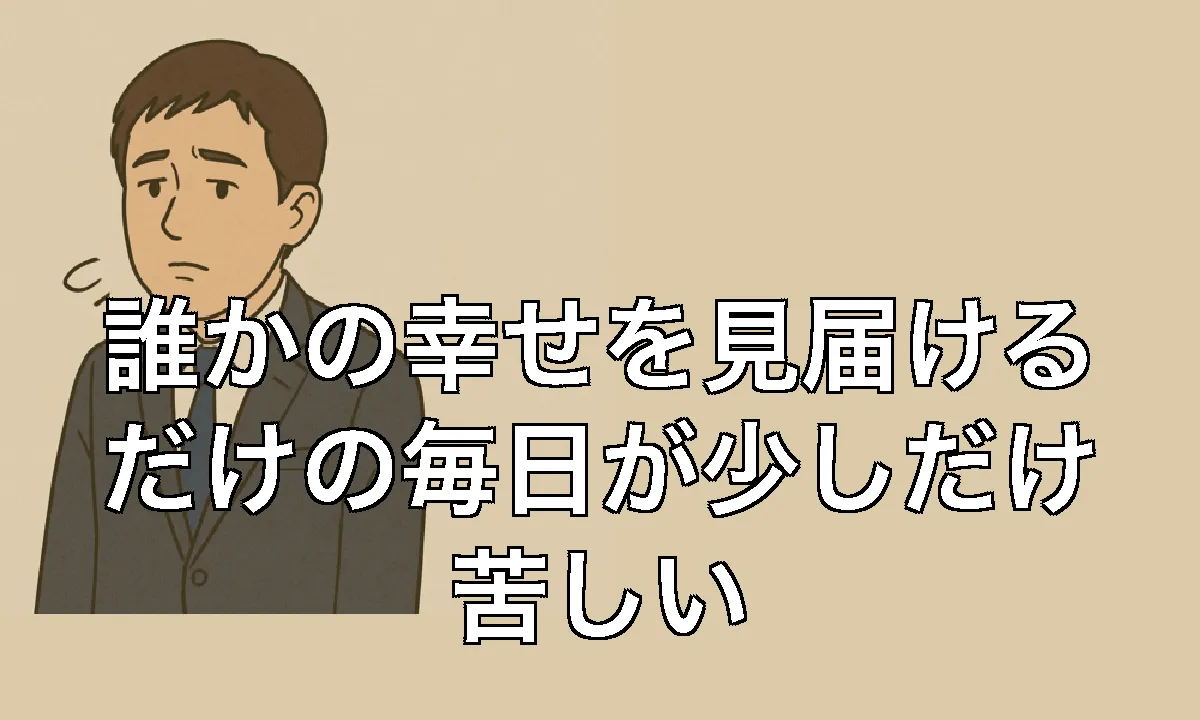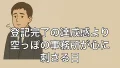幸せそうな誰かを送り出すたびに
司法書士という職業柄、多くの人の節目に立ち会うことになる。結婚、相続、登記変更。そこには、たいてい「おめでとうございます」「よかったですね」と言える空気が流れている。こちらも表情だけは笑っているし、形式的には感情を込めた言葉をかける。でも、終わって事務所のドアを閉めると、ふと深いため息が出る。そのたびに、「また自分は見送る側か」と、胸の奥に冷たいものが残る。人の幸せは祝福して当然なのに、なぜこんなに虚しくなるのだろう。
先生のおかげです その言葉が重たく感じる日
「本当に助かりました、先生のおかげです」——そう言われるのはありがたいことだ。でも、その言葉を聞けば聞くほど、自分の存在価値を“人の幸せに奉仕すること”でしか感じられなくなっていく。しかも、こちらの心の中までは見透かされることはない。ただ業務をこなした結果としての感謝。それ以上でもそれ以下でもない。だからこそ、感謝の言葉すら時に空虚に響いてくるのだ。
手続き完了の瞬間が一番のクライマックス
結婚登記にしても、不動産の名義変更にしても、全てはその「手続き完了」の瞬間に集約されている。法務局に提出され、受理された書類。それが証拠であり結果であり、証明である。依頼者はそこで一区切りとなり、満面の笑みで帰っていく。残されたこちらは、静かなデスクに座り、報酬を記帳し、次の依頼を待つだけ。自分の役目は、その「クライマックス」の舞台裏にすぎない。
けれどそこに自分はいないような感覚
そうした仕事の積み重ねの中で、いつしか「自分がここにいる」という実感が薄れていった。確かに署名も押印もしたし、手続きを行ったのはこの手だ。それでも、どこかで心だけが置き去りになっている感覚が拭えない。幸せそうな人たちの物語の中に、自分は一度も出演していない。舞台袖からスポットライトを見ているだけ。そんな思いが、年々色濃くなってきている。
結婚登記の書類を眺めながら
結婚する二人が持参した書類。名前が連なり、住所が変わり、新しい家族の始まりを記す文書。見慣れているはずなのに、たまに目に止まってしまう瞬間がある。その瞬間、妙な感情が込み上げてくる。「ああ、この人たちはこれから一緒に暮らしていくんだな」と思う一方で、「自分には一体何が残っているんだろう」と、問いが脳裏をかすめる。事務所に戻れば現実が待っているが、その書類だけが何かを教えてくれる。
笑顔の依頼者と書類の隙間にある孤独
依頼者の笑顔は本物だ。それを否定するつもりはまったくない。ただ、その笑顔の裏側にある“自分の存在感の薄さ”に打ちのめされることがある。彼らのストーリーに登場する「先生」は、ただの助演であり、すぐに忘れられてしまう存在だ。何かを成し遂げたというより、手伝ったに過ぎない。そう割り切るべきなのに、感情はそう簡単に整理できるものではない。
祝福の言葉が口先だけにならないように
せめてもの抵抗として、祝福の言葉はできる限り丁寧に、本心から伝えるようにしている。口先だけになってしまったら、この仕事の意味がさらに薄れてしまいそうで怖い。相手にとっての一大事に立ち会っている以上、その時間を誠実に受け止めたい。それがたとえ、こちらの心にぽっかり穴をあける結果になったとしても。
それでも心のどこかで刺さる棘
どれだけ丁寧に振る舞っても、どれだけ感情を込めても、心の片隅にはいつも小さな棘が残る。それは嫉妬でもなく、羨望でもない。ただ、欠けたピースを見せつけられるような感覚。その棘は日を追うごとに抜けにくくなり、いつの間にか日常に溶け込んでいく。
独身のまま司法書士として生きてきて
気づけばこの歳まで独身だ。婚活だのマッチングアプリだの、そんな話題には正直ついていけない。そういうものに乗り遅れた、というより、最初からその車両には縁がなかった。仕事に集中していたら時が過ぎた、というのも言い訳だ。本当は、何かを恐れて踏み出せなかっただけかもしれない。
モテないとか もうそういう次元ではない
よく冗談まじりに「モテない」とか言って笑い飛ばしているが、もうそういう段階でもない。需要の問題でも、魅力の問題でもなく、根本的に“人と生きる”という選択肢を遠ざけてしまった気がする。仕事ばかりしているからじゃない。たぶん、自分で自分を狭くしてしまっていたのだ。
選ばなかったのか 選ばれなかったのか
「選ばなかった」と思えばカッコがつく。でも「選ばれなかった」と思えば、少しだけ胸が苦しい。真実はきっとその中間なんだろう。誰かを見送ってばかりの人生で、気づいたときには、自分の隣に誰もいなかった。それだけの話だ。
事務所に響くキーボード音が答えのようだ
夕方、依頼者も事務員も帰った後の事務所。静寂の中に響くキーボードの打鍵音だけが、自分の今を証明している。それが心地よくもあり、虚しくもある。もう一人の自分が、その音を聞いて「それでいいのか?」と問いかけている気がする。