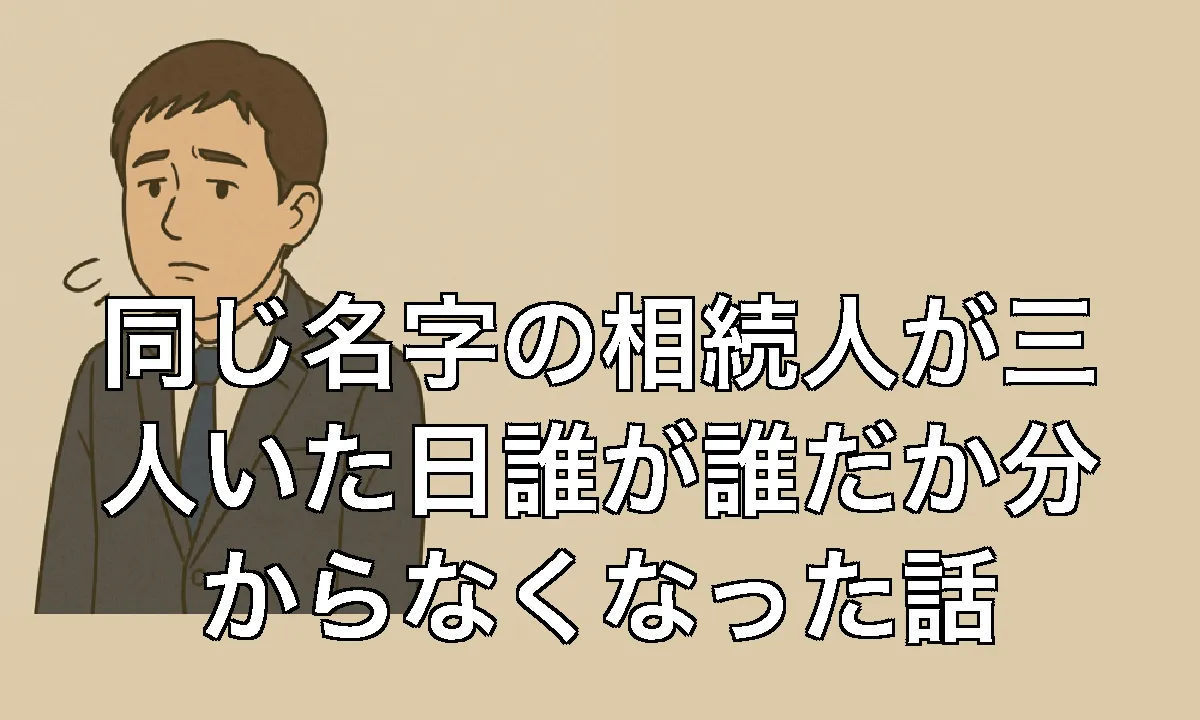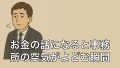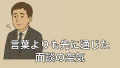相続の現場で起きた一つの混乱
あの日の午前中、何か嫌な予感がしていたんです。普段通りに登記の書類を確認しながら、電話と来客対応をこなしていたところ、「相続人が三人います」というご相談がありました。書類を見た瞬間、違和感がありました。三人とも同じ名字で、しかも似たような名前。え? これって一体誰が誰なんだ? というのが正直な第一印象でした。名字が同じだからと言って、ここまで混乱するものかと自分でも驚きました。地方の司法書士としていろんな苗字には慣れているはずだったんですが、今回ばかりは対応を誤れば手続き全体が止まってしまうと感じました。
名字が同じ相続人が三人登場した瞬間
相談者が持ってきた資料を広げると、そこには「田中 太郎」「田中 次郎」「田中 三郎」と並んだ名前が。思わず「これは冗談ですか?」と聞き返しそうになりました。でも、もちろん本気。しかも三人とも兄弟ではなく、従兄弟関係だったんです。法定相続人としての位置づけはそれぞれにあるのですが、本人確認のたびに頭がこんがらがる。電話で「田中さん」と呼んでも「どの田中さんですか?」と聞き返される始末。まさに“田中地獄”でした。
書類に記載された氏名の違和感
書類上では一応フルネームで区別できるんですが、問題はその先。本人確認の際に「田中 太郎さんですね?」と尋ねても、「はい、でも私の母方の戸籍がこうで…」と話が脱線していく。補足情報がむしろ混乱を招くことになり、結果的に私は同じ書類を三度確認する羽目になりました。書類は正しくても、脳みその中が処理しきれなくなってくるというか。たかが名字、されど名字。これほどまでに“同じ名前”の威力に打ちのめされたのは初めてかもしれません。
電話口で呼び間違えるたびに増すストレス
電話対応ではさらに地獄を見ました。「田中さんですか?」と聞くと「どの?」となり、しまいには「前に話した田中です」と言われても、どの田中かさっぱり。手帳に特徴や話した内容をメモしておくんですが、似たような内容でどれが誰だったかが曖昧になる。結果的に三人に同じ話を繰り返してしまい、向こうも不信感を抱いたようでした。こっちだって好きで間違えてるわけじゃないのに…とため息しか出ませんでした。
最初は軽く考えていた名前の重なり
正直、最初は「まあ何とかなるだろう」と思っていたんです。珍しい名前でもないし、戸籍や書類をしっかり見れば区別がつくはず、と。しかし、実務はそんなに甘くなかった。名前が同じだと、すべてのやり取りに一手間かかる。郵便物一つ取っても、誰宛なのか分かりづらいし、封筒に「田中様」としか書かれていなければ全員該当するようなもの。現場の混乱って、こういう小さな違和感の積み重ねで爆発するんだなと痛感しました。
字の違いを説明されても頭に入ってこない
漢字が違うんです、と言われても、例えば「太郎」と「太朗」みたいな違いって、口頭で聞いてすぐにピンと来ないんですよ。相手はその違いで完全に分かっている前提で話してくるので、こっちが一瞬でも戸惑えば「前も説明しましたよね?」みたいな空気になる。そこまで自信満々に言われると、こちらが悪いような気すらしてくるんですよね。でも内心では「こんなの毎回正確に覚えられるか」と思ってました。
手書きメモが役に立たないレベルの混乱
普段はメモ魔のようにメモを取っている私でも、この時は限界を感じました。というのも、全員の名前が似ていて、それに加えて話す内容や性格も似通っていて、メモを読み返しても「田中さん=?」としか思えない状態に。結局、自分の頭で整理できない情報は、いくら記録しても意味がないんだなと痛感しました。人の記憶って意外とアテにならないんですよ。司法書士やっててこのレベルの混乱に陥るとは…なかなかショックでした。
業務の進行が止まることへの苛立ち
この混乱が長引くと、自然と他の業務にも支障が出てきます。次の依頼が入っているのに、前の案件が処理できない。頭の中が整理できていないから、集中力が落ちて、ミスも増える。仕事の効率って、こういうところから崩れていくんですよね。そしてそのストレスは、気づけば態度や言葉に現れてしまい、事務員にも当たってしまう。自分で自分が嫌になる瞬間です。
自分の処理能力に自信をなくした日
何のためにこの仕事を選んだんだろうと考えました。昔はもっとシャープに頭が動いていたはずなのに、今は目の前の情報すらまともに整理できていない。電話を切るたびに「ああ、また混乱させた」と後悔する。こんなに自信をなくしたのは、司法書士試験に落ちたとき以来かもしれません。歳のせいか、仕事の重さがどんどん肩にのしかかってくるように感じます。
忙しい日に限ってこういう案件が来る
なぜか忙しい日に限って、ややこしい案件がやってきます。それも、こっちの余裕がない時に限ってです。不思議とそういう引き寄せがあるんですよね。冷静に対応すればなんてことないことも、心に余裕がないと、すべてが爆発の導火線になります。電話一本で感情が揺れるような、そんな日が続くと「もう全部休みたい」と思うこともあります。
電話対応で心がすり減っていく感覚
一件一件は短い電話でも、それが連続すると消耗が激しい。特に「また田中さんか…」と思うたびに、気持ちが重くなっていく。最初のころは丁寧に応対していたけど、途中から言葉が荒くなってきたのが自分でも分かるんです。自己嫌悪にもなりますが、それでも仕事は止められない。この仕事って、気持ちの切り替えが本当に難しいんですよね。
解決に向けた一筋の工夫
こんな状況でも、なんとか打開しないといけない。そこで思いついたのが、相関図とあだ名の導入でした。それぞれの関係性を図にして壁に貼り、さらに「長男田中さん」「市外田中さん」などと呼び分けるようにしたら、ようやく混乱が和らぎました。アナログだけど効果絶大。情報を整理するだけで、精神的な負担もグッと軽くなるんですよね。
相関図とあだ名の導入でようやく整理
最初は面倒に思えたんですが、紙に書いて視覚的に整理することで一気に楽になりました。関係性を図で見ると、「誰が誰の子か」「誰がどの家に住んでいるか」などが一目瞭然。あだ名も、本人に了承を得てから使うことで混乱が減りました。やっぱり、人間の脳は視覚に強いんだと改めて実感。もっと早くやっておけばよかったと思いました。
一歩引いて見たら見えてきた関係性
問題にどっぷり浸かっていると、見えるものも見えなくなります。でも、一歩引いて図にしてみると、なぜこんなに混乱していたのかが見えてきました。「情報の塊」ではなく、「一人ひとりの物語」として関係を見ることで、ようやく頭が整理されたというか。司法書士って、結局“人の話”を聞く仕事なんだなと再確認しました。
冷静になるために一人で散歩した昼休み
もうどうにもならないと思った昼、少しだけ事務所を抜けて近所の川沿いを歩きました。風が気持ちよくて、少しだけ頭がクリアになったんです。そのあと事務所に戻って相関図を描いてみたら、すっと整理が進んでいきました。焦るときほど、立ち止まる勇気が必要なんですね。仕事に追われていると忘れてしまいがちですが、こういう時間って本当に大事です。
同姓問題に備えた今後の対策リスト
今回の件を教訓に、今後は「名前が似ている相続人が複数いる場合」の対応マニュアルを作ることにしました。相関図の作成、あだ名の使用許可、メモの書き方などを明文化。将来の自分がまた同じ混乱に陥らないように。たとえこの業務が誰にも評価されなくても、少しでも自分のストレスを減らせるなら、それだけで十分です。