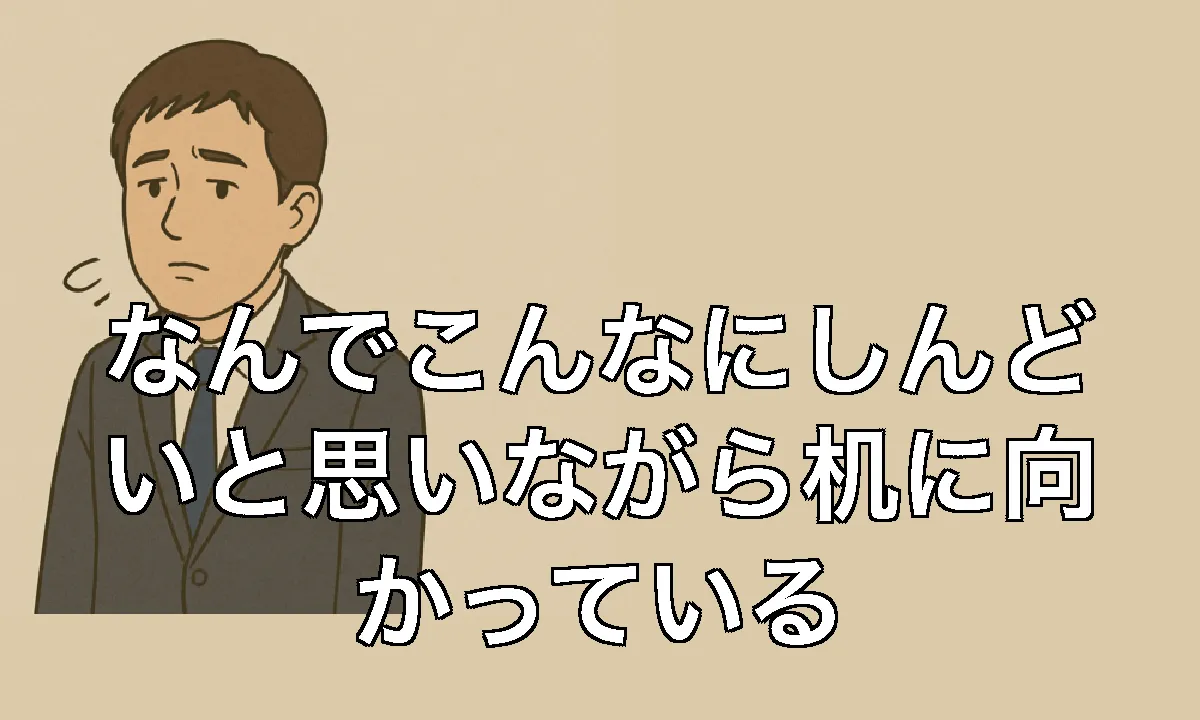しんどいと感じる朝の始まり
朝、目が覚めた瞬間から、もうしんどい。枕元のスマホを手に取り、通知の数にため息。カーテンの隙間から光が差し込んでいて、「あぁ、今日も始まってしまったな」と思う。目覚ましが鳴る前に目が覚める日は、大抵、何かの心配ごとがある。そんな日は、もう一度布団に潜り込んでも眠れず、ただ天井を見つめるだけ。気持ちのどこかで「もう嫌だな」と思いながらも、身体は勝手に着替えを始めている。誰も代わりはいないし、今日も一人で事務所を開ける。
目覚ましが鳴る前から憂うつ
最近は目覚ましの音を聞く前に、自然に目が覚めることが増えた。年齢のせいもあるかもしれないが、それ以上に心がざわついているのだ。前日のお客様対応で気になった言葉、メールの返事が遅れていること、申請のミスがないか……そんなことが頭をぐるぐるして眠りも浅くなる。思えば、司法書士になりたての頃はもっと希望があった。「自分が誰かの役に立てる」って誇らしかった。でも今は、目覚めた瞬間から心がずっしりと重たい。
夢の中ですら仕事の続きをしている
先日は、夢の中で登記簿をチェックしていた。何件も申請を抱えている状態が夢にまで出てくると、「もう少し仕事と距離を取りたいな」と思う。でも、結局は翌日も同じ書類と向き合っている。まるで終わりのないループ。休日すらも心が休まらない。おそらく「ミスしてはいけない」という意識が常にあるからだろう。責任感なのか、被害妄想なのか、どちらにしてもぐっすり眠れる夜はめったにない。
事務所のドアを開ける手が重たい
通勤途中、ふとコンビニに寄ってコーヒーを買う。事務所の前に立った瞬間、カギを取り出す手が止まる。「このドアを開けたら、今日も戦いが始まる」──そんな気分になる。誰かが待っているわけでもない。事務員の子はまだ来ていない時間。でも、机の上のファイルや受信メールの山を想像するだけで、足取りが鈍る。立ち止まって、深呼吸して、ようやく鍵を差し込む。たかが数秒、されど毎朝繰り返される儀式のようなものだ。
誰にも頼れないという孤独
司法書士という仕事は、意外と「一人職場」が多い。事務員を一人雇っているが、結局のところ責任の最終地点は自分にある。誰かに相談したところで、専門的すぎて共感されづらいし、同業の友人とは愚痴を共有する程度。気軽に「ちょっとこれお願い」と投げられる相手がいない日々は、静かな孤独に似ている。誰にも頼れない、でもやらなきゃ終わらない。それがこの仕事のリアルだ。
一人雇ってるけど結局全部自分が背負う
今の事務員さんは、明るくてよく働いてくれる子だ。でも、登記申請や法的判断など、専門性が問われる部分はすべて僕が見る必要がある。事務所の電話が鳴った瞬間、たとえ昼食中でもすぐに出る。急ぎの案件、急な来客、登記漏れの連絡。全部自分で対応しなきゃという気持ちが抜けない。ある意味で「誰かに任せることが怖い」のかもしれない。その結果、いつまでたっても肩の荷が下りない。
専門職の壁と事務との板挟み
司法書士は「実務家」だと思われがちだが、意外と泥臭い作業も多い。申請のための書類チェック、補正対応、取引先との連絡……。事務仕事と法律知識の両立は難しく、どちらかを疎かにすればすぐに信頼を失う。自分が板挟みになる感覚は、元野球部時代のキャッチャーを思い出す。ピッチャーの癖も、バッターの動きも見て、チーム全体を支える役割。それに似て、今の自分も見えないところで全体を支えている気がする。
先生って言葉がプレッシャーになる日
「先生、お願いします」と言われるたびに、正直、少し気が重くなる。信頼の証なのはわかっている。でも、自分の中では「先生」ほど似合わない言葉はないと思っている。だって、心の中はいつも不安だし、書類のミスに怯え、支払いの遅れに悩み、人間関係にもビクビクしている。そんな自分が「先生」と呼ばれるのは、どこか居心地が悪い。名前で呼んでもらえる方が、気持ちが楽になるのに。
それでも続ける理由
ここまでネガティブなことばかり書いてしまったけど、それでもこの仕事を続けているのは、「ありがとう」の一言に救われる瞬間があるからだ。書類の束を抱えて帰っていった依頼人が、ふと帰り際に見せた笑顔。それが、ふと心の奥に温かく残る。「ああ、自分はまだ人の役に立てているのかもしれない」──そんなふうに思える瞬間が、ぎりぎりの心をつなぎとめてくれている。