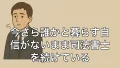気づけば今日も始まってしまった
朝起きた瞬間、もう気力が湧かない。眠りの質が悪かったのか、単に疲れが取れていないのか、自分でもよくわからない。だけど、そんなことを考える余裕もなく、いつものように顔を洗って、無理やりネクタイを締める。何年も同じルーティンを繰り返しているのに、今日は特に何もかもが億劫だ。司法書士としての責任感?そんなものはとっくに霧散して、ただ「行かなきゃ」という義務感だけで足を前に進めている。
頭が回らない朝のルーティン
いつもと同じように事務所のドアを開け、書類の山と向き合う。それだけなのに、まるで脳が砂を噛むような感覚で働かない。事務員の彼女が「おはようございます」と声をかけてくれるが、その挨拶すら受け止める余裕がない。返事をしながらも、頭の中は空っぽで、何を優先して手をつけるべきかの判断がつかない。ルーティンはただの形式にすぎず、意識は半分、どこか遠くに行っている。
コーヒー一杯で乗り切れるはずがない
デスクに座ってとりあえずコーヒーを淹れてみる。こういう時は温かい飲み物で気分を整えようとする癖がある。けれど、その日ばかりは全然効かない。むしろ胃がむかついてきて、余計に不快感が増すばかりだ。何杯飲んでも頭はぼんやりしたまま。こんな状態でクライアント対応なんてできるのか、自分でも不安になってくる。
事務所の鍵を開けた瞬間に後悔が始まる
今日は何か嫌な予感がしていた。実際、事務所の鍵を開けたときからその直感は当たっていたのだろう。コピー用紙が切れている、FAXが紙詰まりしている、そんな些細なことすら、妙にイライラする。何よりも「このまま今日が始まってしまう」ことに対する絶望感のほうが大きい。仕事が嫌いなわけじゃない。ただ、全部が重たく感じるだけだ。
「またやったか」と思った瞬間
その日は午前中に不動産の登記申請が一件あった。内容自体はそこまで難しいものではなかったが、なぜか書類に不備があった。添付すべき証明書を入れ忘れていたのだ。法務局からの電話で気づくという、最低なパターン。言い訳も浮かばない。ただ、相手に謝ることしかできなかった。「またやったか」と、心の中で呟きながら、机に突っ伏したくなるような気分だった。
書類の添付漏れに気づいたのは相手からの電話
電話が鳴ったとき、何か嫌な予感がした。受話器を取ると、予想どおりの指摘だった。「証明書が入っていませんでした」。その瞬間、時間が止まったような気がした。自分がその作業をした記憶が、曖昧なのだ。確かに準備したつもりだった。でも、「つもり」がどれだけ信用ならないか、痛感した瞬間だった。
ミスの内容すら覚えていない自分に驚く
一番情けなかったのは、何をミスしたのか、すぐに把握できなかったことだ。「そんなはずはない」と思ってファイルを見直すと、確かに抜けている。何度確認しても、どこかで「自分がやったこと」を信じたいのに、現実は残酷だった。こんな基本的なところでつまづく自分が、本当にプロなのかと疑いたくなる。
言い訳も出てこないという絶望
言い訳というのは、まだ自分を守る余力があるときに出てくるものだ。けれど、その日は違った。ただただ「」と繰り返すことしかできなかった。どう言えば状況がよくなるのか、何を説明すれば納得してもらえるのか、そんなことすら考えが及ばない。完全に思考停止。真っ白な頭で、無表情のまま、電話を終えた。
「すみません」しか出てこない無力感
本当に情けなかった。長年この仕事をしていて、謝罪の場面も数多く経験してきた。でも、今回は違う。「すみません」しか言葉が出ない。語彙が貧困なのではなく、自分の中にもうエネルギーが残っていなかったのだ。しかも、相手はそこまで怒ってもいなかった。それが余計に刺さった。「大丈夫ですよ」と言われた瞬間、涙が出そうになった。
昔はもっと口が回っていたはずなのに
若いころは、失敗しても口八丁でなんとか取り繕えた。とっさに機転が利いて、それなりに納得してもらう術を知っていたつもりだった。でも、今は違う。体力も気力も落ちてきて、ひとつの失敗が重くのしかかる。昔の自分に助けを求めたくなるほど、今の自分には余白がない。
信用が目の前で溶けていく感じ
ひとつのミスで、何年も築いてきた信頼が音もなく崩れていく気がする。実際はそこまで大きな損害ではないかもしれない。けれど、自分の中では「もうダメかもしれない」という思いが渦巻く。たとえ相手が許してくれても、自分自身を許すことができないのだ。
自分を責める声と無言の空気
電話を切ってからの時間がつらかった。事務所の空気が一気に重たくなり、事務員も気を遣って話しかけてこない。自分自身の中でも「またかよ」という声がずっと響いている。何をやっても空回りする日、誰とも目を合わせたくない。ただただ、何も起きなかったことにして、早く今日が終わってほしいと思うだけだった。
事務員の沈黙が刺さる
普段は世間話もする事務員も、その日は何も言わなかった。優しさなのか気まずさなのかは分からない。ただ、その沈黙が逆に刺さる。自分の不甲斐なさを、無言で指摘されているような気がして、居たたまれない。かといって、自分から話す余裕もなかった。
電話を切った後のデスクがやけに遠く感じる
ほんの数メートルの距離なのに、デスクに戻るまでが遠かった。座ってしまえばまた作業が始まる。それが分かっているから、身体が動かない。まるでデスクが断崖絶壁の向こうにあるかのように感じる。ため息だけが空しく響く。
それでも明日は来る
どんなに最悪な日でも、夜は来て、そして朝もまた来る。逃げたい、休みたいという気持ちはあっても、現実は止まってくれない。誰に頼れるわけでもないこの仕事。せめて自分くらいは、自分を責めすぎないようにしたい。うまくいかない日の自分を、そっと見守るくらいの余裕が、いつか持てるようになれたらと思う。
ちょっとだけ立ち直るきっかけ
そんな夜、ふとスマホを見ると、昔の同期からのメッセージ。「最近どう?疲れてない?」たったそれだけの文章が、妙に心に染みた。誰かが気にかけてくれているという事実。それだけで、少しだけ救われたような気がした。明日もまたうまくやれるかは分からないけれど、もう一日だけ、頑張ってみようかという気になれた。
ふとした優しさに救われた話
コンビニで店員さんが「お気をつけて」と言ってくれた。たったそれだけなのに、涙が出そうになった。ミスばかりの一日でも、自分が全否定されたわけじゃない。そう思えるきっかけが、意外と身近なところにあるんだと気づいた。
昔の同期からの一言が効いた
司法書士としての肩書きも、責任も、全部を抱え込んで潰れそうな時、「あのとき一緒に飲んだバカ話、またやろうよ」と言ってくれた同期の存在は大きい。誰かが自分を覚えていてくれる。それだけで、もう少しだけ、やってみようと思える。