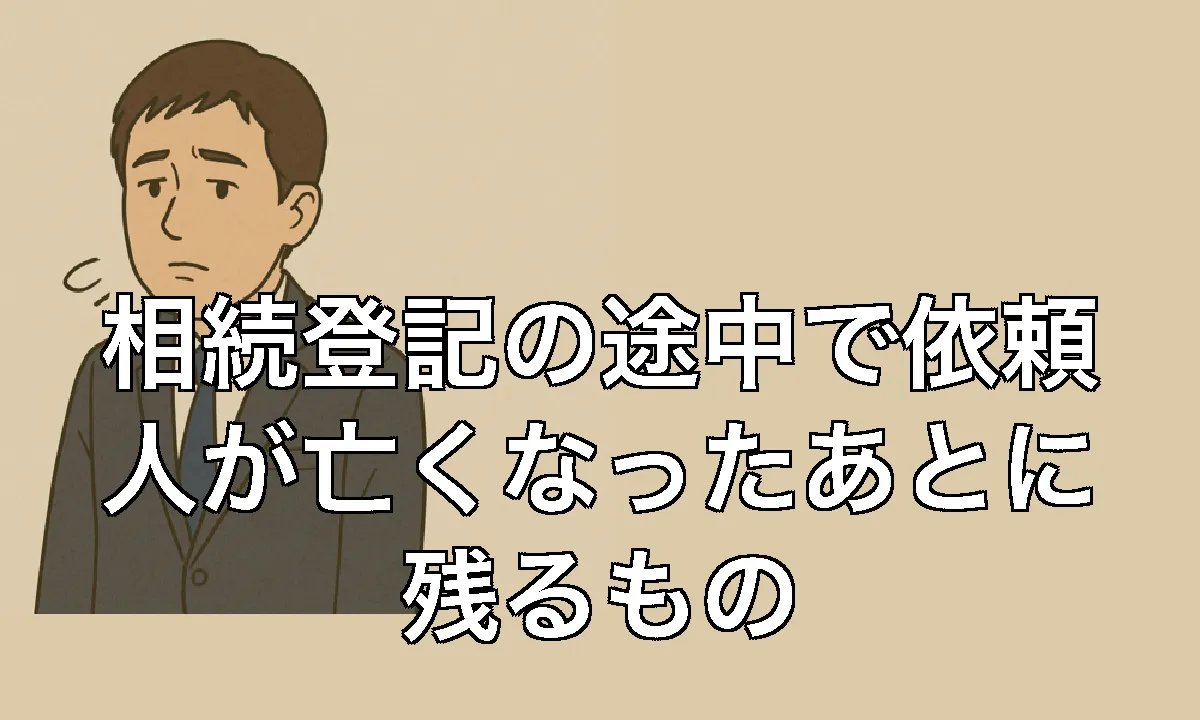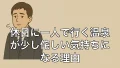あの日突然届いた一本の電話
午前10時過ぎ、いつもなら登記情報の整理をしている時間。事務員が少し青ざめた顔で私の部屋に入ってきた。「あの、○○さんが、亡くなったそうです」。一瞬、何を言われているのか分からなかった。ちょうど相続登記の準備を進めていて、残すは印鑑証明を取りに行ってもらうだけだった。昨日も電話で、「明日市役所行ってきます」と笑っていたのに。現実感がなかった。でも、こういうことは、たまにある。分かってはいても、毎回、心に重くのしかかる。
「昨日までは元気だったのに」事務員の声が震えていた
実を言うと、この依頼人とは何度もやりとりをしていて、世間話も多かった。「司法書士さん、昔野球やってました?」と聞かれて「元・補欠です」と答えたら大笑いされたのが、なんだか印象に残っている。事務員の声は震えていたけど、それも無理はない。彼女は書類の整理だけでなく、時々依頼人の電話対応もしていた。事務所としては淡々と処理すべきなのかもしれないが、こういうとき、感情と仕事の間に線を引くのが難しい。
依頼人とのやり取りを思い返して
登記とは無関係な話を、なぜかよく覚えている。「畑でとれたキュウリ、持ってくよ」と言われたことや、「うちの孫が司法書士目指してるんですよ」と照れくさそうに話してくれたこと。手続きの記録には残らないけれど、私の中にはちゃんと残っている。業務では「依頼人」として接していたけど、やっぱり一人の人間として見ていたんだな、と実感する。
その瞬間から手が止まる
あの日の午後は、何も手につかなかった。書類は山積み、期限の迫る案件もあった。でもどうしても机に向かえなかった。「自分がもっと早く準備していれば」とか、「あのとき書類を取りに行くのを急かせていれば」と、意味のない後悔ばかりが頭をぐるぐると回る。自己満足だと分かっていても、止められなかった。
感情と実務の間で揺れる
司法書士という仕事は、感情をあまり表に出さない方が楽だ。特に相続や死亡登記の場面では、冷静でいることが求められる。でも、依頼人が亡くなると、どうしても仕事の「対象」だったものが、「人」に戻ってくる。今回も、書類のファイルを開いた瞬間、そこに押された名前の印影がやけに生々しく見えてしまった。どうしても割り切れない。
書類の山が急に重たく見えた
いつもなら何とも思わずにやっている作業が、このときはやけにしんどかった。戸籍の束も、委任状も、受け取ってくれる相手がもういないのかと思うと、ただの紙なのに重かった。事務員にも「今日は早めに帰っていいよ」と伝えたが、自分の方こそ帰りたかった。だけど、片づけないと、次に進めない。そう自分に言い聞かせた。
進めるべきか止めるべきか
亡くなった依頼人の登記、途中で止まったまま。遺族がいるなら、そこから再スタートもできる。でも、こちらから声をかけていいものか迷った。通夜や葬儀の最中に「登記の件ですが」なんて言えるわけがない。結局、数週間後に遺族から連絡があった。「父が司法書士さんのことを信頼してました」と言われて、やっと前に進む気持ちになれた。
司法書士という職業の重さを知る
こういう出来事のたびに、「自分のやっていることって何なんだろう」と思う。ただの書類作成代行ではない。でも、感情ばかりに浸っているわけにもいかない。そのバランスが難しい。若い頃は「淡々と、きっちりやる」のが正義だと思っていたけど、今は少し考えが変わってきた。
亡くなった方と関わる責任
相続や遺言の案件は、どうしても人の死と隣り合わせになる。最初は慣れなかったけど、今は「ごく普通のこと」として受け止めるようになった。でもその一方で、責任は重くなる。遺族にとっては「最後の手続き」になることもあるから、ミスは許されない。その重圧を背負っているのが、自分なんだと自覚する。
ただの手続きでは片づけられない
登記は「ただの作業」に見られがちだけど、実際には人生の節目と深く関わるものだ。生まれて、結婚して、死んでいく。そのたびに、紙の上で証明される。だからこそ、単なる事務ではない。私はただの補助者ではない。そう思えるようになったのは、たぶんこの仕事で何度も人の死を見てきたからだ。
残された家族の戸惑いに寄り添う
葬儀後、遺族と話す機会があった。「何から始めればいいか分からないんです」と言われたとき、私は「大丈夫ですよ、ゆっくりでいいです」と返した。その一言に、奥さんが泣いた。手続きの説明よりも、たったそれだけで泣いた。それが忘れられない。専門家だからこそできる「寄り添い方」があるんだと思う。
登記の途中で止まるという現実
司法書士の仕事は、必ずしも完了までいけるとは限らない。途中で止まる案件もある。その現実を受け入れるのも、またこの仕事の一部だ。昔はそれが悔しかったけど、今は「そういうものだ」と思えるようになった。自分の仕事は人生に寄り添うもの。だからこそ、終わらなくても、意味がある。
進められない手続きと進めねばならない気持ち
感情では止まりたい。でも、司法書士としては進めなければいけない。このジレンマをどう処理するか、今でも悩む。今回も「数日休もうかな」と思ったが、結局事務所にいた。やることは山ほどある。でも、それで気が紛れる部分もあった。淡々と進めることで、自分を保っていたんだと思う。
期限と感情の板挟み
法務局の期限、依頼人の家族の気持ち、自分の感情。そのすべてがズレているとき、正解が見えなくなる。登記申請の期限は延ばせない。でも、「急いでください」とは言えない。そんな中で、自分の言葉ひとつが人を救うことも、傷つけることもある。それが怖くて、言葉を選ぶようになった。
自分の中に残ったもの
依頼人の死をきっかけに、自分が何を大切にしているのかを見つめ直した。この仕事をしていて、一番嬉しいのは「ありがとう」と言ってもらえること。だけど、それ以上に、「あの人に頼んでよかった」と思ってもらえることかもしれない。効率ではなく、信頼。それを実感できた出来事だった。
業務の中で感じる人の生死
司法書士の業務は、形式的なものが多い。でもその裏には、確かに人の生き死にがある。若い頃はそこに気づかなかった。今は違う。人が亡くなるたびに、自分の中で何かが削れていくような気がする。でもそれが、私の中で人間らしさを保ってくれているのかもしれない。
慣れなきゃダメだと思ってはいるけれど
事務員にも「この仕事は慣れが大事ですよ」と言っているけど、自分自身はまだ慣れていないのかもしれない。むしろ、慣れたくないのかもしれない。人の死をただの作業として処理できるようになったら、もう終わりだ。そう思っている自分がいる。だから今日も、依頼人の名前を一つひとつ丁寧に確認していく。
ふとしたときに来る喪失感
登記が完了して、家に帰って、ご飯を食べているとき。急に思い出すことがある。「あの人、どうしてるかな」って。もういない人なのに。テレビから流れる野球中継を見ながら、ふと涙が出そうになることもある。そんな日々を重ねながら、自分の仕事の意味を探している。
司法書士も人間だと認めること
肩書きや専門性で武装していても、中身はただの人間だ。感情もあるし、疲れるし、愚痴も出る。モテないし、独り暮らしで寂しい夜もある。それでもこの仕事を続けているのは、「意味がある」と信じたいからだ。だから今日も、事務所の灯をつけて、誰かの人生に静かに寄り添っている。
泣いてもいい立ち止まってもいい
「先生、強いですね」と言われることがある。でも本当は、泣きたい夜もある。立ち止まりたい日もある。それでも動く。それが司法書士なんだと思う。たまに立ち止まったときには、依頼人の笑顔を思い出して、また前に進む。それでいいじゃないか、と思っている。
優しさは非効率でもいいと思えた
業務効率、売上、期限、事務作業――全部大事だ。でも、優しさはもっと大事かもしれない。少し時間がかかっても、寄り添うことの方が、長く記憶に残る。今回の件で、それを学んだ。そしてそれが、この仕事の本質なんじゃないかと、今は思っている。