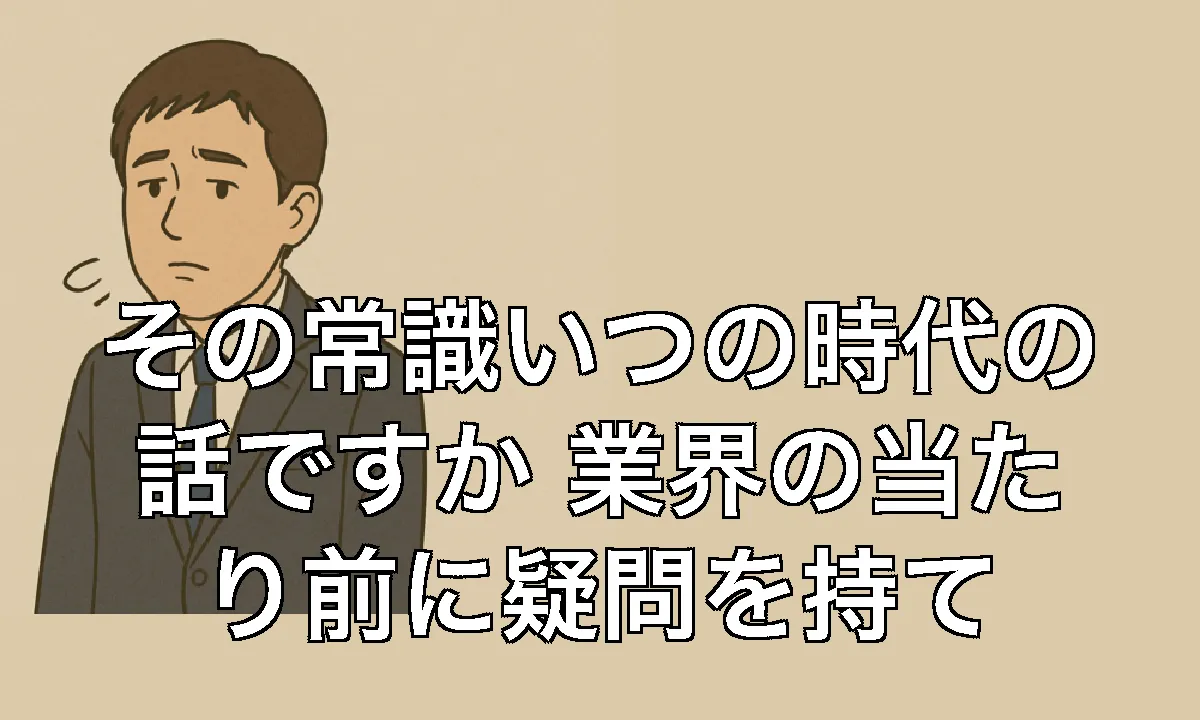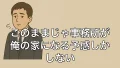業界の常識が自分の首を締める瞬間
司法書士という仕事は、正確さと迅速さが求められる世界です。しかしその一方で、「これが業界の常識だから」「昔からこうやっているから」という空気に支配されがちです。気づけば自分もその常識に従って、非効率で無意味な手続きを繰り返していました。たとえばFAX文化。クライアントがメールで送った書類をわざわざ印刷し、それをまたFAXで送るように言われたとき、ふと「これって何の意味があるんだろう?」と感じたのが始まりでした。
昔ながらのやり方を続けることの怖さ
昔からのやり方には「安全性」や「信頼性」という強みがあるのは事実です。ですが、やみくもにそれを守るだけでは、変化に取り残されるリスクも抱えます。とくに独立開業後、時間の使い方に敏感になると、旧来の慣習がただの“足かせ”に見えてきます。昔ながらの手続き方法を崩すことに最初は恐怖がありましたが、それよりも、非効率な作業をしている自分にイライラしてしまう時間の方が問題だったのです。
気づけば「誰のための仕事か」が見えなくなる
「このやり方が決まりだから」と言われ続け、何のためにやっているのかもわからないまま作業をする。そんな日々を繰り返していると、依頼者の顔が見えなくなってしまいます。例えば、登記申請の際に必要書類を郵送で送ってもらうようお願いしたとき、メールで済むのに…と相手からの疑問の声が。それを聞いた瞬間、「あ、自分はただ慣習に従ってるだけで、相手の利便性を考えていない」と気づかされたのです。
古い方法に時間を取られる毎日
一日を振り返ると、印刷、捺印、郵送といった作業に半分以上の時間を費やしていることに気づきます。しかも、そうした作業は誰にでもできる単純作業が多い。つまり、自分の専門性が全く活かされていない時間が多いということです。せっかく依頼者にとっての“頼れる専門家”であるはずなのに、書類の封筒詰めに追われる毎日に、何度も虚しさを感じました。
「これが普通」という言葉の落とし穴
「これが普通」と言われると、不思議と反論しにくくなります。でも、その“普通”がいつ、誰が決めたものかを考えると、実は根拠のないことが多い。特に士業界では、年配の先輩が言う「これが常識」という言葉が強すぎて、若い世代が何も言えなくなってしまうことがよくあります。でもそれって、思考停止ではないでしょうか。常識という名の下に、思考と成長のチャンスが奪われている気がします。
先輩の教えが正しいとは限らない
あるとき、先輩司法書士に「登記の際は必ずこうしろ」と言われた方法が、実は現在では非効率だと知ったことがありました。それを他の事務所に確認すると、今ではもっと簡単な手続き方法が一般的とのこと。信じていた先輩の教えが必ずしも正しいとは限らない、という現実に直面し、それ以降「教え=正解」と思い込まないように意識するようになりました。
マニュアル通りの対応で失う信頼
一度、依頼者から「その対応って、どこかのマニュアルに書いてあるんですか?」と皮肉を言われたことがあります。実際、マニュアル通りの対応しかできない自分がいたのは事実です。その瞬間、相手の気持ちに寄り添うことなく、ただ型にはまった対応をしていたことに恥ずかしさを感じました。
元野球部的に言えば「送りバントしか知らない打線」
何かを変える勇気が出なかった自分を振り返ると、高校野球時代の「とりあえず送りバント」戦法が重なります。安全策ばかり選んで、本当の勝負を避けていた。送りバントも必要ですが、それしか知らない打線では点が取れないように、常識だけでは突破力がないのです。
じゃあどうすればいいのか 自問の日々
古い常識に違和感を覚えたからといって、すぐに全部を変えるのは難しい。でも、それに気づいたときこそがチャンス。変えるにはどうすればいいか、自分に問い続ける日々が始まりました。最初の一歩は「疑うこと」、そして「誰のために仕事をしているのか」に立ち返ることでした。
事務員さんからのひと言にハッとした
ある日、事務員さんが「それってやらなくてもいいんじゃないですか?」と何気なく言ったのがきっかけで、慣習を見直すようになりました。自分では当たり前だと思っていた作業が、外から見るとただの無駄だったんです。その言葉がなかったら、今も変わらず惰性でやっていたかもしれません。
「それってやらなくてもいいんじゃないですか」
この一言は、まさに目からウロコでした。業界の外にいる人だからこそ言えた素朴な疑問。私たちが「常識」として疑わないものを、他人の視点から見ることで、はじめて無駄に気づけることがあります。それからは、外部の意見をもっと柔軟に聞くようにしました。
外の世界から見た非常識こそヒント
一度、ITベンチャーに勤める友人と話をしたとき、彼が「それってアプリで一瞬だよ」と言ったのを聞いてショックを受けました。私が何十分もかけていた作業が、外の世界では秒で終わる。内輪の常識にとらわれず、外からの視点を取り入れることで、業務に風を通すことができるようになりました。
新しいやり方に挑む怖さと気持ちよさ
変えることには不安がつきものです。ですが、試しに小さな改善から始めてみると、意外にも依頼者の反応は良好でした。むしろ「前よりスムーズになりましたね」と喜ばれることが多かったのです。自分の中の“怖さ”が勝手に作った幻想だったのかもしれません。
業務効率化アプリを使ってみた結果
最近導入したスケジュール管理アプリ。最初は設定に手間取りましたが、一度慣れると手放せません。紙のメモと手帳でぐちゃぐちゃになっていた予定が、数タップで整理され、ミスも激減。これまでのやり方を変えるのは勇気がいりますが、試してみる価値は十分にあると感じています。
「こんなに早く終わるなんて」と驚いた自分
手続きの一部を自動化したことで、あっという間に終わった業務。それを見て「もっと早くやればよかった」と後悔しました。でもこの後悔が、変化を楽しむきっかけになりました。変わることは怖い。でも、それ以上に得られる自由と可能性は大きい。
でも結局ヒマになったらまた愚痴を言う
空いた時間に喜びつつも、手が空けば空いたで「なんか暇すぎる」と文句を言ってしまうのが人間というもの。結局、仕事量の問題じゃなく、心の持ちようなんだと、ちょっと反省した出来事です。
それでも常識は壊しすぎない方がいい
新しいものに挑むことも大事ですが、常識をすべて否定するのは違うと思います。依頼者が安心して任せられるのは、一定の型やルールがあるから。壊すのではなく、活かし方を変えるという視点が必要です。
依頼者が求める「安心感」とのバランス
常識があることで、依頼者は「ちゃんとしている」と感じてくれます。たとえば、書類の受け渡しをきちんと対面で行うという古い慣習も、高齢者には大きな安心感につながります。その気持ちを理解せずにすべてデジタルに移行してしまうと、信頼を失うリスクもあるのです。
変えていいところと変えちゃいけないところ
変革の鍵は、どこを変えるべきか、どこは守るべきかを見極めること。すべてを効率化すればいいというわけではありません。例えば、電話でのやり取りは面倒でも、相手の温度を感じる大切な時間です。そこに価値があるなら、残す意味があるのです。
一人事務所の限界と向き合う
一人事務所だからこそ、業務のすべてを自分で回さなければいけません。それはつまり、変化の自由がある代わりに、失敗の責任も全部自分に降ってくるということ。だからこそ、慎重に、でも確実に、自分なりの最適解を探す必要があります。
「俺しかやらないなら俺が変わるしかない」
結局、事務所の仕組みを変えられるのは自分しかいません。愚痴を言っても誰も助けてくれないなら、まず自分が動くしかない。そう思って、一歩ずつでも変えていくようになりました。思ったよりも、変化は身近にあるものです。
愚痴る前に深呼吸の習慣を
最近は、愚痴を言う前にまず深呼吸するようにしています。たったそれだけで、視点が少し変わることがあります。感情で動くより、ひと呼吸おいて理性的に考えることで、やるべきことが見えてくる気がします。
でも深呼吸しても誰も褒めてくれない
深呼吸したところで、誰かが「えらい!」って言ってくれるわけでもないし、何かが劇的に変わるわけでもない。でもそれでも、愚痴を減らせたらちょっと自分が楽になる。そんな気づきがあるだけでも、深呼吸する価値はあると思います。