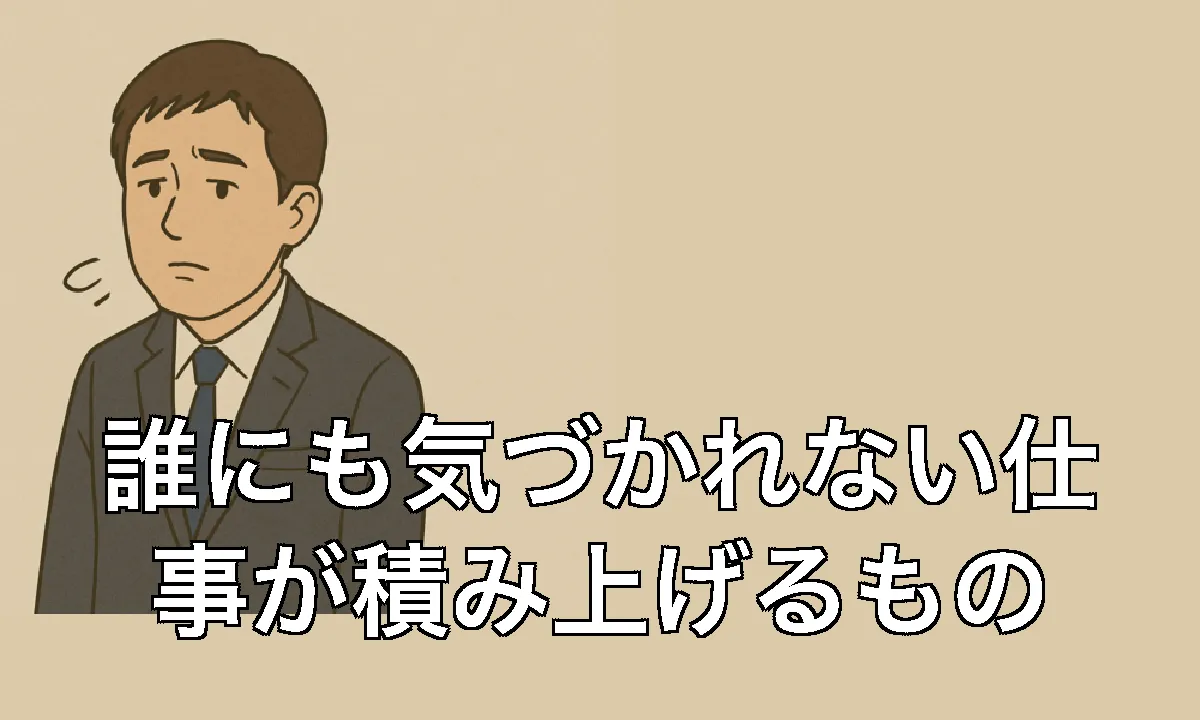気づかれない仕事に意味はあるのかと問いたくなる日
朝から晩までこなしているこの仕事、果たして誰かが見てくれているのだろうか——。そんな疑問が頭をよぎるのは、一日が終わって誰もいない事務所で椅子にもたれたときだ。登記が通っても、完了通知が届いても、依頼人が満足して帰っても、そのプロセスに誰がどれだけ時間を費やし、どれだけ神経をすり減らしたかなんて、誰も気にしない。いや、気にされないことを前提とした仕事なのだろう。分かってはいる。けれど、それでも「自分はここまでやってきた」と誰かに認めてほしい、そんな気持ちを持ってしまうのは弱さだろうか。
努力が報われるとは限らない司法書士の日常
司法書士という職業は、裏方に徹することが求められる。主役は常に依頼人であり、関係者であり、そして結果そのものだ。だから、どれだけ完璧な書類を整え、どれだけ丁寧な説明をし、どれだけ期日を死守しても、「ありがとう」は来ないこともある。むしろ、当然のこととして受け取られる。努力が報われる世界ではない。それでも、クレームもトラブルもなく一日が終わるだけで、無意識にホッとする。評価されないことに慣れてしまった自分に気づいたとき、何とも言えない寂しさが胸をよぎるのだ。
書類の山に埋もれて誰も知らない戦いがある
机の上に積み重なる書類は、まるで自分の存在をかき消すように広がっていく。たった1文字のミスが命取りになる世界で、注意力を研ぎ澄まし続けるのは正直、神経が磨り減る。ある日、法務局で指摘された細かな記載ミスを、誰にも言えず一人で修正して出し直した。誰にも責められなかったけれど、誰にも「よくやった」と言われなかった。そういう仕事だと分かっているが、「見ていてくれる人がいればな」と思ってしまった自分が情けなかった。
「ありがとう」はクライアントからだけじゃないと信じたい
ありがとうという言葉を、最近はもっぱらコンビニのレジや配達員さんに言っている気がする。逆に自分は、いつ言われたっけ? 仕事が無事終わったとき、依頼人から「助かりました」と言われることはある。でも、それはその場限りで、その後の気遣いなどはまずない。いや、こちらもそれを求めてやっているわけじゃないけれど…。それでも、誰か同業者でも、家族でも、事務員でも、たった一言「よくやってるね」と言ってくれたら、どれだけ救われるだろう。そんな気持ちを否定せずにいたい。
一人で抱える重さを誰に見せたらいいのか
この仕事の孤独さは、なかなか人には伝わらない。一人で受任して、一人で書類を作って、一人で提出して、一人で結果を受け止める。事務員はいてくれるけれど、すべてを共有できるわけじゃないし、責任はやはり自分に降りかかる。何かあったとき、誰のせいにもできない。だからこそ、日々の小さな重さがじわじわと蓄積していくのだ。
「分担」とは名ばかりの実態と現実
事務員がいてくれるだけで助かるのは事実だ。でも、正直、任せられる業務には限界がある。本人の能力の問題ではなく、最終的に責任を負うのが自分である以上、確認・修正・判断のほとんどを自分で抱えることになる。結局、分担という言葉の裏側には、業務を割り振る苦しさと、任せた先で何か起こったときの不安が隠れている。「安心して任せられる」と言えるようになるには、相当の時間と信頼の積み重ねが必要だ。今のところ、まだそこには至っていない。
事務員に任せられない業務の正体
たとえば、相続登記の際に起こる「微妙な表現」の判断。法的に問題がないとしても、遺族間の空気や地域性によってベストな表現が変わることがある。そうした判断は、経験と責任を持って対応しなければならない。マニュアルには載っていない「感覚」が必要になる。事務員にやらせてミスが出たとき、「なぜ任せたのか」となるのは目に見えている。だったら最初から自分でやる方がいい。そんな判断の繰り返しが、また一人分の仕事を積み上げていくのだ。
一人事務所という限界点との向き合い方
実際、体力も気力も限界に近づいていることは、もう何度もある。でも、人を増やすことで解決するかと言えば、それもまた別の問題だ。小規模事務所においては、採用・教育・管理の負担がむしろ重くのしかかる可能性もある。「一人でやるほうが早い」というのは、効率的なようで非効率でもある。その矛盾を抱えながら、日々をこなしていくしかないというのが今の現実だ。
元野球部の粘りがなければとっくに折れていた
学生時代、野球部で鍛えられた「耐える力」が、今の自分を支えていると言っても過言ではない。誰にも評価されず、炎天下で素振りを繰り返していた日々は、今この仕事の「気づかれない努力」に通じるものがある。声が枯れるほど叫んでも結果が出なければ意味がない。それでも、「やり続ける」という意地だけは身に染みて残っている。
監督の無言の圧と今の業界の空気感が似ている
あの頃の監督はほとんど怒鳴らなかった。ただ、視線や空気だけで「ダメ出し」が伝わるような人だった。今の司法書士業界も、ある意味でそれに似ている。表立って指摘されることは少ないけれど、周囲の目、同業者の動き、依頼人の態度などがじわじわとプレッシャーになってくる。声に出さずに「察する」ことが求められる。誰にも咎められないからこそ、自分の中で勝手に重圧が増していくのだ。
声を出しても響かない場所で耐える強さ
一人で文句を言っても、誰かに届くわけじゃない。だからこそ、ぐっと飲み込むしかない場面が多すぎる。でも、声を上げること自体を諦めたくはない。愚痴はある。文句もある。けど、それでも机に向かってパソコンに向かっている自分がいる。あの頃のノック練習のように、繰り返し、繰り返し、同じフォームで投げ続けるように。誰にも気づかれなくても、やり続けることが「仕事」なんだと思うしかない。
結局は泥だらけでも前に進むしかない
きれいなグラウンドなんてこの仕事にはない。泥だらけになりながら、何とか一歩を踏み出していく。そんな毎日だ。休みたい。逃げたい。でも、それでも「もうちょっとだけ頑張るか」と思えるのは、どこかでこの仕事に誇りを持っているからだと思いたい。誰かに認められなくても、自分だけは分かっていたい。今日もまた、自分なりの全力で一歩進んだことを。