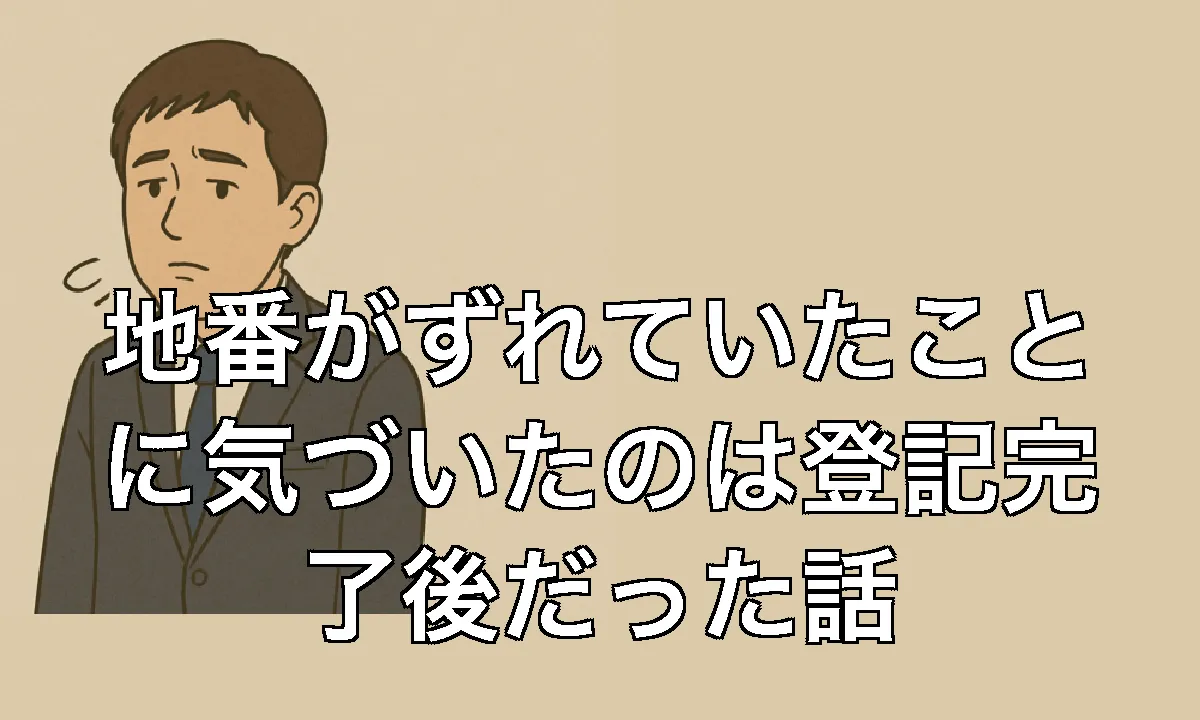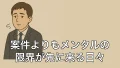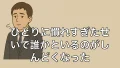あれこれ確認したはずなのに地番が違ったという現実
「こんなはずじゃなかった」と、登記完了証を見ながら呟いたあの日。確かに分筆登記の準備は入念にやったつもりだった。公図も登記簿も、隣地との境界も確認した。けれど、結果として完了した登記簿には、依頼人の土地ではない“ひとつ隣”の地番が記載されていた。ほんの1桁違い。それだけで一気に地雷を踏んだような感覚になった。しかも気づいたのは依頼人ではなく、自分自身が受け取った完了証を再確認した時だった。冷や汗が止まらず、頭が真っ白になったのを覚えている。
完了証を見て冷や汗が止まらなくなった瞬間
分筆登記は、地元の地主さんからの依頼だった。慣れ親しんだエリアで、過去にも何度か登記手続きしたことのある地域。だからこそ油断があったのかもしれない。完了証が届いた日の夕方、机の上で何気なく確認したところ、見慣れた地番の並びに違和感を覚えた。「あれ?この数字…隣の土地じゃないか?」と。何度も見返したが、やっぱり違っていた。過去の測量図と照らし合わせるうちに、どんどん血の気が引いていった。これはミスだ、と。
分筆図も公図もチェックしたのにどうして
この仕事をしていると、図面の確認は日常だ。分筆図をもとに地番を割り出し、公図と照らし合わせ、登記簿と付き合わせる。ミスが起きないように三重にも四重にもチェックしているつもりだった。だが今回は、その中の一つ、公図の古いバージョンを参照していたことが原因だった。最近変更された地番情報を反映していなかったのだ。まさかそんなタイミングで…と思っても後の祭り。いくら「つもりだった」と言っても、完了後の訂正は一筋縄ではいかない。
登記原因証明情報に小さく書かれた“もう一つの地番”
さらに決定的だったのは、登記原因証明情報に“隣接地”の地番が小さく記載されていたこと。作成の段階ではまったく気にしていなかった。「参考程度だろう」と思い流してしまったのだ。だが、それが法務局側にとっては有効な地番情報として処理されたようで、結果的に本来の土地ではなく隣地が対象として処理されてしまった。書類の一文、それも小さな記載がここまで事態を左右するのかと、あとから愕然とした。
凡ミスなのか構造的な問題なのか
一見するとただのヒューマンエラー、つまり凡ミスに見えるかもしれない。けれど、掘り下げてみると、どうにも引っかかる部分が多かった。図面の世代、登記官の処理の仕方、情報共有のズレ…もしかすると、構造的な「間違えやすさ」がそこにはあるんじゃないか。そう思わずにはいられなかった。
事務員さんのせいにするのは簡単だけど
こういう時、つい「どこかで事務ミスがあったんじゃ…」と人のせいにしたくなる。だが実際、この案件においては書類作成から確認まで、ほとんどを自分自身で進めていた。事務員さんが見ていたのは一部の資料の整理だけ。それに、日々忙しい中で彼女も必死にやってくれているのを知っている。ミスを指摘することは簡単。でも、それ以上に「自分がチェックできなかった責任」の重みを感じざるを得なかった。
チェック体制を見直しても人間はミスをする
チェックリストはある。ダブルチェックも、場合によっては第三者チェックも行っている。それでもミスは起きる。完璧な体制なんて、どこにも存在しない。問題は、ミスが起きたときにどう対応するかだと、最近強く感じている。特にこの仕事では、一つのミスが信頼を大きく揺るがす。だからこそ、再発防止策以上に「ミスと向き合う姿勢」こそが問われるのかもしれない。
司法書士なんだから完璧で当然というプレッシャー
「司法書士なんでしょ?じゃあ間違えちゃいけないよね」──依頼人に面と向かってそう言われたわけじゃないけれど、そう思われているだろうなという空気はひしひしと感じる。資格を持っているだけで、間違いの許されない存在として見られる。だが、実際の現場はギリギリの綱渡りだ。制度と人間のあいだにある小さな隙間を、何とか埋めながら進む毎日。そのプレッシャーに耐えきれず、夜ふと眠れなくなることもある。
訂正手続きという名の心労
ミスが発覚した後の訂正手続きは、想像以上に気が滅入るものだった。ただでさえ忙しい中、再度書類を整え、事情を説明し、法務局に頭を下げる。「やり直し」とはいえ、ただ巻き戻せば済む話ではない。そこには、信頼関係の修復という、見えない作業もついて回る。
依頼人に説明するのがいちばんのストレス
正直、法務局への訂正よりもずっと気が重かったのが、依頼人への説明だった。「お金も時間もかけてお願いしたのに、間違えたってどういうことですか?」と言われたらどうしよう…。説明の電話をかけるまでに、何度も原稿のように話す内容を頭の中でシミュレーションした。意外にも、依頼人は怒ることなく、「直してくれればいいですよ」と言ってくれたけど、その一言が逆にぐさりと刺さった。自分のふがいなさに。
プロでも間違えるのかと言われた時の敗北感
別の依頼人との世間話の中で、「司法書士さんでも間違えるんですね」と言われたことがある。軽口だったのかもしれないが、心にはずっしり残った。「間違えないプロ」であるべきなのに、そんな風に見られてしまうことが、こんなにも悔しいとは。自分の中で「信頼を失った」という感覚がしばらく抜けなかった。結局、自分自身が許せなかったのかもしれない。
間違いをどうリカバリーするかに自分の値打ちが出る
でも、ふと思った。完璧であり続けることが無理なら、せめて「ミスした後の対応」で信頼を取り戻すしかないのだと。依頼人への再説明、訂正登記のスピード対応、費用の負担をどうするかの判断。そういった一連の動きで、「この人ならまた頼める」と思ってもらえるかどうか。そこに司法書士としての本質があるのかもしれない。
一人で抱え込みすぎてないか
田舎で司法書士をやっていると、同業者と話す機会も少ない。ましてや、ミスなんて恥ずかしくて人には言いにくい。自然と、心の中にため込むばかりになってしまう。誰にも言えないけれど、誰かに聞いてほしい。そんな気持ちでいっぱいだった。
田舎の司法書士にとって相談相手がいない現実
街中にいるわけでもないし、所属する会の集まりも年に数回。雑談レベルのやり取りはあっても、こういう「失敗談」を腹を割って話せる相手がいない。年齢も立場もバラバラだし、下手に話せば「能力がない」と思われかねない。結局、黙ってやり過ごすしかない。それが田舎の司法書士のリアルなのだ。
愚痴を言える相手がいることのありがたさ
昔の同級生に電話して、つい愚痴をこぼしたことがある。「お前、そんなことあるんだな」って笑われたけど、それで少し救われた。専門知識がなくても、ただ話を聞いてくれる人がいるだけで、気持ちは軽くなる。人は、話すことで立ち直れる。今さらながらそう思った。
元野球部のくせに守備範囲が狭い
学生時代、外野を守っていた。どんな打球も全力で追いかけていたつもりだった。でも今の仕事では、カバーしきれていないところがたくさんある。広い視野を持たねば、という思いはあるけれど、現実はなかなかうまくいかない。自分の限界と向き合うのも、プロの仕事のうちなのかもしれない。
自分の苦手なことを認める勇気
「完璧でいたい」という思いが、逆に自分を苦しめているのかもしれない。苦手なことは苦手、と割り切る勇気も必要だ。分筆や地番の確認は、今後は信頼できる測量士にきちんと依頼し、チェック体制も客観視できるよう工夫していく。全部を一人で抱え込まない。そういう判断も大切だと感じている。
外野からの指摘が意外とヒントになる
失敗の話をしたとき、知人から「そんなの、AIで管理できないの?」と聞かれた。冗談半分だったが、ふと我に返った。昔と違って、今はツールも情報も揃っている。技術的にできることが増えてきた今こそ、頼れるところは頼っていくべきなのかもしれない。
それでも続ける理由があるとしたら
ふとした瞬間、辞めたくなることもある。でもそれでも続けている理由は、やっぱり依頼人の「ありがとう」や「助かりました」の言葉。自分が必要とされている、と感じられるその一瞬が、何よりの支えになる。
依頼人のありがとうが刺さる日
先日、ある高齢の依頼人から手紙をもらった。「先生がいてくれて助かりました」と、拙い字で書かれていた。泣きそうになった。失敗もあるけれど、それでも誰かの役に立てている。そう思えるだけで、もう少し頑張ってみようかなと前を向けた。
司法書士としてのやりがいは失敗の先にある
うまくいかないことの方が多い。でも、それでも乗り越えてきた数だけ、少しずつでも強くなれている気がする。ミスを恐れず、向き合い、謝り、改善していく。その積み重ねこそが、この仕事のやりがいなのかもしれない。