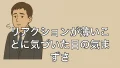笑いたいだけなのに笑えない日々
ふと鏡を見たとき、自分の顔があまりにも険しくて思わず目を逸らした。司法書士の仕事は人と関わる機会も多いはずなのに、気づけば誰とも心から笑い合った記憶がない。笑うことは特別なことじゃなかったはずだ。学生時代、野球部の仲間とバカみたいに笑い転げていたあの日々が、今ではまるで夢のよう。誰かと笑いたい、ただそれだけなのに、それすら難しいと感じるようになってしまった。
笑顔が一番遠い朝のはじまり
朝、目覚ましが鳴る音にイラつくのが日課になっている。カーテンの隙間から差し込む朝日を浴びても、何も気分は晴れない。朝食もとらず、ぬるくなったインスタントコーヒーを流し込む。気づけば笑顔を作る筋肉の使い方を忘れかけている。笑顔を作る相手がいないのだから当然かもしれないが、それがまた自分を情けなくさせる。
コーヒーがぬるく感じるのは気のせいか
自分で淹れたコーヒーがぬるく感じるとき、それは温度の問題じゃない。心の温度が下がっている証拠だと最近気づいた。コンビニのレジの若者が発した「いってらっしゃいませ」の一言がやけに温かく感じた朝もあった。そういう小さな出来事が妙に胸に刺さるのは、普段どれだけ心が乾いているかの裏返しだろう。
テレビの音が虚しく響く事務所の朝
朝一番の事務所は静まり返っている。テレビの音だけがやけに大きく響き、誰にも届かないニュースを垂れ流す。相槌を打つ相手がいないから、笑いどころがわからない。何気ないバラエティ番組の笑い声が、逆に自分を追い詰める。こんな風に笑えなくなる日が来るなんて、思ってもみなかった。
孤独と戦う法律職のリアル
「先生は頼りになるね」と言われるたび、嬉しい反面、重荷も感じていた。専門職ゆえに、弱音を吐けば信頼を失うとわかっている。だからこそ、孤独を抱えたまま黙って仕事に向き合っている。誰かに話したい気持ちがあっても、それを言葉にする場がない。この職業のリアルは、思っている以上に“ひとり”だ。
相談は受けるけど心の相談はできない
人の悩みを聞くことが仕事のはずなのに、自分の心の悩みは誰にも相談できない。この矛盾は、司法書士を続けるうちにどんどん深くなる。知識も経験も積んで、少しは一人前になったはずなのに、心はむしろ未熟になっている気がする。心を開ける相手がいないのは、どこかで人との距離を測りすぎてきた報いかもしれない。
「先生は強いですね」と言われるたびの空虚
強いと言われるのは、ある意味で褒め言葉なのだろう。でもその言葉の裏には「弱音は吐くな」という無言の圧力があるように感じてしまう。ほんの少しでも「しんどいな」と漏らそうものなら、次の日からの依頼が減りそうで怖い。だからこそ、笑ってごまかすしかない。でも、その笑顔は自分でも嘘だとわかっている。
笑うタイミングすら忘れてしまう日もある
一日の仕事を終え、事務所で一人残る時間がある。メールを返しながら、ふとテレビから流れるお笑いに目をやる。以前なら自然に笑っていた場面でも、今は表情が動かない。笑うタイミングを探しても、感情がついてこない。これが麻痺というやつかもしれない。自分が人間らしさを失っている気がして、寒気がした。
誰かと共有したかった小さな喜び
ほんのささいなこと、例えば道端の猫がごろんと寝転んだ瞬間や、依頼者からの「ありがとう」の一言。そういうことを「今日、こんなことがあってさ」と誰かに話したかった。笑われてもいい、バカにされてもいい。ただ、誰かと“共有”したかった。喜びを分かち合える人がいるだけで、人生の温度はぐっと上がる気がする。
仕事帰りの空がやけに綺麗だった夕暮れ
あの日、夕暮れに染まった空を見上げたとき、胸が締め付けられた。オレンジ色の雲がまるで絵画のようで、誰かと「綺麗だね」と言い合いたかった。スマホで撮ったけど、送る相手もいないまま、フォルダに埋もれていった。この感情を言葉にできないことが、何よりも切なかった。
LINEの履歴が事務員とのやりとりしかない
LINEを開くたびに、現実を突きつけられる。履歴の上位にいるのは事務員で、内容は業務連絡ばかり。「登記簿取れました」「納品いつにしますか」そんな文面の連続に、なんとも言えない空虚さを感じる。プライベートのやりとりがゼロに近い今、つながりという言葉がどれほど遠くなってしまったか、痛感する。
たった一言の「お疲れさま」が心にしみる
そんなある日、事務員がぽつりと「お疲れさまでした」と言って帰っていった。いつもの一言のはずなのに、その日だけは涙が出そうになった。心が弱っていたのかもしれないし、ただ飢えていたのかもしれない。人との関わりに。優しさに。そして、笑いに。誰かと笑い合えるって、こんなにも尊いことだったのか。