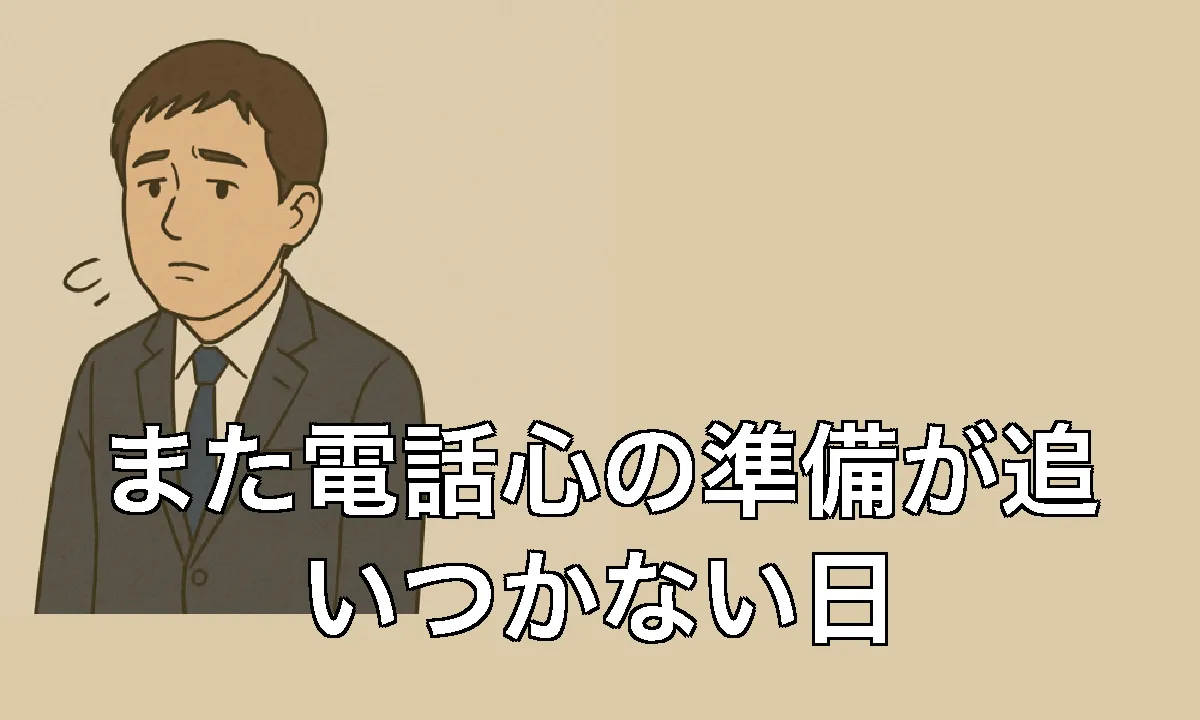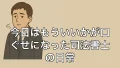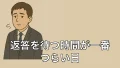朝一番の着信に怯える日々
朝、事務所の鍵を開ける前からスマホが震える。留守電も残さずワン切りのような着信。誰だろう、と画面を見る手が止まる。番号を見て、ため息をつく。これは補正の件か、それとも昨日出した書類の不備か。出るべきか出ないべきか、わずか数秒の間に頭の中がぐるぐると回る。結局、出る。それが「士業」としての習性なのか、ただのビビリなのかは自分でもわからない。ただ一つ言えるのは、「電話が鳴る前の自分」と「鳴った後の自分」では、もう別人のように気力が変わってしまうということだ。
コーヒーを淹れる前に鳴るスマホ
朝の小さなルーティン。ドリップコーヒーを淹れて一息つく——それだけが唯一のリセットタイムなのに、その途中でスマホが鳴る。昨日の疲れを引きずっている体と心に、その音はまるで戦場のサイレンのように響く。しかも、内容はたいてい「急ぎで」とか「至急折り返し」という言葉が含まれている。もう少しだけ時間をください、と言いたいのに、結局すぐ出てしまう自分がいる。コーヒーは冷め、頭は冴えず、心の準備などどこかに吹き飛んでしまったまま、1日が始まる。
寝起きのまま対応する地獄
たまにあるのが、夜明けと同時にかかってくる電話。7時台に着信履歴が残っていると、それだけで心臓がドキッとする。たとえそれが営業電話でも、私のような地方の個人事務所にとっては、その一報が業務の崩壊の始まりにもなる。寝起きの声で受け答えをしながら、内容を必死に頭に叩き込むが、当然うまくいかない。メモを取ろうにも手が震えていて、電話が終わったあとには内容の半分も覚えていない。こんな調子でミスが出ないわけがないと、自分で自分を責める朝が何度もあった。
言葉がうまく出てこない焦り
電話口で言いたいことがまとまらない。頭では整理していても、言葉が追いつかない。相手は当然待ってくれない。沈黙が気まずくなり、とりあえず何かを言ってしまう。その「とりあえず」が後で命取りになる。言葉って本当に怖い。書類の世界では何度も見直せるのに、電話の世界では一瞬で伝えてしまわなきゃならない。噛んだり、詰まったり、余計なことを言ってしまったり。電話が終わったあと、ふと鏡を見た自分の顔がひどく老けて見える時、それが一番応える。
無視できない性格が裏目に出る
電話をスルーする勇気がない。かかってきたら出る、それが「誠実」だと信じてきた。でもその結果、仕事がどんどん詰まっていく。しかも急ぎの案件じゃなかったときの、なんとも言えない徒労感。数分の会話で失う集中力。折り返しのタイミングを探っている間に、他の業務がどんどん先延ばしになっていく。自分の優しさや真面目さが、むしろ自分の首を絞めているような感覚。電話一本に引きずられて、午前中が全部台無しになることもある。
折り返すタイミングを測るストレス
すぐに折り返したら「ヒマなのか」と思われるかもしれない。逆に間が空きすぎると「対応が遅い」と責められる。たった一本の電話に、そんなにも気を使わなければならないのかと自分でも情けなくなる。相手が市役所なら昼休みを避けなければならないし、不動産会社なら夕方の時間帯が忙しい。考えすぎかもしれない。でもこの業界、ちょっとした「気の利かなさ」が致命傷になることだってあるのだ。
かけ直した先に待っているのは補正か怒りか
勇気を出してかけ直すと、だいたい怒っている。書類が足りない、説明がわかりにくい、期日に間に合わない。この3つのどれか。理不尽な怒りもある。たまたま郵便が遅れただけなのに、私の責任にされることも多い。「それはこちらでは把握できませんが…」と言うと、相手はますますヒートアップする。何度も謝り、頭を下げ、それでも納得してもらえないとき、自分が無力な存在に思えてならない。
電話に出るたびに削られていくメンタル
この仕事を始めたばかりの頃は、電話一本一本がやりがいだった。誰かの役に立てていると思えたし、直接声を聞いて感謝されると嬉しかった。でも、いつしかその電話が怖くなった。ひとつひとつが「地雷」に見えてくる。だからか、最近は電話が鳴ると動悸がする。仕事以前に、人として消耗しているのかもしれない。
こちらの準備などおかまいなし
相手の都合でかかってくる電話に、こちらの都合など関係ない。今、別の案件を処理していても、移動中でも、容赦なくかかってくる。特に、トラブル系の電話は「いま対応できるか」が勝負になる。頭を切り替えなければならないが、それがうまくいかない。最初の返答でトーンが噛み合わないと、そのままズレたままの会話になる。準備さえできていればうまくいったのに、という悔しさが残る。
資料も気持ちも整わないまま応答
「あの件ですが」と言われても、すぐにはピンとこないことも多い。資料を開いて確認したいが、電話口では待ってもらえないこともある。結果的にあやふやな返答になり、後から補足メールを送る羽目になる。だったら最初からメールにしてくれたらいいのに、と内心で何度も思う。だが相手にとっては「話す方が早い」のだろう。そのギャップが埋まらないまま、今日もまた電話が鳴る。
言葉のすれ違いが不安を増幅させる
言ったつもり、伝えたつもりでも、相手には届いていなかった。そんなことが何度もある。とくに高齢の依頼者や不慣れな相手だと、ニュアンスの違いが命取りになる。郵送か持参か、委任状が必要か不要か、その一言で業務の進捗がまったく変わってしまう。「確認しましたよね」と言われると、こちらとしては「しましたけど…」としか言えない。そのすれ違いが、不安をさらに大きくする。
電話対応の呪縛から逃れたい
電話を取るたびに自分が少しずつ壊れていく気がする。決して誰かを責めたいわけじゃない。けれど、どうしても「電話が多い日」は疲労感が段違いなのだ。書類を作る作業の方がよほど気が楽だ。ならば、電話に依存しない働き方を模索すべきではないか——そう思うが、現実はそう甘くない。
LINEやチャットではダメなんですか
正直なところ、LINE WORKSやチャットツールを導入したい。文字なら記録も残るし、誤解も少ない。でも、相手がそういうツールに慣れていないケースが多すぎる。そもそもアプリのインストールから始めなければならないこともある。結局、「電話のほうが早い」「話せばわかる」という結論に戻ってくる。こちらの思惑は通じないまま。
説明しすぎると誤解されるジレンマ
電話では簡潔に説明しなければならない。でも、簡潔すぎると誤解される。じゃあ丁寧に説明しようとすると、今度は「くどい」と言われる。この塩梅が本当に難しい。正確に、かつ簡潔に。それがどれほど高度なスキルか、もっと広く認識されてほしい。こちらも人間なのだから、たまには言い間違えることもある。けれど、それが命取りになる場面があるのが、士業のつらさだ。
結局、顔を見ない不安は解消できない
会って話せばすぐに伝わることも、電話ではなかなか伝わらない。声のトーン、話す間、言葉の選び方——どれをとっても、相手の感情や背景を読み取るのは難しい。だから、最後にはやはり「一度ご来所いただけますか」となる。顔を合わせれば、少しほっとする。でもその分、余計に電話が怖くなるという矛盾も抱えている。
電話文化と士業の矛盾
士業の世界では、まだまだ電話が主流。FAXさえ現役だ。けれど時代は変わっている。情報の伝達手段も多様化しているのに、それが反映されない業界。自分たちがその文化を支えてしまっているという事実にも、少しだけうしろめたさを感じる。
なぜいまだに電話が一番早いなのか
「電話の方が早い」その言葉は、今や呪文のように繰り返される。でも本当にそうなのだろうか?電話をかけて、繋がるのを待ち、名乗り、説明して、確認して、メモを取り——その一連の流れは、決して効率的とは言えない。メールやチャットで済む内容も多い。にもかかわらず、それが受け入れられない文化が、この業界には根強く残っている。
人と話すのが苦手な士業もいる
士業=人当たりが良くて説明上手、というイメージがあるかもしれない。でも実際は、机に向かって書類を作る方が得意な人も多い。私もそのひとりだ。会話が得意ではない。特に電話のように相手の表情が見えないやり取りは、ものすごく緊張する。それでも、「それが仕事」として受け入れてきた。でも限界はある。
でも声を聞いて安心しましたと言われると弱い
そんな中でも、たまに「声を聞いて安心しました」と言ってくれる人がいる。その瞬間、すべてが報われた気がする。言葉には重さがあり、温度がある。自分が何かの助けになれたと思えるその瞬間のために、また電話に出てしまう自分がいる。そして今日もまた、心の準備ができないまま、着信音が鳴り響く。