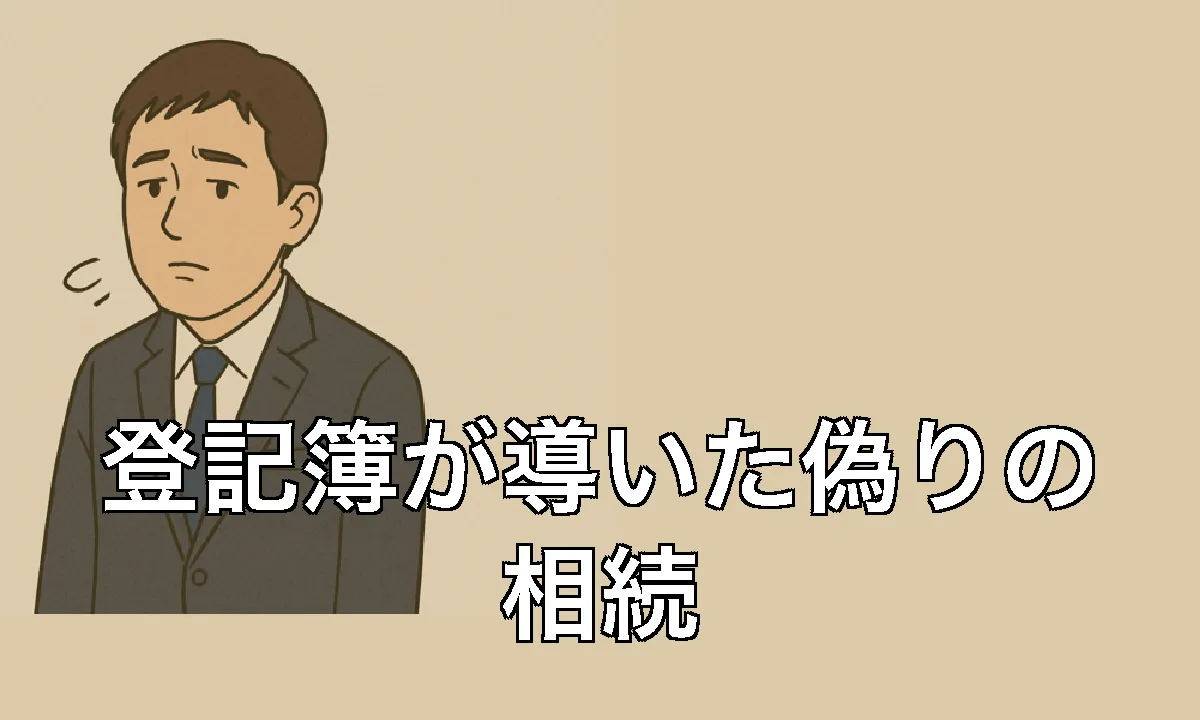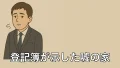朝一番の訪問者
夏の朝、冷房がようやく効き始めた頃、事務所の扉がバタンと乱暴に開いた。
サトウさんが「今日は静かだといいですね」と言っていた矢先だ。
男はスーツに身を包み、やや緊張した面持ちで書類を差し出した。
不機嫌なサトウさんの低い声
「朝イチで飛び込みですか。予約してませんよね?」
サトウさんの声は冷たいが、的を射ている。
男は「あの、急ぎでして…」と戸惑いながら答えた。
差し出された一枚の戸籍謄本
戸籍には、亡くなった父親の名前と、息子を名乗る依頼人の名前が並んでいた。
一見すると普通の相続案件に見えるが、なぜか違和感が拭えなかった。
戸籍に記載された死亡日は、つい最近のものだった。
依頼内容は相続登記
「父が亡くなりまして、土地の相続登記をお願いしたいんです」
淡々と語るその口調に、どこか作られた芝居じみた空気が漂っていた。
私の中に小さな警鐘が鳴り始めた。
何かが引っかかる依頼人の態度
相続の話をするには、あまりに感情がこもっていない。
まるで、他人事のような語り口だった。
サトウさんも無言のまま、じっと依頼人を観察していた。
被相続人の死亡日が怪しい
戸籍には確かに死亡の記載がある。
だが、登記簿を確認すると、所有権がすでに移転していた形跡がある。
まるで、死ぬ前に何か細工があったかのようだ。
登記簿から読み取れる違和感
法務局のオンライン登記情報では、数ヶ月前に仮登記がされていた。
その仮登記が何らかの形で本登記に切り替わっていたのだ。
しかも、それは依頼人に有利な内容だった。
所有権移転のタイミング
死亡の約1週間前に仮登記が入り、死亡日直後に完了。
普通ならその逆だ。何かが順序を飛ばしている。
「この順番、おかしいですね」とサトウさんがつぶやいた。
仮登記に残る奇妙な履歴
登記原因が「贈与」となっていた。
死期が近い父親が、なぜ急いで土地を息子に贈与したのか。
しかも、その時点では入院中で、意思能力も怪しかったという。
市役所と法務局への調査
私は市役所へ向かい、死亡届の提出日を確認した。
提出日は死亡の翌日、だが書類が不自然に整いすぎていた。
「まるで準備していたみたいですね」と窓口の女性がこぼした。
死亡届と登記日付の食い違い
登記完了日は、死亡届が受理されるより前だった。
それは明らかに矛盾している。
だれかが、書類を先回りして操作していた可能性がある。
職員の「おかしな話ですね」の一言
「こういうケース、最近多いんですよ」
市役所の職員は呆れたように言った。
やれやれ、、、なんだかサザエさんの波平が「バッカモーン!」と叫びそうな展開だ。
もう一人の相続人の存在
戸籍の続柄を丹念に追うと、もう一人の子が存在していた。
行方不明とされていた姉だった。
その名前は、依頼人が提出した遺産分割協議書にはなかった。
隠されていた姉の存在
私はその姉に連絡を取った。
彼女は「何も知らされていませんでした」と驚きと怒りをあらわにした。
これで話が大きく動く。
遺産分割協議の闇
全員の署名押印が必要な協議書に、姉の名前はなかった。
つまり、偽造された協議書で登記が進められていたということだ。
これはもう、単なる手続きミスでは済まされない。
サトウさんの推理
「こういうとき、よくあるんですよ。戸籍も登記も専門家を使わずにやろうとするから」
冷静な声で、事件の核心を突く。
私は相変わらず感情が先に出てしまうタイプだ。
「これ、典型的なやつですね」
「相続を急ぎすぎて、姉の存在をなかったことにしたい。
だけど、登記簿と戸籍は嘘をつけない」
サトウさんの推理は、ほぼ的中していた。
過去の判例から見えてくる構図
私は過去の判例をいくつか洗い、似た事例を発見した。
無断登記による損害賠償が認められたケースだ。
これは、依頼人の立場が一転する可能性がある。
偽造された印鑑証明書
法務局に調査嘱託を提出し、印鑑証明書の真偽を問う。
その結果、姉の印鑑証明書は偽造されたものと判明した。
決定的証拠だった。
司法書士としての出番
「私、証拠書類まとめます。提出は明日でいいですね?」
サトウさんが冷静に確認する。
私もようやく役に立つ時が来た。
調査嘱託という武器
司法書士には、調査嘱託制度を使って事実を照らす力がある。
それは地味だけど確実な武器だ。
今回も、それがものを言った。
法廷ではなく登記の現場で戦う
依頼人は結局、登記の抹消に応じることになった。
姉にも正式な権利があると認めざるを得なかったのだ。
裁判にせずに済んだのは、登記簿がすべてを語っていたからだった。
家族間トラブルに潜む犯罪の芽
相続の争いは、時に犯罪の入口になる。
司法書士は、その一歩手前で止める役割を担っている。
ただの書類屋では、済まされない場面がある。
善意と悪意の境界線
依頼人は最初、自分の正義を信じていたのだろう。
だが、それが他人を踏みつけるものだったと、後から気づいたようだった。
その気づきがあるなら、まだ救いはある。
真実は登記簿が語っていた
誰が嘘をついても、登記簿と戸籍は正直だ。
淡々とした書類の中に、確かな事実が刻まれている。
我々司法書士は、それを読む目を持たなければならない。
紙に残るのは冷たい証拠だけ
登記簿は、感情を語らない。
けれど、その無機質な記録こそが、真実を伝えてくれる。
そして、それを解釈するのが我々の仕事だ。
依頼人の本当の目的
後日、依頼人から手紙が届いた。
「姉とは、話し合うつもりです」とだけ書かれていた。
ようやく、嘘の相続から一歩前に進んだのかもしれない。
静かな結末と日常への帰還
事務所に戻ると、サトウさんが冷たいアイスコーヒーを机に置いた。
「今日は静かに過ごせますかね」
私は笑って、「やれやれ、、、それはフラグってやつだよ」と答えた。
「やれやれ、、、結局こうなるのか」
その時、また電話が鳴った。
「ええ、亡くなった方の名義がまだそのままでして」
やれやれ、、、次の事件がもう始まっていた。
サトウさんの氷のような一言
「シンドウ先生、フラグはちゃんと回収してくださいね」
彼女はそう言って、自分のアイスコーヒーを一口すすった。
事件は終わっても、日常は終わらない。