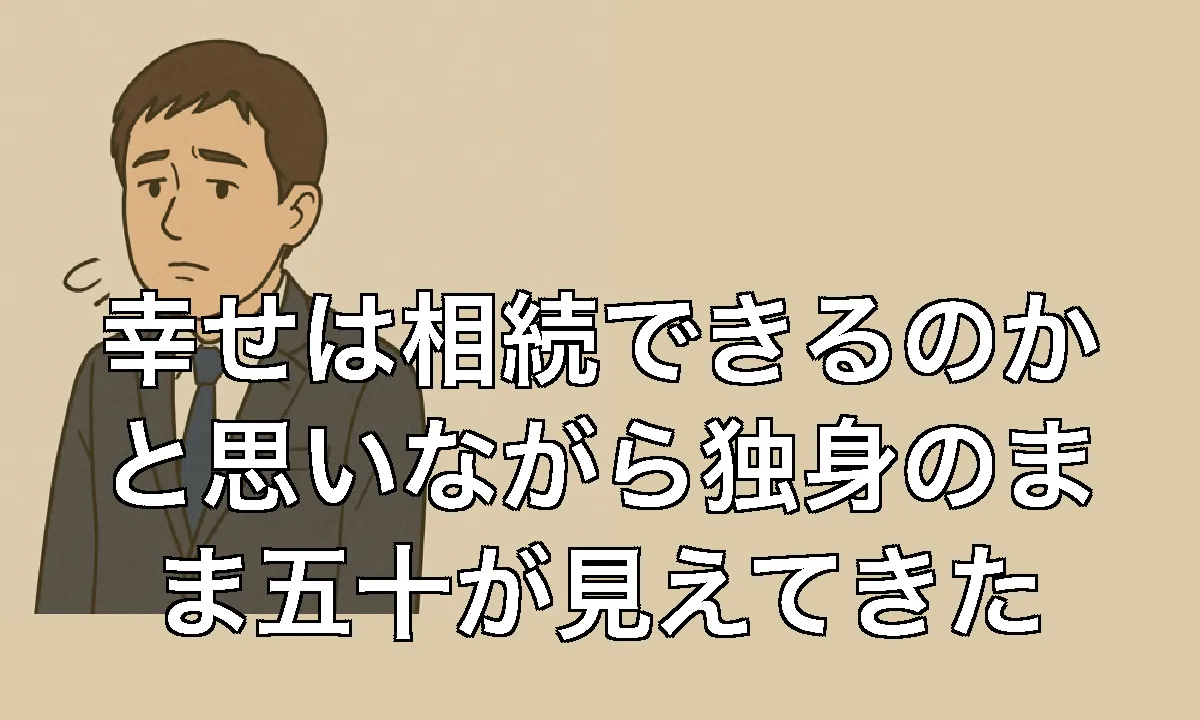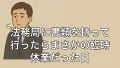独身司法書士として迎える朝の重さ
朝起きて、台所に立ち、インスタント味噌汁にお湯を注ぐ。何年も同じような朝を繰り返しているけれど、どこか気力が湧かない。昔はもっと体が軽かったはずだが、最近は布団から出るのにも少し時間がかかるようになった。事務所はそこそこ忙しいし、仕事の内容自体に不満があるわけじゃない。でも、どこか満たされない感じがずっと心の底にある。おそらく、それは「誰かと過ごす時間」がごっそり欠けているからなのだろう。
目覚ましの音だけが響く部屋
30代のころは、こんなに孤独が響くとは思っていなかった。目覚ましが鳴っても誰も止めてくれない。テレビの音をつけなければ、今日という日の最初の音は、自分の咳払いか冷蔵庫のうなり声だ。ああ、誰かが台所で立っていてくれたら、と何度思ったか分からない。でも気づけば、そういう風景は「他人のもの」になっていた。自分が選ばなかった結果とも言えるけど、今さら選び直せるわけでもない。
誰のために働いているのか分からなくなる瞬間
司法書士として働いていれば、それなりに人の役に立てている感覚はある。でも、それはどこか「他人の人生の話」だ。登記が完了し、笑顔で帰っていく依頼者を見送るとき、自分の心はいつも置き去りだ。「ありがとう」と言われても、それを誰かと分かち合うことはない。この孤独な実感は、たぶん結婚して子どもでもいれば、多少は薄まるのだろうと思ってしまう。
元野球部の根性はどこへ行ったのか
若いころはもっとがむしゃらだった。高校時代、野球部で泥だらけになりながら走ったグラウンド。その頃は何もなくても、仲間と笑えていればそれだけで幸せだった。あの頃の根性や情熱はいったいどこへ行ったんだろう。目の前の書類に囲まれ、静かな事務所にこもる日々。気づけば体力も気力も、ちょっとずつ削られているような気がする。
「幸せ」って何だろうとふと考える
最近、依頼者の中にも年配の方が増えてきた。遺言や相続の手続きを頼まれるたび、「この人は自分の人生を幸せだと感じていたのだろうか」と、ふと思う。形式的な手続きだけを進めていくうちに、こちらまで感情が無機質になっていくような気がするけれど、どこかで「自分もそろそろ何かを残す立場かもな」と感じる瞬間が増えた。
目に見えないものは相続できるのか
不動産や預金は相続できても、「思い出」や「ぬくもり」はどうやって伝えられるのか。形式的な遺言の文面には書けないものが、実はいちばん大事なのかもしれない。幸せとは、形ではなく、空気や間、言葉の節々に宿るものだと思う。けれど、それを残す術は、正直、今の自分には分からない。たぶん、それが分からないまま年を取っているのだ。
依頼者の笑顔と自分の感情の温度差
登記が終わり、ホッとした顔で帰っていく依頼者を見るたびに、どこか置いてけぼりを食らったような気分になる。あの人たちは誰かのために家を買い、守り、受け継がせようとしている。自分には、そういう誰かがいない。ただ淡々と処理するだけの日々が、少しずつ自分を冷たくしている気がしてならない。
親が残してくれたものと残してくれなかったもの
うちの親は、普通の人だった。田舎の小さな工場勤めで、特別裕福でもなかったが、家族のために必死に働いてくれていたと思う。でも、心のつながりの部分では、何かが足りなかった気がする。たぶん、言葉にして気持ちを伝えることが、苦手だったんだろう。それを相続してしまったのが、今の自分かもしれない。
形ある相続と形なき欠落
土地や家は遺されたけれど、そこに宿る「安心感」や「愛情の記憶」は、思い出そうとしても薄い。形式的には立派な遺産でも、心を温めてくれるものではなかった。自分が誰かに何かを残すとしたら、果たしてそれは「足りている」のだろうか。今のままでは、空っぽの箱を渡すことになりはしないかと不安になる。
家族という安心感を受け継げなかった話
昔、友人の家に遊びに行ったとき、夕食後の団らんに何とも言えない安心感を覚えた。父親がテレビを見ながら笑い、母親が台所で洗い物をし、子どもが膝に乗っていた。その空気感こそが「幸せの正体」だったのかもしれない。うちにはなかった空気。それは、今でも自分の人生から欠落しているように思う。
事務員の存在が支えになっていることに気づく瞬間
この歳になって、ようやく誰かと一緒に働くありがたみが分かってきた。うちの事務員は無口だけれど、丁寧な仕事ぶりで、さりげなく気遣ってくれる。お茶を入れてくれたり、忘れ物をそっと補ってくれたり。そんな小さな優しさに、どれだけ救われているか分からない。幸せとは、そういうところにあるのかもしれない。
たった一人でも分かち合える仕事の喜び
朝からバタバタと書類の山に追われ、気づけば夜になっている。そんな日でも、ふとした拍子に「お疲れさまでした」と声をかけ合うとき、「今日も何とか乗り切ったな」と少しだけ報われた気持ちになる。一人で働いていた頃には感じなかった感覚だ。分かち合える相手が一人でもいるだけで、人はだいぶ救われる。
他人の“幸せ”を手続きするという皮肉
司法書士という仕事は、他人の人生の節目に立ち会う仕事でもある。結婚、出産、相続、死。どれも大切な人生の局面で、書類と印鑑と法律に囲まれた中で「幸せ」を見届ける。でも、自分にはそれが訪れない。誰かの幸せを見送るだけで終わっていくのかと思うと、少しだけ胸が痛む。
遺言や相続に関わるたびに心がざわつく
「この人は誰に何を託したのか」と思いながら遺言書を読み込むたび、自分には託す相手がいないことを思い知らされる。家もなければ、子もいない。兄弟も遠く離れて暮らしている。自分が亡くなったとき、誰が何を整理するのだろう。何を残せるのだろう。そんなことばかり考えるようになってしまった。
書類に書けないものこそ、大事だと知っている
幸せは、登記簿にも戸籍にも書かれていない。けれど、確かにそこにあったものだと、多くの依頼者の顔から感じ取れる。自分はそれを、自分の人生の中でどれだけ味わってきたのだろう。書類ばかりを追いかけてきた時間の中で、大事なものを置き忘れてきた気がしてならない。
結婚も家族もないまま司法書士として生きるということ
「おひとりさま」なんて軽い言葉じゃ表現できない何かが、この歳になると重くのしかかってくる。仕事に逃げてきたつもりはない。でも気づけば、それしか残っていなかった。それでも、誰かの力になれるのなら、この仕事を選んだことに意味はあると信じたい。そう思わないと、やっていけない。
「それで本当にいいのか?」と自分に問う日々
寝る前、天井を見つめながら「これでよかったのか」と問いかける自分がいる。答えは出ない。出せない。でも、少なくとも、誰かに何かを届けられているなら、それでいいのかもしれない。幸せは形じゃない、誰かとの関係の中にあるんだと、最近やっと思えるようになってきた。
もし自分が死んだとき、何が残せるのか
人に見せられる財産もない、自慢できる人生でもない。それでも、自分が悩みながら、もがきながら、それでも前を向こうとしてきた軌跡は、誰かの慰めにはなるかもしれない。そう信じて、今日も机に向かう。それしかできない自分だけど、それでもいいと思える日が、ほんの少しずつ増えてきた。
通帳でも不動産でもなく、何か温かいものを
「ありがとう」と言われた瞬間のこと、「またお願いします」と手を振られたときの温度。それはきっと通帳の残高よりも大事な何かだ。自分が残すものは、そういう記憶や、少しでも人に優しくできたという実感なのかもしれない。少なくとも、それを信じていないと、今日を積み重ねることすらできない。
後輩たちへ「幸せの相続」について語るなら
若い司法書士たちを見ると、どこかまぶしくて、そして羨ましくなる。でも、同時に「ちゃんと悩め」とも言いたくなる。悩んで、苦しんで、それでも誰かの人生に寄り添えるようになってほしい。幸せは、自分の中にあるんじゃない。誰かと過ごした時間の中に、ふと宿るものなのだから。
答えはないけれど、問い続ける姿勢だけは残したい
幸せを相続するにはどうしたらいいのか。その答えは、たぶん誰も持っていない。でも、問い続けること、考え続けること、それこそが一つの“遺産”になるのかもしれない。自分の人生はそれほど特別じゃないけれど、その悩みや葛藤の跡を、誰かが見つけてくれたらいい。ほんの少しでも、誰かの道しるべになれば。