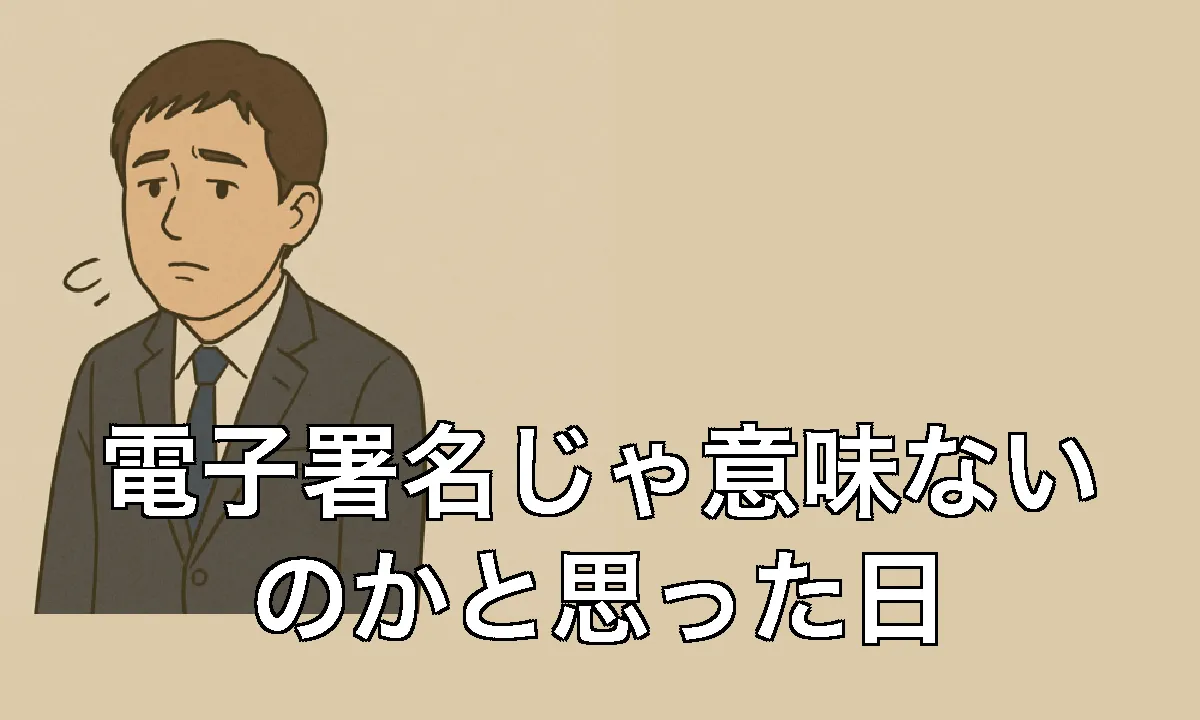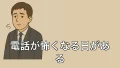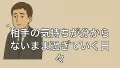電子署名が拒否されたあの瞬間の戸惑い
ある日、ある金融機関から届いた書類に、電子署名を付けて返送した。自分なりに効率よく、セキュリティにも配慮して対応したつもりだった。だが数日後、先方から届いたのは「この書類は直筆でご署名をお願いします」という一文。正直、頭が真っ白になった。「いやいや、電子署名の法的効力はご存知では……?」という気持ちをぐっと飲み込んで、「失礼いたしました。再度直筆にてお送りします」とだけ返した。なんともいえない無力感と、時代とのギャップを感じた一日だった。
デジタル化に乗ったつもりだった
司法書士としても、一人の事業者としても、業務の効率化は常に頭の片隅にある。特に最近は、電子契約サービスも使いこなせるようになってきたし、「紙から脱却するんだ」と意気込んでいた。しかし現実は甘くない。相手によっては、電子署名なんて見たこともないという態度で返してくる。まるでこちらが先走ったかのような扱い。元野球部の癖で「チームプレイが大事」と思ってやってきたけど、この業界、まだまだ個人プレイで回っているのかもしれない。
紙文化の壁はまだ厚かった
昔ながらの紙文化、ハンコ文化、そして「書いた感」のある署名文化。司法書士の現場はまさにそれの温床だ。もちろん法的には電子署名も立派な本人確認手段だけど、「気持ちの問題です」と言われたらもう反論も難しい。まるで「手紙の方が温かい」と言われてる気分。いや、それは分かるけども……こちらも暇じゃないんだ、と言いたくなる。しかも、毎回それで時間を食うと、こっちは本当に残業確定である。
署名ひとつで差し戻される現実
この業界では、「一字一句ミスが許されない」なんてことも日常茶飯事だ。署名もその一部で、形式が違えば即差し戻し。今回のように「直筆じゃないと認めない」と言われたとき、頭に浮かんだのは「またか…」という諦め。電子署名で通った件もあるのに、相手が違えばこの有様。柔軟性というものはどこへ行ったのだろう。まるで審判によってstrikeゾーンが違う草野球の試合に参加してるような気分だ。
直筆でお願いしますに込められた空気
「直筆でお願いします」――たったそれだけの一文に、いろんな意味が詰まってる気がしてならない。おそらくそれは、「昔ながらのやり方に従え」という無言の圧力だ。こちらがいくら丁寧に対応しても、「そうじゃない」と返されることの虚しさ。まるで期待を裏切った生徒のような気持ちになる。「お前、空気読めよ」と言われてるようで、正論が通じない場面にイライラする。でも、相手の立場も分からなくはないのがまた腹立たしい。
相手の顔色をうかがう自分がいる
昔はもう少し自分のやり方に自信があった。けれど年々、「波風立てずに済ませたい」という気持ちが勝ってきている。司法書士として間違ったことはしていないのに、「直筆でお願いします」と言われた瞬間、自動的に「すみません」と答えてしまう自分がいる。まるで家庭で怒られた子どもみたいな反応。主張するのが面倒になるのは、歳のせいなのか、孤独のせいなのか。どっちにしろ、もう少し強くなりたいとは思ってる。
どうしても飲み込めない納得できなさ
納得はしてない。してないけど、やり直した。やり直さないと前に進まないから。とはいえ、「これは正しくないよな」という気持ちはずっと胸の中に残っている。正直に言えば、疲れる。事務所を出るとき、誰にも愚痴を言えない自分がいて、コンビニのレジで「袋いりますか?」と聞かれた瞬間に「はぁ…」とため息をついてしまったりする。そんなときは、もう自分で自分を励ますしかない。
効率化と現場感覚のすれ違い
効率化は正義だと思っていた。でもそれはあくまで「こっち側の理屈」だったのかもしれない。いくら便利な仕組みを整えても、現場がそれを受け入れなければ意味がない。このギャップは、想像以上に大きくて深い。司法書士という仕事は、法律と現実の狭間で揺れることばかり。ときに合理性を語ることが、空気の読めないやつの烙印を押されることもある。
事務員との愚痴タイムが始まる
「またですか?」と事務員が苦笑いする。こっちもつられて「うん、まただよ」と言いながら、二人で茶をすすりながらの愚痴タイムが始まる。こういう時間があるからまだ救われてる。もし一人だったらと思うとゾッとする。事務員がいるだけで、ひとまず笑えるし、話せる。たった一人の存在が、今日一日をやり過ごす力になる。そんな小さな支えが、この仕事には必要だ。
また直筆ですかのため息
「また直筆ですかね」って言葉を聞くたびに、「これもう合言葉か?」と思う。もう笑うしかない。電子化の波が押し寄せる世の中で、なんでこの業界はこんなに頑ななんだろうと考え込む。別に新しい技術に目をつぶれと言ってるんじゃない。ただ、もう少し柔軟に、少しだけでいいから時代に合わせてくれたら、どれだけの人が救われるんだろう。自分だけじゃない、みんなが息苦しい。
それでも現場を回すためにやるしかない
最後はやるしかない。それが現実。文句を言っても変わらない。だったらやるしかない。でもその「やるしかない」が、いつの間にか積み重なって、自分の心を少しずつすり減らしている。仕事が終わって、家に帰っても何もしたくない日が増えた。だけど、それでも現場は回さなきゃいけないし、誰かの登記が進まなければ、その人の人生も止まってしまう。そう思えば、ペンを持つ手にも力が入る。
便利なはずの仕組みが通じないとき
便利なはずの仕組みが通じないときほど、徒労感が強くなる。せっかく覚えて、試して、使いこなせるようになったのに、それが否定されるのはきつい。無駄だったのかと疑ってしまう。けれど、その積み重ねが、いつか時代を変えるのかもしれないという希望もどこかにある。だから、完全には折れたくない。
制度と現実のギャップに疲れる
制度は前を向いている。でも現場は後ろを見ている。そんなことが多すぎる。法律が整備されても、それが実際に使われるには、まだ何年もかかる。ギャップの中で仕事をしていると、感情がついていかなくなる瞬間がある。思考と気持ちのズレ。それが積もると、ふとした瞬間に「もう嫌だ」と口にしてしまう。実際、やめたくなることは何度もある。
電子化への期待がまた遠のく
今回の件で、正直なところ電子化への期待はまた一歩後退した。「いつか分かってもらえる日が来る」と信じていたが、その日が思ったより遠い気がしてならない。自分が古くなる前に、時代が少しでも進んでくれたらと願う。でも、現実は変わらない。日々の積み重ねの中で、少しずつでもいいから、受け入れてくれる人が増えることを願っている。
前に進んだはずが後戻りする感覚
今回、確かに前に進んだつもりだった。電子署名を使いこなして、スムーズに仕事を終わらせようとした。でも、現実は後戻りだった。それでも、その一歩がなければ進化はないと思いたい。人は失敗して、拒否されて、それでもやり続けて、やっと少しずつ変わっていける。だから、たとえまた直筆を求められても、次もまた電子署名で出してみようと思っている。めんどくさいけど、それが自分なりの「変えたい」意思表示だ。
それでもやっぱりやるしかないという気持ち
結局のところ、文句を言いながらも、やるしかない。司法書士という職業は、そういう矛盾と正面から向き合うことが仕事なのかもしれない。疲れる。でもやめない。やめられない。だって、やってきたことに意味があったと信じたいから。電子署名がまた拒否されても、それでも書類は送るし、登記はする。それが自分の仕事であり、生きている証なのかもしれない。