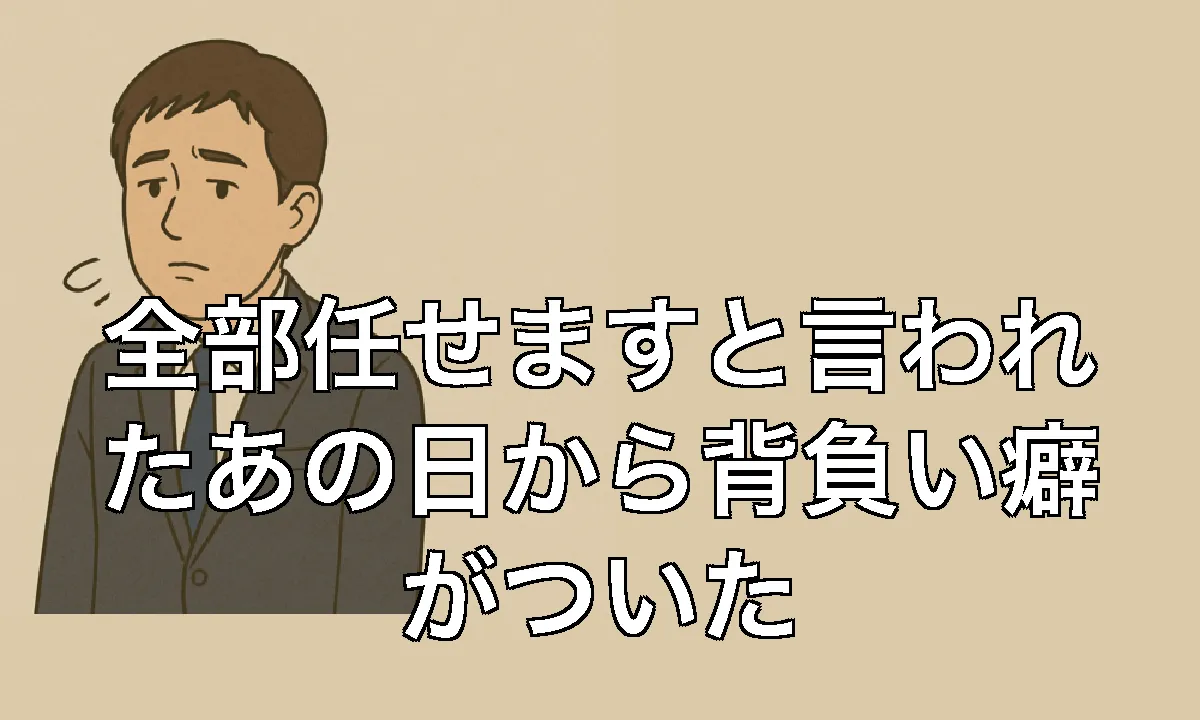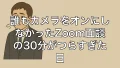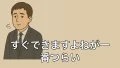一言の「任せます」が重すぎる時がある
「全部先生に任せます」。この一言に救われたような気がしたのは最初のうちだけだった。地方で一人事務所を切り盛りする身としては、信頼されるのはありがたいことだと、そう思っていた。でも気がつけば、その「任せます」は、決断を丸投げされていることでもあった。責任はすべてこちらに降りかかる。うまくいけば「さすが先生」、うまくいかなければ「そうじゃなかった」と陰で言われる。それが現実だ。
ただの信頼じゃなかった
あのときの依頼者は、初老の男性だった。遺産分割協議について親族と揉めているが、もう考えるのが嫌だという。疲れ切った顔で「もう全部先生に任せます」と言った。人の良さそうな笑顔だった。信頼されているんだと思って、その瞬間は少し誇らしかった。でも実際には、その人は自分で決める覚悟も放棄していた。「任せる」という言葉の裏には、「責任もあなたが取ってね」という無言の圧力があった。
責任感と引き受け癖の境界線
私は昔から頼まれると断れない性格だった。元野球部のキャプテン気質が残ってるのか、「お前に任せる」と言われると、ぐっと力が入ってしまう。でも、司法書士として働くうちに、それが危険なことだと痛感するようになった。信頼と依存はまったく別のものだ。線引きをしなければ、ただの便利屋にされてしまう。それでも「先生にしか頼めない」と言われると、嬉しさと共にプレッシャーがのしかかってくる。
優しさで引き受けたことが仇になる瞬間
ある日、任された案件で揉めごとが起きた。書類通りに進めたはずが、他の相続人から猛反発を受けた。「先生に任せたって言うから、黙ってたのに」と言われたとき、目の前が真っ白になった。自分の判断が間違っていたのか、いや、依頼者が家族に説明を怠っていたのか。でもそんな責任の所在なんて、依頼者にとってはどうでもいいのだろう。「先生が決めた」で済まされる。その瞬間、優しさで引き受けたことが自分の首を絞めていた。
断ったほうが良かったかもしれない後悔
あのとき、「それはご自身でお決めください」と突き放せていれば、違う展開があったのかもしれない。でも、そんな勇気はなかった。頼られるのが嬉しいという気持ちと、断って見捨てるように感じられる後ろめたさが勝ってしまった。優しさと無責任の境目は、自分がどこまで責任を背負うかで決まる。そしてその境界線を越えてしまったとき、人は後悔をする。私も、その一人だった。
司法書士という職業の“なんでも屋”感
司法書士の仕事は法律職と見られがちだが、実際には“なんでも屋”のような感覚に陥ることがある。登記や書類作成だけでなく、人間関係の調整や家族間の揉め事の仲介まで求められる。相談に来る人の中には、こちらが専門職であることすら理解していない人もいる。とにかく「困ったら先生に聞こう」という空気が地方には根強くあるのだ。
聞かれてないのに判断を迫られる日々
「これでいいですよね?」「間違いないですよね?」と、念押しするように聞かれる日々。そのたびに「これは私の判断ではなく、あくまでご自身で」とやんわり返すが、相手は納得しない。どこかで「先生が言うなら」と言質を取りたがっているのが伝わってくる。でもその“判断”の責任を後で問われるのは私なのだ。まるで、目に見えない爆弾処理を毎日しているような気分になる。
「先生の言う通りで」と言われる怖さ
一見すると信頼されているように見える「先生の言う通りで」は、実は一番危ういセリフかもしれない。自分の考えや意思を放棄した人からは、後で何を言われてもおかしくない。過去に一度、ある高齢女性に「全部先生に言われた通りにしたのに」と責められたことがある。こちらは説明し、確認し、納得を得たつもりだったが、その“納得”は本当に本人のものだったのか。それ以来、「任せます」という言葉が怖くなった。
背負い込むと本来の業務が見えなくなる
本来やるべき仕事は、登記であり、契約書の確認であり、法律の専門家としての助言のはずだ。でも、相談者に深く踏み込みすぎると、気づけば相手の人生相談まで引き受けてしまっている。そして時間も気力も削られて、気づけば本来の業務が後回しになっている。忙しいのは業務のせいではなく、背負い過ぎている自分のせいなのかもしれないと、自分に問いかけることも増えた。
誰かに頼れたら少しは楽になるのか
「先生しかできないから」そう言われるのは名誉なことのようで、実は呪いの言葉でもある。事務所にいるのは、事務員さん一人。彼女は真面目でよくやってくれているが、やれる範囲は限られている。結局のところ、判断も責任も、最後には自分一人で抱えることになる。頼れる仲間がいればと思うことはあるが、それを求める余裕すらなく日々が過ぎていく。
事務員一人ではどうにもならない現実
登記の入力、書類の確認、相談者の応対、電話の受け答え……。事務員一人に任せるには限界があるのに、どうしても手が回らないときは頼るしかない。彼女は文句も言わず応えてくれるが、その分、こっちの申し訳なさが積み重なっていく。人を増やしたいと思っても、田舎で司法書士事務所に応募する人なんてほとんどいない。気づけば、頼りたいけど頼れない現実に囲まれていた。
外注という選択肢の難しさと孤独
一度だけ、書類作成の一部を外注したことがあった。内容は問題なかったが、やはりどこかで「これは自分の手を通していない」という不安が残った。もしミスがあったら、自分の信用が傷つく。それならば自分でやるしかない、という思考に戻ってしまう。外注は時間を生むけれど、同時に「信用の壁」と「孤独感」を突きつけてくる選択肢でもあった。
「先生しかできないこと」に縛られて
「この案件は先生じゃないと無理ですよ」と言われることがある。嬉しい反面、それが枷にもなる。どこかで、「これは自分しかやれない」という思い込みが自分自身を縛っているのだ。そんな風にして、背負い癖が強化されていく。でも時々、ふと立ち止まって、「本当にそうか?」と問い直す。もっと手放しても、誰かに任せてもいいのかもしれない。そう思えたら、少しだけ肩が軽くなった気がした。
肩の力を抜くために必要なこと
全部を背負わない。これは私自身が今、身につけようとしているスキルだ。司法書士という立場は、頼られやすく、同時に孤立しやすい。でも、自分が倒れてしまったら元も子もない。だからこそ、時には“断る勇気”や“誰かに任せる覚悟”も必要だ。それは決して無責任ではなく、自分を守るための選択でもあるのだ。
全部を引き受けない覚悟
かつての私は、「任せます」と言われるたびに、すべてを背負っていた。だが今は、ほんの少しずつだけど、「それは一緒に考えましょう」と返すようになった。それでも不安にはなる。断ったことで関係が壊れるんじゃないかとか、信用を失うんじゃないかとか。でも、全部を引き受けた結果、自分が壊れそうになるよりはずっといい。自分の限界を知り、守ることもまたプロの姿勢だと思うようになった。
断ることが相手のためになることもある
ある依頼者に、「それはご自身でお考えになるべきことです」と初めてきっぱり伝えたことがある。相手は一瞬驚いた顔をしたが、数日後にはきちんと方針を決めて戻ってきた。「自分で決められて良かった」と言ってくれた時、ああ、断ることも優しさなんだと実感した。いつも受け止めるだけが優しさじゃない。時に突き放すことで、相手も自分も強くなる。それを教えてくれた出来事だった。
少しだけ自分を甘やかしてみる
最近は、帰り道にコンビニでプリンを買うことにしている。小さなご褒美だけど、「今日も頑張ったな」と思える瞬間があると、また明日もやろうという気持ちになる。誰にも褒められない仕事だからこそ、自分くらいは自分を認めてやらないとやっていられない。全部を背負い込むのではなく、時には手を抜く勇気も持って、もう少しだけこの仕事を続けていこうと思う。