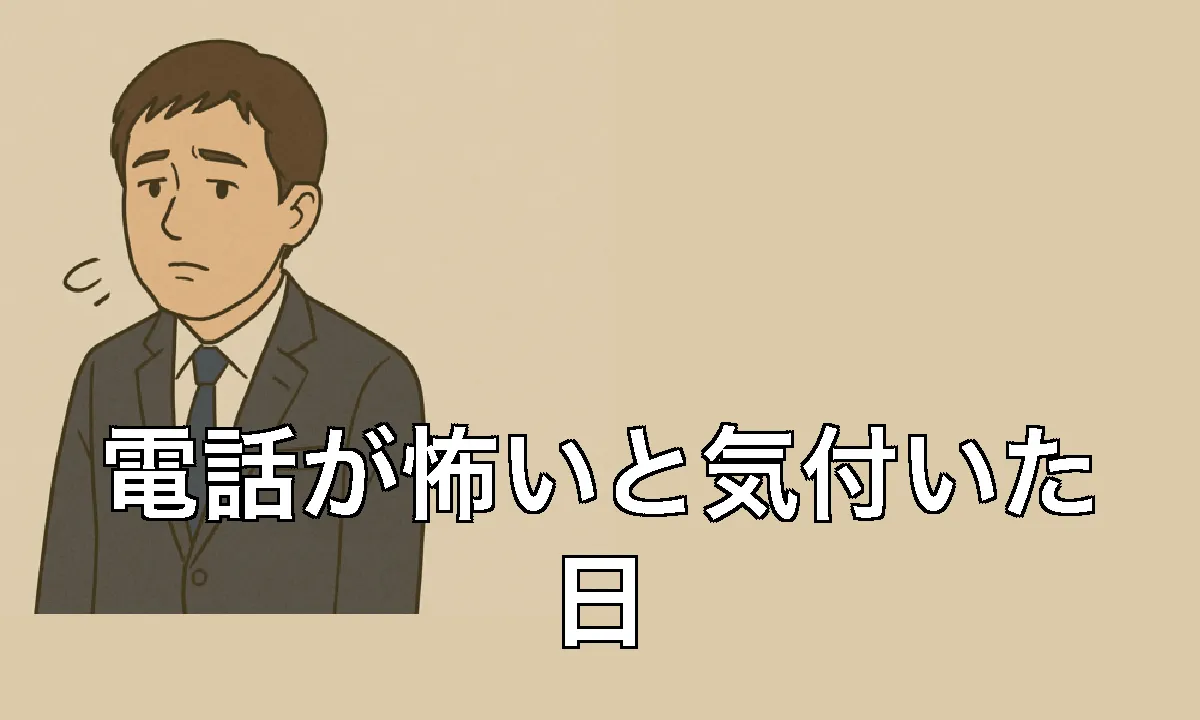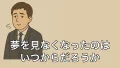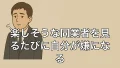電話が怖いと気付いた日
電話対応がいちばん神経を削る理由
司法書士という職業柄、電話は避けて通れません。けれど、この「電話」というツールが、実は私にとって一番のストレス源だと気付いたのは、開業して数年経ってからのことです。業務中に鳴る電話は、いつも「何かが起こった合図」のように聞こえてしまい、そのたびに胸がズンと重くなる。依頼の電話もあれば、クレーム、急ぎの対応依頼、資料の不足確認など、どれも「気持ちを整える間」を与えてくれないのです。
いつ鳴るか分からない不意打ちのストレス
一番辛いのは、集中して書類を作っているときに、突然鳴り出す電話の音です。頭の中で論理を組み立てている途中に、それがガシャーンと崩れるような音で遮られる感覚。例えば、決済書類の準備で神経を使っているときなどは、鳴った瞬間にイライラよりも「うわ、勘弁してくれ」というため息が漏れます。そして電話を取ると、事務的な声で「今いいですか?」。いや、正直言ってよくない。でも出ないわけにはいかないんです。
集中しているときほど鳴るというあるある
なぜか本当に集中している時間帯に限って電話が鳴る確率が高いんです。これは私だけじゃなく、事務員の彼女もよく「今ですか…」と苦笑いしています。特に午後の2時〜4時の間は集中モードに入ることが多いのですが、そのタイミングで電話が立て続けに3件くらい鳴ると、もう何をしていたのかすら思い出せないこともあります。リズムが崩れると、その後の作業効率がガクンと下がるのもつらいところです。
それでも出ないわけにはいかない現実
電話に出ない=対応が遅い、印象が悪い、という評価につながるのがこの業界。依頼人や不動産業者は、メールよりもまず「電話派」が多い。しかも彼らは「出ないなら他へ頼もう」と考えることもあるため、こちらも応答を疎かにはできません。怖いと思っても、電話は無視できない。これがまた精神的にジワジワくるんですよね。電話が鳴るたびに、心のどこかが削られていく感じがします。
相手の顔が見えないことがこんなに辛い
電話のやっかいなところは、相手の表情が一切見えないという点です。口調ひとつ、言葉の選び方ひとつで、相手の機嫌を勝手に想像してしまい、それがストレスを生む。何気ない返事に「イラッとしてないかな?」「怒ってる?」と不安になり、電話を切った後もしばらく気になってしまうことが多々あります。メールなら一呼吸おけるけれど、電話にはその余裕がない。
声のトーンひとつで地雷を踏む恐怖
ある日、相続の件で依頼人と話していたときのこと。こちらは丁寧に説明していたつもりだったんですが、相手の声のトーンが徐々に硬くなっていき、「それっておかしくないですか?」とピリついた雰囲気に。たった一言が「説明不足」と受け取られてしまうと、相手の反応がガラッと変わる。電話では表情も目線もないから、トーンや間で察するしかない。でもそれが外れると、地雷を踏んだような空気になってしまうんです。
沈黙の5秒が生み出す圧と不安
電話の途中で相手が黙る瞬間って、ものすごく怖いんですよね。「ん?怒ってる?納得してない?」と勝手に考えが巡ってしまう。メールなら沈黙も読み手のペースだけど、電話は違う。沈黙は「不満」の前兆のように感じてしまいます。特に、こちらが説明を終えた後に無言が続くと、「何かまずいこと言ったかも…」と内心冷や汗が出ます。実際はただ考えていただけ、ということも多いんですが。
電話越しの依頼内容が一番ややこしい
書類の内容や手続きの詳細を、電話だけで済まそうとする依頼人は少なくありません。けれど、それが一番トラブルの元。こちらが正確に聞き取れなかったり、相手が言い忘れていたりして、後から「あれ言いましたよね?」と食い違いになる。電話で済む話など、実はほとんどないんですよね。せめて一度メールしてほしい、心の中で何度もそう願っています。
口頭説明だけで判断させる依頼人たち
「ちょっと確認なんですが」と始まって、延々と口頭で物件の内容や相続人関係を話されることがあります。そのたびに、手元でメモを取りながら「これ、あとで整理できるか…?」と不安になるんです。資料があれば一発で理解できる内容を、あえて電話で済ませようとする。しかも「あれ?あのとき話しましたよね?」と後から言われても、言ったかどうかなんて録音してるわけでもないし、確認しようがない。
後からあの件ですけどと言われても
一番困るのは、「先週お電話した件ですけど」と切り出されるケース。名前も日付も内容もあいまいなまま話が始まり、「え?何の話?」と混乱するんです。こちらも何十件と電話を受けているので、すべてを記憶しておけるわけじゃありません。せめて名前と要件をもう一度言ってほしい。でもそれを聞くのも、なんだか申し訳ない気がして…とにかく電話は、始まりから終わりまで気を遣いっぱなしです。
なぜ電話でのやりとりだけ疲労感が倍増するのか
書類作成や登記手続き、役所対応などと比べても、電話でのやりとりが一番疲れる気がします。終わったあと、どっと疲れが出る。これは「常に即答を求められる」「ミスが許されない」「相手の意図をくみ取らなければならない」といった要素が重なっているからだと思います。とにかく、一瞬たりとも気を抜けないんです。
メールや書面との決定的な違い
メールやFAXは、こちらのタイミングで確認し、内容をじっくり読んでから対応できる。でも電話は、相手のペースに完全に巻き込まれます。「今すぐ答えて」と言わんばかりの間合いで話が進むため、こちらの考える時間もなければ、準備する時間もない。ミスを防ぐには、電話しながらメモを取り、終わったあとに必ず記録を残す。この二重の作業が、また精神的に重たいんです。
事務員任せにできない事情
電話対応を事務員に任せられたら楽になる、と思うかもしれません。でもうちは人手が足りないし、内容も専門的なことが多く、どうしても私が直接出ることになります。事務員が取っても、結局「先生に代わってもらえますか?」と言われてしまう。電話は物理的にも精神的にも、なかなか逃げ場がない仕事のひとつです。
それでも電話を無視できない職業の宿命
どれだけ苦手でも、どれだけストレスでも、電話は仕事の命綱のひとつ。依頼人との信頼構築にも関わるし、何より「すぐつながる安心感」が求められているのが現実です。正直、電話じゃなくて全部メールにしてくれたら、どれだけ楽かと思うこともあります。でも、そういうわけにもいかない。これが司法書士という仕事なんだと、割り切るしかない部分もあります。
一件の電話が信頼を左右する怖さ
以前、忙しさにかまけて電話を数回取れずにいたら、「電話に出ない先生は信用できない」と言われたことがありました。たった一度のミスで信頼が崩れる、そういう世界です。だからこそ、体調が悪くても、手が離せなくても、なるべく電話には出るようにしている。でも、これが心身を消耗させる原因にもなっているのは間違いありません。
取引先や依頼者の中には電話命な人も
中には「電話じゃないと落ち着かない」というタイプの人もいて、何度も電話をかけてくる方もいます。書類が届いたかどうかの確認すら電話で来る。こちらがメールで返信しても、折り返し電話がかかってくることもあります。こうなるともう、電話対応という業務が一つの専門職なんじゃないかと思えてくるほどです。
電話を避けたい自分と職業倫理のはざまで
電話が怖い。そう感じる自分はおかしいのか、弱いのか、と自問することもあります。でも、これだけ神経を使う業務なのだから、誰だってしんどくなるのは当たり前だとも思うんです。避けたいけれど、避けてはならない。それがこの仕事の一番しんどいところかもしれません。電話対応に疲れ果てた日の帰り道、ふと「別の仕事だったらこんなに神経すり減らさないのかな」と考えてしまう夜もあります。