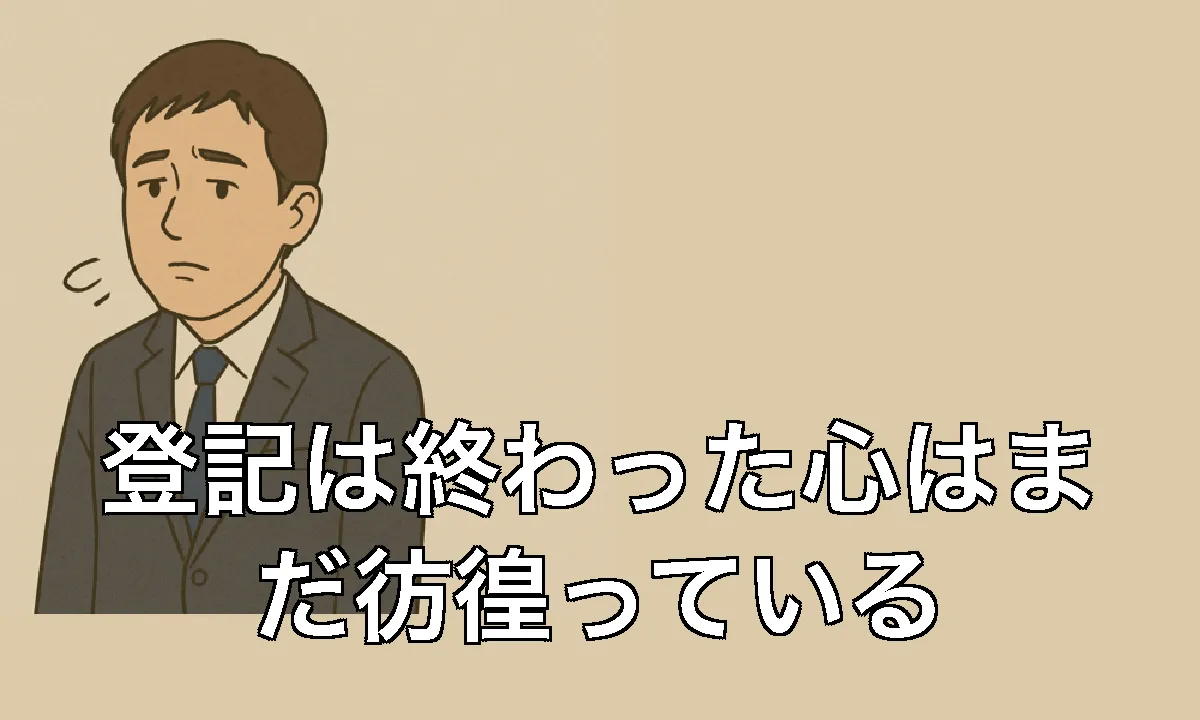登記は終わった心はまだ彷徨っている
登記完了の報せと心のざわつき
登記完了の報せをクライアントにメールで送った瞬間、いつも感じるあの虚しさ。達成感よりも「これでまた一件終わった」という機械的な感情が胸に残る。書類に不備はない。期限内に処理もできた。けれど、何かが心の中でくすぶる。この仕事、ずっと続けてきたけれど、最近はとくに「俺って何のためにやってるんだろう」と思うことが増えた。仕事自体は好きだし、誇りもある。けれど、感情の行き場がないまま、毎日の業務に埋もれていく感覚は消えない。
書類の山と静かな達成感の不在
机の上に積まれた登記書類の山。整理が終わるころには、日も傾いている。ひとつひとつの処理には確かに意味があるし、依頼人にとっては大切なことだ。でも、淡々と作業を終える自分に対して、「俺は感情を失った機械なんじゃないか」と感じることがある。若いころはもっと一件一件に熱を持って取り組んでいたような気がする。それが今では「終わらせること」ばかりが目的になってしまった。完成印を押す手が、なんとも言えない虚無を抱えている。
「終わった」という事実と「終われない」感情
登記簿に印が入り、受理されたと報告が届くと、安堵と同時に空白がやってくる。「やっと終わった」と思う一方で、自分の心のどこかがずっと終わっていない。引きずってるとかそういうことじゃない。ただ、終わったはずなのに心が置き去りにされてる感じ。まるで、走り終えたマラソンのあとに、どこかに忘れ物をしてきたような違和感。処理が終わることと、自分の気持ちが整理されることは、まったく別なんだと、最近ようやく気づいた。
登記簿に名前は載っても自分の居場所は載らない
登記簿には確かに名前が残る。司法書士として、自分の仕事の証が刻まれていく。それなのに、そこに“自分自身”はいないと感じることがある。ただの名前。ただの職印。ただの手続き。その背後にいる“自分”の存在は、どこにも記録されない。心がさまよっているのは、もしかすると、「ここにいていい」という感覚を見失っているからかもしれない。名前は残っても、自分の足跡は感じられない。そんな寂しさがいつもまとわりつく。
事務所の静けさがやけに響く午後
登記が一段落してふと時計を見ると、午後2時すぎ。事務員さんは隣の部屋で入力作業に集中していて、話し声もない。電話も鳴らず、ただ静けさだけが事務所に満ちている。忙しいときには欲しかった「静けさ」なのに、いざ訪れると、それはむしろ不安を連れてくる。自分が透明人間になったような気さえして、椅子に座っているのに地に足がついていない感覚になる。そんな午後が、ここのところ増えた。
忙しさの波が引いたときに訪れる虚無
仕事の波が引いたとき、自分には何も残っていないように思えることがある。あれだけ詰め込まれた予定が終わり、気が抜けた瞬間、まるで空っぽの箱だけが机の上にあるような感覚。達成感もなければ、余韻もない。ただ、「終わったな」という事実と、それに対する感情の不在。学生時代、試合が終わったあとのベンチで感じたあの放心感に少し似ている。でも、あの頃は仲間がいた。今は、誰とも言葉を交わさずにそのまま日が暮れていく。
無機質なFAX音と心の隙間
その午後、突然FAXが鳴った。ブゥゥゥという音に、一瞬「誰かからの連絡か」と期待した自分がいた。でも、届いたのはどこかの銀行からの通知文。それを手にとって、ふと笑ってしまった。「俺は何を期待してたんだろう」と。誰かとのつながりを、機械の音に求めるくらいには、心が乾いているんだと気づいた瞬間だった。
椅子の軋む音が寂しさを強調する
ふと体を動かしたとき、椅子がギィと音を立てた。その音が、静かな事務所の中に響いて、やけに寂しく感じた。「誰かと会話してたら、この音も気にならなかっただろうに」と思いながら、もう一度ゆっくり背もたれに体を預けた。人の気配が恋しくなる。でも、電話をかけるほどの相手もいないし、かけたところで何を話せばいいかもわからない。ただこの音だけが、自分の存在をささやかに主張している。
愚痴をこぼせる相手がいない日々
事務員さんには感謝している。彼女がいなければ仕事は回らないし、正確に処理してくれているのもわかっている。でも、だからこそ、気軽に愚痴をこぼすわけにもいかない。気を遣ってしまう。結果、自分の中にたまったものが行き場をなくしていく。飲みに行く相手もいない。同業者との集まりはあるけど、そこでも「ちゃんとしてる自分」を演じてしまう。本音を出す場所がなくなって久しい。
雑談すら手間に感じる閉じた生活
たまに事務員さんが「今日、寒いですね」なんて話しかけてくれる。それすら、自分は「うん」とだけ答えてしまう。雑談って、気持ちに余裕がないとできないんだと最近気づいた。話すためにはまず心を開かないといけない。けれど、自分の心はもう、ずっと鍵をかけたままだ。開け方も忘れた。
事務員さんに気を遣って本音が言えない
事務員さんの前で、あまり機嫌を悪くしたくない。事務所の空気が重くなるし、彼女に気を遣わせるのも申し訳ない。だから愚痴も言えず、ため息も我慢してしまう。でも、その「我慢」が積もっていって、気づけば自分の中で爆発しそうになっている。言葉にできないまま、心の中だけで溜まり続けていくのは、本当にしんどい。
LINEの未読数と話し相手の不在
スマホを見ても、LINEは広告ばかり。友達リストは多いのに、気軽に連絡できる相手はいない。連絡があったとしても仕事絡み。夜中に「ちょっと話聞いてくれないか」なんて送れる相手なんて、もう何年もいない。そのことに、時折ものすごい孤独を感じる。
元野球部の自分が目指した正義感
昔、自分は“正義感の塊”だった。高校球児のころ、理不尽なことが大嫌いで、仲間のためなら本気で監督に食ってかかるようなタイプだった。それが今、目の前の仕事に追われて、「理不尽」どころか「無感情」にもなっている自分がいる。誰かを守るための仕事を選んだはずなのに、守れているのかもわからなくなっている。
人の役に立ちたいという初心の記憶
司法書士を目指した頃のことを思い出すと、胸が痛くなる。「人の人生の節目に寄り添える仕事」だと思っていた。実際、そういう場面もある。でも現実は、作業に追われ、気持ちを寄せる余裕すらなくなっている。依頼人の不安を解消するどころか、そっけない返答をしてしまって、あとで自己嫌悪に陥ることもしばしばだ。
土埃舞うグラウンドと今のデスクワーク
野球部だったころは、どれだけ泥だらけになっても仲間と笑い合えた。それが今、埃っぽい書類とパソコン画面の中で、ただ孤独に向き合っている。汗だくでも誰かと向き合っていた過去と、涼しい部屋でひとり静かに仕事をこなす今。そのギャップに、心がついていかない。
「頑張る」が口癖だったあの頃とのギャップ
「頑張ろうぜ!」が口癖だった高校時代の自分が、今の自分を見たら、どう思うだろう。「無理すんなよ」と言ってくれるか、「そんなことでいいのか」と喝を入れるか。どちらにしても、今の自分は、あの頃の自分に胸を張れない。だけど、じゃあどうすれば胸を張れるのか、それもよくわからない。
それでもやっぱり辞めない理由
ここまで書いてきて、自分でも思った。「じゃあ、なんで辞めないんだ?」と。その答えは、やっぱり依頼人の顔にある。書類を渡したときの「助かりました」「安心しました」という一言。それだけで、救われる瞬間がある。ああ、自分にもまだ意味があるんだと。
手続きの先にいる人の表情
登記は無機質だ。法律も事務も機械的だ。でも、その向こう側には必ず“人”がいる。相続、売買、会社設立――いろんな人生の転機に立ち会ってきた。たった一言の「ありがとう」が、思っていた以上に胸に沁みる。手続きの奥にいるその人の表情が、仕事の意味を思い出させてくれる。
依頼人の「ありがとう」が心に残る瞬間
昔、ある高齢の女性の相続登記を手伝ったとき、「これでやっと、安心して主人の仏壇に手を合わせられる」と言われた。その言葉が、いまだに頭から離れない。登記という仕事が、誰かの心の区切りになっている。そう思うと、この仕事にもちゃんと意味があるのだと、少しだけ救われる。
自分の存在意義をかろうじて支えるもの
正直、日々の仕事の中で「やりがい」なんて忘れている。でも、ふとした瞬間に依頼人の表情や言葉が心に刺さって、「自分はここにいていいのかもしれない」と思える。それはかろうじて、自分を支えてくれる細い糸。その糸を切らさないように、今日もまた、静かな事務所で一件の登記を終わらせていく。