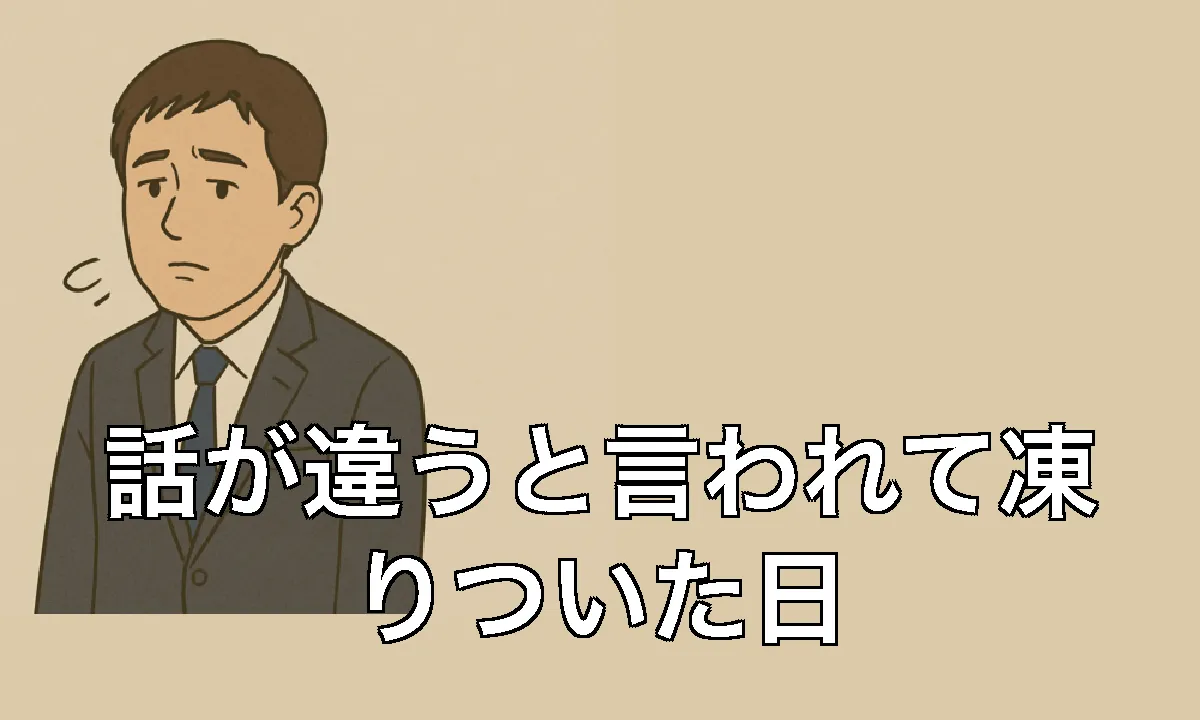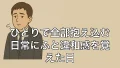朝一番の電話で嫌な予感がした
その日は、天気だけはやたらと良かった。快晴の空が逆に不吉に思えるのは、何かしら心に引っかかるものがあったからだろう。朝の8時過ぎ、まだ一口目のコーヒーにすらありつけていないうちに、電話が鳴った。表示された番号は見覚えのある不動産業者。前日に調整した案件のことで連絡が来るのは分かっていたが、まさか、あんな展開になるとは思ってもいなかった。
いつものようでいつもと違う空気
電話の第一声は、いつもと同じように軽い口調の営業マンの声だった。「先生、おはようございます。例の件でちょっと確認がありましてね…」と。その時点では、こちらも「はいはい、何か書類か説明が抜けてたかな」と気楽に構えていた。しかし話が進むにつれて、空気が徐々に変わってきたのが分かった。言葉尻が鋭くなり、口調が強くなってくる。嫌な予感は、的中する時ほどゆっくりと近づいてくる。
相手の「ん?」にこちらの鼓動が早くなる
「あの…話が違うんですよね」と、不動産業者の担当が言った瞬間、こちらの胸にドスンと重い石が落ちた気がした。何が「違う」のか。書類通りに進めているつもりだったし、説明もしていたはず。なのに、そう思っていた“共通認識”が、相手にとっては“すれ違い”になっていた。心の中で何度も「何が?どこが?」と自問しながらも、電話口では平静を装うことに必死だった。
一気に全身から汗が吹き出した瞬間
その後、該当の契約書類を確認しながら説明を重ねるうちに、背中にじっとりと汗が滲み始めた。クーラーをつけていたはずなのに、まるで熱帯雨林の中にいるような不快な湿気が体を包んでいた。言葉が詰まりそうになりながらも、なんとか誤解を解こうとするが、相手の不満げな「はあ…」という息が電話越しに突き刺さる。誤解で済めばまだいいが、信頼の崩壊は秒読みだった。
契約書に書いたはずの内容が通じていない
何度も確認した契約書。そこには確かに、問題の条項が記載されていた。だが、それが相手に伝わっていなければ意味がない。「書いてありますよ」では済まされないのが、この仕事の厳しさだ。読み手がどう解釈したか、説明の際の言い回し、表情、資料の提示順序——些細な差異が信頼関係を大きく左右する。今回はその“ズレ”が最悪の形で現れてしまった。
誰が何をどこまで説明したのか
私は誰に、どこまで、どういう順で説明していたか。記録を辿ると、相手が途中で別の担当者に変わったことがわかった。前任者には確かに伝えていた内容だった。しかし引き継ぎが曖昧だったらしく、後任者には情報が届いていなかった。その事実に気づいたとき、私は深くため息をついた。「ちゃんと話せば伝わる」は幻想だ。こちらから何度でも丁寧に、確実に伝えねばならない。
言った言わないの応酬が始まる
「それは聞いていません」「いや、説明しましたよ」——この不毛なやり取りがどれだけ心を削るか。司法書士を長くやっていても、ここは慣れることがない。証拠が残っていればまだいいが、口頭だけで済ませたやり取りほど後を引く。自分の記憶を信じつつも、相手の立場も理解しようとすればするほど、ジリジリと精神が削れていく。冷静に、でも悔しさを飲み込んで話し続けるしかない。
説明責任はどこまでが自分の範囲か
不動産業者との取引では、登記以外の範囲にも踏み込まざるを得ないことがある。だが、そこにリスクも潜んでいる。どこまでが「好意」で、どこからが「責任」なのか。善意で行った説明が、誤解を招けば一転してこちらの落ち度になる。私はこの一件を通じて、「境界線」の大切さを改めて痛感した。曖昧なまま進めた自分にも、責任の一端は確かにある。
不動産業者との温度差に戸惑う
あちらはあちらで営業のスピード感がある。こちらは法律に基づき、慎重に進める必要がある。その温度差は、時に致命的だ。感覚の違いからくる誤解や苛立ちが、お互いの信頼関係を脆くする。今回の件でも「もう少しスピーディーにできませんかね」と言われ、内心「こっちは機械じゃない」と叫びたくなった。けれど、それを飲み込んで笑うのが、この仕事の辛いところでもある。
先方の「常識」とこちらの「前提」
不動産業者が当然のように思っている進行手順と、司法書士としての必要な確認作業にはギャップがある。たとえば「書類はFAXで済ませましょう」と言われても、こちらとしては原本確認が必要だ。どちらが正しいとかではなく、前提が違うのだ。だが、こうした違いが共有されないまま進むと、「なぜできないのか?」という不満に変わる。それを一つひとつ丁寧に説明する手間は、決して軽くない。
信頼ってこうして崩れていくのか
信頼は、一朝一夕では築けないのに、崩れる時は本当に一瞬だ。電話一本、言葉ひとつで「ああ、この人にはもう頼めない」と思われるかもしれない。その怖さが常に付きまとう。私はこの業界に入って20年近く経つが、未だに「失敗するのが怖い」と思っている。自信なんてものは、何度でも粉々にされる。そして、そのたびに自分の無力さを噛みしめるのだ。
うまく笑えないまま終わった打ち合わせ
結局、誤解はどうにか説明し直すことで解消した。だが、最後まで相手の顔は曇っていた。「ああ、なんかもうダメだな」と、直感で思った。そういう空気は、言葉よりも先に伝わる。相手が「納得した」というより「諦めた」顔をしていた時の、あの虚しさ。どれだけ丁寧に対応しても、すれ違いは完全には防げない。笑顔で終われなかったその日、私は帰宅してからもしばらくぼんやりと天井を見つめていた。
事務員さんの一言に救われた
重たい打ち合わせを終えて戻ると、事務員の彼女が「先生、大丈夫でしたか?」と声をかけてくれた。その時、思わずため息混じりに「まあ、なんとか…」と返したが、心の中ではその一言に救われていた。味方がいるって、やっぱりありがたい。たった一人の事務所だけれど、この“たった一人”の存在が、どれだけ心の支えになっているか、自分でもよく分かっている。
「先生が悪いとは思いませんよ」
話を少し聞いてもらった後に彼女がぽつりと言った。「それ、先生が悪いとは思いませんよ」。それだけの言葉が、何よりもしみた。誰も責めてこない中で、自分だけが自分を責めてしまうのがこの仕事の厄介なところだ。だからこそ、誰かが「大丈夫」と言ってくれることに、こんなにも救われる。私はまだまだ、誰かの言葉にすがって生きている。
一緒に冷や汗をかいてくれる存在の大きさ
事務員さんも、私と同じように電話の内容を気にしていたらしい。「先生が電話してるとき、すごい顔してましたよ」と冗談交じりに言われたが、その言葉が嬉しかった。冷や汗をかくのは一人で十分だと思っていたけれど、誰かが横で「大変だったね」と言ってくれるだけで、重みが少し軽くなる。結局、人は人にしか救われないのだと、しみじみ思った。
それでも仕事は続いていくという現実
冷や汗をかこうが、信頼を失いかけようが、翌日はまた朝が来る。別の依頼者が別のトラブルを抱えてやってくる。司法書士という仕事は、立ち止まる暇がない。けれど、時にはこうして立ち止まって振り返ることで、自分の未熟さや、誰かへの感謝を再確認できる。そうやって、少しずつでも進んでいくしかない。もう一度、笑顔で終われるように。