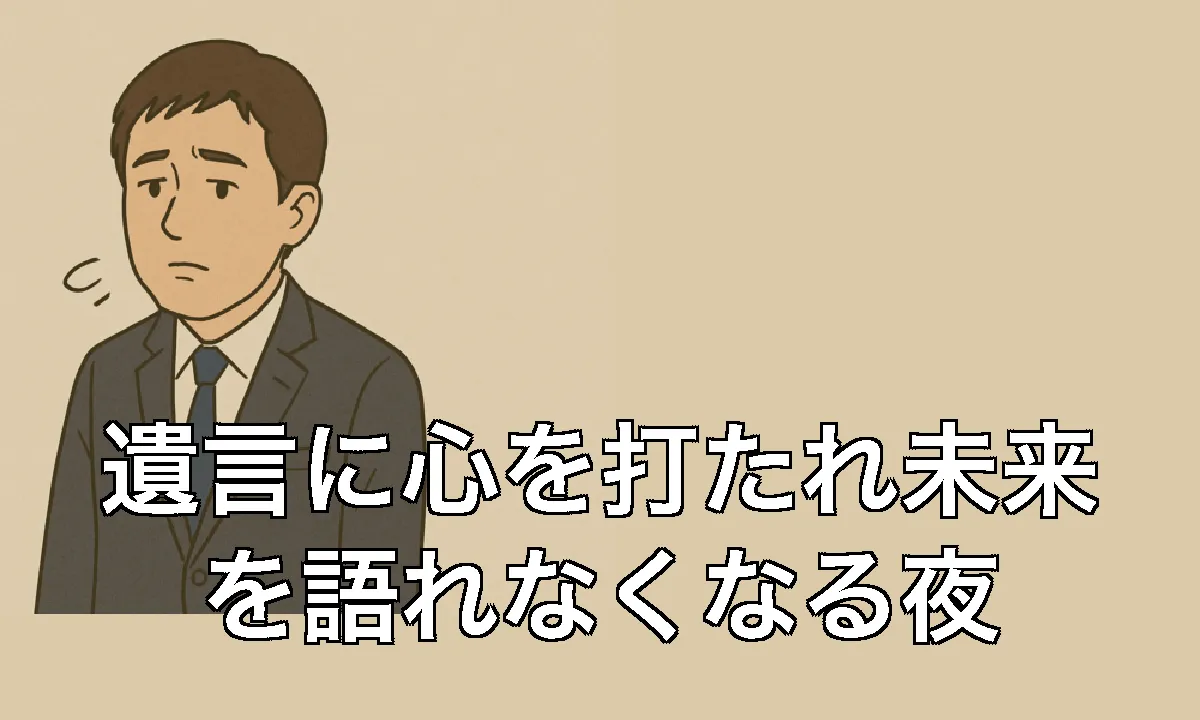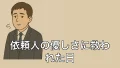遺言を読み上げるという仕事の重さ
司法書士という職業の中でも、「遺言の読み上げ」はとくに心が重たくなる業務の一つです。書類としては一通の文書ですが、そこには故人の最後の想いが詰まっている。形式通りに進めようとしても、心が追いつかないことがあるんです。先日、とある高齢の女性の遺言を読み上げる機会がありました。内容はシンプルでしたが、手書きで綴られた一行一行に滲んだ愛情が、思いのほか私の胸に迫ってきました。
書類以上のものがそこにはある
遺言はただの文書じゃない。これは何年もこの仕事をしてきてようやく実感としてわかってきたことです。若いころは「形式を間違えず処理すること」が第一でした。でも、あるとき依頼者のご家族が遺言を聞きながら涙を流すのを見て、ハッとしたんです。この紙切れ一枚が、残された人たちにとってどれだけ大事な意味を持つのか、自分はわかっていなかったと。
行間ににじむ人生の温度
「子どもたちへ ありがとう」たったこれだけの文でも、その人の人生が伝わってくる気がします。先日読んだ遺言には、定年後に趣味を始めたことや、亡くなった奥様との思い出も綴られていました。文字から、言葉の奥にある体温みたいなものが伝わってくるんですよね。こういうとき、自分は一体何をしているのかと、ふと立ち止まってしまいます。
形式では測れない一通の想い
法的に有効かどうか、それだけを見れば、私たちの役割は「チェックマン」です。でも、それだけで済む話じゃない。心を込めて書いたその人の言葉が、家族を癒したり、人生の締めくくりになったりするわけですから、そこに向き合う覚悟が求められます。私は未だにその覚悟ができていないまま、ただこなしているのかもしれません。
初めて涙をこらえられなかった日
数年前、ある依頼で私は仕事中に泣きそうになったことがあります。70代の男性が亡くなり、奥さんと娘さんに遺言を伝える場でした。「短くてすみません。でも、ありがとう。幸せでした。」という内容で、簡潔ながらもその人らしさがにじんでいました。読み終えた瞬間、奥さんが深くうなずきながら「この人らしいわね」と微笑んだんです。もうだめでした。
感情を殺すことが習慣になっていたはずなのに
仕事柄、感情を表に出さないようにしています。泣いたら失礼、そう思って。でもその日は、涙が勝手にこぼれそうになって、メガネを曇らせながら何とか読み終えました。形式的な業務を淡々とこなしていた自分が、急に「人」としてそこにいた。プロ意識が崩れたというより、ようやく人としての感情を取り戻したような気もしました。
事務員の沈黙が今でも忘れられない
そのとき隣にいたうちの事務員も、いつもなら次の段取りを淡々と進めるのに、そのときだけは黙って手を止めていました。言葉を発せず、ただ手を胸の前で組んでいた姿が、なぜか印象に残っています。ふたりとも、その瞬間だけは業務じゃなくて、人間としてそこにいた。そんなふうに感じています。
遺言が投げかける問いは他人だけのものか
遺言を書く人の想いに触れていると、ふと自分のことを考えざるを得なくなります。「自分が死ぬとき、何を残せるだろう」と。依頼人の人生を見つめることが、自分の未来を見つめることに繋がっている気がして、時々、怖くなるんです。
自分はどう生きてきたのかと問われた気がした
ある遺言には「人は誰かの役に立てれば幸せだ」と書かれていました。シンプルだけど、深い言葉です。自分はどうか。誰かの役に立てているのか。ひたすら書類を処理して、登記完了のスタンプを押して、ただ日が過ぎていくだけじゃないか。答えはすぐには出ません。
答えられないまま仕事に戻る自分
そんなことを考えても、すぐに次の案件が待っています。電話が鳴るし、事務所の書類は山積みだし、役所にも行かないといけない。だから考えるのをやめて、またいつものように仕事に戻る。でも、心のどこかにその問いだけは刺さったままなんです。「お前はどう生きる?」って。
喪失感と空虚さを背中に背負って
何人もの遺言に触れてきて、それぞれの人生の終わりを見届けているはずなのに、自分自身の「生き方」については何ひとつ言語化できない。それがまた情けなくもあり、怖くもあります。日々の忙しさに流されて、ちゃんと立ち止まることを避けている自分がいます。
孤独と無言の帰り道
その日の業務が終わって、事務所を出るとき、ふと足が止まります。帰り道はいつもと同じはずなのに、胸の中だけがやけに重たい。遺言を通して誰かの人生を垣間見たあと、自分の人生の「空白」を抱えて歩くのは、想像以上に堪えるんです。
仕事終わりの道に答えは落ちていない
夕焼けに染まる町を歩きながら、「このままでいいのか」と問いかける。でも道端に答えは落ちていない。誰も教えてくれない。だから足取りは重くなるし、前を向くのがつらくなる。元野球部で、声だけは大きかった自分が、今はもうほとんどしゃべらないまま帰る毎日。
弁当の蓋を開けても誰も隣にいない
スーパーで買った弁当を開けるとき、隣に誰かがいて「お疲れさま」と声をかけてくれたらどれだけ救われるだろう。そんな妄想をしながら、テレビをつけてごまかす。バラエティ番組の笑い声が、逆に虚しく響くこともあります。
テレビの音がやけにうるさく聞こえる夜
いつもの夜。部屋の隅にかけたスーツ、洗い忘れたコップ、鳴らないスマホ。それらが「これが自分の暮らしなんだ」と物語ってくる。テレビの音だけが元気に響いていて、それがどこか自分を責めてくるような気もする。今日もまた、静かでうるさい夜が過ぎていきます。