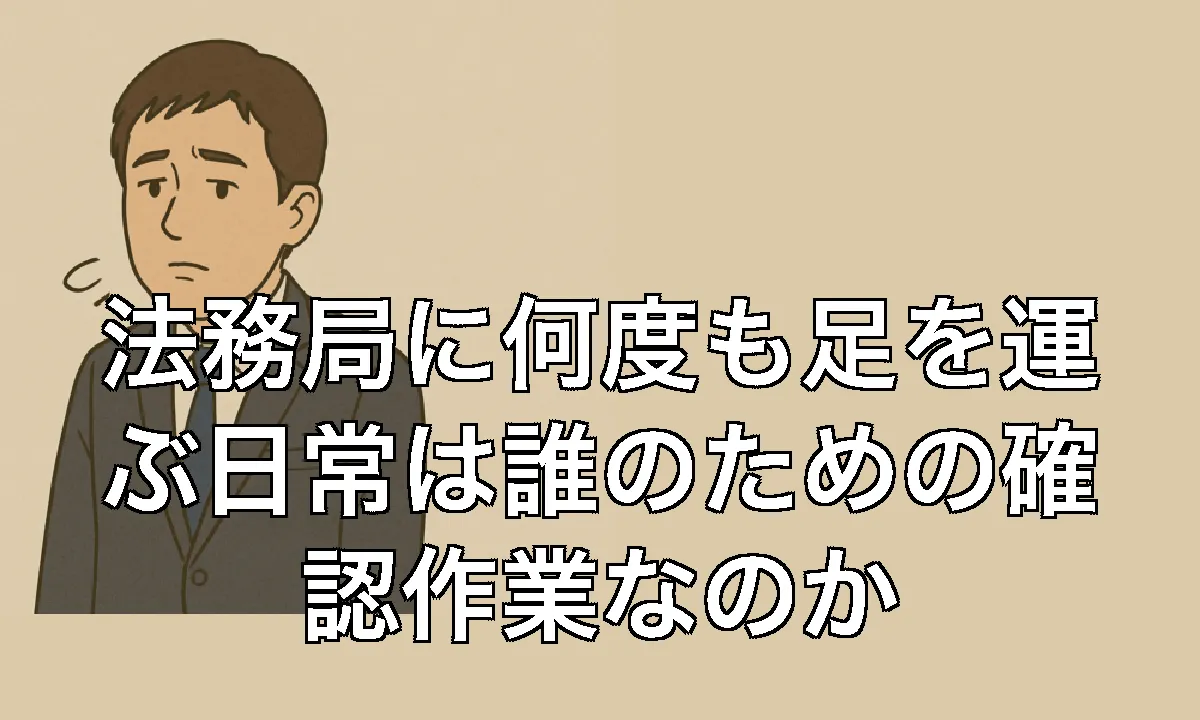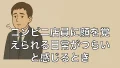朝一番の法務局で待つ理由
朝7時半、誰もいない事務所でコーヒーを飲みながらため息をつく。今日は登記の提出がある。依頼者からは「一発で通してほしい」と釘を刺されたが、果たしてそううまくいくだろうか。法務局の窓口に並ぶのは、慣れていても心が重い。書類のチェックはしたつもりだが、何度見ても不安は消えない。確認作業はした。でも窓口で「この書き方だと…」とつぶやかれるたび、自分の確認など意味がなかったかのように感じるのだ。
並び直しのストレスは慣れでは解決しない
開庁と同時に入っても、混み合う日は混む。番号札を取って、待って、書類を出して…。一見ルーティンに見えて、そのたびに胃がキリキリするのは、やっぱり「突き返されるかも」という恐怖があるからだ。何年この仕事をしていても、慣れたつもりでも、ストレスは減らない。法務局の職員が悪いわけじゃない。だけど、どうにも「減点方式」に晒されているようで、肩がこる。
そもそもなぜ何度も足を運ぶのか
根本的な話をすれば、窓口で一発OKが出るケースは、実はそれほど多くない。特に相続登記や法人関係の複雑な案件になると、「この欄も記載してください」「添付書類が不十分です」と言われることも多々ある。郵送で対応すれば?とも言われるけど、地元の法務局はなぜか窓口主義。急ぎ案件も多く、足を運ばざるを得ないのだ。わかっていても、やっぱり納得はできない。
確認不足か融通のなさか
返される理由が明確ならまだしも、「微妙なんですが…」という、いわば“職員の解釈”に左右されるケースが一番困る。こっちは事前に法務局に電話して確認した上で出してるのに、窓口では別の人が対応して、違う解釈が飛び出す。「これはケースバイケースでして」と言われたときのがっかり感といったら。こちらの確認不足か、職員の融通のなさか、いや、その両方かもしれない。
書類の不備に気づくのはいつも提出後
デスクで何度も見直した書類。間違いはないはず…そう信じて提出するが、案外抜け落ちているのが「基本的なこと」だったりする。「委任状の日付が申請書と違う」だの「住民票の有効期限切れ」だの、慣れてるつもりでも気が抜けている。そうなると、また戻って修正して、再び並ぶことになる。こうして1件の申請に半日が潰れる。仕事の効率?そんなものは幻想かもしれない。
こちらの責任?それとも窓口側?
一度、所有権移転の登記で、申請書に軽微な誤記があった。受付の担当者は気付かずに受理したが、補正の連絡が数日後に入った。「いや、それ出すとき言ってくれよ」と思ったが、怒っても始まらない。結局、こちらの責任として処理するしかない。責任の所在が曖昧なまま、時間と労力だけが減っていく。誰のための手続きなのか、本当に考えさせられる。
絶妙な言い回しで押し返される書類
「この内容ですと、受付は可能ですが…」という微妙な一言。これ、実質的に「やめといた方がいい」と言われてるようなもの。窓口でこう言われると、依頼者の顔が浮かんでしまって、結局引っ込めて再確認する羽目になる。強く出れば通るかもしれないが、リスクは負いたくない。だから毎回、慎重に、でもちょっと悔しくて、引き下がる。結局、また並び直す。
「形式上の問題です」の破壊力
ある日、建物表題登記の案件で「地番の記載順序が違います」と言われた。内容は正しいのに、「形式上の問題」として受付を断られた。これがどれだけ地味に心を削るか、同業ならわかるだろう。直せば済む話なのに、その一言で申請全体がストップするのだ。ルールを守るのが仕事とはいえ、杓子定規すぎる対応には、心が折れる。
事務員との連携ミスが生む二重苦
うちの事務員は真面目でよく働いてくれる。だけど、時に「言ったつもり」「聞いた気がする」のズレが生まれる。たとえば添付書類の有無。私は「念のため印鑑証明も付けて」と言ったが、彼女は「不要だと思ったから入れなかった」と。結局その判断が仇となり、法務局で不備扱い。私も怒れない。自分の説明不足だったのかもしれないと考えてしまうのだ。
忙しさにかまけて確認不足になりがち
午前は相談、午後は書類作成、夕方は外出…という日々が続くと、細かい確認を怠りがちになる。「このくらい大丈夫だろう」という油断が命取りになるのが司法書士の仕事だ。たった一枚の添付忘れで、申請が全体的にやり直しになる。何度「もっと丁寧にやっていれば」と思ったことか。だけど、毎日の業務量をこなすだけで精一杯なのも事実なのだ。
「ちゃんと見ておいて」と言ったつもりだった
信頼して任せる。でも、任せっぱなしではいけない。ある日、相続登記の添付書類の中に、古い戸籍が混ざっていた。「これ、除籍じゃなくて現戸籍だけじゃん…」と気づいたのは法務局の窓口でだった。もちろん自分も見た。でも「見たつもり」であって、「確認した」わけじゃなかった。どこかで「大丈夫だろう」と思っていた。甘かった。
後から怒れない優しさが仇に
問題が起きても、事務員を責めたくない。彼女だって一生懸命やっているのは分かっている。怒ったところで、関係がギスギスするだけ。だけど、モヤモヤは残る。たまに「なんであのとき確認してくれなかったの」と思ってしまう。結局、自分の責任として処理する。それが独立開業者の宿命なんだろうなと、また静かにため息をつく。
地元の法務局だからこその人間関係
小さな地方都市では、法務局の職員も顔なじみになってくる。でもそれが必ずしも良い方向に働くとは限らない。「あの先生、また来たよ」と思われてないか、妙に気になる。こちらが気を使いすぎなのかもしれないけど、微妙な距離感がいつも頭をよぎる。窓口の空気が妙にピリついている日なんかは、もう一歩踏み出すのもためらってしまう。
顔なじみになっても優しくはならない
法務局の職員も忙しいのは分かる。だけど、顔なじみだからといって、対応が柔らかくなることは基本的にない。むしろ逆で、「この人ならちゃんとしてるだろう」と思われているのか、ちょっとした不備にも容赦ない指摘が入る。「あれ?新人の頃の方が優しかった気がするな」と思うことすらある。慣れ合いはない。むしろ、無言のプレッシャーが強まる。
無言のプレッシャーに耐える朝
窓口で書類を差し出すときの数秒間が、一番緊張する。目の前でじっと書類を見る職員。沈黙。目線が止まる。小さくうなずく。その一連の動きに、こちらは呼吸を止める。「あ、これ言われるな」と思った瞬間には、すでに心が萎えている。こっちも慣れてるけど、やっぱり苦手だ。
「また来たんですか」の一言が刺さる
笑顔で言われた「また来たんですか?」が、妙に心に残る。いや、来たくて来てるわけじゃないんです。こちらだって、一発で済ませたい。だけど制度も人間も完璧じゃない。それでもやるしかないから、また朝から並ぶ。そんな自分を少しだけ褒めてやりたい、と思うけど、誰も褒めてくれないから、自分でコーヒーをいれて静かに飲む。