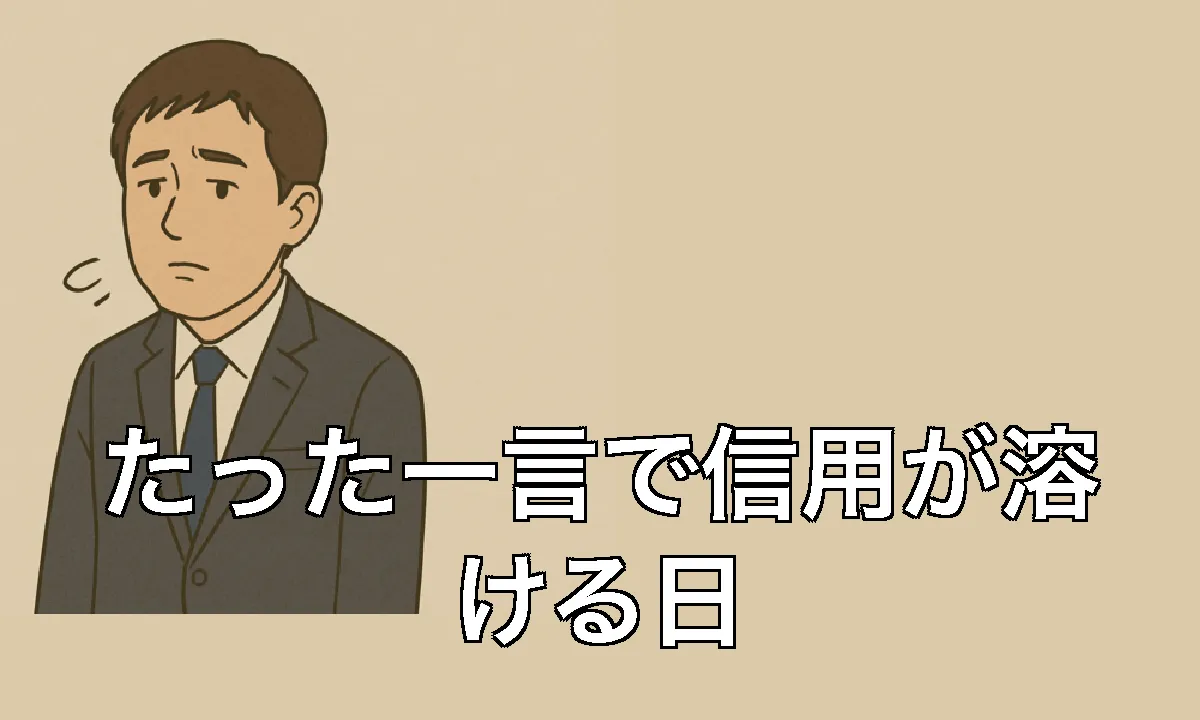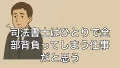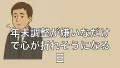信頼は積み上げても一瞬で崩れる
司法書士という仕事は、信頼の上に成り立っています。毎日のように他人の人生に関わる書類を扱い、名前や住所、金額など、どれも一字一句間違えてはいけないものばかりです。そんな中で「うっかり」の一言が致命的になることがあります。私もかつて、たった一言の言い間違いで依頼人の信用を失いそうになった経験があります。積み上げた関係性が、一瞬で氷のように溶けていく感覚は、今でも忘れられません。
ちょっとの言い間違いが招いた取り返しのつかない事態
数年前、ある遺産分割の案件で、依頼者に対して「被相続人」というべきところを「被告人」と言い間違えてしまいました。自分でもすぐ気づいて訂正したものの、相手の表情が変わったのがわかりました。冗談として流してくれる空気ではなく、その場の空気が凍りつきました。訂正すれば済むと思っていた自分が浅はかだったのです。相手にとっては大切な家族を侮辱されたように感じたのでしょう。
お客様の顔がみるみる曇る瞬間
その瞬間のことは今でもよく覚えています。話していた依頼者の女性の顔が、ふと曇り、目線が逸れていきました。言葉は交わさずとも、「あ、この人に任せて大丈夫かな」と思われたのがはっきり伝わってきました。こちらとしては単なる口の滑りでしたが、相手にとってはそれだけでは済まない感情が生まれていたのです。
訂正の言葉が届かないあの空気
「すみません、言い間違えました」と即座に訂正しましたが、その後の打ち合わせはどこかぎこちなく、最後まで気まずさが残りました。ミスを認めたところで、空気の冷たさは解けません。人の気持ちは言葉だけで取り戻せるものではないのだと、身をもって痛感しました。
言葉の重さを忘れていた自分
司法書士という肩書きに慣れ、忙しさを理由に言葉の一つひとつをおろそかにしていたことを反省しました。日々の業務に追われるなかで、「言葉はただの道具」という感覚になっていたのかもしれません。しかし、相手にとってはその「ただの一言」が心に刺さることもある。そう気づいたのは、この言い間違いをきっかけにしてからでした。
事務所内の雑談が引き金になることも
気をつけなければならないのは、依頼者との面談だけではありません。事務所内の何気ない雑談や電話のやり取りでも、言葉は外に漏れている可能性があります。以前、ちょっとした冗談で「またあの案件か…面倒だな」なんて事務員に漏らしたら、それが別のルートから依頼者の耳に入ったということがありました。完全に自業自得ですが、信用の修復にはとても時間がかかりました。
事務員の冷ややかな視線と沈黙
事務員からも「それ、言わないほうがよかったですね」と、冷たく言われたことがあります。忙しさのなかで感覚が鈍っていた自分にとって、その言葉はなかなか刺さりました。彼女は決して怒ったりするわけではありませんが、沈黙の圧力が地味に堪えるのです。
誰も悪くないのに場が凍る不思議
不思議なことに、誰かが怒っているわけでも責めているわけでもないのに、事務所の空気が凍りつく瞬間があります。そんなときこそ、自分が何かやらかしたのではと振り返るようにしています。そういう時の直感は、大抵当たっているんですよね。無意識のうちに、誰かの信頼を少しずつ削っている。怖い話です。
日常業務に潜む地雷
私たちの業務には、毎日が地雷原のような側面があります。書類の一言一句、話し言葉、ちょっとした言い回しすべてが「爆弾」になりうる。気を抜いた瞬間に、それが爆発してしまうんです。特に相続や離婚など、感情が絡む案件では注意が必要です。相手は常に緊張しており、こちらの一言に過剰に反応することもある。それは悪意ではなく、当然の反応なのだと理解しなければなりません。
電話口の一言が命取りになることがある
電話応対での「適当な返事」も、のちのち命取りになります。「あーそれ、たぶん来週までには大丈夫です」なんて曖昧な返答が原因で、トラブルになったことが何度もあります。相手は「来週までに必ず終わる」と思い込んでしまうわけです。忙しさにかまけてそのあたりが雑になると、信頼の糸は簡単に切れてしまいます。
メールの文面ひとつに潜む勘違いの種
文章にすると伝わると思いがちですが、逆に伝わらないこともあります。例えば「確認中です」という一文が、「まだ何もやっていないのか」と受け取られることもあります。感情が読み取れないからこそ、慎重に言葉を選ばなければならない。テンプレートを使ってもいいですが、そのまま使うと機械的になり、冷たい印象を与えてしまいます。
信頼を取り戻すためにできること
失った信頼を取り戻すのは容易ではありません。でも、不可能ではありません。まずは素直に謝ること、言い訳せずに認めること。そして、これからどうするかを相手に示すこと。そうやって少しずつ、相手との関係を修復していくしかないんです。小手先のテクニックではなく、誠意だけがものを言う世界だと感じます。
謝るタイミングと誠意の出し方
謝るにもタイミングがあります。相手の気持ちが爆発する前に、先回りして謝るのが理想ですが、現実は難しい。気づいたときにはもう遅いということもあります。それでも、「すみませんでした」の一言が、自分の誠意を伝える一歩になります。形だけではなく、言葉の重さをしっかり噛みしめながら伝えることが大切です。
二度と同じミスを繰り返さないための仕組み
同じ失敗を繰り返さないために、私は「ミスメモ」というノートを作りました。言い間違えた言葉、トラブルになったやりとりを全部書き留めて、定期的に読み返しています。地味ですが、自分にとっては結構効いています。自分のパターンを可視化することで、次のミスを予防できるようになりました。
愚痴を減らすにはどうすればいいのか
信頼を損ねる原因の一つに「愚痴」があります。誰かに聞いてもらいたいだけのつもりが、言葉が勝手に走ってしまうことも多い。私も事務員に対してつい愚痴をこぼしてしまうことがあるのですが、最近は「一回口にする前にノートに書いてからにしよう」と決めています。愚痴の99%は口に出さなくて済むことばかりです。
それでもまた言い間違える現実
どれだけ気をつけていても、人間ですからまたやらかします。完璧を目指すほどに空回りしてしまう。でもそれでも、信頼は取り戻せるし、築き直せると信じています。間違えることを恐れず、でも軽く見ずに、地道に仕事を続けていくしかない。そんな日々の積み重ねが、少しずつ信用を再構築してくれるのだと思います。
完璧を目指して疲弊するより等身大で
司法書士という仕事は、完璧さを求められる場面が多いです。でも人間である以上、完璧ではいられない。むしろ「完璧にやろう」と思えば思うほど、しんどくなってしまう。最近は、「まずは誠実であること」を最優先に考えるようにしています。間違えても、隠さず、逃げずに向き合う。それが信頼回復への一番の近道です。
信頼されるのはミスしない人ではなく正直な人
最後に気づいたのは、信頼される人とは「絶対にミスしない人」ではなく、「ミスしてもごまかさない人」だということです。私自身、完璧な人間ではありませんが、できるだけ正直であろうとしています。その姿勢を見て、信頼を寄せてくれる人も少しずつ増えてきた気がします。信頼は、一言で壊れることもあれば、一言で育て直せることもある——そう思っています。