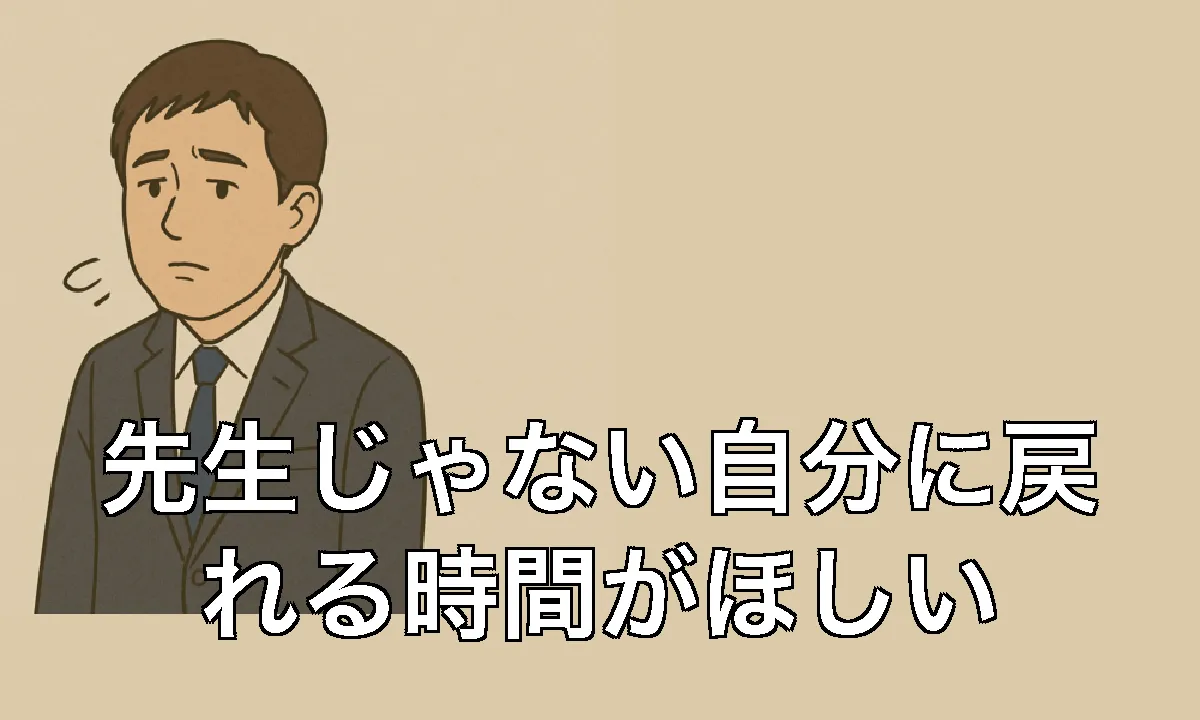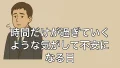先生じゃない自分に戻れる時間がほしい
名前ではなく役職で呼ばれる日々に疲れるときがある
日々「先生」と呼ばれ続けると、自分の名前を忘れそうになる瞬間がある。司法書士という肩書はありがたいし、信用の裏返しだというのもわかっている。でも、「先生」と呼ばれ続けることで、自分自身がどこか遠くへ行ってしまうような感覚に襲われる。特に忙しい時期になると、名前ではなく機能として扱われているように感じるのだ。「書類の件、先生に聞いて」「先生、登記の進捗どうなってますか」——そんなやりとりが日常になり、ふとしたときに「これ、俺じゃなくてもいいんじゃないか」と思ってしまう。
先生と呼ばれることの重みと孤独
「先生」と呼ばれることには、責任が伴う。その責任を果たすべく、毎日机に向かい、電話を取り、登記簿をチェックし、裁判所の申立書を書き続ける。でもその重みは、ときに孤独を生む。誰かに「ねえ、たつや」と呼ばれたのはいつだっただろう。高校時代の野球部では、名字でも名前でも気軽に呼び合っていた。それが懐かしくてたまらなくなるときがある。信頼と引き換えに失った人間関係のゆるさ。ふと、それが恋しくなる。
仕事を離れても肩書がついてくる
スーパーで買い物をしていると、たまに依頼人に出くわす。「あ、先生もこのへん使うんですね」なんて声をかけられると、嬉しい反面、どこか居心地の悪さもある。プライベートのつもりだったのに、途端に仕事モードに引き戻される感じだ。近所の居酒屋にふらっと入っても、知り合いに会えば「先生も一人飲み?」と聞かれ、肩書きが外れない。結局、仕事と生活が混ざり合ってしまう。いつから「自分」と「仕事」の境界が曖昧になったのか、自分でも思い出せない。
自分の時間を持てないという現実
カレンダーを見れば予定がびっしり。打ち合わせ、申立て、登記、郵便チェック、事務員さんとのやりとり、そして電話の嵐。仕事があるのはありがたい。でも、そこに「自分の時間」はあるだろうか。昼休みすら、相談の電話に追われて消えていく。好きだった野球観戦も行けていない。休日に出かけようと思っても、気になる案件があれば気が休まらない。「休み」とは言うけど、心はまったく休んでいない。
スケジュール帳に埋もれる休日の存在
昔は週末に温泉に行ったり、友人と草野球をしたりしていた。今はそんな予定を書き込むスペースすらない。スケジュール帳を開くと、そこにあるのは依頼人の名前と申請期限ばかり。たまにぽっかり空いた日があっても、「ここで何か進めておこう」と思ってしまう。効率よく動くことが習慣になりすぎて、何もしない時間に罪悪感すら覚える。頭では「休もう」と思っていても、体がそれを許さない。
事務員との会話すら事務的になっていく
事務所にいると、事務員さんとの会話もどこか機械的になっている。「この書類確認しましたか?」「この印紙は貼っておきますね」——そういったやり取りは当然必要だけど、感情のやりとりはどんどん薄くなっていく。昔は雑談も交えて笑ったこともあったのに、今は業務に追われるばかり。こちらが余裕をなくしているのか、話しかけることすら遠慮されている気がして、さらに孤独感が増していく。
雑談ができない空気感がしんどい
ある日のお昼、コンビニのおにぎりを食べながら、ふと「最近、誰かと世間話したっけ」と思った。それくらい、事務所の空気がピリピリしていたのだ。もちろん仕事に集中することは大事。でも、人間ってそんなに完璧じゃない。少しの雑談や笑い声が、むしろ場を和ませることもある。今の自分はそれを忘れていた。もっと、余白のある働き方をしてもいいのかもしれない。
他人の人生に関わる重圧
司法書士の仕事は、人の人生に深く関わることが多い。相続、遺言、離婚、成年後見。どれも当事者にとっては重大な問題であり、その書類を扱う自分にも重圧がのしかかる。「間違えてはいけない」「ミスしたら信用を失う」——その気持ちは、年々強くなる。誰かの人生の一部を担っているという責任感。誇りでもあるけれど、同時にしんどい。
間違いの許されない日々の中で
たとえば、ある日提出した登記申請。役所から戻ってきたのは「補正通知」だった。一瞬で血の気が引いた。小さな記載ミスだったが、それが依頼人の手続きを遅らせることになる。そのときの自分の不甲斐なさに、自宅でひとり呆然とした。誰も責めてこない。でも自分自身が許せない。こうした日々のプレッシャーが、積み重なるとボディブローのように効いてくる。
責任感と不安の間で揺れる気持ち
責任感が強い分、ミスに対する恐怖も強い。「次は絶対に間違えないように」と思えば思うほど、プレッシャーは増していく。依頼人に信頼されるのはうれしい。でも、その信頼が自分の首を絞めることもある。「もし失敗したらどうしよう」——そんな不安が、ふとした瞬間に頭をよぎる。責任を背負いながらも、どこかで軽やかに働けるようになりたいと願う。
ただの自分として過ごせる時間の価値
そんな中でも、ふとした瞬間に「先生」ではない自分に戻れることがある。それは、名前で呼ばれる瞬間だったり、仕事と無関係な会話だったり。とても些細なことなのに、心の奥がじんわりと温かくなる。誰かの役に立つことも嬉しい。でも、それ以上に、自分自身が自分として存在できる時間が必要だと思う。
名前で呼ばれる関係性のありがたさ
久しぶりに会った高校の同級生に「稲垣、元気か?」と声をかけられたとき、なんだか泣きそうになった。そのひと言には、仕事も肩書きも関係ない素の自分がいた。自分を取り戻したような気がして、思わず「お前も老けたな」と返してしまった。名前で呼ばれるということ、それは存在をまるごと認めてもらうことかもしれない。
友人や家族すら気を使う立場になっていた
最近では、家族からも「忙しいんでしょ?」と遠慮されることが増えた。「また連絡するね」と言われるたびに、距離ができていることを痛感する。こちらが忙しそうにしているせいで、気を遣わせてしまっているのだろう。思えば、少し連絡を返すだけで、世界はまたつながるのに、自分でその糸を切っていた気がする。
コンビニの店員の何気ない一言に救われる瞬間
ある朝、近所のコンビニでレジを通したとき、若い店員さんが「今日は暑いですね、お疲れさまです」と笑顔で声をかけてくれた。たったそれだけなのに、胸の奥にふっと風が吹いたような感覚がした。その瞬間、誰でもない「自分」に戻れた気がした。誰かに認識されることの、なんとありがたいことか。
それでもやめない理由は何なのか
ここまで愚痴を並べてきたが、それでも自分はこの仕事を続けている。なぜかといえば、人の役に立っていると感じられる瞬間があるからだ。依頼人が安心した顔で「助かりました」と言ってくれるとき、「やっていてよかったな」と思える。先生じゃない自分も大事だけれど、先生としての自分もまた、大切な一部だ。
依頼人の笑顔に報われる感覚
以前、認知症のお母さんの成年後見人の手続きを終えたとき、娘さんが涙を浮かべながら「これでやっと安心できます」と言ってくれた。その一言が、すべての苦労を吹き飛ばした。自分の仕事が、誰かの人生の支えになっている。その実感が、次の日も机に向かう原動力になるのだ。
先生じゃなくても必要とされる喜び
きっと理想は、「先生」じゃなくても誰かにとって必要な存在になること。名前で呼ばれても、肩書きで呼ばれても、どちらでも自分が認められていると思えるようになりたい。今はまだ、バランスの取り方がわからないけれど、少しずつ「自分」としての時間も取り戻していけたらいい。そう思いながら、今日もまた書類にハンコを押している。