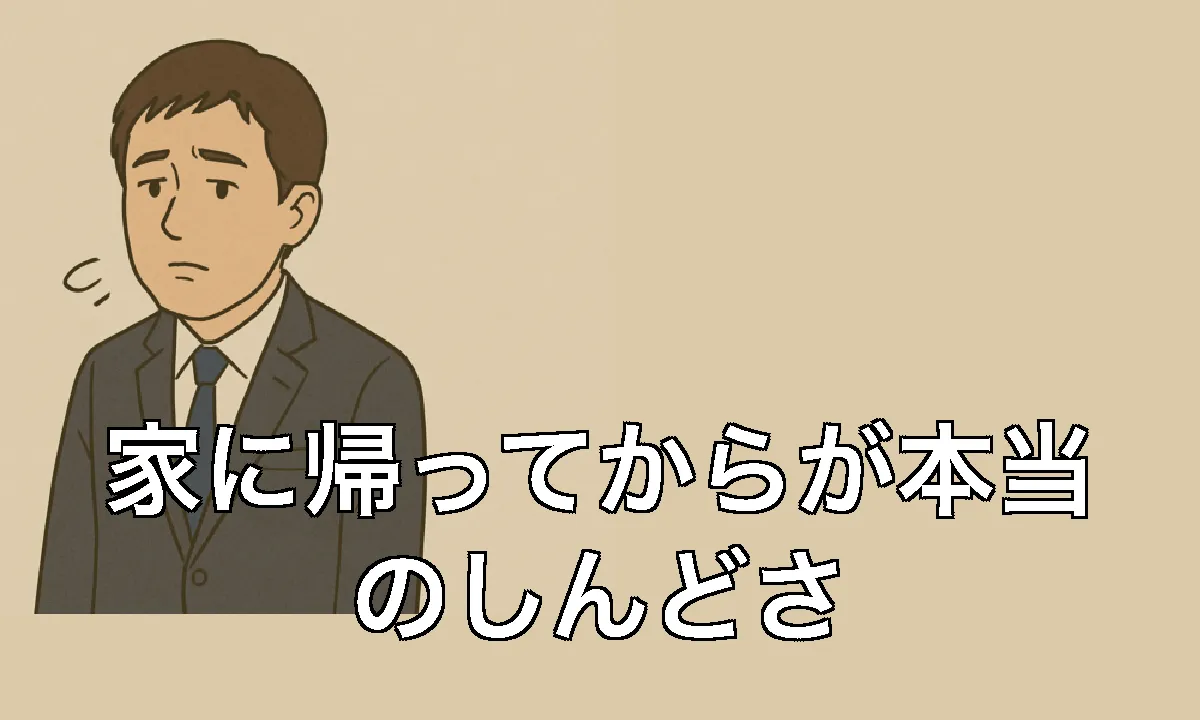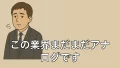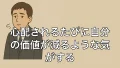ひと仕事終えても気が休まらない夜がある
司法書士という仕事は、業務時間が終わったらスイッチを切れるようなものではない。表向きには事務所を出れば「お疲れさま」だが、本当の戦いは家に帰ってから始まることが多い。風呂に入って、ビールを開けて、ふと一息ついたその瞬間に、急に不安が湧き上がる。「あの書類、添付忘れてないか?」「あの申請、受理されるかな?」。もう一度パソコンを立ち上げ、メールを確認し、気づけば深夜。仕事は終わっているのに、心が終わらせてくれない。それが、しんどさの本質なのかもしれない。
業務時間中よりも自宅での疲労感が強い理由
業務中は、ある意味「やること」が明確で、体は忙しくても頭は指示通りに動いている。しかし家に帰ってからは、自分自身の感情と向き合わされる。デスクワークの疲れ以上に、気疲れがずっしりと重くのしかかる。例えば、完了報告を出した案件に「ありがとうございます」と返ってくればホッとするが、返信がないと「何かミスしたか?」と不安になる。たとえ誰にも言えなくても、こうした“自宅残業”とも言える心の働きが、日々の疲労感を加速させている。
「今日もちゃんとやれたか」が頭をよぎる
独立している以上、誰かに「よく頑張ったね」と褒めてもらう機会はない。だからこそ、家に帰ってふと鏡を見ると、自分で自分を評価してしまう。「今日のあの対応、ベストだったか?」「依頼者の気持ちを汲めたか?」。答えは出ないし、出たとしても自信のないまま。元野球部だったころ、試合後に監督からの一言で救われた夜があった。でも今は、試合に負けたかどうかも、自分で判断しなきゃいけない。その重さが、日を追うごとに蓄積していく。
チェックリストは終わっているのに心は終われない
ToDoリストにはチェックが並び、形式的には今日の仕事は完了している。でも頭の中のチェックリストはそう簡単に終わらない。例えば、完了とされた登記案件が、明日の朝になって何かの添付書類の不備で戻されるかもしれない——そんな妄想すら湧いてくる。事務員には「お疲れさまでした」と言って帰ってもらうけれど、自分はまだ帰れていない。体は家にいても、心はまだ事務所に置いてきぼりだ。
一人事務所の“無音”が逆に重たくのしかかる
家に帰ってくると、音がないことが逆にプレッシャーになることがある。日中は電話の音、キーボードの音、人の声——それなりに賑やかだ。でも夜になると、静かすぎて耳鳴りがするような感覚になる。そんな時、無意識にテレビやラジオをつけるけれど、内容は全く入ってこない。ただ音が欲しいだけだ。一人でやっていると、孤独が音でごまかされる瞬間がある。それもまた、しんどさの一部だと最近思う。
誰とも話さない夜の孤独
仕事中は依頼者と話す機会がある。でもそれは「会話」ではなく「業務連絡」に近い。プライベートな話をする相手がいない日が続くと、会話の勘が鈍ってくる。独身だし、気軽に電話できる友達も少ない。コンビニのレジで「温めますか?」と聞かれて、「あ、はい」と答えるのが今日の唯一の会話だった——そんな日もある。あの空虚感は、説明しがたい。でも、それが日常になっている。
テレビの音がやたら大きく感じる理由
一人暮らしの静けさの中で、テレビの音がやけに大きく感じる夜がある。別にボリュームを上げたわけじゃないのに、なんだか音が刺さる。笑い声や明るいBGMが、自分の生活とはかけ離れていて、逆に寂しさが増す。元々バラエティ番組が好きだったのに、最近は見るのがしんどくなってしまった。自分の生活音と世の中の“賑わい”のギャップを感じてしまうからかもしれない。
なぜか眠れない日が続くとき
布団に入ってからが、ある意味一番の戦場だ。何もすることがなくなると、思考が暴走する。昼間に気づけなかったミスが夜中になって浮かんできて、「ああ、やっちゃったかも」と思う頃にはもう寝付けない。そうして朝方になって、あれは妄想だったと気づく。無駄な自己否定の夜は、眠れなかった自分にさらに自己嫌悪を呼ぶ。これを何度も繰り返してしまう。
疲れているはずなのに目が冴える不思議
体は間違いなく疲れているのに、目だけはランランとしてしまう夜がある。事務所を閉めて、夕食を済ませ、風呂にも入って、あとは寝るだけという状況なのに、布団の中で過去の案件を思い出してしまう。あるいは、明日の予定を何度もシミュレーションしてしまう。脳が休まらないというのは、こういうことなのだろう。疲労とは、体よりもむしろ“考えすぎること”によって増幅するのかもしれない。
「明日こそは早く寝よう」が毎日更新される
目覚ましを止めながら「今日は早く寝よう」と誓う。それなのに、気づけばまた深夜までスマホをいじっている自分がいる。心のどこかで「今寝ても、どうせまた途中で目が覚めるだろう」という諦めがあるのかもしれない。昔の野球部の仲間が送ってくれるLINEの通知が、唯一少しホッとできる時間。だけど、それに甘えてるわけじゃない。ただ、寝る前に誰かとつながっていたいだけなんだ。
誰にも弱音を吐けないというしんどさ
愚痴は多いほうだと自覚している。でも、それを誰に向けて言うかとなると、急に口が重くなる。事務員には聞かせたくないし、母親に電話するのも気が引ける。SNSも向いていない。だから、誰にも言えないまま、ひとりで抱えて、夜に溶かしてしまう。吐き出す場所がないというのは、想像以上にしんどいことだ。
身近な人ほど心配をかけたくないという矛盾
身近な人間にこそ本音を言えばいい——そんな正論は知っている。でも、相手の顔が浮かぶと、やっぱり言えなくなる。母に「最近どう?」と聞かれたとき、つい「順調だよ」と答えてしまう。実際はそんなわけない。でも、心配をかけたくないという気持ちが勝ってしまう。そうして嘘を重ねていると、本当の自分の感情がわからなくなってくる。
“聞いてくれる人がいない”のではなく“話せない自分がいる”
話を聞いてくれる人がいないわけじゃない。でも、「これを言ったら面倒だと思われるかな」とか、「愚痴ばっかりで嫌がられるかも」とか、余計な気遣いばかりしてしまって、結果的に言えない。つまり、聞いてくれる人がいないのではなく、話せない自分がいるのだと思う。そうやって、話せなかった言葉が心の中に積もっていく。
それでも明日は来てしまう
眠れなかった夜も、自己嫌悪の夜も、終わらない心配の夜も——朝は容赦なくやってくる。カーテンの隙間から光が差し込んだ瞬間、「また今日も始まるのか」とため息をつく。それでも、誰かが待っているから、机に向かってまた仕事を始める。それしかできないから。しんどさの中で、それでも続けるしかないという日々を、今日もまた繰り返す。
リセットできないまま朝が始まる
朝の光を浴びても、昨日の気持ちはリセットされていない。夢で見たミスの続きを引きずったまま、朝ご飯も喉を通らない日がある。そんな朝に、依頼者からの「今日伺ってもいいですか?」の電話が鳴る。そこでスイッチを入れなきゃいけない自分がいて、また無理をする。でも、そうしないと、自分の存在意義が消えそうで怖い。だから今日もまた、笑顔をつくって応対する。