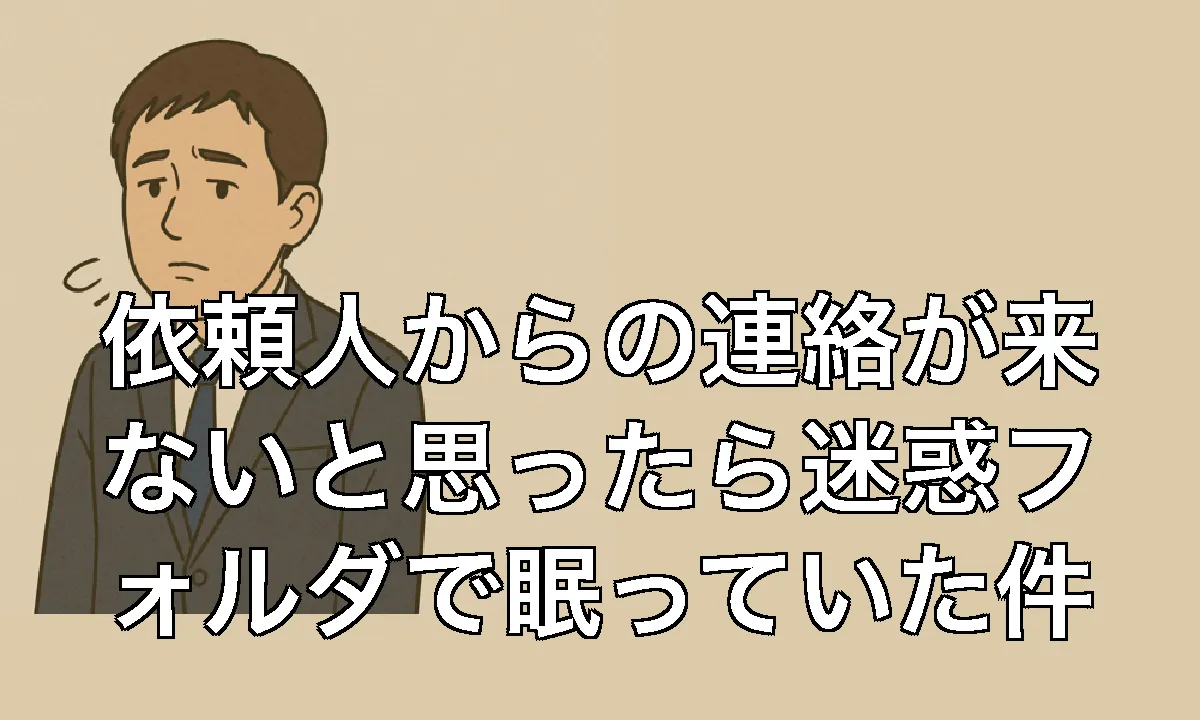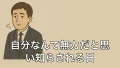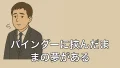メールが届いていないと思い込んでいた朝
朝、いつものように事務所に入り、PCの前でコーヒーを飲みながらメールチェックをしていた。ある依頼人からの返信を数日待っていたのだが、何度見ても届いていない。あの人、ちょっと反応が遅いタイプだったか…いや、今回は少しおかしいぞ。内容的には急ぎだったはずなのに。どこか不安が頭をよぎる。私はせっかちでも神経質でもないが、「音沙汰がない」ことに妙なプレッシャーを感じることがある。信頼関係というのは、些細なことで揺らぐものだ。
依頼人の沈黙に違和感を覚えた瞬間
それにしてもおかしい。あの依頼人、いつもは即レスとまではいかなくても、翌日には何らかの返信をくれるタイプだった。電話を入れるのは少し気が引けるが、このままでは書類の進行に支障が出る。ふと、「もしかして」という直感がよぎり、迷惑メールフォルダを開いてみる。…あった。件名も本文もすべて既読になっていない。「お世話になっております。書類確認いたしました」と、しれっとそこに眠っていた。思わずため息が出た。
返信が遅れているのはこっちなのかあっちなのか
状況としては、完全にこちらの見落とし。依頼人にしてみれば、「ちゃんと送ったのに、なんで無視されてるんだろう?」と不信感を持たれても仕方がない。でも、こちらとしても通知すらされていないメールにどう反応しろというのか。まるで野球でストライクゾーンの外を狙ったつもりが、審判に「あれ入ってたよ」と言われるようなもの。見えてないものには、どうしたって対応できない。
待ってる側と気づかない側の温度差
依頼人は返信を送った安心感がある。でもこちらは、届いてないという前提で時間を費やしている。この温度差が積もると、信頼関係にヒビが入るのが怖い。実際、私も逆の立場なら「この人ほんとに大丈夫か?」と思うだろう。今まで築いた関係が一通のメールで崩れるなんて、なんとも虚しい。それでも現実は、そういう理不尽さに満ちている。何度も「気づいていれば」と後悔してしまった。
迷惑フォルダという落とし穴
誰が得をするんだ、この仕組みは…と愚痴りたくなる。迷惑フォルダの中には、実はまともなメールがけっこう入っている。ウイルスまがいのスパムだけじゃない。依頼人からの真面目なメールだって、プロバイダの気まぐれで突っ込まれてしまうことがある。これじゃ、誤審どころか試合が成立しない。しかも通知されないことも多いから、本当にたちが悪い。
気づくまでの数日間のモヤモヤ
まるで幽霊屋敷でドアが開かない理由を考えていたら、実は後ろから鍵がかかっていたような感覚だ。何が原因かも分からず、連絡が途絶えたと思って悩んでいた自分がバカらしい。でも、バカらしいと思う一方で、依頼人に迷惑をかけてしまったという罪悪感も強く残る。結果としては、「確認しなかった自分の落ち度」と言われれば、その通りである。
メール文化と信頼のズレ
メールという便利な道具は、信頼の上に成り立っている。しかしその信頼が、技術的な落とし穴ひとつで崩れることもある。特に法律や登記のような正確性が命の仕事では、小さなミスが命取りになる。私たちは「届いているはず」と思っているが、それは思い込みかもしれない。迷惑フォルダに振り分けられるたびに、その信頼は揺らいでしまう。
こちらの落ち度なのに言い訳がましくなる
結局、依頼人には「迷惑フォルダに入っていたようです」とメールで返信をした。言い訳ではなく、事実なのだが、それでも「返信が遅れてしまい」と頭を下げる文面になった。相手がどんな反応をするか分からないからこそ、こちらは丁寧に、そして慎重に。だがその丁寧さが、かえって保身に見えることもあるから難しい。
見てなかったとは言いにくいけど言うしかない
「見落としていました」と正直に伝えるしかない。でも、それが本当に届いていなかっただけだとしても、信じてもらえるかどうかはまた別の話。とくに書類のやり取りがシビアな案件では、少しの遅れが命取りになることもある。「忙しかったんです」とは言えないし、「そっちのメールが変だったのでは」とも言えない。ただ謝る。…情けない話だが、それが現場のリアルだ。
素直な謝罪と気まずさの境界線
「本当にでした」と書いて送信ボタンを押す手が、妙に重い。相手がどう思っているかを想像しすぎて、自分の中で勝手に悪者になっているような気さえする。けれど、ここで誠実に謝らなければ、関係はもっと拗れてしまう。だからこそ、「どんなに気まずくても素直に謝る」ことを選んだ。言葉だけじゃ伝わらないから、気持ちを込めたつもりだ。
言い訳に聞こえない説明って難しい
何を言っても、結局は言い訳に聞こえるのがこの手のトラブルだ。特に、メールなんて今や誰でも使ってるし、「迷惑フォルダに入ってたんですよ」なんて言えば、聞こえようによっては「そんなの確認しとけよ」と思われるのがオチ。ちゃんと説明して、ちゃんと謝って、それでも相手の中にモヤモヤが残るのは仕方ない。でも、やるべきことはやった、そう思うしかなかった。
そもそもなぜ迷惑フォルダに入ったのか
技術的なことは正直よく分からない。ドメイン認証だのSPFレコードだの、専門家に聞かないと理解不能だ。たしかに、私の事務所のメールは独自ドメインを使っている。でも、なぜそれが迷惑メール扱いされるのかまでは分からない。パソコンって、こちらが思っている以上に勝手な判断をしてくる。
迷惑判定のロジックなんて知ったこっちゃない
迷惑メールの基準って一体なんなんだ。本文に「契約書」「登記」「報酬」なんて単語が入っていたから?HTML形式でちょっと装飾しただけでスパム判定されるとか、意味がわからない。そんなこと言い出したら、まともな業務連絡なんて全部ダメになってしまう。プロバイダの気分で信頼関係が壊れると思うと、なんともやるせない。
GmailとOutlookの気まぐれ
同じ内容のメールでも、Gmailでは迷惑扱いされるのに、Outlookでは普通に届いたりする。もうこれは、完全に運としか言いようがない。通知もなければアラートも出ない。ただ静かに、迷惑フォルダで眠っている。それに気づくまでに数日かかるというのも、事務所運営としては致命的だ。なのに、システム側は一切責任を取らない。理不尽だ。
ドメイン設定とか本当に苦手
事務員の子にも聞いたが、彼女も「それは詳しい人に頼んだ方がいいですね」と苦笑い。結局、私はネット検索で設定方法を調べて、SPFとDKIMを必死に設定した。こういうのがあるから、PC関係のことは本当に嫌になる。でも、やらないとまた同じことが起きる。だから、やる。嫌々でもやる。それが一人事務所の現実だ。
メールだけに頼ってはいけないのかもしれない
今回の件で痛感したのは、メールは便利だけど万能じゃないということだ。これからは電話確認やLINEでの補足連絡も視野に入れていくべきかもしれない。効率よりも確実性を優先すべき場面は、想像以上に多い。小さなミスが、大きな信頼を失うことにつながる。その重みを忘れないようにしたい。
電話確認のひと手間を惜しまないという決意
昔は電話確認が当たり前だった。それが今では「電話は面倒」と言われる時代。でも、迷惑フォルダに埋もれた一通のメールで信頼を失うくらいなら、ひと手間かける価値はある。実際、今回も電話していれば一発で解決していた。効率化の名のもとに、重要なことを見失ってはいけない。そう、身に染みて感じた。
結局アナログが一番確実という皮肉
デジタル化、ペーパーレス、クラウド時代…便利になったけど、トラブルも増えた気がする。紙で確認していた時代の方が、むしろ安心だった部分もある。人の手で確認し、人の目で見る。そのアナログさが、信頼の土台になっていたのかもしれない。これからは便利さと信頼性のバランスを、もっと考えていきたい。
でも時間も人手も足りない現実
理想はわかっている。全部確認して、全部連絡して、全部記録して。でも、一人で回してると、理想と現実のギャップに潰されそうになる。事務員だって万能じゃない。だからこそ、ミスを減らす仕組みを作らないと、自分が壊れる。技術に頼りすぎず、でも技術も活かす。そのバランスが、これからの課題だ。