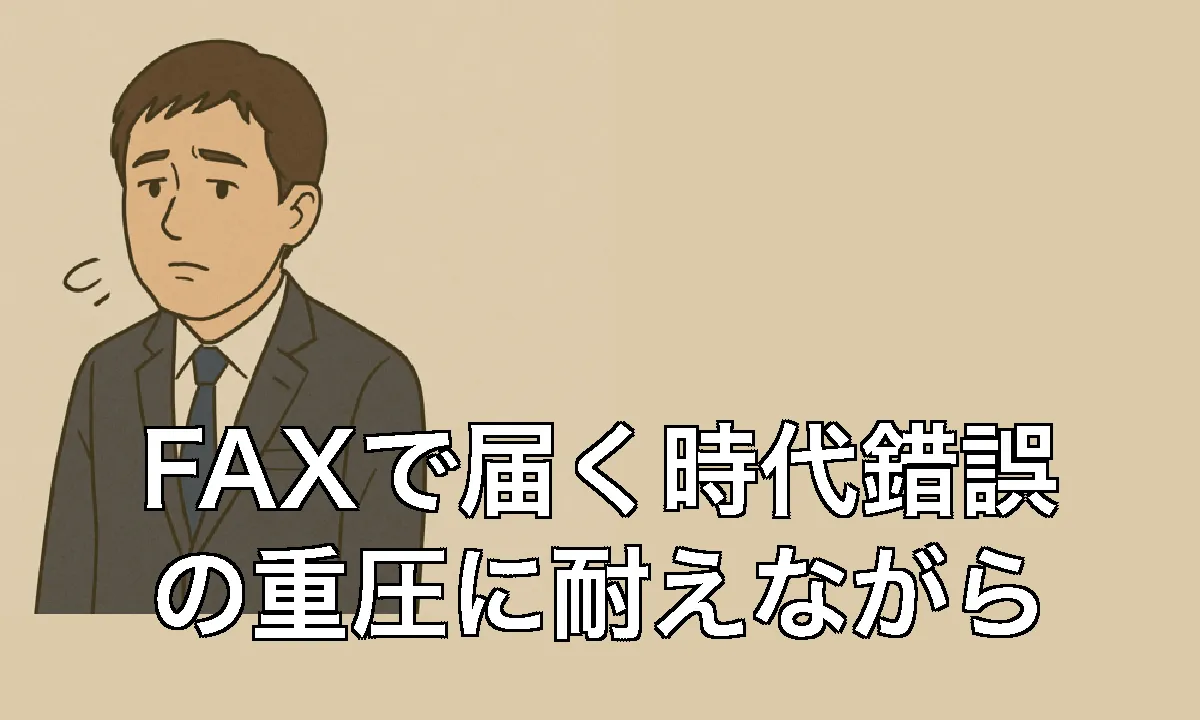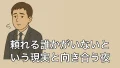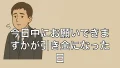まだFAXですかという気持ちが喉元でつかえる
「令和のこの時代に、まだFAX?」と思ってしまう。そんな感情が込み上げるたび、自分がどこか古い世界に閉じ込められているような感覚になる。メールもチャットもあるのに、依頼はFAX一択。紙が詰まり、トナーが切れ、しかもそれが“当然”として扱われる。司法書士として働いていると、未だにFAX文化が根強く残っている現実に直面する日が多い。事務員がひとりしかいない小さな事務所では、たかが一枚の紙でも、受け取るまでにかかる労力が想像以上に大きい。
デジタル化と言いながら紙で縛られる現場
役所も銀行も「オンライン化を進めています」と謳ってはいるけれど、現実は違う。ちょっとした照会書や確認書は、PDFではなくFAXでの送付を求められることが珍しくない。電子署名やクラウドでのやりとりができる時代に、なぜか紙とFAXだけは根強く残っている。効率化の波が押し寄せているはずの業界なのに、いざフタを開けてみれば、結局こちらがプリントアウトして手書きで返信。昭和から何も変わっていないような空気に、ただただため息が漏れる。
PDFで送れば済むはずの書類がなぜか出力前提
こちらからPDFを添付してメールを送っても、「プリントアウトしてFAXで再送してほしい」と返ってくることがある。わざわざ電子化された情報を紙に戻し、今度はアナログ手段で送り返す。まるで文明を逆行するかのような作業だ。しかも、その対応を求めてくる相手が「若手」と言われる年齢層だったりすると、なおさらやるせない。どうしてこんな非効率が黙認されているのか、本当に不思議で仕方がない。
トナー切れの絶望と事務員のため息が重なる朝
ある朝、出勤するとFAX機からエラー音。トナーが切れていた。すぐに予備を探すが在庫はなく、事務員と顔を見合わせて無言になる。「ああ、今日も始まったな」という気持ちだけが部屋に広がる。FAXでしかやりとりできない相手がいるという現実。こういうトラブルがあるたび、なんで自分はこの仕事を選んだのかと、ちょっとだけ後悔する。でも誰も悪くない。だからこそ、余計にしんどい。
FAXの音が鳴るたびに心がざわつく理由
「ピー…ガーガー…」というあの音。昔は業務連絡の証のように聞こえたのに、今は心がざわつく。大抵、急ぎの対応が求められているか、面倒な書類が送られてくる。しかも受信した瞬間にすぐ対応しないと“対応が遅い”と見なされてしまう。メールで送ってくれれば時間も把握できるし、内容の確認も楽なのに、それを許さない空気が未だにこの業界にはある。
いつも緊急 いつも手書き いつも突然
FAXで届く書類に共通する特徴。それは「急ぎで」「手書きで」「事前連絡なし」の三拍子だ。電話一本すら入れず、突然届く照会書に「今日中に回答ください」と書いてあるときの虚無感ときたら。こっちの予定も無視されたような気持ちになるし、当然そのしわ寄せはこっちの事務員にもいく。小規模事務所では、一人の事務員に過剰な負担がかかるのが常。自分の手を止めてでもフォローせざるを得ない。
電話とFAXに支配される時間割
自分のスケジュール帳には、実際の予定よりも、「いつ誰からFAXが来るか」「何時に電話が来そうか」といった“予測不能”なことが支配している。時間を区切って作業するのが理想だけど、FAXや電話がその流れを崩してくる。集中し始めたころにガーガーと音が鳴り、すべてが中断される。効率的に仕事を進めるには向かない環境に、自分で自分をなだめながら仕事を続ける毎日だ。
本当に今それ必要だったのかを考えてしまう
たとえば、相続登記の補正依頼。明日でも間に合うはずの内容が、わざわざFAXで「本日中にご対応を」と送られてくる。相手方はたぶん、機械的に送っているだけなのだろう。でも、こちらとしてはその一通が一日の流れを狂わせる。手を止めて、書類を探し、内容を確認し、手書きで回答。気がつけば一時間以上経っている。「本当に今すぐ必要だったの?」と毎回自問してしまう。
紙が重いのではない 圧が重いのだ
何グラムの紙よりも、その向こうにある「やれよ」という圧力のほうがずっと重い。紙の書類は、単なる情報の媒体ではなく、上下関係や慣習の象徴になってしまっているのかもしれない。FAXという手段で届く依頼は、時に「急げ」「言われた通りにやれ」「黙って対応しろ」という無言の命令にも感じられる。それに逆らう気力もなくなり、今日もまた受話器を取ってしまう自分がいる。
効率よりも慣習が優先される空気
「今までそうしてきたから」と言われると、何も言い返せない雰囲気がある。FAX文化が残っているのは、技術の問題ではなく“人の気持ち”の問題だ。相手のやり方に合わせることが“礼儀”とされ、そこに疑問を投げかけると「神経質」「変わってる」と言われかねない。本来であれば、より効率的でストレスのない方法を選ぶべきなのに、それができないというジレンマに、ただただ疲れてしまう。
「今までもこうしてきたから」が仕事を鈍らせる
昔のやり方を守ることが美徳だという風潮が、実は効率や品質を下げていることに気づいていない人が多い。FAXはその象徴だ。時間も手間もかかる、紛失のリスクもある、それでも「これが普通」とされてしまう。自分が新人だったころは、先輩のやり方に従うことが当たり前だったが、今ではその“当たり前”が足かせになっている。変える勇気が持てないまま、ただ疲弊していく。
声をあげるよりも飲み込む方が楽だと悟る瞬間
正直、FAXをやめましょうと言ったところで、相手が変わらなければ意味がない。それどころか、関係性にヒビが入るリスクもある。だから何も言わず、黙って受け取って黙って返信する。そんな日々が積み重なると、いつしか「言わないほうが楽だ」と思うようになる。自分が我慢すれば済む話だと、無意識に処理してしまう。でもその我慢は、確実に心を削っていく。
それでも僕らは今日もFAXを受け取ってしまう
FAXが悪いわけじゃない。使い方次第で便利な場面もある。でも、今の使われ方はどうにも時代錯誤で、無力感を抱くには十分すぎる。それでも僕ら司法書士は、今日もFAXを受け取って、書類を広げて、黙々と処理していく。誰にも気づかれず、誰にも褒められず。ただひたすら、誰かの依頼に応えるために。
誰かを責めるよりも自分をなだめる日々
「しょうがないよな」「みんなそうしてるしな」そんな言い訳を並べながら、自分の気持ちをなだめている。他人を責めても意味がない。でも、そのやりきれなさを誰かと共有したい。だからこうして、文章にして吐き出しているのかもしれない。この記事を読んで、「うちも一緒だよ」と思ってくれる人がいたら、それだけで少し救われる。
事務員に頼めず自分で紙を詰まらせる午後
午後、事務員が外出している間にFAXの紙が詰まり、必死に中を開けて直そうとしたが、逆に悪化させてしまった。紙まみれになりながら、昔の自分なら笑っていたであろう場面で、今はただ疲労感だけが残る。誰かと分担できるわけでもなく、今日も一人で紙と格闘する。FAXなんてなければ、もう少し穏やかな一日だったかもしれない。