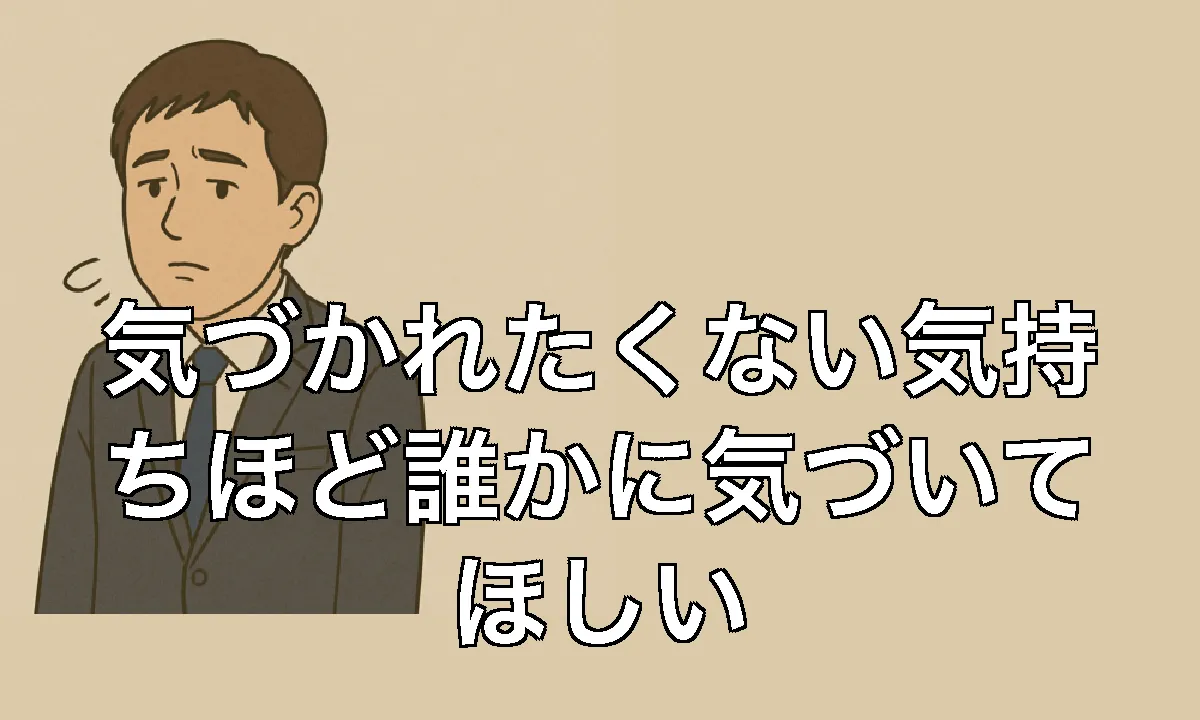気づかれたくない気持ちほど誰かに気づいてほしい
忙しさに隠した本音はどこに行くのか
司法書士という仕事は、感情を置き去りにしてでも手続きを優先せねばならない場面が多々あります。相手の不安に寄り添いながらも、こちらは慌ただしく印鑑と書類の山に埋もれている。そんな毎日の中で、「大丈夫ですか?」と声をかけられることはほとんどありません。でも、だからこそ思うのです。誰かがそっとこちらの疲れに気づいてくれたら、どれだけ救われるか。かといって「疲れてます」と自分から言うのは妙に照れくさい。忙しさの中に、本音はどんどん埋まっていきます。
目の前の依頼に追われて心の余裕が削れていく
朝から相続登記、午後は決済の立会、夕方には急ぎの書類作成。気づけば昼食すら忘れている日もあります。目の前の依頼に応えることが、いつの間にか自分を削っていく作業になっていて、余裕なんて言葉は遠い昔の話。仕事があることはありがたい、そう思う反面、ふとした瞬間に「あれ、自分は何のためにやってるんだろう」と立ち止まりたくなる。でも立ち止まれないから、どこかで誰かに「お疲れさま」と言ってほしい。でも、言われたら言われたでうまく返せない。それが本音です。
誰にも言えない苛立ちが積もる日々
たとえば、登記の補正を食らったときのやるせなさ。役所の担当者はあっさり「再提出お願いします」なんて言いますが、その一言の裏にある手間と気持ちを誰も知らない。クライアントには迷惑をかけたくないから必死に対応しますが、その苛立ちを吐き出す場がないんです。昔、野球部でエラーしても誰も責めず、むしろ「次いこ、次!」って声をかけてくれたあの空気が懐かしくなります。
気づかれたくないのは弱さではなく誇りかもしれない
「弱音を吐かない=強さ」だと信じてきた時期がありました。司法書士になってからは特にその傾向が強くなり、頼られることを誇りにしてきた。でも、気づかれたくないのは弱さじゃなくて、むしろ“自分の中で処理したい”という不器用な誇りなのかもしれません。だから、気づかれたくないけど、完全に無関心でいられると、それはそれで寂しい。矛盾してますよね。
事務所で交わされない言葉たち
事務所には事務員さんが一人います。とてもよく働いてくれていて、こちらも信頼して任せています。ただ、それ以上の会話になるとどうしても壁がある。距離を取りすぎてもぎこちないし、近づきすぎても仕事に支障が出る。その微妙な距離感の中で、本当は誰かに聞いてほしいことが喉の奥で引っかかるのです。
事務員との距離感に感じる妙な孤独
彼女とは長い付き合いになりますが、仕事の話以外を深くすることはほとんどありません。以前、こちらが風邪気味でフラついていた時も、特に何も言わず通常運転。それが逆にありがたかった反面、ちょっとした気づきの一言があれば、もっと違っていたのかもしれない。誰かと近すぎるのも息苦しいけど、遠すぎるのもやっぱり寂しい。そういう微妙な距離に、日々揺れている自分がいます。
声をかけたいけど気まずさが先に立つ
たとえば、ふとした瞬間に「今日は寒いですね」と話しかけたいこともあるけれど、突然そんな話をするのも変かなと尻込みしてしまう。話すタイミングを逃すと、もうどうでもよくなってしまうのがまた虚しい。こちらの性格もあるでしょうが、相手に気を遣いすぎて結局言えずじまい。結果、事務所に流れるのは静かな時間ばかりで、その沈黙に小さな孤独を感じるようになります。
話せる相手がいても話せる内容じゃない
友人や同業者に飲みの席で愚痴ることもあります。でも、「それは大変だったね」と言われると、それ以上深掘りされたくなくて話を変えてしまう。結局、誰にも本当の意味では打ち明けていないのかもしれません。話せる相手がいても、話せる内容ではない。そんなジレンマが、また一つ、気づかれたくない気持ちを積み重ねていきます。
「大丈夫です」が口癖になってしまった理由
本当は「ちょっと疲れてます」と言いたいのに、口から出るのは「大丈夫です」。それは誰かに心配されるのが面倒だからでもあり、誰かの時間を奪いたくないという遠慮でもあり。結果として、気づかれない存在になっていく。そしてまた、「誰か気づいてくれないかな」と思ってしまう、厄介なループです。
頼れるはずの誰かに頼れない現実
以前、昔の同級生に「最近どう?」と聞かれたとき、「まあまあだよ」と答えました。でも、その時本当は「疲れてる。ちょっと限界かも」と言いたかった。だけど言えなかった。相手に心配をかけたくないし、下手に重い話をすると嫌われそうな気もする。だから結局、また自分の中にしまい込んでしまう。こうしてまた“気づかれたくないけど気づいてほしい”気持ちが膨らんでいきます。
元野球部だった頃のように背中で語るつもりが
学生時代は野球部で、何も言わなくてもチームメイトが察してくれる関係が心地よかった。あの頃は、黙っていても背中で何かが伝わっていた気がします。でも今は、背中を見てくれる人すらいない。見ているのはパソコンの画面か、書類の束。背中で語るつもりが、ただ黙って疲れているだけになってしまっている現実に、ふと寂しさを感じます。
プライドより先に疲労がにじみ出る
本当は「まだやれる」と思いたい。でも年齢もあるのか、夕方には肩が重くなり、目もショボショボしてくる。それでも「まだ大丈夫です」と言ってしまう自分がいます。プライドというより、職人としての意地。でも、最近ではその意地よりも先に疲労感が勝ってきた気がします。気づいてほしいけど、気づかれたら自分の限界を認めることになる。それが怖いのかもしれません。