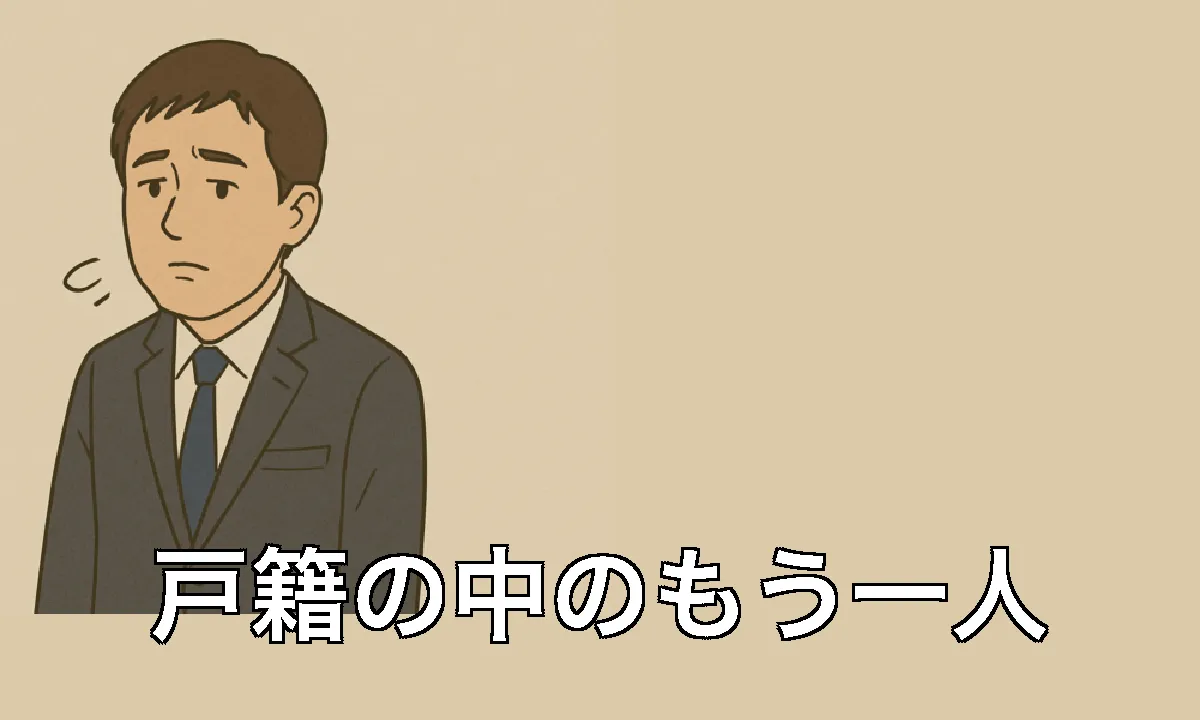登記申請の朝に届いた封筒
朝から雨がしとしと降っていた。郵便受けには茶封筒が一通、無造作に突っ込まれていた。差出人の記載はない。
私は濡れた封筒を手に取り、事務所のデスクに置いた。なんだか、嫌な予感がする。そういう直感だけは、昔から妙に当たる。
「また変な案件かもしれませんよ」と背後でサトウさんがぼそっと呟く。彼女の予感も、だいたい当たる。
差出人不明の戸籍謄本
封筒を開けると、中には一通の戸籍謄本が入っていた。しかも、それは依頼人のものではない。赤の他人の名前が記載されていた。
「いたずらでしょうか?」私は首をかしげたが、サトウさんはすぐにパソコンを叩き、依頼人の名前と照合し始めた。
「名字は同じですね。でも本籍も違うし、繋がりは見えません。何か意図がありますよ、これ」と彼女は断言した。
不審な戸籍の記載内容
私はその謄本をめくりながら目を凝らした。昭和の終わりに誰かが除籍され、謎の人物が新たに記載されている。
出生の記録がやたら曖昧で、「事実婚の子」といった表現が多用されていた。まるで、書いた者が何かをごまかそうとしているようだった。
やれやれ、、、。また厄介な話に巻き込まれそうな気がした。今日の予定、すでに3件も登記申請が詰まっているのに。
消えた本籍地と見知らぬ名前
住所を確認するために、私は謄本に記された本籍地をネットで検索した。しかし、今はその地番そのものが存在していなかった。
「幽霊地番ですね」とサトウさんがポツリ。彼女の言葉に、私は一瞬『地縛霊に取り憑かれた登記簿』というサザエさん風な妄想をしてしまう。
いやいや、そんなバカな。と思い直したが、この謄本には確かに“生きていない”何かがあった。
依頼人の正体
一方、依頼人の田所という男は、申請書類を整えて再び事務所に現れた。彼は60代で、やけに無口な人物だった。
「こちらの戸籍ですが、あなたとは関係が?」と私は戸籍謄本を差し出した。彼は少し怯んだ後、「それは…昔の話です」とだけ答えた。
この瞬間、彼の中に何かを抱えているのが見えた。ルパン三世の銭形警部なら、すでに手錠を構えていたかもしれない。
語られない過去と口ごもる遺言
依頼人は父親の遺言を示したが、それは手書きの走り書きで、形式も要件もなっていなかった。
「父は…生前、本当に苦労したんです。その分、俺が家を守らなきゃいけないって…」と彼は語った。
だが、私の司法書士としての直感が警鐘を鳴らしていた。何かが決定的に欠けている、と。
相続登記が進まない理由
遺言では登記はできない。それに、法定相続情報一覧図を作成しようにも、戸籍の内容が合致しない。
私は黙って謄本を並べ、矛盾を確認していった。すると、ある時点で「長男」が突然別人になっていることに気づいた。
「これ、兄弟をすり替えてますね」とサトウさんが冷静に言う。その一言が、全ての歯車を動かした。
法定相続情報一覧図との矛盾
一覧図に記された人物の一人が、実際には死亡していないか、もしくは存在しない可能性があった。
つまり、戸籍上だけで操作された“もう一人”が、相続の権利を持たされていたことになる。
相続人を偽る行為は重罪だ。だが、それを行った動機は一体何なのか。私にはまだ見えていなかった。
調査開始とサトウさんの推理
私は思い切って、依頼人の了承を得て、市役所に過去の除籍簿を閲覧しに出向いた。そこには驚くべき記録があった。
昭和53年、一度婚姻したはずの女性が離婚後、別の男性との間に生まれた子を「田所家」の籍に入れていたのだ。
「これ、親子関係の隠蔽ですね」とサトウさん。彼女の推理は早かった。
市役所職員の一言が突破口に
「ああ、その方、昔“二人の父”がいたって騒がれてましたよ」と職員が何気なく言った。
その言葉に、私はピンときた。つまり、その子どもは生物学的な親と戸籍上の親が違っていたのだ。
そう考えると、あの不自然な戸籍の矛盾もすべて辻褄が合った。
戸籍を偽った理由
戸籍上の長男は、実際には依頼人とは血縁のない人物だった。だが、父親が強引に養子にしていた。
その人物が相続を主張すれば、依頼人が育った家は他人のものになる。父の想いと現実が、ずれていたのだ。
依頼人は、家を守るために、戸籍からその人物を“消す”という選択をしたのだ。
亡き父が残した秘密の婚姻届
さらに調査を進めると、かつて提出されたが不受理となった婚姻届の写しが見つかった。
そこには、実の母と実父の名が連なっていた。つまり依頼人は、認知されていない実子だったのだ。
皮肉にも、その届出が受理されていれば、今回の相続争いは起きなかっただろう。
戸籍の中のもう一人の存在
すべての証拠を整理し、依頼人に伝えると、彼は静かにうなずいた。「あいつに家をやるよ」と一言だけ言った。
争うことよりも、終わらせることを選んだようだった。司法書士として、私はその判断を尊重した。
やれやれ、、、人の心も登記簿のように整理できれば楽なんだが。
認知された子と法定相続の真実
法的な整理は進み、登記は予定より一週間遅れで完了した。私は法務局へ提出する書類を確認しながら、ため息をついた。
正しさとは何か。血か、想いか、あるいは書類か。今回ほど、その問いに悩んだことはなかった。
「悩む時間があれば登記終わらせてください」とサトウさんが容赦なく言ってきた。はいはい、ごもっとも。
全ては家の名義を守るためだった
依頼人は登記完了の報告を受け取り、穏やかな表情で礼を言って帰っていった。
背中には、重荷がひとつ消えたような清々しさがあった。もしかしたら、彼なりに赦しを得たのかもしれない。
人が家を守るのではない。家が人を試している。そう思った。
兄と弟の対立と和解
後日、実の兄とされる人物からも連絡があった。「もういいんです。父の家はあいつのもんですよ」
互いに話し合いを持ったとのことだった。まるでキャッツアイの姉妹のように、譲る愛がそこにあった。
血ではなく、過去ではなく、今を生きる選択が、和解を導いたのだろう。
やれやれ案件は無事解決
静まり返った夕方の事務所。私はやっと一息ついて、残りの書類に目を通した。
この案件も一件落着。何だかんだで、うまく終わった。やれやれ、、、。
「終わったなら、ちゃんと片付けてください」とサトウさんの塩対応が締めくくってくれた。
塩対応のサトウさんの小さな笑み
ふと見ると、サトウさんがほんの少しだけ、口元を緩めていた気がした。気のせいかもしれないけれど。
それが、今日いちばん救われた瞬間だった。
明日は明日で、また新しい戸籍とにらめっこだ。
残された登記簿に記された名前
最終的に、登記簿には依頼人とその“兄”の名が並んで記載されることとなった。共有名義という選択。
それが正しいかどうかはわからない。ただ、これが彼らなりの答えなのだろう。
そして私は、また新しい謎に巻き込まれることを想像しながら、そっと事務所の灯りを消した。