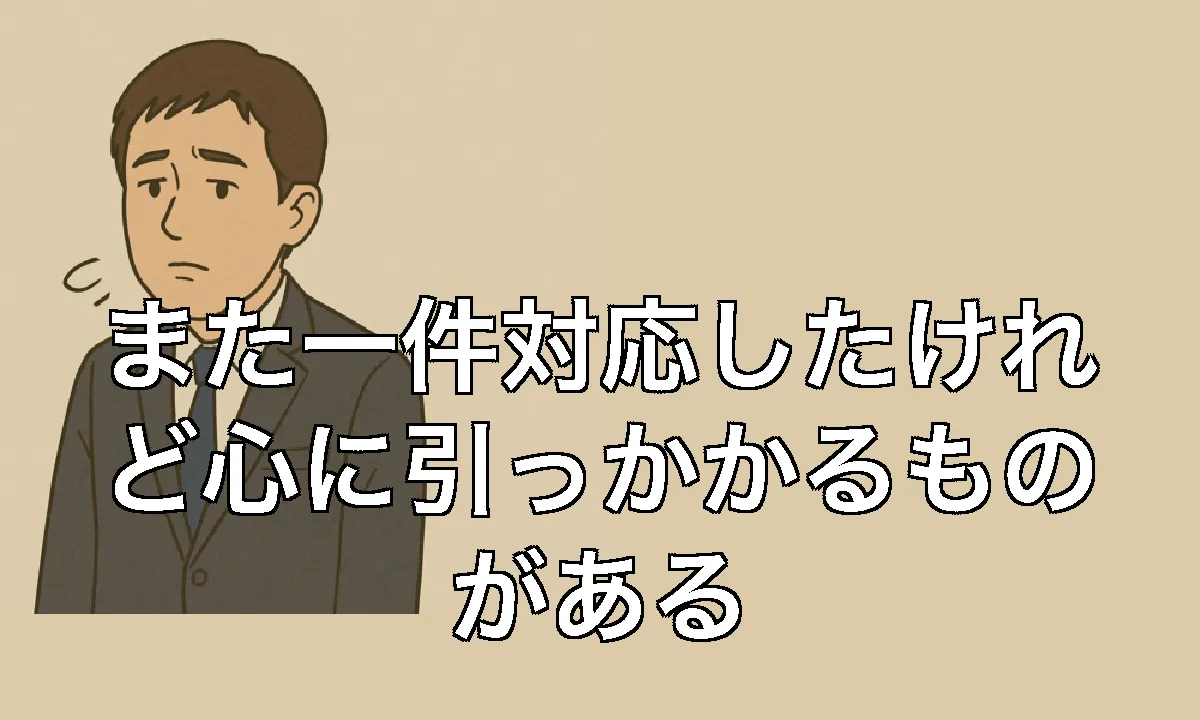対応は終わったのに心が晴れない日
司法書士という仕事は、ひとつひとつの案件に終わりがあるはずなんです。登記が完了したとか、書類が整ったとか、形式上は「終わった」と言える。でも、心の中では終わっていないことがあるんです。今日は、そんな「心残り」について書いてみようと思います。つい先日も、一件の相続登記を終えたんですが、どうにもすっきりしない気持ちが残りました。業務としては完了している。でも、あの依頼者の表情が忘れられない。笑顔がなかった。怒っていたわけでもない。けれど、「何か伝えきれていなかったんじゃないか」という引っかかりが残るんです。
完了報告のメールを送ったあとに残るもやもや
あの日、事務所で相続登記完了の連絡メールを送信しました。形式通りの文面で、書類は郵送しますと添えて。返ってきたのは、あっさりした「ありがとうございます。」の一文だけ。返信があっただけ良い方かもしれません。でも、何か物足りなさを感じたんです。いや、正確には「自分に何か足りてなかったのかも」と不安になったという方が近い。書類の完成度の問題ではなくて、たぶん「対応としての温度」みたいなもの。もっとできたんじゃないか、そんな気持ちがいつまでも残っていました。
書類上は完璧でも納得できない理由
内容にはミスもなく、法務局からも補正なしで受理されて完了した案件です。形式的には非の打ちどころがない。でも、仕事って、それだけじゃ足りないときがある。たとえば、かつて別の案件で「丁寧に対応してくれて助かりました」と言ってもらえた時、あれは業務外のほんの一言を添えただけでした。「お父様が生前大切にしていた土地だったんですね」とか、そういう小さな気遣い。でも今回は、それを省いた気がする。忙しかったからというのは言い訳ですね。相手の気持ちに寄り添う余白が、自分に残っていなかった。
「あの時もう少し話を聞いていれば」という後悔
電話でのやりとりの中で、依頼者の口調に少し迷いがあったのを思い出します。「兄とはもう話せないので…」と小さく漏らしたあの一言。本当は、その続きを聞いてあげるべきだったんじゃないか。事務的に「では書類を送りますね」と終わらせてしまったあの瞬間を、ずっと引きずっています。司法書士はカウンセラーじゃない。だけど、人の人生の節目に関わる以上、ほんの少しの「気遣い」が、依頼者の心に残るものになることがあるんです。
依頼者の表情が忘れられないとき
たまに面談で来所される方の中に、強く印象に残る表情をされる方がいます。この前の依頼者もそうでした。言葉少なで、終始緊張していて、笑顔が出ないまま帰られた。相続登記って、遺産を整理するだけじゃないんですよね。感情の整理も含まれてる。こちらは業務の流れに慣れてしまって、形式的に進めてしまいがちだけれど、相手にとっては「一生に一度の大きな転機」かもしれない。そう考えると、自分が発する一言、沈黙の時間、すべてがその人の記憶に残る可能性がある。責任の重さを、改めて痛感します。
笑顔じゃなかったことに気づいた帰り道
夕方、自転車で帰る途中にふと、その依頼者の顔を思い出しました。あの人、帰り際もずっと表情が変わらなかったな…って。帰りの道すがら、「もう少しだけ自分に余裕があればな」と思いました。依頼が多くなってきて、毎日がぎゅうぎゅう詰め。でも、それを理由に人への配慮を削ってしまったら、この仕事の本質が崩れてしまう気がするんです。
そもそも何のためにやっているのかと立ち止まる
夜、事務所で帳簿を付けながら、「そもそも何のためにこの仕事をやっているんだろう」と考えることがあります。もちろん生活のため。でもそれだけじゃここまで続けられなかった。何か、誰かの役に立っている感覚があるからやってこれたんだと思います。なのに、ここ最近はその実感が薄い。形式に追われて、心が追いついていない。そんなとき、「また一件終わった…」という達成感と一緒に、ぽっかりとした空虚感もやってくるのです。
誰かの役に立っているという実感の希薄さ
たまに、依頼者から丁寧なお手紙をいただくことがあります。そういうときは「やっててよかった」と素直に思える。逆に、何の反応もない時期が続くと、「本当に自分の対応はこれで良いのか?」と自問自答するようになります。承認欲求とかじゃないんです。ただ、誰かの人生の節目に関わっていながら、記憶にも残っていないかもしれないと想像すると、寂しくなるだけなんです。
感謝されたいわけじゃないけど無反応はつらい
「ありがとう」が欲しいわけじゃない。でも、無反応は想像以上にこたえます。それはまるで、誰にも見られずにピッチング練習だけ繰り返しているようなもの。元野球部だからこそ、声援やリアクションがどれだけ自分を支えてきたか知ってる。今は、無観客試合をずっと続けてる感覚。そんな中でも、丁寧に投げ続けなきゃいけない。それがこの仕事だとは分かっていても、やっぱりしんどい時はあるんです。
仕事は増える一方で考える余裕がない
この数年、地方でも相続や成年後見の相談は増え続けています。ありがたい話ではあります。でも、ありがたさと「処理しきれない」という現実は別問題。仕事は山積み、依頼者は待っている、そして自分は一人事務所。事務員さんに任せられる業務にも限界があるし、結局「一番面倒な部分」は自分でやるしかない。時間的にも精神的にも、常に限界すれすれの中で動いています。
事務員と二人三脚の限界
今の事務員さんは真面目で丁寧な人で、とても助けられています。でも、彼女にも家庭があって、フルタイムではない。結果として、書類のチェックや法務局とのやりとりは、やはり自分で担う部分が多くなる。「全部任せて大丈夫かな」という不安もあって、ついつい自分で抱え込んでしまう。これが結果として、対応の余裕を削ってしまっている。悪循環ですね。
回せてはいるが、回しきれていないという焦燥
一応、仕事は進んでいます。登記も終わっているし、締め切りも守っている。でも、心のどこかで「もっと丁寧にやりたかった」と思うことがある。たとえば、案件ひとつ終えるたびに、机の上の書類が雪崩のように押し寄せる。それを見た瞬間、「次、次…」と自分に言い聞かせてる。でも本当は、一件一件にもっと気持ちを込めたいんですよ。理想と現実のギャップに、焦りばかりが積もっていきます。
人を雇う怖さと責任のはざまで
「もう一人雇えば?」と周囲に言われることもあります。でも、地方の個人事務所でそれは簡単じゃない。まず人が来ない。来たとしても、教える時間も余裕もない。そして何より、給料を払い続ける責任が怖い。独身だし、守る家族がいるわけでもないけれど、それでも「人の生活を支える」というプレッシャーは重い。だったら自分で頑張る方が気が楽だと、そうして今日まで来てしまったのです。
心残りを減らすためにできることはあるのか
きっと完璧な対応なんてないんだと思います。それでも、せめて「やりきった」と自分で思えるように、小さな工夫はできる気がします。最近は、少しでも相手の状況に触れるような言葉を添えるよう心がけています。書類を送るだけでなく、手紙に一言「この度のこと、お疲れさまでした」と書くだけでも、何かが違う気がしています。それが自己満足かもしれない。でも、それで心残りが減るなら、それもまたこの仕事の一部だと思うのです。
時間がなくても一言添える努力
メールや手紙、LINEでのやり取り――形式にこだわらず、気持ちを伝える手段はたくさんあります。書類を整えるのに全力を注ぐのは当然として、ほんの一言でも「人と人」として関わる言葉を残せたら、それが相手の記憶にも、自分の気持ちにも違いを生む。だから、どんなに疲れていても、せめて「おつかれさまでした」「大変でしたね」の一言を忘れないようにしています。
完璧じゃなくても気持ちを伝えることの意味
ミスのない仕事。それはもちろん大事です。でも、心を込めることも同じくらい大事だと、最近は強く思います。誰にも伝わらなかったとしても、自分が「ちゃんと向き合った」と思えたら、それが次の力になる。この仕事に誇りを持ちたいなら、効率だけを追わず、心を置いていくような仕事は避けたい。だからこそ、また一件終わったとき、「心残りはない」と言えるような仕事を目指して、明日もまた書類を作り続けようと思います。