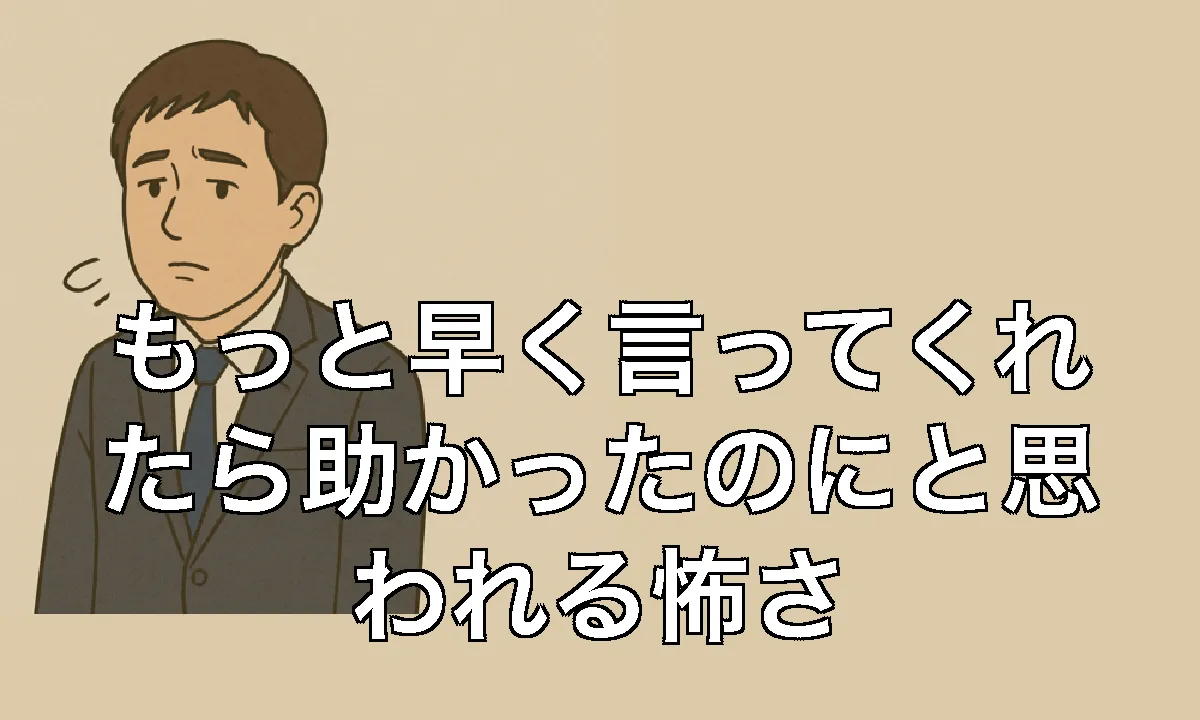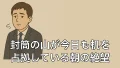もっと早く言ってくれたらの一言に刺される日々
「もっと早く言ってくれたら助かったのに」――この一言ほど、心をえぐられる言葉はない。別に怒鳴られたわけでもないし、責め立てられたわけでもない。ただ静かに、でも確かに、自分の力不足や気づかなかったことを突きつけられる。司法書士として仕事をしていると、こうした言葉に出くわす機会は決して少なくない。依頼者に悪気がないのはわかっている。それでも、夜中ふとその言葉が脳裏をよぎり、眠れなくなる日もある。あの手続きをもっと早く気づいていれば、あの提案を一言添えていれば――。その「たられば」が、胸の中に溜まっていく。
誰のためにやっているのか分からなくなるとき
「お任せします」と言われて動き始めるのに、結果的に「そんなの聞いてない」「そういう意味じゃなかった」となると、もうこちらとしては何をどうすればいいのかわからなくなる。司法書士は心を読めるわけではないが、どこかで“完璧に理解して当然”という空気を感じてしまう。最近も、登記の件でご家族との関係がこじれている案件があり、あれこれ配慮したつもりだったが、結果として「もっと早く方向性を説明してくれたら」という言葉を浴びた。こちらなりに気を回したつもりが裏目に出ると、「結局何のためにやってるんだろう」と思ってしまう。
信頼してくれていると思っていたのに
その方とは何度もやりとりをしていたし、ちょっとした雑談も交えながら関係性は築けていると思っていた。それだけに、「もっと早く…」の一言は意外だった。信頼関係があったはずなのに、それでも足りなかったという現実。どうしてあの時、もう一歩踏み込んで確認しなかったんだろうと自問する。こちらの「言わなくてもわかってくれているだろう」という思い込みが、一番危険だと知っていながら、やっぱりそれに甘えてしまっていたのかもしれない。
失望されたような目がつらい
一番堪えるのは、直接的な言葉よりも、ふとした瞬間の目だ。あれは完全に「がっかり」した人の目だった。怒っているのではなく、諦めているような、どこか距離を取るような視線。あの目を思い出すたびに、胃の奥がキリキリする。ミスじゃない。説明が遅れただけ。でも、その一歩の遅れが「信頼の崩壊」につながってしまう。たった一言の説明を後回しにしただけで、すべてが壊れてしまうのがこの仕事の怖さだ。
司法書士は予知能力者じゃない
依頼者の心を完全に読むことはできない。けれど、それを求められているように感じる瞬間がある。「あ、それ言ってなかったですね」「そんな背景があったんですか」といった会話を交わすたび、こちらは内心ヒヤヒヤしている。状況を完全に理解できていないまま進めた書類作成ほど、不安なものはない。でも、どこまで聞くのが適切かは常に悩みどころだ。プライバシーや感情に踏み込みすぎても逆効果になる。まるで地雷原の上を歩いているような感覚になる。
伝えられない情報が業務に大きく影響する
たとえば、ある相続の件で、家族関係がかなり複雑な案件があった。依頼者は「兄とはもう連絡取っていない」とだけ言っていたが、実はその兄と金銭的なトラブルを抱えていて、それが大きく登記手続きに影響した。早めにその事情を知っていれば、書き方や流れを変えることもできた。でも、そこを聞き出すには相当な信頼と、タイミングと、勘がいる。話してもらえなかった自分に非があるのか、話さなかった依頼者に原因があるのか――結局、ぐるぐると悩むだけだ。
でもそれを言い訳にしてはいけない空気
「言ってくれなきゃ分からない」というのは当然の主張だ。でも、だからといってこちらが「それは聞いていなかった」と言い訳すれば、相手の不信感は一気に高まる。特にこの仕事は「プロなんだから察してよ」という無言の期待を背負っている。そういった“空気”を読むのもまた、仕事のうちだと思わされる。だけどそれが一番疲れる。説明しても伝わらない。聞いても話してくれない。何をどうしてもズレが生まれる。もはや「正解」が分からない世界だ。
反省と謝罪の繰り返しに疲れる
気を遣ったつもりだった、配慮したつもりだった。だけど結局、「」「今後気をつけます」のループになる。それが毎月のように繰り返される。その一つひとつは必要な対応であり、反省もする。でも、心のどこかで「もう勘弁してくれ」と思ってしまう自分もいる。人として、プロとして、それでいいのかと自問する日々。気を張っていないと潰れてしまう。
事務員さんのほうが冷静に処理している現実
正直、うちの事務員さんのほうがうまく立ち回っている場面が増えてきた気がする。こちらが焦っているときほど、冷静に「先生、それは最初に言っておいたほうが良かったですよ」とポツリ。まるでカウンセラーか教師のように諭される。年下の女性だが、もう「先生」として見られている気がしない。でもそれで業務が回っているなら、それでもいいのかもしれない。
年下の一言に救われることもある
以前、登記の内容が複雑で相手先にうまく伝えられず、クレーム寸前になったことがあった。落ち込んでいたところ、事務員さんが「大丈夫ですよ、あの方いつもあんな感じですから」と笑ってくれた。なんというか、その一言がなければ立ち直れなかったと思う。冷静な視点と柔らかい言葉。年下だけど、ずいぶん頼れる存在になっている。
元野球部のプライドがちょっと邪魔をする
学生時代、キャプテンをやっていたこともあって、「最後は自分が責任を取る」という意識が染みついている。だからこそ、事務員さんの助言を素直に聞けないときがある。「ここまで言われるようになったか」と自分を情けなく思うこともある。でも、いまはもうそういう時代じゃない。肩書きや経験だけで信頼されるわけじゃない。そうわかっていても、つい意地を張ってしまう自分がいる。
素直にごめんが言えるようになってきた
最近やっと、素直に「ごめん」と言えるようになってきた。完璧じゃなくていい。むしろ、不完全であることを受け入れて、それでも誠実に対応していくこと。それが大事なんだと気づいたのは、ここ数年のことだ。今後もたぶん、「もっと早く言ってくれたら助かったのに」と言われ続けるのだろう。でも、そこで立ち止まらず、少しでも減らせるよう努力し続けるしかない。