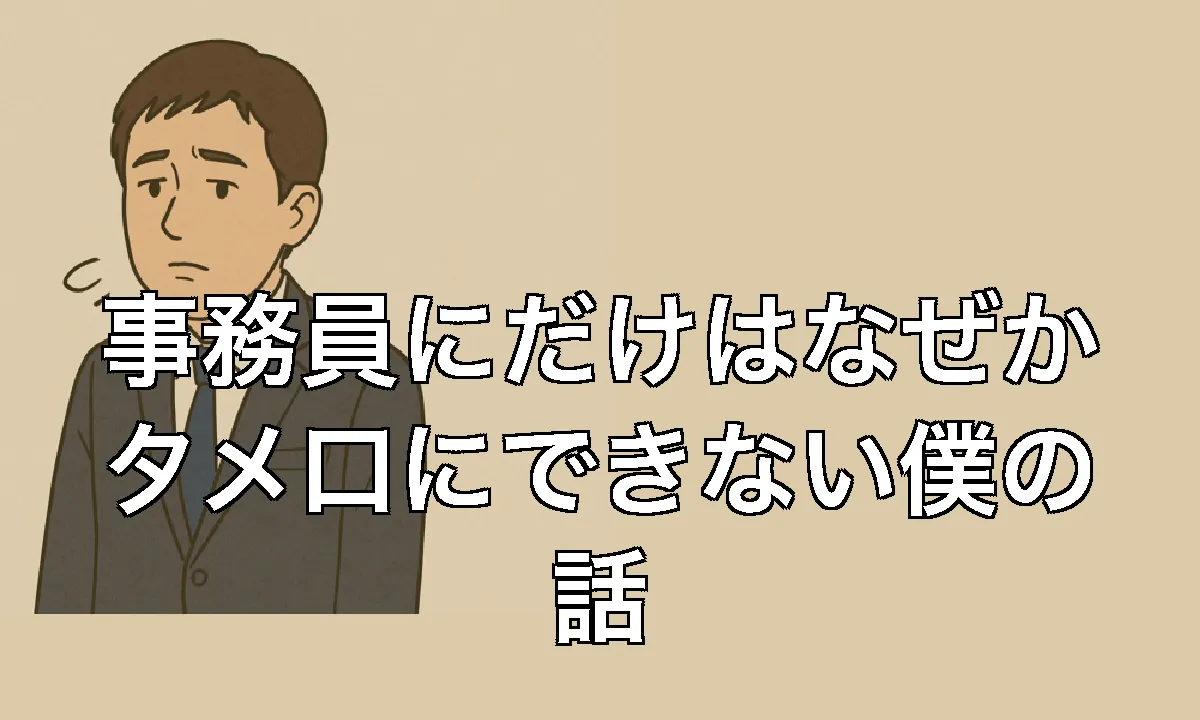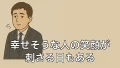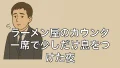気がつけば敬語を崩せない存在になっていた
司法書士として独立して10年以上になるが、いまだにうちの事務員さんにだけは敬語が抜けない。別に上下関係があるわけでもないし、彼女は年下で、しかも入社当初から「もっと気楽にしてくださいよ」と言ってくれていた。でも、どうしてもタメ口に切り替えることができない。自分でも不思議なくらい。事務所の空気がピリついてるわけでもない。むしろ彼女がいるおかげで穏やかにまわっていると感じているくらいなのに、何年経っても「〜してください」「ありがとうございます」ばかりが口から出てしまう。
同じ空間にいても距離感はずっと変わらない
一緒に弁当を食べたり、忙しい時には笑い合ったりするのに、距離感だけは変わらない。それが良いのか悪いのか、自分でもわからない。ただ、同じ時間を過ごしているのに、どこか「お客様」のような扱いをしてしまっている気がする。彼女の方は気を遣ってくれているのか、「先生」って呼び方を続けてくれている。でも、その言葉の中にどこか諦めのようなニュアンスも感じてしまうのは、自分の被害妄想だろうか。
最初の印象を引きずる不器用な性格
敬語が抜けないのは、最初に自分が作ってしまった空気のせいだと思う。開業して最初の頃、とにかく余裕がなくて、仕事でも人間関係でも「ミスできない」という思いに囚われていた。特に女性との距離感がうまく取れない自分にとって、敬語は心のバリアのようなものだった。だから、事務員さんと接するときも、つい固い態度を取ってしまった。そして、そのまま年月だけが過ぎてしまった。
「最初からフランクに話せばよかった」と思う日
ある日、他の事務所の同業の先生が、事務員さんと笑いながら冗談を言い合っている姿を見て、妙に羨ましく感じたことがある。別に仲良しごっこがしたいわけじゃないけれど、自分にはない温度がそこにあった。後悔するなら今からでも変えればいい。でも、それができないのが自分という人間だ。
肩書よりも空気を読むのが先になる職場
先生と呼ばれても、偉そうにするのが苦手だ。むしろ「自分なんかが…」という気持ちが抜けない。でも、そのくせ相手の目を気にして、壁を作ってしまう。事務所という狭い空間では、ちょっとした言い回しひとつで空気が変わる。だからこそ、無難な敬語に逃げる。でもそれは、彼女の優しさに甘えているだけかもしれない。
敬語の裏にある自分の不安と劣等感
敬語を使っているとき、自分が少しだけ「良い人」になれている気がする。丁寧に接することで、相手に不快感を与えずにすむ。つまり、波風を立てたくないだけなのだ。これは優しさではなく、ただの逃げだと最近思うようになった。
年下でも「さん」付けしてしまう自意識
学生時代は上下関係が厳しい野球部にいた影響か、年下相手でもつい「さん」付けしてしまう癖がある。それが悪いわけではないと思うけれど、事務所の中でそれをやっていると、かえって相手との壁になってしまうこともある。名前を呼ぶたびに、ちょっとした距離を感じる。そして、気づけばその呼び方が変えられなくなっている。
プライドよりも「嫌われたくない」が勝つ
結局、自分の行動基準は「嫌われたくない」なんだと思う。事務所は小さな社会であり、ひとりの事務員さんとの関係が崩れれば、全部が崩れる可能性だってある。だからこそ、波風を立てるくらいなら敬語のままでいた方がマシだと思ってしまう。そうして自分の気持ちをごまかしながら、今日も「ありがとうございます」を繰り返している。
モテない人生と無関係ではない気がする
女性との距離の取り方がうまくないのは、ずっと昔からだ。恋愛経験も乏しく、気づけば独身のまま中年になった。そんな自分が、女性の部下に対してどう接していいかわからないというのは、ある意味当然かもしれない。だから、敬語という鎧を着て、余計な感情が出ないように自分を守っているのだ。
仲間意識よりも上下関係を選んでしまう癖
事務所を運営する立場として、仲間というより「職場の役割」として人を見てしまうことがある。そうすることで線引きができるし、業務もスムーズに進むと思っていた。でも本当は、自分が人との深い関係を怖がっているだけなのかもしれない。
タメ口を試みた日の空気の重さ
ある日、「それ取って」と言ってみたことがある。完全なタメ口だった。でも、言った瞬間に、空気が止まった気がした。たぶん気のせいなのだろうけど、自分の中ではものすごく居心地が悪かった。事務員さんはいつも通り笑って返してくれたけど、自分のほうが「やっちまったな」と心の中で冷や汗をかいていた。
「あ、いまのちょっと気まずかった?」の沈黙
その時の沈黙が、今でも忘れられない。ほんの数秒のことだったけど、自分の中では「やっぱり敬語でいた方がいい」という結論に至るのに十分な時間だった。相手が気にしていないのはわかってる。それでも、長年作ってきた関係性を一言で壊すのが怖かった。
優しさを装った壁があることに気づく瞬間
自分が敬語を使っているのは、礼儀正しさではなく、距離を取りたいからだ。そこには優しさよりも臆病さがある。相手が親しげに話してくれても、その壁は取り払えない。優しさの仮面をかぶって、自分の弱さを隠しているだけだった。
相手は気にしていないのに自分だけが意識する
人間関係って、実は片思いの連続なのかもしれない。こちらがどれだけ気を遣っても、相手は気にも留めていない。事務員さんは、もっと気楽に接してくれていいと思っているかもしれない。でも自分だけが、その気楽さを拒んでしまっている。
僕の敬語は相手のためじゃなく自分の保身
仕事を円滑にするために、礼儀や形式は大事だと思う。でも、それが「相手のため」ではなく「自分のため」になっていないか?と自問することがある。敬語という盾を使って、相手に踏み込まれないようにしている。そんな自分が少し情けない。
会話を失敗したくないという小心さ
敬語で話していれば、たいていの会話は波風立たない。突っ込みすぎないし、浅く広く受け流せる。だけど、それって本当に「会話」だろうか。自分の言葉で話すことを恐れて、マニュアルみたいな関係しか築けていない気がする。
「やめてもいいよ」が言えない関係性
もし敬語をやめて、距離を詰めた結果、うまくいかなくなったらどうする?そんな不安が常に頭にある。だからこそ、自分から変化を仕掛ける勇気が出ない。現状維持は安全だけど、孤独だ。
敬語をやめたら仕事も崩れそうな怖さ
関係性が変わることで、仕事にまで影響するのではないかという恐れがある。そんなこと、ないってわかってる。でも、自分にとって事務員さんは唯一無二の存在で、彼女がいてくれることでこの事務所が成り立っている。そのバランスを壊す勇気がない。
ふとした瞬間に見える事務員さんの本音
ある日ふと、「先生って、ずっと敬語なんですね」と笑われた。その言葉に悪意はなく、むしろ柔らかい冗談のようだった。でも、自分にとっては核心を突かれたようで、返す言葉に困った。その時初めて、「自分が距離を作っているんだ」と実感した。
「ずっと敬語なの変ですよね」と笑う声
彼女は笑っていたけど、そこには少しの寂しさもあったように思う。距離を作るのは、相手の信頼を拒むことでもある。気づかないうちに、自分の不安が、相手に冷たさとして伝わっていたのかもしれない。
それでも心地よい距離があることに救われる
敬語のままでも、きっと関係は悪くない。むしろ、うまくいっている。それでも、自分の弱さに少し向き合いたくなった。たまには雑談で「〜だよね」と言ってみてもいいかもしれない。敬語かタメ口かじゃなくて、相手をちゃんと見て話すことが大事なんだと、最近やっと思えてきた。