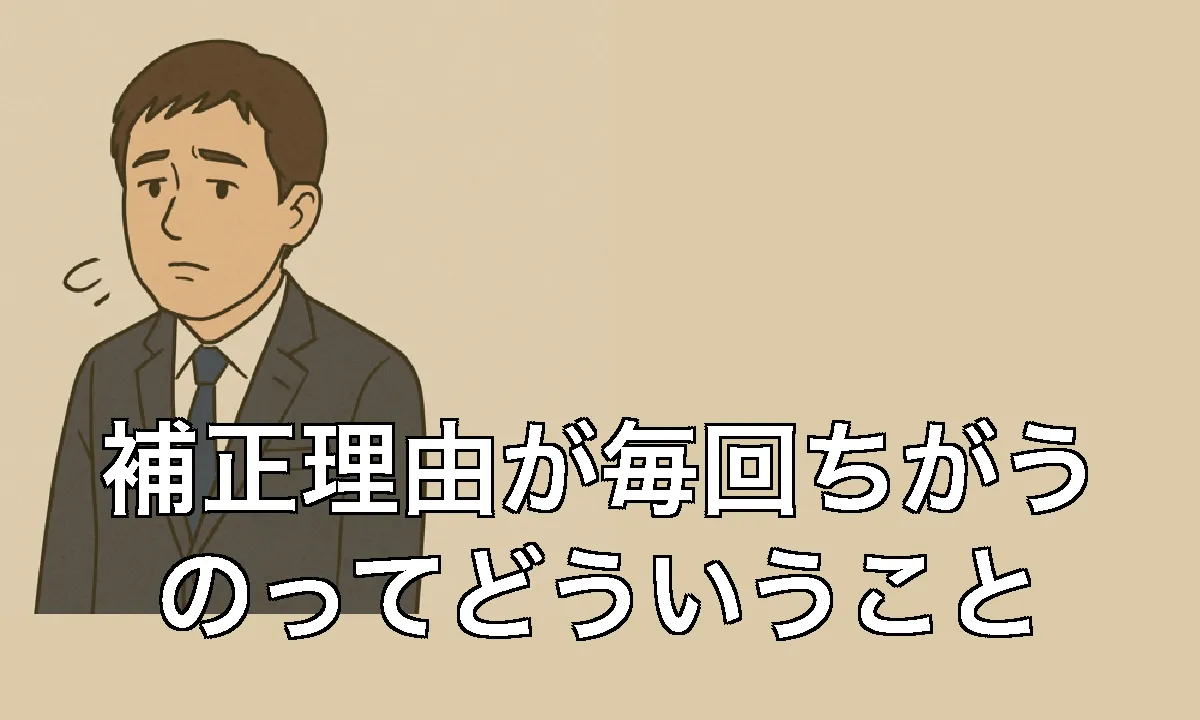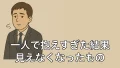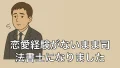毎度違う補正理由に心が折れる
司法書士の業務で避けて通れないのが「補正」です。書類を提出して、待っていたら電話が鳴る。「すみません、補正です」と言われるたび、少しずつ心がすり減っていきます。しかも問題なのは、補正の“理由”が毎回違うこと。前回はOKだった表現が今回はNGになったり、担当者によって対応が変わったりと、まるで運任せのような状況。ルールに沿ってやっているつもりなのに、なぜこうも違うのか。そんな疑問と苛立ちを抱えながら、また書類と向き合う日々です。
前回OKだったのに今回はダメ?
「えっ、これ前に通ったのに?」という経験、司法書士なら一度や二度ではないはずです。まるでファミレスで、前に頼んだセットメニューが今日は注文不可になっているような感覚。「担当者が違うので…」と説明されることもありますが、それってどうなの?と思ってしまいます。登記は法的な手続きであり、ルールに基づいて処理されるべきもののはず。なのに審査のたびに基準が変わると、こちらとしては何を信じて書類を作ればいいのか、混乱するばかりです。
基準があいまいすぎる登記審査の現場
担当者ごとに見方が違うのは人間だから仕方ない部分もあるでしょう。でも、「同じ法務局内でこれだけ判断がバラつくってどういうことなんだ」と思うのが正直なところです。しかも訂正箇所が些細な言い回しだったり、字体だったりすることも。「ここ、ゴシック体でなく明朝体にしてください」と言われたときには、もはや呆れて笑うしかありませんでした。あいまいな基準で振り回されるこちらの身にもなってほしいと切に思います。
「この前は通ったんですけど」の虚しさ
補正の電話が来たとき、「この前は通ったんですけど」と言ってみることもあります。でも、ほとんどの場合は「今回は違う担当者なので」と軽く流されて終わり。まるでコンビニでレジの人が違うから値段が変わる、みたいな理不尽さを感じます。言っても無駄、と分かっていてもつい口にしてしまうあたり、自分の中に積もったモヤモヤをどうにか出したいんでしょうね。そんな自分にまた疲れるという悪循環。誰か共感してくれたら、ちょっとは報われるのに。
電話対応のたらい回しと無言の圧
補正内容が曖昧で、念のため電話で確認しようとすると、たらい回しになることも珍しくありません。「その件は〇〇担当なので…」と言われ、次にかけても「少々お待ちください」で長時間保留。ようやくつながっても、「まぁ、そういう解釈もありますが…」と煮え切らない返事。しかも、どこかこちらが悪い前提で話されるのが地味に堪えます。言葉にされない圧力というか、「なんでわかってないの?」という空気。いや、わかってたら聞かないってば。
法務局との距離が近すぎて疲れる
田舎だと、法務局と司法書士の距離が物理的にも人間関係的にも近いです。良い面もありますが、そのぶん言いにくいことも言われやすくなります。「あの件、ちょっと厳しめで返しておきました」と冗談めかして言われたこともあり、内心はカチンときました。顔を合わせる機会が多いぶん、余計に気を遣うのが地方のつらさ。制度やルールよりも“空気”が補正理由になっている気がして、納得できないまま頭を下げるのも、もう慣れましたけどね。
事務員には任せられない微妙なやりとり
こういう補正対応って、結局のところ事務員には任せにくいんですよ。判断がぶれるからこそ、ニュアンスを読みながら調整する必要がある。でも、こっちも他の案件に追われていて、全部に丁寧に対応してる余裕なんてない。気づけば、「この補正対応だけで今日の午前中が潰れた」なんてこともあります。仕事は山積み、でも誰にも任せられない。そんなループの中で、ふと「何やってるんだろう」と虚しくなることもあります。
補正が重なると業務が止まる
一件一件の補正は小さなズレかもしれません。でも、それが重なってくると、業務の流れ全体が止まってしまいます。補正対応は基本的に“最優先”ですし、そこに神経を持っていかれると、他の業務が手につかなくなるのです。気持ちの切り替えもうまくいかず、結局、効率もモチベーションもガタ落ち。気をつけているつもりでも、どこかでまた補正になる。この負のループが本当に厄介です。
急ぎ案件ほど補正が刺さる皮肉
なぜか、急ぎの案件に限って補正が入るんですよね。急いでるときほど、ほんの小さなミスを見逃しやすい。そしてその“見逃し”を、いつもより厳しめに指摘される。ある日、相続登記の急ぎ案件で、申請書に添付した住民票の写しが1日古かっただけで補正にされたことがありました。相手の都合で期日が決まっていたのに、こっちは深夜まで対応していたのに、「もうどうしようもない」という気持ちになりました。
時間管理がすべて狂ってしまう瞬間
補正対応って予測できないから怖いんです。スケジュールがぎっしり詰まっているときほど、1件の補正が連鎖的に全体に影響を及ぼします。「あれ、これって今日中に間に合うのか?」と焦る時間が増えるほど、ミスも増える。まるでドミノ倒しのように、予定していた段取りが次々崩れていくのを感じます。そうなると、精神的にも余裕がなくなり、イライラしてしまう。たかが補正、されど補正。小さな揺らぎが、大きなストレスになるのです。
補正中は書類が人質になっている気分
補正中の書類って、なんか人質みたいなんですよね。こっちが修正しない限り、解放されない。しかも、審査が再開されるまでのタイムラグも含めて、もどかしいことこの上ない。いつ戻ってくるのか、内容に問題ないのか、不安が募るばかりです。しかもクライアントには「遅れてます」としか言えず、こちらの不手際と捉えられてしまうこともある。本当は違うのに、説明のために謝るしかない。その積み重ねが、地味に心を削っていきます。
「補正=こちらの落ち度」と思われる重圧
補正が入ると、たいてい「こっちが悪かったのかな」と思ってしまいます。でも、実際は法務局の解釈の違いや、担当者の判断だったりもします。それでもクライアントに説明する立場上、「」と頭を下げるしかない。なんだか、どこにも正義がないように感じてしまう。誰かが悪いわけじゃないのに、誰かが悪者にされる。それが“補正”という仕組みの、どうしようもないところです。
クライアントへの説明が地味にしんどい
補正が入ると、まず「なんで?」と聞かれます。それに対して「今回は法務局の指摘で…」と説明しても、「それって間違いだったってことですか?」と詰められることもあります。きちんと説明すれば納得してくれる方もいます。でも中には、「プロなんだから完璧にやってくれ」と言われることもある。そのたびに、「完璧なんてあるのか?」と自問するんです。心がどこかで折れかかってるのを、自分でも感じます。
謝るしかないけど納得してない自分
「」と言いつつも、内心では「納得できない」と思っている自分がいます。それが積もってくると、表情にも出てしまうんですよね。事務員に「先生、今日ちょっと顔こわいですよ」と言われたこともあります。そりゃ、そうなるよ…と思いながらも、笑ってごまかすしかない。補正の理由が統一されていれば、こんな気持ちにならずに済むのに。そう思うのは、きっと僕だけじゃないはずです。