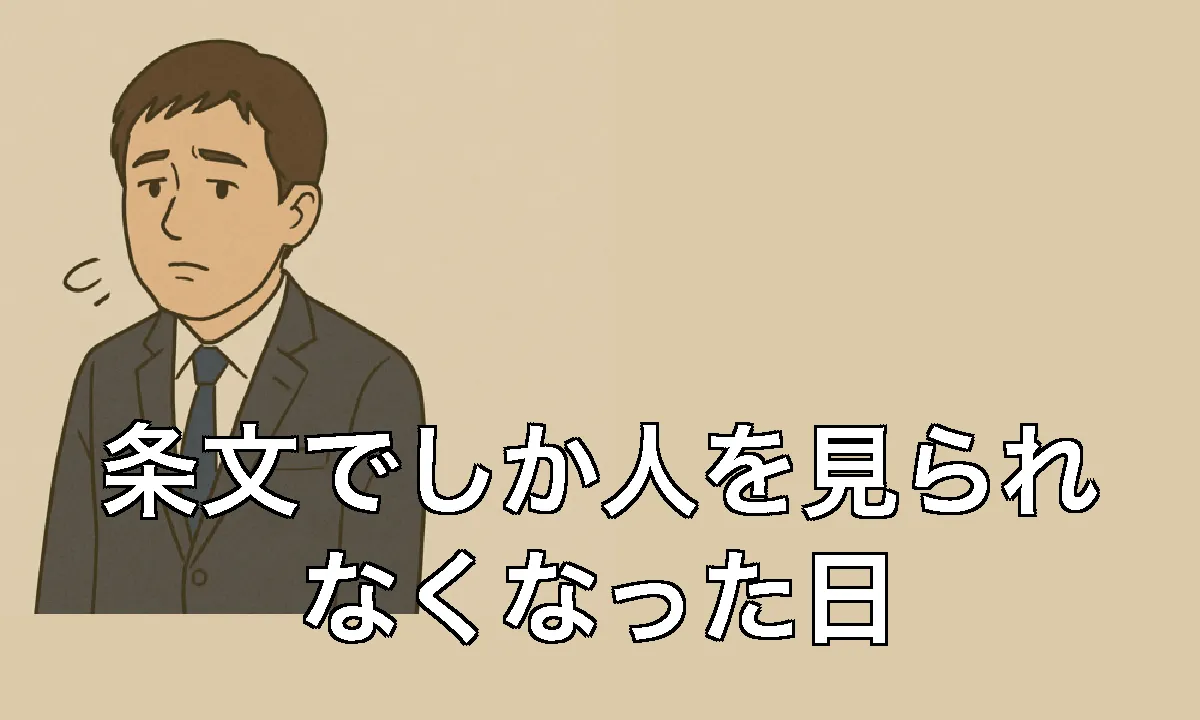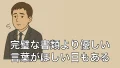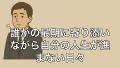気づけば人の言葉をまず疑うようになっていた
毎日契約書ばかり読んでいると、どうも心のフィルターがおかしくなる。たとえば誰かに「また今度ご飯行きましょうよ」と言われても、「それ、ちゃんと履行される約束ですか?」と心の中でつぶやいてしまう。実際にはただの社交辞令かもしれないし、相手の都合もある。でも、一度「文言の裏」を読む癖がつくと、気軽な言葉が全部、怪しく聞こえるようになるのだ。自分が過敏すぎるのかもしれないけど、司法書士という仕事柄、人の善意や信頼に“疑う余白”を見出してしまうようになってしまった。
「善意」の一言が信じられない
相続登記で揉めている家族のやり取りを、数えきれないほど見てきた。「兄貴がそう言ったんだから信じてたのに」「口約束だったけど、絶対に分けてくれるって言ってた」——そんな言葉が、後になって血の通わない争いに変わっていく。善意が裏切られる瞬間を見続けていると、誰かが「大丈夫ですよ」「任せてください」と言っても、どこかで「本当に?」と思ってしまう。信じたいのに、職業的な警戒心がそれを邪魔する。まるで、手を差し伸べられても、差し出された手の裏側を確認してしまうような感覚だ。
契約書ばかり読んでると疑い深くなる
契約書には「もし〜だった場合」の世界がぎっしり詰まっている。それを読むたびに、「最悪の事態」を想定する訓練をしているようなものだ。しかも、それを相手がどう裏をかくかまで含めて読む。そんな毎日を繰り返していると、日常生活でも「この人、あとで何か言ってくるかもな」と思うようになる。人間不信というほどではないけれど、楽観的に人を信じる力は、ずいぶん削がれた気がする。実家の母に「最近元気なの?」と聞かれても、「何かの前振りか?」とすら思ってしまうのだから、もはや末期かもしれない。
書面に残ってないと不安になる職業病
飲み会の幹事に「会費は3000円でいいよ、足りなかったら後でいいから」と言われたとき、「それって口約束で大丈夫なのか」と頭の中で勝手に心配していた。しかも、領収書が出ないとちょっともやもやする。これはもはや一般的な感覚ではないのかもしれない。言った言わない、払った払ってない、そんな小さなことでさえ「証拠」が欲しくなる。これは完全に職業病で、誰が悪いわけでもない。けれど、それによって気楽な人間関係が築きにくくなっているのは確かだ。
心のどこかで“裏”を探す癖がついた
言葉そのものを額面通りに受け取れない。表情や口調、タイミングを読みすぎてしまう。人と話していても、どこかで「本音は別にあるのでは?」と邪推してしまう自分がいる。それが常に正しいわけではないこともわかっている。でも、油断して信じたせいで揉める場面をたくさん見てきたからこそ、自然と「裏を読まなきゃ」というスイッチが入ってしまう。結果として、人を心から信じることができず、どこか孤独な立ち位置に自分を追い込んでしまうことになる。
善人もリスク要因に見えてしまう
どれだけ善良そうな人でも、「万が一」を想定してしまう癖がある。昔、知人に「保証人になって」と頼まれたことがあった。断るのは申し訳ない気もしたけれど、頭の中では自動的に「連帯保証」「求償権」「債務不履行」という言葉が回り出して、結局断ってしまった。相手は理解を示してくれたが、やはり少し距離ができてしまった。信頼されることよりも、自分が傷つかないことを優先してしまう——そんな自分に、時々嫌気がさす。
書類の世界では「好意」は無力
契約書に「信頼しています」と書いても、それはなんの効力も持たない。法的には「履行義務があるかどうか」がすべてであり、気持ちや思いやりは見向きもされない。そうした世界で生きていると、どうしても「好意」や「善意」に対する信頼感が薄れていく。現実の人間関係では気持ちが大切なのだが、それを心から受け入れることが難しくなる。自分でも、この感覚は少し寂しいと思う。
信頼と保証の境界線が消えていく
信頼していたつもりの人に裏切られたとき、そのショックを和らげるために「書いておけばよかった」と思うようになる。つまり、信頼と保証の境界線を混同し始めるのだ。これは非常に危うい感覚で、本来は別物であるはずの「人との信頼」と「契約上の保証」を同じ天秤に乗せてしまう。こうなると、人間関係そのものに緊張感が生まれ、「何を信じればいいのか」がわからなくなる。まさに、条文に心が支配された瞬間だ。
プライベートでも契約目線が抜けない
休日、友人と喫茶店で話していたとき、ふと「ここのコーヒーは税込なのか、税別なのか」とレシートを確認している自分に気づいた。些細なことではあるけれど、こういう癖が、日常生活に染みついてしまっている。恋愛でも「この人、本当に長く付き合うつもりがあるのかな」とか、「別れるときの条件はどうなるのか」など、つい先のことを想像してしまい、素直に楽しめない。人生にまで契約の目線を持ち込んでしまっている。
飲み会の会話にも「証拠」を求めてしまう
「今度一緒に旅行行こうよ!」という言葉に、「それって具体的にいつ頃?旅費は?行き先は決まってる?」と、つい条件を確認したくなってしまう。盛り上がった雰囲気に水を差すわけにもいかないので口には出さないが、心の中ではチェックリストが動き出している。まるで、その場で「契約の成立」を意識しているような感覚で、楽しいはずの時間が少しだけ緊張を伴う。これはもう、癖というより職業の副作用かもしれない。
「本音と建前」を言質で処理する思考
誰かが「大丈夫ですよ」と言ったとき、それが本音なのか建前なのかを分析する癖がついている。司法書士として、依頼人の言葉を正確に記録するためには必要なスキルなのかもしれないが、プライベートでそれをやってしまうと、ただの面倒な人になってしまう。「今の言葉、あとで撤回しないよな?」と、内心では言質をとる感覚で人と接しているのは、なかなかにしんどい。
友人に対しても損得で測ってしまう瞬間
悲しい話だが、たまに「この人と付き合ってて、何か得があるのかな」と思ってしまう瞬間がある。本心ではそんなことを考えたくないし、人間関係に損得なんて持ち込みたくない。でも、職業柄、常に「費用対効果」や「リスクとリターン」を考えてしまう。心の底から人と付き合うのが難しくなっているのを感じる。それでも、そんな自分を止められないのが、一番やるせない。
それでも人を信じたい気持ちはある
ここまで書いておいてなんだが、人を信じたいという気持ちが、まったくなくなったわけじゃない。ただ、どう信じればいいのかが、わからなくなっているだけだ。条文や契約書の世界に慣れすぎた結果、「信頼=保証」という考え方に染まってしまっている。それでも、仕事を離れた日常のなかで、ふと誰かの何気ない言葉に救われることがある。その瞬間だけは、条文を忘れて、ただの一人の人間に戻れたような気がするのだ。
疑い疲れたあとに残るもの
疑って疑って、それでも裏切られることはある。でも、疑ってばかりだと、何も始まらない。そういうジレンマを何度も繰り返しながら、少しずつ“人間関係の落とし所”を探している。きっと完全に信じることも、完全に防ぐこともできない。でも、それでも付き合っていくしかない。疑い疲れたあとに残るのは、やっぱり「信じたい」という気持ちなのかもしれない。
信頼は書面じゃなく時間が育てる
結局のところ、本当の信頼って「文面」じゃなくて「年月」だと思う。何度も会って、何度も助け合って、喧嘩もして、それでもまた会って——そうやってできるものなのだろう。司法書士という職業をしている限り、どうしても形式や証拠に頼らざるを得ない。でも、それだけじゃ足りないことも、だんだんわかってきた。信頼は契約書には書けないし、判子じゃ証明できない。そこが、人間の面倒くさくも愛おしいところなのかもしれない。
ひとりの司法書士としての再確認
今日も、依頼人の「先生、助かりました」の言葉に、思わずうなずいてしまった。契約書でも覚書でもない、ただの言葉。それでも、心に響いた。そんなとき、少しだけ思うのだ。「まだ、自分は人を信じたいんだな」と。条文に心を縛られながら、それでもどこかで、信じたい。信じられる。そう思える瞬間がある限り、この仕事を続けられるのかもしれない。