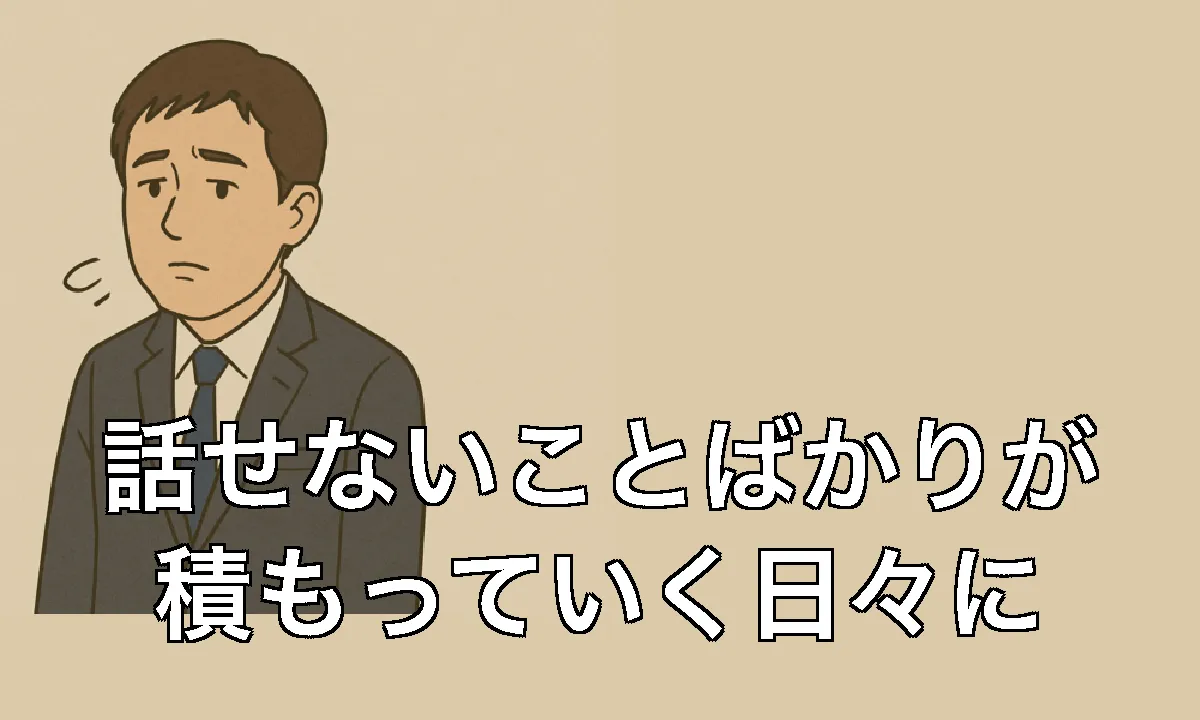相談できないことが増えていく理由
日々の仕事をこなすうちに、ふと気づくと「誰にも話せないこと」がどんどん積もっていく感覚に陥ることがある。特に司法書士という仕事は、日常的に人の問題や秘密に関わるぶん、自分の内面をさらすことがどこか後ろめたくなってしまう。たとえば、登記のトラブル対応で精神的にすり減った日でも、「プロだから当然」と自分に言い聞かせてやり過ごす。結果、気づけば心の中にしまったままの愚痴や不安が引き出しのように溜まり続け、開けることすら億劫になってしまうのだ。
誰かに話すことのハードルが高すぎる
年齢を重ねるにつれて、「こんな話をしても迷惑だろうな」とか「弱音を吐いたら格好悪いな」といった意識が先に立つ。昔は居酒屋で先輩に愚痴をこぼしたり、野球部の仲間とバカ話で笑っていたのに、今は誰に話していいかすらわからない。特に独立してからは、同業者にはライバル意識もあって本音が出せず、家族もいないから相談相手がいない。いざというときに「話す力」を失ってしまっていることに気づく瞬間が、一番つらい。
優しさが仇になるとき
事務員が一人だけの事務所では、気遣いが先に立ってしまう。こっちが疲れていても「大丈夫?」と聞かれて「うん、大丈夫」と反射的に答えてしまう。相手に心配かけたくないという優しさが、逆に自分の弱さを閉じ込める鎖になっている。先日もクレーム対応で胃が痛くなるほど疲弊していたが、事務所では笑顔を保っていた。夜になってコンビニでひとり弁当を食べながら、「誰かに聞いてほしかっただけなんだけどな」とふとこぼれる。それを口に出すこともできないまま、次の日が来る。
こんなこと言っても仕方ないの壁
「こんなこと、誰に話しても仕方ない」。そう思ってしまうと、本当に誰にも話せなくなる。そして言葉にならない重みだけが心に残る。たとえば、依頼者の対応で心をすり減らしても、「それが仕事だから」と切り替える。しかし感情の置き場所がない。元野球部だった自分は、感情はグラウンドで発散していたが、今の仕事ではそうもいかない。何もかも飲み込むクセだけが身についてしまい、言えなかった言葉が日に日に胸に沈んでいく。
司法書士という仕事の性質が孤独を助長する
司法書士という職業は、外から見ると「堅実で信頼される仕事」と映るかもしれない。だが実際には、細かい確認と判断の連続で、孤独との付き合いが日常だ。人と接することはあっても、それは“相談される側”であり、自分が相談する機会はほとんどない。悩みを打ち明ける場がなく、気づけばひとりごとが増えていることに気づく。事務所の空気に自分の考えや葛藤が充満していくが、それをどこにも出せないまま、静かに仕事が続いていく。
どこかでいつも一人で抱えている
トラブルが起きたとき、最後に判断するのは結局自分だ。「こうしておけばよかったかもしれない」「もっと早く気づけたのに」――そんな後悔を誰にも共有できず、自分で抱え込む。最近も登記の手続きで申請ミスがあり、修正に奔走したが、依頼者には事務員にも本当のところは話していない。怒られるわけじゃないけど、信用されなくなる気がしてしまう。こうしてまた一つ、話せない出来事が自分の中に残る。
悩みの種類が少し特殊すぎる問題
司法書士の仕事には、法務的な判断や手続きの専門性が求められる。だからこそ、同じ業界以外の人には悩みを説明するのが難しい。たとえば、依頼者との信頼関係や、不動産登記の微妙な解釈の違いなど、専門的すぎて「それってそんなに大変なの?」と思われるのがオチだ。そうなると、話すこと自体をやめてしまう。共感してもらえないなら話す意味がない、そう思ってしまう。専門職ゆえの孤独だと、痛感する瞬間がある。
愚痴すら相手を選ぶ
愚痴って、言える相手がいないと余計につらい。昔の友人と飲んでも、「司法書士って稼げるんでしょ?」と軽く言われてしまう。そんなとき、日々のしんどさや事務所経営のプレッシャーなんて、口にできなくなる。事務員にも言えない、友人にも言えない。愚痴すら閉じ込めて、気づけばため息が増えていく。誰かに言えたら少しは楽になるのに、そういう存在が見つからない自分に、時々嫌気が差す。
事務所という閉ざされた空間の中で
一人事務所に近い環境では、会話が極端に少ない日もある。朝から晩までパソコンと書類とにらめっこ。電話は依頼者対応ばかりで、気楽な雑談なんて生まれない。孤独と静寂がセットになって、気づけば小声でひとり言をつぶやいている自分がいる。笑えてしまうけど、これが現実だ。そんな空気の中では、自分の悩みすら声に出さなくなってくる。心の中の声がだんだん聞こえなくなっていく感覚が怖い。
事務員に話せることと話せないこと
事務員はいても、話せる内容には限界がある。業務上の連携は問題ないが、経営の悩みや精神的な疲労感はなかなか共有できない。「自分が頑張らないと」と思ってしまうせいで、必要以上に背負ってしまう。たとえば、「今月の売上ちょっと厳しいな」と思っても、事務員の生活を考えると不安を煽るようなことは言えない。自分の中でだけ処理して、笑顔を作って応対する。そういう日々が続くと、どこか壊れそうになる。
話さないまま積み上がるストレス
誰にも言えないストレスは、静かに、けれど確実に積もっていく。まるで湿気のように、気づけば心の中が重たくなっている。最近では、ふとしたことでイライラしたり、眠れない夜が増えてきた。けれど、それも誰にも言えず、「きっと疲れてるだけだろう」と片づけてしまう。ストレスの根本に向き合わずに日々を回していくうちに、感情が鈍くなっていくような気がして、時々ゾッとする。
笑ってごまかす技術だけが上がる
年を取るにつれて、笑ってごまかす技術ばかり上手くなった気がする。本当はつらいのに、「まぁ、なんとかやってますよ」と言ってしまう。それが癖になって、自分の本音を自分ですら見失いそうになることがある。いつからか、「本音を言うこと」自体が怖くなっていた。このままでいいのか、どこかでリセットできるのか――そんなことを、コンビニの帰り道にぼんやり考える。誰にも言えないまま、また一日が終わる。
それでも聞いてくれる人がいたら
それでも、もし聞いてくれる誰かがいたらどうだろう。たとえ具体的な解決にはならなくても、「わかるよ」と言ってくれるだけで、心がふっと軽くなることがある。誰かの一言で、自分の中の見えなかった部分に気づかされることもある。そう思うと、話すという行為は、自分を取り戻すための小さな一歩なのかもしれない。閉じ込めた言葉を、少しだけ外に出せるようになりたいと思う。
話せた瞬間に少しだけ楽になることもある
以前、仕事帰りにたまたま会った同業者に、思い切って少しだけ愚痴をこぼしたことがある。「俺も似たようなことあったよ」と返されたとき、驚くほど安心した。誰にも言えなかったことを口にしただけで、気持ちが軽くなったのだ。そのあと帰り道にふと涙が出そうになって、慌てて深呼吸した。あのときの感覚を、もっと大事にすべきだったのかもしれない。今でも、時々あの会話を思い出す。
誰にも言えないを前提にした付き合い方
「誰にも言えない」と決めつけてしまうと、本当に誰にも言えなくなる。けれど、少し目線を変えて、「言わなくても察してくれる人」や「何も言わずにいてくれる人」が身近にいることに気づくこともある。無理に話さなくても、そばにいてくれるだけで救われるような存在。そんな人との付き合い方を大切にできたら、少しだけ自分を許せる気がする。言葉だけが、すべてじゃないのかもしれない。
愚痴を聞いてくれる存在のありがたさ
結局のところ、人はひとりでは生きていけない。愚痴を聞いてくれる存在がいることのありがたさを、歳を取るごとに実感するようになった。最近では、月に一度だけ昔の野球部仲間と話す時間を作っている。他愛もない話の中に、自分を戻せる瞬間がある。聞いてもらうことは、恥ではない。むしろ、それを受け取ってくれる人がいることこそが、大人になった証なのかもしれない。