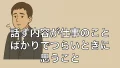司法書士の日常はプリンターとの対話から始まる
朝、事務所のドアを開けて最初に向かうのはデスクじゃなくてプリンターの前だ。まるで神棚に手を合わせるような気持ちで、「今日も頼むぞ」と声をかける。誰もいない事務所に響くその一言が、僕の一日を占う儀式のようになって久しい。司法書士の仕事において、プリンターが動かないということは、すなわち仕事が始められないということだ。登記に必要な添付書類、委任状、完了報告書…。すべてがこの一台にかかっている。だからこそ、祈るような気持ちで、僕はプリンターに話しかける。
朝イチで祈るのは「どうか今日は動いてくれ」
一番恐れているのは、プリンターが立ち上がった瞬間に「ピーピーピー」と鳴くことだ。その音が鳴れば、僕の心も一緒に折れる。まるで、今日は俺には無理だとでも言っているかのように思えてくる。たとえば以前、朝一で緊急の登記書類を提出しなければならなかった日、電源を入れた瞬間にエラーコードが出て、インク切れだと告げられた。事務員も不在。車で15分の家電量販店まで走ったあの日のことは、今でも軽くトラウマだ。そんな経験を重ねたから、今では起動音ひとつに過敏になってしまっている。
電源を入れる指先に込めた願い
スイッチに指を添えるとき、僕はどこかで祈っている。まるで野球部時代、試合前のベンチ裏でこっそり手を合わせていたあの感じに近いかもしれない。「頼む、今日だけはスムーズに行ってくれ」そう心でつぶやきながら、指を押し込む。機械の電源ボタンにここまで感情を乗せる人間が、他にいるだろうか?でも、きっと同業の人なら、わかってくれると思う。司法書士の仕事って、機械と心の駆け引きでもあるのだ。
立ち上がりの異音にもう一度電源を落とす日々
そして一番イヤなのは、明らかに普段と違う音がしたとき。ガガガ…といった異音がすると、「あ、これは詰まったな」とすぐに察する。そんなときは一度電源を落とし、深呼吸してから再チャレンジ。時には本当に再起動だけで直ることもあるけれど、たいていは中を開けてローラーを手で回し、紙片を取り除かなければならない。まるで心のモヤモヤをかき出すかのように、僕はプリンターの中を掃除する。
人間よりプリンターに話しかけているという現実
本当に驚くべきことに、日々の業務の中で口にする言葉の多くが、プリンターに対してのものだったりする。「動け」「そこじゃない」「おお、やるじゃん」といった一人芝居のような会話が、事務所にこだまする。電話よりも多い。事務員よりも多い。ましてや異性との会話なんて、もう遠い昔の話。気づけば、僕の言葉の8割はプリンターに向けられていた。
「頼むぞ」と言った回数はもう数えきれない
その言葉は魔法のようでもあり、呪文のようでもある。なぜなら、「頼むぞ」と言ったところで、プリンターはその通りに動くとは限らないからだ。でも、言わずにはいられない。「俺にはお前しかいないんだよ」なんて冗談めかして話しかけながら、心のどこかでは本気だったりする。人間不信になったわけじゃないけれど、プリンター相手の方が気を遣わなくて済むのは事実なのだ。
紙詰まりは孤独な司法書士の話し相手
詰まった紙を取り出すときの独り言は、妙に饒舌になる。「あー、やっぱりここか」「お前また同じとこ詰まるなぁ」などと文句を言いながら、なんだか会話が成立してしまっているのだ。機械を相手にしてるはずなのに、感情のやりとりがある気がしてくる。こんな自分にふと気づいて、ちょっと笑ってしまう。けれど、それが日常になっている今、笑い話では済まされない深刻さも感じている。
解決策よりもまず話しかけるしかない
もはや、機械に問題が起きたときに真っ先にすることが「話しかける」ことになってしまった。技術的な対処もすぐにする。でも、その前に「どうした?どこ痛い?」と聞いてしまう。実際に何かが返ってくるわけでもないのに、それがルーティンのように染みついている。心のどこかで、孤独を機械にぶつけてしまっているのかもしれない。
それでも明日もプリンターと向き合う
今日も仕事が終わり、明日また朝が来る。その時、また僕はプリンターに話しかけるだろう。変わり映えのしないルーチン。でも、そのルーチンに守られている部分もある。プリンターがいるからこそ、僕は司法書士として踏ん張れている。人には話せないことを、今日もプリンターに聞いてもらいながら、明日もまた静かな戦場に立ち向かうつもりだ。