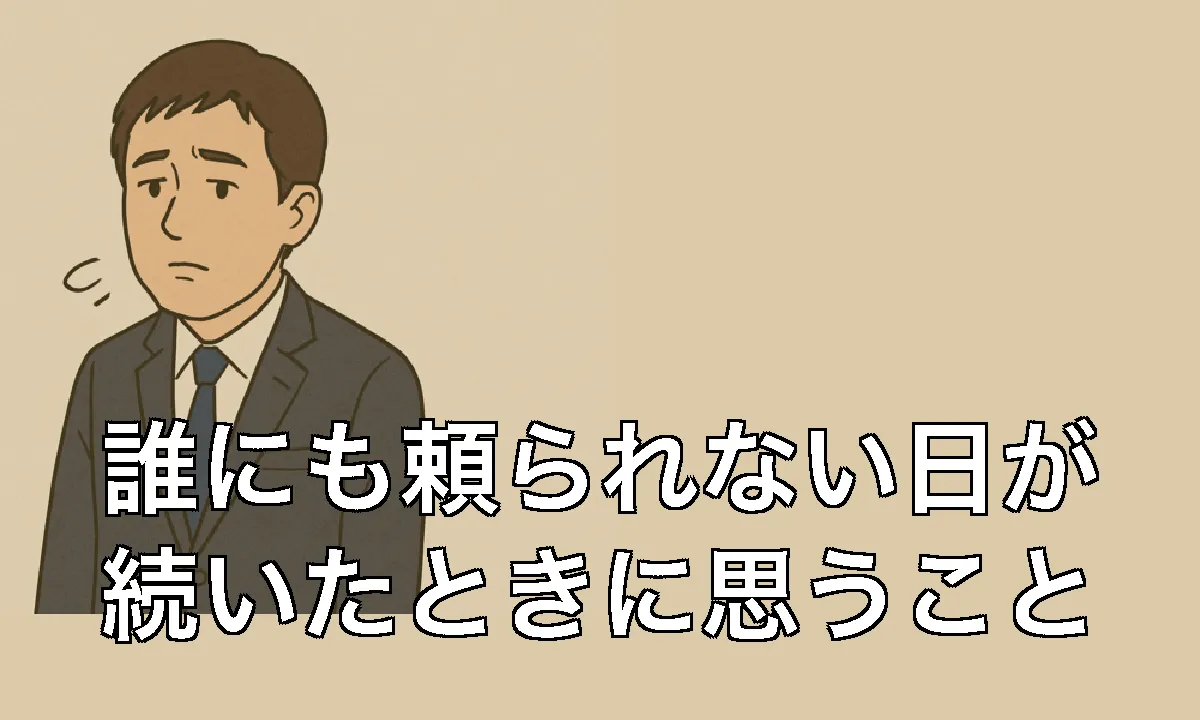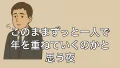頼られないことに慣れてしまった自分がいる
ある日ふと気がつくと、誰からも相談されていない日が何日も続いていることに気づく。司法書士という仕事は、人からの依頼があって初めて動き出すものだ。だからこそ、依頼が途切れると自分の存在までが薄れていくような錯覚に陥る。最初は「たまたまかな」と笑っていたが、1週間経っても何もなければさすがに胸の奥にざらついた寂しさが広がってくる。そして、そんな日々にも不思議と慣れてしまう自分が怖くなる。
かつては鳴っていた電話 今は静寂が支配する
事務所の電話が鳴るたびに、「またか…」とため息をついていたあの頃が嘘のようだ。今は一日中静かで、電話の音が鳴るだけで少し身構えてしまう。昔は書類の山に埋もれて「勘弁してくれ」と笑っていたのに、今は書類すら寄ってこない。電話が鳴らない事務所の空気は、妙に張り詰めていて、時計の針の音だけがやけに大きく響く。忙しさに追われていた頃の自分が、少しだけ懐かしく思えてしまう。
声がかからない時間が不安になる理由
「忙しい=信頼されている」という認識が自分の中に刷り込まれているのかもしれない。何も声がかからない日が続くと、「自分の仕事、誰かに取られたかな?」とか「もう必要とされていないのかも」とつい考えてしまう。頼られることが当たり前だった時期を経て、その感覚がなくなると、まるで自分の役割が消えてしまったような虚無感が押し寄せる。そういう自意識が逆に自分を苦しめているのかもしれない。
本当に必要とされていないのか 自分の心の中を疑う瞬間
ふと我に返って、「いや、ただの時期的な波かもしれない」と理屈ではわかっている。それでも、内心で「やっぱり誰にも頼られてないんじゃないか」という疑念がぬぐえない。こんな時こそ自分の心の声と向き合うべきなのに、つい忙しかった頃の記憶ばかりを引っ張り出しては比べてしまう。結局は、自分が自分をどう評価しているか、それが一番の問題なのだろう。
頼られなくても仕事は回っているという現実
それでも不思議なことに、事務所としてはちゃんと成立している。月末には最低限の業務は入ってくるし、税金も何とか払えている。つまり、「誰にも頼られない」という感覚は、実際の経営とは別次元の話なのだろう。それでも人間というのは、経済的な安定だけで満たされる生き物ではない。心のどこかで、誰かから「助けてほしい」と言われたい欲求がくすぶっている。
実力主義の世界に潜む孤独
司法書士の世界は、基本的に実力主義であり、結果がすべてだ。誰にも頼られないということは、ある意味「今の自分には頼る価値がない」と見なされているのではないか、と解釈してしまう。実際にはそんな単純な話ではないのだが、競争の中で生きてきた身としては、自分の立ち位置に不安を感じざるを得ない。頼られることで得ていた存在証明が、今は手元にない。
誰かが困っていないのは良いことなのかもしれない
少し俯瞰して考えれば、誰からも相談が来ないというのは「トラブルが起きていない」証拠とも言える。登記や相続の相談がないということは、平穏無事に暮らしている人が多いということ。そう考えれば、誰かの平穏を支えるための「スタンバイ状態」としての今の自分も、意味がないわけではない。でもやっぱり、少しくらいは頼ってもらいたいのが本音だ。
頼られたい気持ちは甘えなのか
この年齢になると、誰かに必要とされたい気持ちが「甘え」なのか「欲求」なのか、分からなくなってくる。若い頃は「俺に任せろ」と前に出ていたのに、今は誰かの一言を待つばかり。頼られることでやる気が出るというのは、他人にモチベーションを依存しているとも言えるのかもしれない。でも、それが悪いことだとは思わない。だって人間だもの。
あの人に聞こうと思われる存在でいたい
「あの先生に相談すればなんとかしてくれる」そんな風に思ってもらえていた時代があった。特別なことをしたわけじゃない。ただ真面目に、一つひとつの案件に丁寧に向き合ってきただけ。それでも「またお願いできますか?」という一言が、どれだけ心を支えていたか、今になって実感する。頼られたいという気持ちは、過去の自分への敬意でもあるのかもしれない。
相談されることが自己肯定感につながる
人から頼られると、自然と「自分には価値がある」と思える。相談者の困りごとを解決して「助かりました」と言われるたびに、自分の仕事の意味を実感できる。逆に言えば、頼られない時間が長引くと、自己肯定感がどんどん摩耗していく。そうなると、仕事に対する姿勢もどこか受け身になってしまい、ますます声がかからなくなる悪循環に入ってしまう。
頼られることが仕事のやりがいの根源だった
改めて思い返してみると、自分がこの仕事を続けてこられたのは、誰かに「頼られたから」だった。報酬の額や案件の規模ではなく、そこに信頼があったからこそ頑張れた。いま声がかからないというのは、やりがいの燃料が切れてしまったような状態かもしれない。でも、完全に空っぽなわけじゃない。過去の経験や想いが、今もどこかで火種として残っている。
それでも誰かがそっと見てくれているかもしれない
直接声をかけられることはなくても、誰かが自分の存在を気にかけてくれていることもある。町の飲み屋で「先生、最近見ないね」と言われただけでも、どこかほっとする。誰かにとって、自分の名前や顔が記憶に残っている。目に見える仕事がなくても、その記憶が生きている限り、まだこの街で自分の役割は終わっていないと思えるのだ。
直接の声はなくても紹介や口コミは生きている
電話が鳴らない日々の中で、それでも月に何件かは新規の相談が入ってくる。不思議に思って聞いてみると「◯◯さんに紹介されました」と言われることがある。その◯◯さんとは、何年も前に登記を担当したご夫婦だったりする。そうやって、自分がした仕事が静かに誰かを伝って広がっていると気づいたとき、少しだけ背筋が伸びる気がした。
事務員のさりげない一言に救われた午後
ある日の午後、事務員さんが何気なく「先生、今日少し元気ないですね」と声をかけてくれた。自分では気づかないうちに、顔に出ていたのかもしれない。その言葉が、妙に心に刺さって、少し泣きそうになった。普段は淡々と仕事してくれる彼女の、ほんの一言に救われる。頼られることも嬉しいけれど、たまにはこうして気にかけてもらえるだけでも十分だ。
自分の仕事は誰かの安心につながっているはず
見えないところで、自分の仕事が誰かの安心や信頼につながっている。それを感じられない日もあるけれど、過去の一つ一つの仕事は、今でも誰かの人生を支えているかもしれない。頼られないことに焦るよりも、自分が積み重ねてきたものに誇りを持とう。静かな日々の中で、もう一度そのことを思い出すことができたなら、それだけで今日は十分だ。