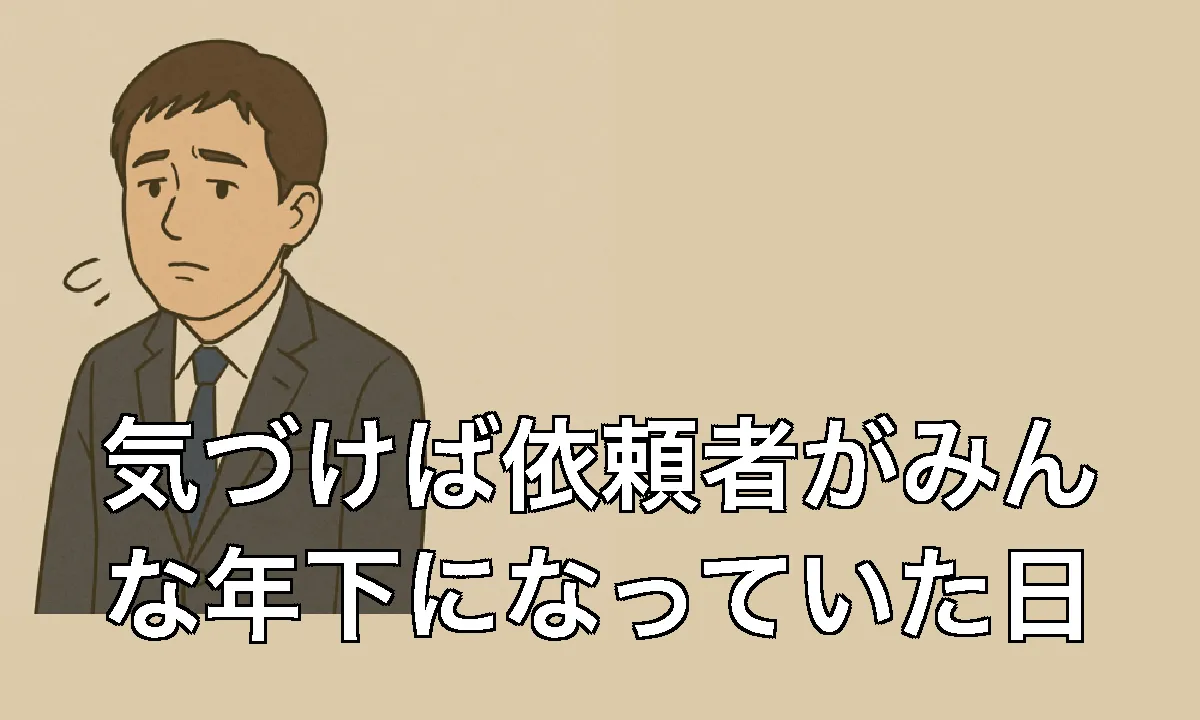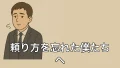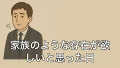若いつもりだった自分が、いつの間にか年上になっていた
司法書士として独立して十数年、バタバタと仕事に追われているうちに、ふと気づけば依頼者の多くが自分より年下になっていた。昔は「先生お若いですね」と言われることもあったが、今やその言葉も社交辞令にしか聞こえない。年齢のギャップを意識せずにはいられない瞬間が増えてきた。書類を交わすたびに、自分が「経験豊富な人」として見られていることに気づくが、内心では「いやいや、こっちも手探りだよ」と思ってしまう。年を重ねた分、責任は増したが、中身はそれほど変わっていない気がするのだ。
年下の依頼者が増えて気づいたこと
ある日、不動産登記の相談に来たのは20代の若い夫婦。結婚を機に家を建てたらしく、しっかりと予習もしてきていて、こちらが説明する前に要点を押さえていた。思わず「えらいね」と口に出しそうになったが、それはもはや上から目線に聞こえる年齢差。彼らの姿に、自分が30歳前後の頃、右も左もわからずに相談に行ったあの初々しさを思い出す。時代が変わり、情報が溢れる中で、若い人たちのほうが堅実で冷静な場面も多い。そんな現実に直面すると、こちらも背筋を伸ばさざるを得ない。
初対面での違和感 敬語が刺さる瞬間
最近、初対面の依頼者がほぼ全員「先生、よろしくお願いします」と丁寧な敬語を使ってくるようになった。もちろん礼儀としてありがたいのだが、どこか自分が「年配者」として扱われていることに軽いショックを受ける。かつて自分もそうしてきたのだが、いざ自分がその立場になると戸惑いがある。少し砕けた雰囲気で接してみても、向こうが律儀にかしこまると、余計に距離を感じることも。敬意はありがたいが、どこかで「おじさん化してるな」と自覚してしまう自分がいる。
平成生まれの依頼者に相続を説明する自分
平成生まれどころか、令和生まれの子どもを持つ若い親から相続の相談を受けたとき、自分が完全に「上の世代」に突入していることを痛感した。まだまだ自分は現役で頑張っているつもりだが、彼らからすれば、私は「経験豊富な中年男性」。しかも、質問がとてもロジカルで、こちらの説明にも食い気味で理解してくれる。そんな姿勢に「すごいな」と思う一方で、「自分がこの年代のとき、こんなにしっかりしてたっけ?」と情けない気持ちにもなる。年齢が上というだけで尊敬されるわけではない、ということも痛感する日々だ。
同年代の相談が減った理由を考えてみた
昔は、同じ世代の依頼者と話していて、話題の感覚も合い、冗談も通じていた。しかし今は、依頼者の多くが自分より10歳以上若く、共通の話題を見つけるのも難しくなってきた。最近はSNSで調べてから相談に来る人も多く、こちらの知識や言葉遣いが古く感じられないよう、無理に若作りする自分が少し情けない。なぜ同世代の依頼が減ったのかと考えると、ある程度落ち着いて自分で判断できるようになっているのか、単純に私の宣伝不足か…いずれにせよ、少し寂しさを感じてしまう。
住宅ローン世代からキャリア相談世代へ
以前は、住宅ローンや相続の手続きなど、ある程度年齢を重ねた人からの依頼が多かった。しかし最近は、「起業するために会社を設立したい」とか、「フリーランスとして契約書を見てほしい」といった、ライフステージの入口に立っている若者からの相談が増えている。自分の20代は、そんな選択肢があることすら知らなかった。世の中が変わったのか、若者がすごいのか…いや、両方だろう。時代の流れに置いていかれないように、こちらも学び続ける必要があると痛感する。
こちらは経験豊富でも向こうは物怖じしない時代
一昔前なら、法律家に相談するのは「ちょっと怖い」「敷居が高い」と思われていた。だが今は、若い依頼者たちがフラットな感覚で事務所にやってくる。もちろん礼儀正しいが、妙にビビることもなく、時にはこちらに「こういう場合はどうなんですか?」と強めに切り込んでくることも。たぶん彼らにとって、我々のような士業は「専門家のひとつ」に過ぎないのだろう。それはそれで健全な時代なのかもしれない。だが正直、ちょっとだけ寂しい気持ちもある。
年齢だけじゃない 価値観のギャップに戸惑う日々
年下の依頼者が増えただけでなく、その価値観や行動様式にも違いを感じるようになった。たとえば連絡手段ひとつとっても、電話よりLINE、メールよりDM。こちらの常識が相手には通じない、という場面が確実に増えている。もちろん柔軟に対応する努力はしているが、どこかで「昭和の人間だな」と自覚せざるを得ない瞬間も多い。書類の進め方、連絡の頻度、言葉の選び方――時代は変わっている。戸惑いながらも、なんとかついていこうとしている自分がいる。
時代の常識とこちらの常識
昔なら、契約書はきっちり紙で交わし、面前で押印するのが当然だった。今では、「PDFで送ってください」「電子署名でも大丈夫ですか?」という質問が飛んでくる。こちらが「紙じゃないと心配」と思ってしまうのは、ただの思い込みなのかもしれない。便利になったはずなのに、どこか不安になるのは、やはり価値観の違い。世代間の常識は意外と深い。司法書士としての原理原則を守りつつも、柔軟さを失わないことが、今後ますます重要になってくる。
書類よりもLINE感覚なやり取り
連絡手段もどんどん変わってきた。電話に出ない、折り返しが遅い、メールよりSNS…最初は不安だったが、こちらが柔軟に合わせないと相談自体が進まない。書類のやり取りもPDF中心、プリンターの使用頻度が激減した。一度、紙で送ってほしいというと、「PDFが読めないんですか?」と真顔で聞かれてしまい、自分の老化を実感した。便利なはずの技術が、自分を「時代遅れ」に追い込んでくる。だけど、これは避けられない変化なのだ。
電話が嫌いな世代とどう付き合うか
電話が嫌いな若者世代とのコミュニケーションは、なかなか難しい。こちらは「ちょっと話したいから電話するね」の感覚なのに、向こうからすれば「急に電話をかけてくるのは失礼」らしい。そんな時代になったのだ。メールでも敬語を完璧に使い、チャットではスタンプで感情を表現する。人との距離感が昔とまるで違う。でも、それに順応できないのは、こっちの責任なのかもしれない。時代が変わったなら、自分も少しずつ変わっていくしかない。