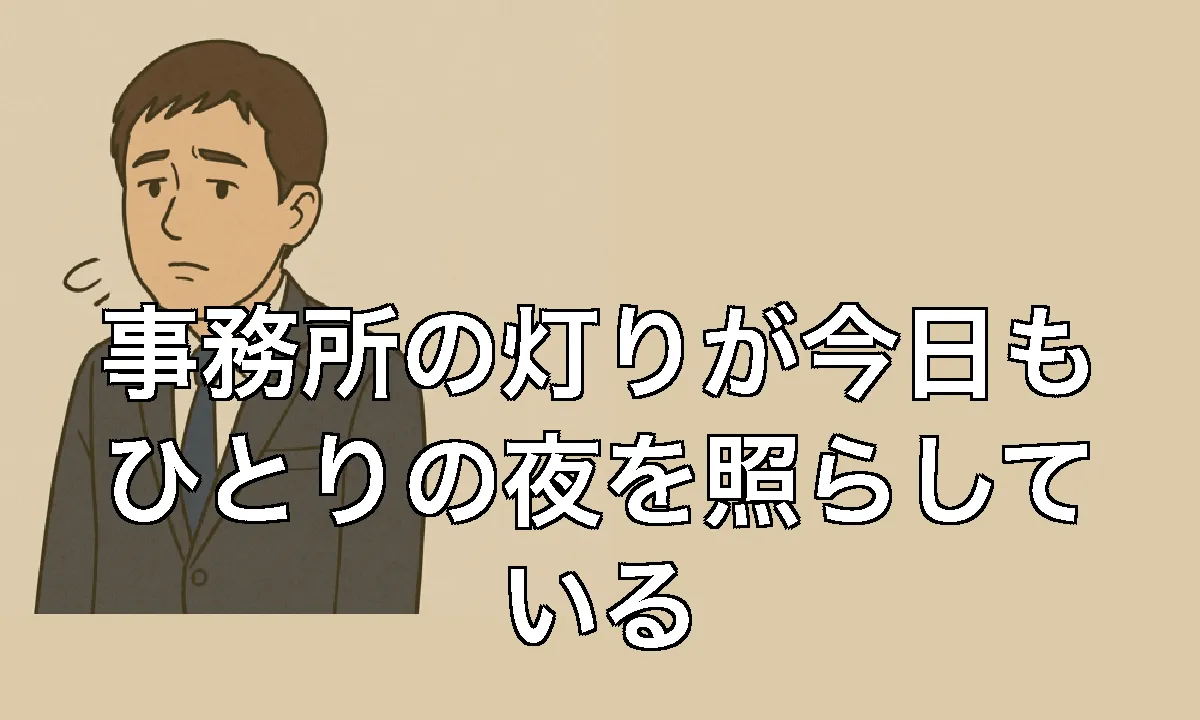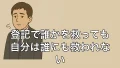今日もまたひとりきりの残業が始まる
商業登記の締切、相続の期限、そして「至急対応お願いします」と書かれたFAX。気づけば夜の帳が下りていて、事務所にいるのはもう自分だけ。45歳、独身、地方の司法書士。事務員さんは定時で帰ったし、それでいいと思ってる。むしろ帰ってくれてホッとする瞬間すらある。でもそのあとにくる静寂の中で、パチッと鳴る蛍光灯の音に自分の孤独が照らされる。
気づけばいつも最後のひとり
「今日は早く帰ろう」と毎朝思ってるのに、いつの間にか時計の針は夜の9時を過ぎている。若い頃ならまだしも、もうそんなに無理がきく年でもない。なのに、自分が帰るタイミングを見つけられない。誰かに強制されているわけでもないのに、自分で自分を縛っているような感覚になることがある。
事務員さんはとっくに帰っている
うちの事務員さんは30代の女性で、とても気が利く人だ。定時になったら「お先に失礼します」と一礼して帰る姿は清々しくも羨ましい。こちらが残っているのを気にしてか、たまに「先生も早く帰ってくださいね」と言ってくれる。でもその言葉が帰れない自分への皮肉に聞こえてしまうのは、完全にこちら側の心の問題だろう。
時計の針と蛍光灯の音だけが味方
夜の事務所は静かだ。電話も鳴らず、訪問もない。聞こえるのはキーボードの音と、時おり天井の蛍光灯がパチッと音を立てる音だけ。昔、部活の朝練のときに、まだ誰もいないグラウンドで一人素振りをしていたのを思い出す。あの頃も孤独だったが、今ほど重たくはなかった。今は、この静けさが少し怖い。
「俺がやらなきゃ」から抜け出せない
小さな事務所だから、仕事を振れる人もいない。「俺がやらなきゃ」という感覚が当たり前になっている。だけど、たまにそれがしんどくなる。「誰か助けてくれ」と声に出したくなるときもある。でも、そんなことを言える相手も、場面もない。結局また自分で処理して、次の日も同じことを繰り返す。
断ることに罪悪感がある
「先生しか頼れる人がいなくて」と言われたら、断れない。本当は無理なスケジュールでも、何とかしてしまう。おかげでどんどん自分の首を締めていく。誰かに迷惑をかけるくらいなら、自分が我慢すればいいと思ってしまう。でもそれが続くと、精神的にも体力的にも限界がくる。
優しさと責任感が首を絞める
昔から「いい人だね」とはよく言われてきた。野球部でも、頼まれると断れない性格だった。それは今も変わらない。優しさと責任感は時に美徳だけど、時に自分を壊す刃にもなる。誰かに「もう少し自分を大事にして」と言われても、ピンとこない。自分を大事にする方法を、まだ知らないのかもしれない。
司法書士という仕事の静かな重さ
司法書士の仕事は派手さはないけれど、地味に重い。一通の書類で人の人生が変わることもあるし、たった一言のミスが信頼を失うこともある。外から見ると「書類作成の人」で済まされがちだが、実際には心の奥深くまで立ち入ることも多い。
誰かの人生を背負うような感覚
遺産分割の相談で泣きながら話す依頼者を前にしたとき、ただの書類業務では済まされないと感じる。こちらが冷静さを保たなければならない場面ほど、感情を揺さぶられる。身内同士が争っているときは、書面の向こうにある「心の亀裂」をどう扱うかに悩む。気づけば、自分の気持ちの処理ができずにいる。
書類の向こうにある「人の事情」
「簡単な名義変更です」と言われても、実際には背景に離婚、死別、長年の確執があることも少なくない。書類は淡々としているが、その裏には物語がある。ときにはそれが心にのしかかって、終業後も頭から離れない。だからこそ、仕事を「早く終わらせる」だけでは済まされないのだ。
言葉にしにくいプレッシャーがある
「ミスがあってはいけない」という圧が常にある。完璧を求められる仕事で、なおかつ人からはその完璧さが当たり前と思われている。「先生に頼んでよかった」と言ってもらえるのは嬉しい。でも裏では、胃がキリキリするような緊張と戦っていることを、誰かに伝えたくなる日もある。
一人事務所という孤独な戦い
地方の小さな司法書士事務所は、基本的にワンオペに近い。事務員さんは助けてくれるが、最終判断や責任はすべてこちらにある。誰にも相談できず、誰にも頼れない感覚は、想像以上にきつい。背中を丸めてデスクに向かっていると、自分が事務所の一部になってしまった気すらしてくる。
誰にも愚痴れない日々
「仕事どう?」と聞かれても、「まあまあです」と答えるのが癖になった。本音は「毎日ギリギリです」なのに、それを言う場所がない。友達とも疎遠になり、恋人もいない。SNSで誰かが楽しそうに飲みに行ってる投稿を見ると、自分が取り残されたような気持ちになる。
休むことへの不安と罪悪感
休みを取ると、その間に依頼が来るかもしれないと不安になる。取ったとしても、頭の片隅で「大丈夫かな」と気にしてしまう。仕事を理由に休みを断るとき、「そんなに忙しいんですか?」と軽く言われると、うまく笑えない。たまには本気で、誰かに休ませてほしいと思う。
心をすり減らしながらも続ける理由
それでもこの仕事を辞めようとは思わない。時折もらえる「ありがとう」の一言が、不思議と心に沁みる。自分が役に立っている、誰かの助けになれているという感覚は、この孤独な日々を支える大きな支柱だ。
依頼者の「ありがとう」が支えになる
どんなに疲れていても、「本当に助かりました」と言われた瞬間だけは報われる。書類を手渡したとき、依頼者がホッとした顔を見せてくれるとき、自分の存在意義を再確認できる。人のために役立っているという実感は、何よりの報酬だ。
感謝の一言で報われる瞬間
「他のところで断られて困っていたので、先生が引き受けてくれて嬉しかったです」と言われたことがある。その一言で、三日連続の深夜残業の疲れが吹き飛んだような気がした。単純かもしれないけど、それだけで「明日も頑張ろう」と思えてしまうのが、この仕事の不思議なところだ。
やっていてよかったと感じる刹那
たった一度の感謝が、何百回のしんどさを上書きすることがある。確定申請が無事に通ったとき、相続人全員の笑顔が見えたとき、「この道を選んでよかったのかもしれない」と思う。そういう瞬間がある限り、事務所の灯りを今日も灯し続けていく。