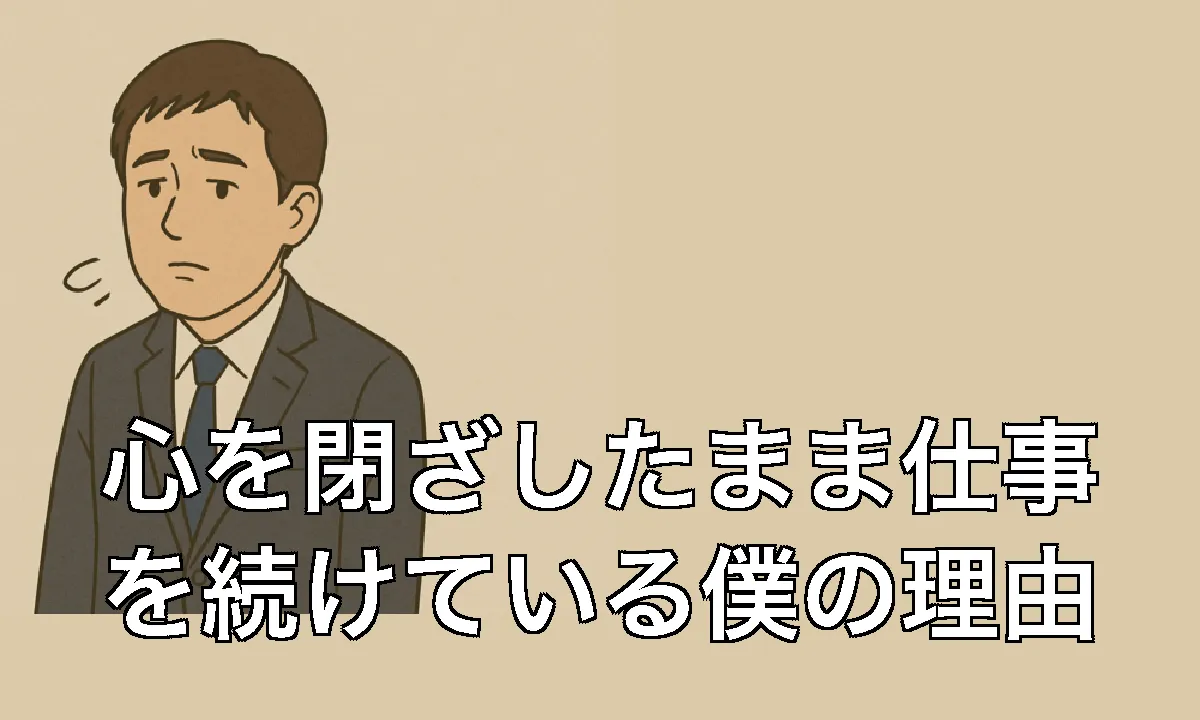朝の挨拶すら億劫になる日もある
朝、事務所に入って「おはようございます」と言うだけなのに、なんだか気持ちが重い日がある。もちろん事務員は気さくに返してくれるし、空気が悪いわけでもない。ただ、自分の中で何かが引っかかっている。別に嫌なことがあったわけでもない。でも心が塞がっている。そんな日は、口を開くことすら面倒になるのだ。司法書士としての仕事に支障が出るわけではないが、心のどこかで「これでいいのか」と問い続けている自分がいる。
元気そうに振る舞うのがだんだんしんどくなってきた
昔はもう少し愛想も良かったし、冗談も交えながら人と話すのが得意だった。だが最近は、あえて元気そうに振る舞うこと自体が疲れてしまう。特にお客さんとのやりとりでは、安心感を与えるために一定のテンションを保つ必要がある。それが長年続くと、プライベートでの感情表現まで鈍くなってしまうのだ。たとえるなら、ずっと笑顔の仮面をかぶっていたら、素顔の自分を忘れてしまったような感覚だ。
気を遣いすぎる性格が裏目に出る
相手に嫌な思いをさせたくない、失礼のないようにしたい、そう思って気を遣いすぎるあまり、自分の感情を押し殺してしまうことが多い。打ち合わせ中も、雑談中も、何かを言いかけて「いや、これは言わないほうがいいか」と飲み込む癖がついてしまっている。結果として、誰にも本音を話せず、余計に孤独を感じるようになってしまった。まるで、言葉を選びすぎて沈黙しか出てこない、そんな日々だ。
そもそも自分の感情をうまく言葉にできない
自分の中でモヤモヤしていることを、誰かに説明しようとしてもうまく言葉にできないことが多い。「なんか疲れてる」とか「ちょっと気が重い」と言っても、相手には伝わらないし、自分自身もその正体を掴めないままだ。これは司法書士という職業の中で、感情を排除して正確な手続きに集中してきた結果かもしれない。感情を封じ込めることに慣れすぎたのだろう。
事務員との距離感がちょうどよすぎて逆に孤独
事務員との関係は良好だ。適度な距離を保ちつつ、必要な会話はきちんと交わしている。でも、その「適度な距離感」が、逆に心の壁のように感じることがある。もっと深く話せたらと思う反面、職場でプライベートを出しすぎるのも違う気がして、自ら距離を保っている。結果として、孤独感が積もっていく。話し相手がいるのに話せない、そのもどかしさは意外と堪えるものだ。
なぜか本音を話すタイミングを逃してしまう
「今なら言えるかもしれない」と思った瞬間が何度かあった。でも、その一歩を踏み出す勇気が出ない。相手が真剣に受け止めてくれるか分からないし、何をどう話していいかも曖昧だ。本音を話すこと自体が、いつの間にか大ごとになってしまっている。そうして黙ってやり過ごすうちに、また一人で抱え込んでしまう。気づけば、そういう「タイミングを逃す日々」が何年も続いている。
誰かに心を開いた過去のトラウマ
過去に一度だけ、かなり踏み込んで悩みを打ち明けたことがある。学生時代の野球部の友人に、自分の将来や不安をぽつりぽつりと話した。でも、その反応が「そんなに考え込むなよ」「元気出せよ」みたいな軽い言葉だったのが、妙に引っかかった。悪気がなかったのは分かっている。でもその瞬間、「もう話さなくていいや」と感じてしまった。それ以来、深い話はほとんどしていない。
相談したところでどうにもならないという諦め
仮に悩みを打ち明けても、現実は変わらない。そう思ってしまう自分がいる。仕事の忙しさ、孤独、将来の不安。どれも相談して解決するような問題じゃない。だからこそ、誰かに話す意味を見出せず、口を閉ざしてしまう。まるで、心の引き出しに鍵をかけて、誰にも開けさせないようにしているかのようだ。自分でも、その引き出しの鍵がどこにあるのか分からない。
気軽な相談ができる人が近くにいない
同業の仲間もいないわけではない。でも、みんなそれぞれ忙しく、自分のことで精一杯だろうと思うと、なかなか話しかけられない。プライベートの友人も、地元を離れてしまった人が多く、いまさら深い話をする関係でもない。誰かに相談したいと思っても、ふと「今さら誰に?」と立ち止まってしまう。それがまた、心を閉ざす言い訳にもなっている。
地元という閉じた空間の息苦しさ
地方にいると、良くも悪くも人の目がある。「あの人、最近元気ないね」なんて噂されるのも面倒だから、結局明るく振る舞ってしまう。それが一番無難で、波風が立たない方法なのだ。でも、その生活を何年も続けるうちに、自分の感情を出すことすら忘れてしまった。まるで、感情を飲み込むことが呼吸のようになってしまったようだ。
司法書士という仕事が持つ孤独感
書類に囲まれ、手続きに追われ、感情を排して正確に進める。そんな日々の積み重ねが、いつしか自分を無機質にしていったように思う。人の人生に関わる仕事でありながら、その人の感情には踏み込まない。それが司法書士という仕事だ。誰にも心を開かず、でも誰かのために働く。そんな矛盾の中で、今日もまた、無表情で登記を打ち続けている。
人の人生に関わる重たい場面ばかり
相続、離婚、死亡、不動産売却。司法書士が関わる場面は、人生の節目であり、往々にして重い。そんな場面で、自分の感情を出していたら持たない。だから感情を閉ざし、業務的にこなす。だが、感情を閉ざし続けることが癖になってしまうと、プライベートでも人と距離を取るようになる。それが、心を開けない今の自分を作ってしまったのかもしれない。
成果は見えづらく評価されにくい
司法書士の仕事は、「終わって当たり前」とされる。ミスがないのが当然で、うまくいっても褒められることは少ない。それが地味に効いてくる。誰かに認められることもなく、ただ黙々と仕事をこなす日々。それが孤独を強めていく。自分が頑張っているという実感さえ、だんだん薄れていくのだ。
誰にも褒められない仕事の積み重ね
どれだけ正確に処理しても、「ありがとう」と言われることは少ない。登記完了の連絡をしても、反応は「ああ、分かりました」の一言。それが日常になってしまうと、承認欲求が行き場を失っていく。仕事はこなしている。でも、自分が誰かにとって必要とされている実感がない。その空白が、心を閉ざす理由のひとつになっている。
感情を抑える癖が抜けなくなる
仕事中に感情を抑えるのは当然のこと。でも、それが習慣になってしまうと、プライベートでも感情を出せなくなる。嬉しいことがあっても素直に喜べない。辛いことがあっても「まぁ、そんなもんだ」と流してしまう。そうやって、自分の気持ちに蓋をし続けた結果、もう蓋を開ける方法を忘れてしまったのかもしれない。
独身であることと心を閉ざすことの関係
一人でいることが楽だと感じる反面、たまにふと寂しさが襲ってくる。誰かと生きていくことに、どこか諦めのような気持ちがある。モテないという現実もあるが、それ以上に「誰かと向き合う勇気がない」ことに自分でも気づいている。一人で完結する毎日が、さらに心の扉を閉ざしていく。
誰かと暮らすことが想像できなくなってきた
かつては結婚して家庭を持つことに憧れもあった。でも今は、誰かと生活を共有すること自体が想像できない。自分の生活スタイル、仕事のリズム、感情の起伏。これを誰かに見せることが恥ずかしいし、しんどい。心を開けない自分が、他人と暮らせるわけがないと、どこかで思い込んでしまっている。
恋愛が面倒くさいと思うようになった理由
気を遣うのが億劫だ。やりとりの内容に悩んだり、相手の機嫌を気にしたり、そういう細かいことが負担になる。恋愛は楽しいだけじゃないと分かっているからこそ、踏み出せない。心を開くどころか、最初から閉じたままでいるほうが楽。それが今の自分だ。
それでも僕が仕事を続ける理由
心を閉ざしていても、誰かの役には立てる。誰かの困りごとを手続きで解決できる。それが司法書士の仕事だ。自分の感情を抑えてでも、誰かのためになる。その事実だけが、今の僕を支えている。心の奥がどれだけ孤独でも、仕事の中には確かな存在価値があると信じている。
誰かの人生の節目に関われるというやりがい
相続や登記といった場面は、人生の大きな節目だ。誰かの人生の一部に関わることができるというのは、大きなやりがいだと思っている。直接感謝されることは少なくても、「確実に手続きを終えた」という事実が、誰かの安心につながっている。そこにプロとしての誇りがある。
心は開けなくても信頼は積み重ねられる
本音を語らずとも、仕事で信頼は築ける。それが今の僕にできることだ。誰かと深くつながれなくても、正確な仕事と誠実な対応で信頼を積み上げていく。その信頼こそが、心を開けない自分の、唯一のつながりなのかもしれない。
形式的なやりとりの中にある誠意
事務的なやりとりの中にも、丁寧さや気遣いはにじみ出る。敬語の使い方、書類の整え方、連絡のタイミング。小さな部分に込めた誠意が、相手に伝わることがある。それだけで、心を開かずとも、信頼関係は生まれる。そう信じて今日もまた、書類に向き合っている。
一人だからこそ守れる信頼もある
誰にも頼らず、一人で仕事を回しているからこそ、最後まで責任を持てる。それは、信頼を守るうえで大きな強みだ。寂しさはあるが、誰にも干渉されない分、ブレずに仕事に向き合える。心を閉ざしているようで、実はその静けさの中に、自分なりの誠実さが詰まっているのだと思いたい。