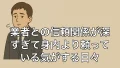ふと訪れる寂しさはどこから来るのか
日中は書類の山に追われているから、そんなことを考える余裕もない。でも、夜になって一人で事務所を閉めて、静かな家に帰ると、不意に胸がチクリと痛むことがある。誰かと交わす「おつかれさま」の一言もなく、冷えた部屋にただ自分だけがいる。それが日常になっているはずなのに、ときどきどうしようもなく、誰かの温もりが恋しくなる瞬間がある。
日常の中に潜む孤独のきっかけ
例えば、コンビニで隣のカップルが「この味好きだったよね」と笑い合っているのを聞いたとき。あるいは、道ばたで子どもを抱えたお母さんが「パパまだかな?」と電話しているのを見たとき。普段は気にならないような何気ない光景が、まるで自分の孤独を突きつけてくる。独身であることを特別意識しているわけじゃないのに、社会の中で“ひとり”が強調される瞬間が、時々やってくる。
静まり返った部屋が告げる現実
仕事が終わって、やっと帰宅。灯りをつけても音がしない。テレビをつけても、どこか虚しい。お湯を沸かしながら、誰かと一緒に鍋でもつついていたら、と思う。湯たんぽを布団に入れても、心の隙間までは温まらない。ふと「なんのために働いてるんだっけ」と思う夜ほど、独り身の空間が冷たく感じる。
忙しさに紛れて忘れたふりをしているもの
日々の仕事は確かに忙しい。朝から晩まで電話と相談、登記の段取りに走り回り、気づけばもう夕方。やることが山積みで、感情に構っている暇なんてない。だから、誰かの温もりなんて、考えないようにしているだけかもしれない。でも心の奥では、ずっと渇いている自分がいるのも、たしかなんだ。
仕事に追われる日々に感情を閉じ込める
相談者の話に耳を傾け、解決策を一緒に探す。それが司法書士の役割だ。でも、ふと気づく。人の悩みばかり聞いて、自分の心は誰が見てくれるんだろうと。誰かの役に立つことで満たされた気になっていたけど、それは仕事としての満足感であって、心の奥の寂しさとは別物だった。
電話と書類に支配される日常
朝イチで鳴る電話、昼過ぎには依頼者が来所、夕方には法務局へ提出。そんな毎日が続いていく。気づけば、プライベートな会話なんて一日一度もしていない日もある。事務員とも必要最低限のやりとり。誰かと他愛ない話をすることが、こんなにも貴重だったなんて、ひとりで過ごす時間が長くなってやっと気づいた。
感情を置き去りにしたままの生活
「感情は仕事に不要」だと、どこかで割り切っていた。でもそれは言い訳かもしれない。湧き上がる寂しさや誰かに甘えたい気持ちを押し込めるために、仕事を盾にしているだけなのかもしれない。割り切れば割り切るほど、自分の中の温もりへの渇望は深くなっていった。
他人の何気ない一言が胸を刺す瞬間
ある日、依頼者に「おひとりですか?」と聞かれたことがあった。たぶん軽い世間話のつもりだったのだろう。でもその一言が、想像以上に心に突き刺さった。笑ってごまかしたけど、帰り道でずっしりとその言葉が胸に沈んだ。言葉って、いつも正面からじゃなくて、横から急に刺してくるから厄介だ。
誰かと住んでるんですかの破壊力
「先生って奥さんいらっしゃるんですか?」——そんな質問、たまにされる。気にしてないふりをして「いやー独身なんです」と返すけど、内心ではちょっとダメージを食らっている。「なんで俺はいないんだろう」「どうして今までうまくいかなかったんだろう」と、気がつくと自己反省モード。笑顔で応えて、心はズタズタというやつだ。
気にしないふりの演技にも限界がある
どんなに慣れたふりをしても、毎回心がざわつく。演技が板についてきた分、逆に自分の本音からどんどん遠ざかっている気がする。そんなときは、たいてい晩酌のビールがいつもより苦く感じる。誰にも見せない分、自分の中でぐるぐると回り続ける孤独が、静かに心を蝕んでいく。
元野球部だった頃のぬくもりの記憶
学生時代、汗まみれで泥だらけになりながら白球を追いかけたあの頃。仲間と笑い合い、叱られ、励まし合いながら過ごした日々が、いまではやけに懐かしい。あのときは、誰かと一緒にいるのが当たり前で、寂しさなんて感じる暇もなかった。あの感覚を、少しだけ思い出す夜がある。
泥だらけでも笑っていたあの頃
練習がきつくても、終わったあとの「お前、今日ミスりすぎ!」みたいな笑い合いがあった。グラウンドの土の匂い、部室の汗くさい空気、全部がいまでは愛しい。誰かと肩を並べて過ごす時間が、どれだけ心を温めていたのか。大人になると、あのときのような関係はなかなか築けない。
肩を組んだあの感覚がいまや懐かしい
試合に勝った帰り道、みんなで肩を組んで校歌を歌った。笑いながら「お前、今日いいとこで打ったな!」って言い合った。あのときの手や肩のぬくもりが、ふとした瞬間に蘇ってくる。今の生活には、そういう“ふれあい”が圧倒的に足りない。人と人との物理的な距離が、心の距離を決めてしまうように感じる。