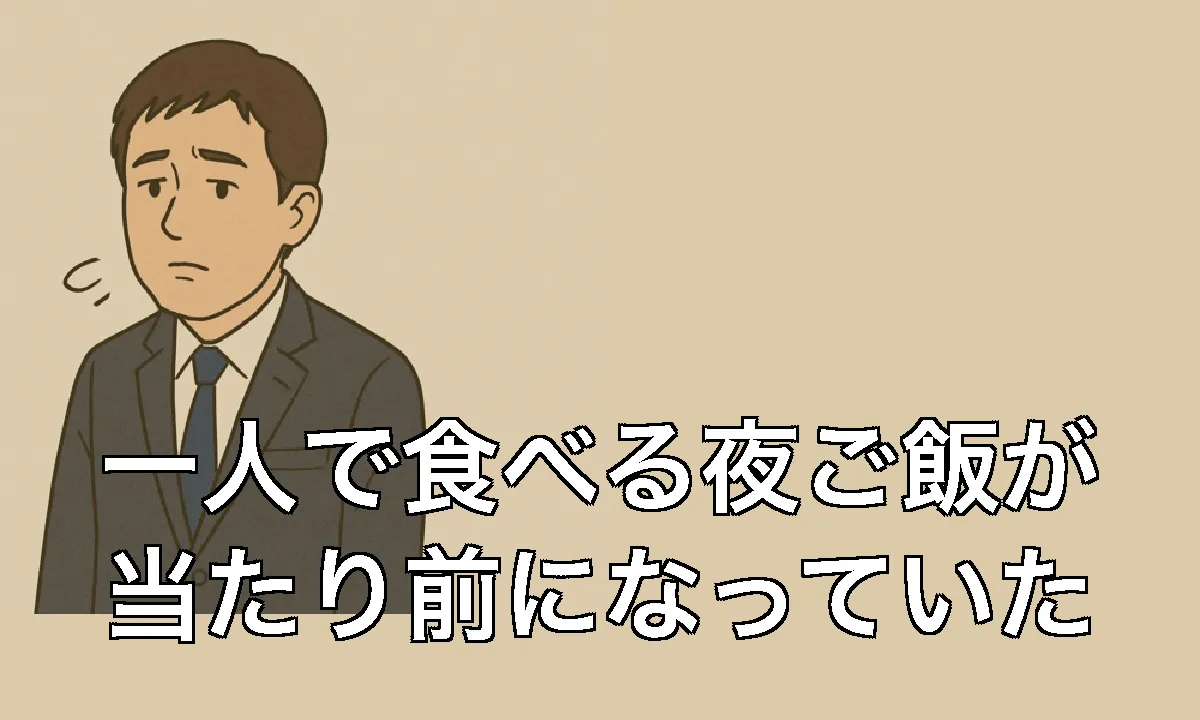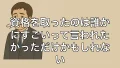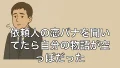夕飯の時間がただのルーチンになった日
「今日の夕飯、何にしようか」——そんな会話をしたのは、いつが最後だったろう。独身のまま司法書士として働き続けて早十数年。家に帰ると、無音の空間。冷蔵庫を開け、残っていた豆腐と卵で簡単に済ませる。気づけば、夕飯の時間は「誰かと過ごすもの」ではなく、「腹を満たすだけの時間」になっていた。最初は寂しかったが、今ではそれも感情として湧き上がってこない。ただ淡々と、口に運び、洗って片付けるだけの夜。ルーチンの一部に過ぎないのだ。
今日は何を食べようから始まる無言の時間
コンビニの棚の前で、「何を食べようかな」と考えている時間が、なんとも言えない孤独に包まれる。誰かと「どれにする?」なんてやりとりをしていた日々が懐かしい。今はスマホのメッセージも鳴らないし、誰かに食べたものを報告することもない。独り身の男が、スーツ姿で一人レジに並ぶ姿は、特別でもなんでもなく、どこにでもある風景。けれど、買った弁当を袋から出し、静かな部屋で一人食べる時間は、やっぱり無言でしかない。
コンビニの灯りが家の明かりのように思える夜
遅くまで仕事をして、帰り道に見えるコンビニの灯り。あの淡い白光が、なぜか心に染みる。家に帰っても真っ暗で、誰かが待っているわけでもない。その点、コンビニはいつでも明るくて、品揃えも変わらない。まるで自分を迎え入れてくれているような錯覚すら覚える。時には、同じ時間に来る他の一人客と、軽く会釈を交わすこともある。名も知らぬ誰かと、同じような孤独を共有しているような不思議な安心感が、そこにはある。
レジの「温めますか」にすら救われることがある
「温めますか?」その一言に、どれだけ救われてきただろう。たとえマニュアル通りの対応だとしても、自分に向けて発された言葉であることに変わりはない。事務所ではクライアントとのやりとりばかりで、感情を込めた言葉をもらう機会は少ない。誰かに気遣ってもらえるということが、こんなにも心に染みるのかと、改めて気づかされる。レジ越しに微笑む若い店員さんの顔を見て、心のどこかがふっと緩む夜もある。
誰かと食べるご飯の記憶が遠ざかっていく
昔は、誰かとご飯を食べるのが当たり前だった。家族と、部活の仲間と、たまには気になる女性とも。だが年を重ねるごとに、そうした時間は徐々に遠のいていった。今では、思い出そうとしても、会話の内容やその場の空気がうまく浮かばない。日常の積み重ねが記憶を塗り替えていくように、孤独な夕飯が自分の「普通」になってしまった。そう考えると、少し切なくもなる。
家族と囲んだ食卓が今は思い出に変わった
実家では、決まって母が夕飯を用意してくれていた。魚の焼ける匂い、父の咳払い、弟との些細な口げんか。そうした音と匂いに囲まれていた食卓は、もうずいぶん前の話だ。司法書士になりたての頃は実家を出ていたが、たまに帰ると嬉しそうに迎えてくれた母の姿が焼き付いている。今はもう、その食卓も空席ばかり。時間が経つにつれ、温もりだけが記憶に残り、現実では再現できなくなっている。
野球部時代の“まかない飯”が懐かしい
大学時代、野球部の合宿で出された“まかない飯”のがっつりした味付けと、みんなで食べる楽しさは今も忘れられない。皿の取り合いや、バカ話をしながら食べた白米は、どこか特別だった。今じゃ同じ量を一人で食べることもないし、誰かと笑いながら食べることもない。何を食べたかより、誰と食べたかが記憶に残っているということを、大人になって痛感している。
仕事が終わると、静かすぎる夜が始まる
ようやく一日が終わったと思ったら、事務所のドアを閉めて無音の時間が始まる。電話も鳴らない、誰も話しかけてこない。そうなると逆に、雑音が恋しくなる。テレビをつけっぱなしにして、誰かの声を流しておく。それが習慣になって久しい。けれど、心のどこかで「これでいいのか?」と問う自分もいる。
書類は山積みでも、会話はほとんどない
仕事中はひたすら書類と向き合い、黙々と手を動かす。事務員さんがいるとはいえ、会話は業務連絡が中心だ。誰かと無駄話をする余裕もなく、ましてやランチを一緒に食べに行くような関係でもない。だからこそ、誰かと日常の他愛ない話をするという時間が、今の自分には決定的に欠けている。
事務員さんとの雑談が唯一の会話かもしれない
「今日は雨みたいですね」とか「暑くなってきましたね」なんて、事務員さんとの雑談が、下手するとその日初めての人との会話になることもある。特別な話じゃない。でも、それが意外とありがたいのだ。天気の話一つで「自分は今日、人間らしく過ごせている」と感じられる。きっと、彼女がいなかったら、今日一言も声を発していなかったかもしれない。
「お疲れさま」の声が誰からも聞こえない
クライアントからの連絡はひっきりなしに来るけれど、「お疲れさま」と声をかけてくれる人はほとんどいない。特に事務所を出た後、電話が鳴るたびにドキッとする。それが案件の急ぎ対応だったり、ただの営業電話だったり。どちらにしても、心が休まらない。だからこそ、誰かからのねぎらいの一言が、どれだけ貴重かを思い知る。
終業後に鳴るスマホは営業電話ばかり
夜19時を過ぎてから鳴る電話の大半は、投資や保険、ホームページ制作の営業だ。番号を見て無視しても、結局またかかってくる。「誰かの声が聞きたい」と思っていたのに、これじゃ逆効果だ。疲れた心に、必要なのは効率や利益の話ではなく、ただの「今日もお疲れさま」という一言なのに。
それでも続けていく理由
孤独も慣れれば道具になる。誰かと分かち合う時間がないなら、自分との対話に時間をかけるしかない。司法書士という仕事は、人の人生の節目に立ち会う仕事でもある。その重みに、誇りを持って向き合っていけるうちは、まだ続けられる気がする。
誰のためでもなく、自分のために仕事をする
昔は「誰かに認められたい」「モテたい」そんな気持ちが原動力だった。でも今は、自分が納得できる仕事をしたいという気持ちが一番強い。たとえ誰かと夕飯を食べなくても、自分がやったことが誰かの役に立ったという実感が、明日のご飯を美味しくする。それが今の自分にとっての支えだ。
誰かに頼られることがある限り、やめられない
ふとしたときに届く「先生にお願いしてよかったです」という言葉。それだけでまた数日頑張れる。直接顔を合わせる機会が減っても、書類の向こうには誰かがいる。その誰かが不安な顔をして相談に来て、最後には笑顔で帰っていく——それがある限り、自分の仕事は無意味じゃないと思える。
一人でも、誰かの力になれることがある
一人でご飯を食べ、一人で寝て、一人でまた朝を迎える。それでも、日中は誰かの人生の一部に関わっている。そう思うと、少しだけ救われる。誰かとご飯を食べることは少なくても、誰かの人生に“必要とされる存在”でいられるなら、それで十分だ。
今日もどこかで誰かの不安を少しだけ軽くしている
今日、相続の相談に来た年配の女性が「安心しました」と言って帰っていった。その一言が、静かな夜を少しだけ温かくしてくれた。たった数十分の面談でも、誰かの気持ちを軽くすることができる。それが、自分の孤独をちょっとだけ和らげてくれる魔法になる。